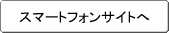お知らせ |
トンボ池・上石神井のしぜん最新情報 |
 |
2024年10月20日(日) ジャコウアゲハ、羽化しました サナギの色が黒っぽくなって、翅(はね)や体のもようがすけて見えるようになってきて羽化が近いようなので、羽化の様子を動画にとろうと準備してあったのですが、別の調べ物をしているわずかな間に羽化していまい、動画はさつえいできませんでした。チョウは、トンボと違(ちが)って羽化にかかる時間はとても短く、あっという間に羽化が終わってしまいます。ただ、翅がしっかり乾(かわ)いて飛び立てるようになるのには少し時間がかかるようです。 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 | ||
 |  |  |
2024年10月18日(金) お菊虫(おきくむし) ジャコウアゲハの蛹(さなぎ)を見つけました。これでジャコウアゲハの卵(たまご)、幼虫(ようちゅう)、成虫(せいちゅう)といった成長(せいちょう)の段階(だんかい)を写真にとることができました。 ジャコウアゲハの蛹はとても変わった姿(すがた)をしていて、お菊虫(おきくむし)と呼ばれることもあるそうですが、そのいわれについて調べてみてください。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||
 |
2024年9月28日(土) お米できるかな? 探検隊では一ヶ月近く前、9月7日に水路の稲刈りをしましたが、イネを刈り取った後の切り株から新しく芽を出し、イネの「ひこばえ」が成長し、草丈は30cmほどと小さいながら、もうすでに小さな穂(ほ)をつけています。「二番穂(にばんほ)」とか「ひつじ」とか呼ばれ、暖かい地域ではこの新しい穂を刈り取ってお米を収穫することがあるそうですが、上小のイネの「ひつじ」は、はたしてお米になるのでしょうか? 画像と情報:しぜん探検隊 |
 |
 |
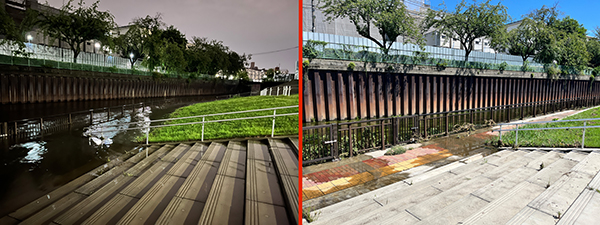 |
 |
2024年8月20日(火) 雷雨後の石神井川 今年は昨年より夕方近くから夜にかけて雷雨(らいう)になることが多いような気がします。昨日19日の夜も雷雨になりました。たくさんの雨が降ったあと、石神井川がどうなっているのか、雨が上がった後に行ってみました。雨で水位が上がり、普段は歩いて散策(さんさく)できるようになっている通路だけでなく、草の生えた斜面の一部まで川の水があふれてきていました。天気になった今日、同じ場所に行って似たような景色になるように写真を写してくらべてみました。一番上の写真を見ると、カルガモが、柵(さく)の手前側、川の水があふれて池のようになったところを泳いでいるのがわかります。川の流れが強すぎて、危険(きけん)を感じたのでしょう。泳ぐのが得意(とくい)なカルガモでさえ危険を感じるような流れの強さ、水の量になったということです。雨が降(ふ)ったあとはけっして川に近づかないようにしましょう。石神井川は西東京市を流れて練馬区を流れてきます。夏の夕立などで西東京市にたくさんの雨が降ったときには、上石神井でまったく雨が降っていないときでも、急に石神井川の水の流れが強くなり、水位が高くなる(水の量がふえる)ことも考えられます。スマホのアプリなどで雨雲の様子を見たり、石神井川の上流にあたる西の方角の空を見て、真っ黒な曇り空になっているようなときには、急いで石神井川の近くで遊ぶのをやめて川の近くから離れるようにしないと危険です。日頃(ひごろ)から、空や雲の様子を見て、天気の変化などに興味(きょうみ)をもつようにしましょう。 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
 |
2024年7月18日(木) ジャコウアゲハ イネの植えてある水路のあたりをジャコウアゲハが飛びまわっていました。6月24日に見かけたものと違って、翅はいたむことなく、きれいな姿をしていました。 ジャコウアゲハは姿(すがた)だけでなく、飛び方もナミアゲハやクロアゲハなどと違って、フワフワと風に舞(ま)うように飛ぶので、遠くから見てもジャコウアゲハであることがわかります。みなさんもぜひ、ジャコウアゲハを見つけてください。クリック→動画:ジャコウアゲハが飛ぶ様子 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
2024年7月19日(金) 校庭でトンボをつかまえたよ 校庭にいた2年生の女の子にもっていてもらいました。人さしゆびと中ゆびでじょうずに羽根をはさんでいます。これは、アカトンボのなかまではありません。ウスバキトンボというトンボで、プールにもよくやってきます。ちょうどおぼんのころたくさんあらわれるので、「精霊(しょうりょう)トンボ」とか「盆(ぼん)トンボ」などともよばれます。たまごがかえってからわずかひと月ほどで成虫になります。何回かそれをくりかえします。プールにもヤゴが生まれますが、寒さによわく、12月ごろにはこのトンボのヤゴはすべて死んでしまいます。それなのに、よく年また見られるのはどうしてでしょうか?しらべてみてください。このトンボは、アカトンボやシオカラトンボの仲間とはちょっとちがうくらし方をしているみたいですよ (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
 |
2024年6月24日(月) ジャコウアゲハ ついに上小の水路わきにあるウマノスズクサにジャコウアゲハがやってきているのを確認しました。産卵(さんらん)している様子はありませんでしたが、バタフライゾーンの中をゆっくりと飛び回り、ときおりウマノスズクサにとまって翅(はね)を休めていました。よく見ると、さんざん飛び回ったからでしょうか、後翅(こうし/後ろばね)がボロボロになっていました。 またやってくるかもしれないので、トンボ池に行ったときには、ジャコウアゲハがいないか探してみましょう。産卵する様子を見ることができるかもしれません。 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 | ||
 |  |  |
2024年6月22日(土) ウマノスズクサとジャコウアゲハ トンボ池の水路の横、バタフライゾーンにウマノスズクサが鉢植えで置いてあるのですが、そこにジャコウアゲハの卵がうみつけられていました。成虫、来ていたのですね。色が黒っぽい卵がふたつほどありました。数時間後には孵化して小さな幼虫が2匹いました。幼虫はこれからウマノスズクサをたくさん食べて、大きく育っていきます。そっと見守りましょう。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||
 | ||
 |  |  |
2024年6月17日(月) ジャコウアゲハの幼虫 3年前、神学院のフェンスぞいに、ジャコウアゲハの幼虫の食草であるウマノスズクサがあるのに気づき、神学院にかり取らないようにお願いしていました。今日、通りすがりにそのウマノスズクサをみたところ、葉を食べたあとがあったので、周囲(しゅうい)を探(さが)したところ、数匹の幼虫がいました。幼虫の写真を撮っていたところ、ジャコウアゲハ(クリック:写真①、写真②/別日撮影)が2頭、卵を産み付けに飛んできていました。神学院にウマノスズクサの保護をおねがいしてから3年目にしてやっと幼虫の姿(すがた)をみることができました。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||
 |
2024年6月15日(土) ヤマトタマムシ 体は緑色の金属光沢があり、虹色にかがやく、とてもうつくしい甲虫(こうちゅう)です。この体の美しさは死んでも色あせません。上石神井憩いの森を散策(さんさく)していて見つけました。東京では、絶滅の危険性が高まっている種に指定されています。成虫はエノキやケヤキの葉を食べるため、夏の日差しが強く暑い日、それらの木の高いところを飛び回っている姿が見られます。また、エノキやケヤキの木の近くの地面に落ちているのをみかけることもあります。 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
2024年6月12日(水) 隊員のKさんやHさんが飼っていたツマグロヒョウモンがめでたく羽化(うか・サナギからチョウにかわること)しました。サナギについていたあの「金バッチ」はどこへともなくきえていました。(まぼろし~~~~~!)金色に光るものがそこについていたわけではないんですね。 |
 |
ぎょぎょ。流血のさわぎ。それともトマトジュースを飲みすぎ? この赤いえき体は、「蛹便」(ようべん)というそうです。サナギからチョウになる時に、よぶんな体えきをすてて身がるになります。まず羽化してすぐに体えきをはねのみゃくに送りこみはねを広げます。はねが広がって完成するとはねのみゃくは中がからになります。あまった体えきは、外に出して飛び立ちじゅんび完了というわけです。 |
 |
ツマグロヒョウモンの名前のいわれ 「つま」とは、着物のすその両はしのところをさします。チョウでいうと、後ばねの下あたりでしょうか。羽化したのはオスですが、やはり「つま」が黒くなっています。メスはオスとちがい前ばねのはじがきれいに青黒く色づいているのが目をひきますが、あの部分がツマグロヒョウモンの名前のいわれではないということです。メスもオスもつま(後ばねの下)が黒くなっているというわけです。 (画像と情報:隊員のHさん、しぜん探検隊) |
 |
2024年6月9日(日) ツバメ 石神井川の近くでたくさんのツバメが飛んでいます。巣立(すだ)った幼鳥も混(ま)ざっているようですが、巣立ってもまだ、自分でエサをつかまえることができないのか、電線にとまって親鳥がエサをとってきてくれるのを待っています。親鳥は飛(と)んだまま器用(きよう)に幼鳥の口にエサを入れてあげています。 (画像と情報:しぜん探検隊) |
 | |
2024年6月1日(土) シジュウカラの巣箱の確認 6月の観察会で、上小西門付近のヒマラヤスギの木に取り付けておいたシジュウカラの巣箱の中の確認とそうじをしました。ひなはもうとっくに巣立ったあとですが、巣材(すざい)や巣立てなかったひなの亡骸(なきがら)の確認をしました。写真は以前に写した子育てをするシジュウカラの巣の中の様子です。この時は動画も撮影しました。→動画リンク (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
2024年5月31日(金) この草・・・なんだ?クイズだよ おさんぽコースを歩いていると、目をひくとげとげの花を見つけました(西東京市内)。畑や庭ではなく、しざいおき場のとなりの空き地に、何本か生えています。葉はハートがたで数十センチの大きなものもあります。草たけは大人のむねから首くらいまであり、けっこう大きいです。さて何でしょう? ア) ゴボウ イ) オニアザミ ウ) ショウガ (画像と情報:しぜん探検隊) |
 |
2024年5月11日(土)トンボ池の「かいぼり」 今年も発見「トンボ池の主」! 5月の観察会では毎年、トンボ池の水を全部抜いて生き物調査と池の大そうじ(=かいぼり)をしています。今年もたくさんのヤゴやクロメダカ、モツゴ、ヌマエビなどの生き物がいることを確認し、同時に増え過ぎた水生植物アサザの間引きをして生き物が住みやすい池になるように環境整備をしました。毎年この日に会うことができるのが、上の写真の巨大ドジョウ。もう何年も前からトンボ池にすみついているので探検隊では「トンボ池の主」と呼んでいます。 画像と情報:しぜん探検隊 |
 |  |
2024年4月28日(日) ツクシじゃないよ! しぜん探検隊の小屋のすぐそば、ちょっと変わったものを発見!。まるでツクシのように地面からニョキニョキっと出ています。でもツクシではありません。ヤセウツボという植物です。もともと南ヨーロッパを原産とする外来種(がいらいしゅ)で、マメ科やキク科の植物に寄生(きせい)して(ほかの植物から栄養をもらって)成長するようです。葉緑素(ようりょくそ)を持っていないため、ほかの植物のような緑色ではなく、全体に褐色(かっしょく)をしています。 (画像と情報:しぜん探検隊) | |
 |
2024年4月26日(金) ツバメの季節になりました! これは先週17日の石神井川です。真ん中あたりにとんでいるツバメが写っています。 今朝は、北口にある「べジファームかのん」の畑で、巣材の土を運ぶカップルを見ました。どこに巣を作っているんでしょうね? (画像と情報:OBのGママさんより) |
 |
2024年4月15日(月) かわいい花見つけた! 花の大きさは、7mmから1cmくらいです。葉が大きいので、つい見落としてしまいそうです。はなびらは5枚で白く、わずかにピンク色をしています。調べると、ナガエアオイらしいです。(葉の柄(え)が長いから)タチアオイやムクゲと同じアオイの仲間です。べつの名前ではハイアオイ(地面をはうから)などとよばれるようです。場所は、トンボ池からほど近いところにある梅(うめ)の木のすぐそば、校しゃのきわです。かなりいせいよく育っています。 画像と情報:しぜん探検隊 |
 |
2024年4月8日(月) いよいよ新年度! 入学、進級おめでとうございます。 校庭では、満開(まんかい)のサクラの花だけでなく、たくさんの春の花や、いろいろな生き物が、君たちに見つけてもらうことを楽しみにまっています。 画像と情報:しぜん探検隊 |
 |
2024年2月24日(土) 春がやってきます 上小のあちらこちらに、フキノトウ(フキのつぼみ)がたくさん出ています。 もうすぐ春がやってくることを知らせてくれているようです。そう思ってさがすと、オオイヌノフグリやホトケノザなどの小さな花も咲いています。 画像と情報:スタッフのつとむ |
 |
2024年2月14日(水) ジョウビタキ(オス) 春をおもわせるような暖(あたた)かな日もあって、シジュウカラもさかんにさえずり始(はじ)めたようです。そろそろ、この写真(しゃしん)のジョウビタキのような北の国からわたってきた冬鳥ははんしょく地にもどり、姿(すがた)を消す時期(じき)でしょうか。最近(さいきん)では、日本に残(のこ)ってはんしょくしているのが確認(かくにん)されることもあるようです。→クリック写真拡大 画像と情報:スタッフのつとむ |
 |
2024年2月3日(土) コモをはずして中を観察しました!出てきたのは・・・ 2月の観察会の時に、校庭西がわにあるクロマツ、アカマツ、ヒマラヤスギにまいたコモを外して、中の虫の冬越しのようすを観察しました。中からは、マツカレハの幼虫175匹、ハムシ、クモ、テントウムシ、カメムシ、ツチバチににたハチが見つかりました。写真は、うっかり手のひらにマツカレハの幼虫を広げたところです。マツカレハの幼虫は毒の毛をもっているので、手でじかにさわることはキケンです。ぜったいにしないようにしましょう。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |
 |
2024年1月12日(金) こおりの華(はな)がさいたよ シモバシラの氷の華(はな) が見られました。12日は、朝の最低気温がー2.7度(アメダス練馬(石神井台)7時ごろ)にまで下がりました。シモバシラは、シソ科の植物で夏には白い花をさかせます。冬には、かれてしまいますが、根は元気です。すい上げた水をくきからふき出して、それがつめたい空気にふれると、氷の華ができるというわけです。東京では高尾山が有名ですが、これは、西東京市向台町にある小さな植物園でとったものです。気温が上がるととけてしまうため、寒い早朝のわずかな時間しか見られません。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |
 |
2023年10月27日(金) 「空を見上げよう!」のページにあるように〈→クリック(空を見上げよう」へ移動〉、今日は昔の暦で9月13日。「後の月(のちのつき)」と呼ばれる十三夜の月を、お月見代わりに撮影してみました。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 |
2023年10月19日(木) 夕焼空 久しぶりに夕焼を写してみました。だんだん色が濃くなって広がり、まるで紅鮭(ベニザケ)みたいな色だなぁと思ってみていたら、あっという間に色がなくなって、灰色の雲になってしまいました。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 |
2023年8月23日(水) 夕空の表情 今日の夕方は、久しぶりにきれいな夕焼けを見ることができました。地平線の下に沈んだ太陽の光を受けて、雲がその表情をさまざまに変える様子は見応えがあります。陽の光が当たらなくなって雲がその色を失った頃、南の空に半月間近の月が輝いていました。(→タイムラプスムービー) (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 |
2023年8月22日(火) 夏らしい雲 突然強い雨が降ったり、雷が鳴ったり、今日はそんな1日でしたね。夕方になって北の空を見たところ、高く成長した積乱雲が、夕日に赤く染められていました。成長した積乱雲の頂上部分が平らになって、いわゆる立派な「かなとこ雲」となっていました。あの下ではものすごい雨になっているんだろうなぁ、そんなことを考えながら1枚写真を撮りました。対流圏の中の温度差によって高く上昇しながら発達する積乱雲も、成層圏に達するとそこでは上昇できずに成長が頭打ちとなって横に広がるようになります。こうしてできた積乱雲の形がかなとこ雲です。つまり、かなとこ雲の平らな部分は、大気圏の中の、対流圏と成層圏の境目ということができます。ちなみに、かなとこ(金床)とは、金属を叩いて加工する時などにその作業台となるものです。今回の写真、頂上部分が綺麗な平ではないので微妙ですが…。 (情報と画像:スタッフのつとむ) |
 |
2023年8月18日(金) 海を渡るトンボ 石神井川の上、そしてその脇の草原の上をたくさんのトンボが群れて飛んでいます。ウスバキトンボです。春から秋にかけて、日本全国で見られるトンボですが、寒さに弱く、八重山諸島など一部の温かい地域を除いては、日本の気候ではヤゴが冬を越せずに、全滅してしまうと言われています。春になると南の温かい地域から海を渡ってやってきて、世代を繰り返しながら、季節の移り変わりとともに少しずつ日本の中を北上していきます。このあたりでは、今の時期に最も多く姿を現し、成虫は水辺から遠く離れるため、街中でも目にすることの多いトンボです。お盆(8月中旬)の頃に群れで飛ぶ姿を見かけるため、「精霊(しょうりょう)トンボ」「お盆トンボ」などとも呼び、「ご先祖様の使い」と考える地域もあるようです。動画→クリック (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 |
2023年7月19日(水) もらったヤゴがトンボになったよ! 事務局にうれしいお便りが届きました。5月に上小のプールで行った「ヤゴ救出大作戦」に参加してくれた、おとなり上石神井北小学校の6年生のMさんからの報告です。Mさんはクラスの「生き物係」をしているそうで、上小で救出したギンヤンマのヤゴを学校に持って行って、ヤゴが大きなあごを伸ばしてアカムシを食べる様子をクラスのみんなに実際に見てもらったりして詳しく紹介してくれたのだそうです。学校が休みの日には家に持ち帰り、最後は家でしっかり羽化させることもできたそうです。上小のプールで育ったヤゴが、同じ上石神井の地域の中で学校のわくを超えて、生き物仲間を増やしてくれているようでなんだかうれしいですね。Mさん、報告ありがとう! (画像:上北小Mさんより) |
 |
2023年7月6日(木) エゴノキに注目! エゴノキという樹木があります。日本各地の雑木林などで見かけますが、公園樹としても植栽されることも多く、最近では、雑木の庭の樹木として人気も出てきています。 そんなエゴノキですが、秋に落ちている実を割ると中に小さな白いイモムシ(クリック:画像1、画像2、画像3)がいて、それを釣り餌にしたりします。釣り人はエゴノキをチシャの木と言うこともあり、中の虫をチシャの虫と呼んだりします。 このイモムシ、エゴヒゲナガゾウムシという小さな甲虫の幼虫で、釣り餌に使うために幼虫はよく見るのですが、今まで成虫を見たことがありませんでした。そこでこの時期、交尾・産卵のためにエゴノキにやってくるらしいエゴヒゲナガゾウムシの成虫を見つけて写真を撮ろうと思いました。 エゴノキはいろいろなところに植えられていますが、落ちている実の中に幼虫がいる割合が高い木と、あまり入っていない木があります。近くでは、立野公園には、落ちている実に幼虫が入っている割合が高いエゴノキが1本あって、そこで成虫を探すことにしました。小一時間探して1匹の成虫(オス)を見つけることができ、撮影しました(クリック:画像)。オスは、白い顔の側面がツノのように出っ張っていて、その先にに目がついているユニークな顔をしています(クリック:画像)。 ユニークといえば、エゴノキでは、エゴツルクビオトシブミ(クリック:画像1、画像2、画像3)という、これまたちょっと変わった姿をした小さな甲虫を見かけることがあります。エゴノキだけでなく、ハクウンボク、フサザクラなどの葉の上でも見られるようですが、メスはその葉を巻くようにして卵の入ったゆりかご(巣)を作ります(クリック:画像)。その筒状に巻かれた葉が地面に落ちていることがあります。丸く巻いた手紙に形が似ているので「落とし文」と呼ばれます。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
 |
 |
2023年7月3日(月) 「かぎたくないけどかいでみたいにおい」の花 トンボ池の水路のわき、バタフライゾーンに植えてあるウマノスズクサの花が咲きました。花は先の開いたやや曲がった筒状で、その基部(もとの部分)が丸くふくらんだ独特(どくとく)な形をしています。花は動物のふんや腐(くさ)った肉のようなくさい匂(にお)いがするそうで、その匂いで小さなハエなどを筒の中におびき寄せて閉じ込めて、受粉(じゅふん)に利用するそうです。このウマノスズクサはジャコウアゲハ(画像:クリック)の食草(幼虫が餌にする)です。上小でジャコウアゲハを見かけたら、ぜひ報告してください。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 |
2023年6月20日(火) 葉っぱの上の理容師さん 体育館の裏、花だん(畑)のシソの上に、カミキリムシがいました。カミキリムシの仲間はとても種類が多く、その姿や大きさは様々です。この黒い体に白い点々のカッコイイ姿のカミキリムシはゴマダラカミキリ。ところで、カミキリ虫の名の由来ですが、「紙きり」でも「噛(か)み切り」でもなく、「髪切り」。強い顎(あご)を持ち、髪の毛をも切る、ということからきていると言います。幼虫が、樹木の幹の中や草花の茎の中を食いあらすため、果樹農家や園芸を楽しむ人たちからは嫌われ者の害虫とされます。一方、美しい姿のもの、珍しいものも多く、昆虫コレクターにとっては人気の昆虫です。カミキリムシの多くは、手で持ったりすると、威嚇(いかく)のため、独特な鳴き声(音?)を出します。(動画:手に持ったゴマダラカミキリ→クリック) (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 | ||
 |  |  |
2023年6月19日(月) ナゾの巨大植物! 体育館脇の上小花壇の一角に現れた巨大な植物。ビロードモウズイカという帰化植物(もとは外国の植物で、日本に持ち込まれて野生でも育つようになった植物)で、大きさは2mほどになるものもあります。上小でもときどき、姿を現します。ふつうにタネでふえるそうですが、そのタネの数は多く、一株のビロードモウズイカで10万個以上、そしてそのタネは10年、場合によっては100年以上発芽能力を保ち土の中で発芽に適した状況になるのをじっと待つのだそうです。人間に気づかれずに、土の中には発芽(はつが)を待つタネがたくさんあるのです。ですから、一見何もないように見える場所から、突然ビロードモウズイカが芽を出し、一気に大きくなることがあるようです。葉は柔らかく、表面に細かな毛がたくさん生えていて、さわるとまるでベルベット(ビロード)のような肌触りで、名前もそれに由来すると思われます。 (画像と情報:スタッフのつとむ) | ||
 | |
 | |
 |  |
2023年6月16日(金) ライポン! オザキフラワーパークにあるラベンダーの花に、モフモフの黄色いハチがいました。コマルハナバチのオスです。地域(ちいき)によって、昭和の子どもたちは、「ハナマルキバチ」「キバチ」「キグマ」などと呼んでいたようです。ネット情報(じょうほう)では、目黒区、大田区、品川区などではこのコマルハナバチのオスを「ライポン」と呼んでいた、とあります。いえいえ、ここ上石神井小学校の昭和の子どもたちも「ライポン」と呼んでいましたよ。刺さないハチとして知られ、休み時間になると、花だんの花にやってくる「ライポン」をつかまえて、手に乗せたり、やさしく手で包むようにして持ったりして遊んだものです。ハチの毒針(どくばり)は、産卵管で、メスにしかありません。つまりオスのハチは針を持たないため刺さない(刺せない)のです。このコマルハナバチのメス(最下段右)は体が黒く、オスとは体の色が全く違うため見分けやすく、オスを「ライポン」としてつかまえてペットのようにして遊んでいたのです。やさしく包むようにして持った「ライポン」は逃げようとして手の中で飛び回ります。その時の羽ばたきの感触は独特のものです。ただし、くれぐれもメスのコマルハナバチには手を出さないよう! (画像と情報:スタッフのつとむ) | |
 |  |
2023年6月1日(木) きれいに並んでるね。 大きくなりすぎないようにと、低い場所まで幹(みき)を切りつめたクヌギ。幹のとちゅうからたくさんの新しい枝(えだ)を出しています。そんなクヌギの葉に、てんとう虫の卵(たまご)がきれいに並んで産み付けられていました。 (画像と情報:スタッフのMさん) | |
 |
2023年5月22日(月) ミズカマキリをみつけたよ!! 22日(月)に3年生のヤゴ救出が行われました。たくさんのヤゴにまじって、こんなものがとれました。ミズカマキリです。水の中をゆうゆうと泳いでいるところをカゴですくいました。ミズカマキリは、カメムシの仲間で、全国の水田、池や沼、自然ののこっているプールにもいることがあるそうです。県によっては準絶滅危惧種(じゅんぜつめつきぐしゅ)にもなっているようです。上小のヤゴ救出の時に見つかったのは、20年ぶりくらいでしょうか。本当にひさしぶりの再会です。前足から尾までを計ると10センチをこえます。するどい前足で小魚などのえものをとらえ、口でからだの中に消化液(しょうかえき)を入れてとかしてすいます。このように小動物のえいようをとって水中(上)にくらしているコンチュウはほかにどんなものがいるのか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |
2023年5月17日(水) 地上のツバメ 初夏らしい気候になって、あちこちでツバメが飛ぶ姿を見かけるようになりました。上小のプールでも水を飲むために水面ぎりぎりを飛ぶツバメを見ることができます。今日はそんなツバメにまつわる植物の紹介です。写真はセリバヒエンソウ。上小のいろいろなところで見ることができます。その名前ですが、葉が植物のセリに似ているため「セリバ」、ヒエンとは漢字では「飛燕」と書きます。花の形を飛んでいるツバメ(燕)に見立てたものだそうです。休み時間などに見つけてみましょう。花の形、飛んでいるツバメに似ているかな? (画像と情報:スタッフのつとむ) |
 | |
2023年5月3日(水) 石神井川が面白い! 5月に入り、水温もだいぶ上がってきたのか、アブラハヤが産卵(さんらん)のために集まっているのを観察することができます。上石神井団地近くの右岸の新しくできた公園?の上流側の階段を降りて柵に沿って少し下流側に歩いたあたりで川をのぞきこむと、8cmほどのアブラハヤが群れになっているのがわかります。アブラハヤはこの時期に、砂礫底(されきてい)あるいは砂泥底(さでいてい)といった産卵に適した場所にオスが群れ、そこにメスがやってきて産卵するようです。ぜひこの機会に観察してみてください。そうして川をながめていると、目の前をコサギやカワウが通過したり、カワセミが勢いよく通り過ぎるのを見ることもできます。 (情報と映像:スタッフのつとむ) |
 |
2023年4月23日(土) ホオノキの花 上石神井いこいの森(上石神井4丁目)で、ホオノキの花が咲いていました。白い大きな花で、直径が15cmほどもあります。花の中央には、雌蕊(めしべ)と雄蕊(おしべ)が集まったものが目立ちます。上部が雌蕊が集まったもの、下の方が雄蕊(おしべ)の集まりです。蕾(つぼみ)はろうそくのほのおのような形をしています。花が咲き終わって花びらが落ちると、筆のような形の雌蕊(めしべ)が残ります。葉もとても大きく、幅10〜25cm、長さ20〜40cmほどになります。葉にこうじ味噌を乗せて炭火で焼く朴葉味噌(ほおばみそ)は岐阜県高山の名物です。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
 |
2023年4月22日(土) ツツジ ・ サツキ クイズだよ! 道路ぎわに庭先に、ツツジやサツキがきれいにさいています。花の色も、こいピンク、うすいピンク、むらさき、白、赤、オレンジ・・など目にあざやかです。 ここでツツジとサツキを見分けてみましょう。 左右どちらがツツジでしょうか、サツキでしょうか?(花の大きさやおしべの数がポイントになるかも) (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
 | |
2023年4月13日(木) やってくるかな?!ジャコウアゲハ 神学院のフェンス沿いにはジャコウアゲハの食草であるウマノスズクサが何株か生えています。草刈りの時に刈り取られてしまわないように、昨年、神学院にお願いして、植物名を書いた札を付けさせてもらいました。ウマノスズクサは冬には地上部は枯れてしまいますが、根が残り、春になると新しい芽を出してつるを伸ばします。今年はすでに直径6mmほどの立派なつるが育っています。この辺りではあまり姿を見かけないジャコウアゲハですが、食草に卵を産みにやってきてくれるでしょうか?産卵する成虫を見かけたり、幼虫を見つけたら探検隊に報告してください。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 |  |
2023年4月12日 菜の花なかまたち 菜の花とは、アブラナ科アブラナ属(ぞく)の花の総称(そうしょう)で、春に咲く黄色い花です。キャベツやハクサイ、ブロッコリーなどもアブラナ科の野菜です。写真左はハクサイの花、右側はキャベツの花で、どちらも菜の花ですが、びみょうに花の色合いが異(こと)なります。(クリック→拡大) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 | |
2023年4月3日(月) どんな花が咲くのかな? 上小には何本かクワの木が植えてあります。そのクワの木、ツボミをつけ始めました。どんな花が咲くのか観察してみてください。花が咲いたあと、初夏には実が赤黒くじゅくし、甘くなります。 |
 |
2023年3月31日(金) ツクシが出たよ~ 春のおとずれがたくさん見られるようになってきましたね。ツクシもひょっこりと顔を出しています。ツクシが出たあとにムクっと出てくるスギナも、右のほうに見えますね。仲良くならんだツクシとスギナ、学校で観察ができるのはめずらしい事なんですよ。4月から始まる新しい学年でも、たくさんの発見をして、友達や先生におしえてあげましょう。(東側通路花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 | |
 |  |
2023年3月30日(木) 紫色のじゅうたん! ムラサキハナナが見ごろです! 場所は上小西門を出て上中のグラウンドに沿って西に向かい200mほど行った右側です。たくさんの花が咲いて、まるで紫色のじゅうたんをしいたようです。ムラサキハナナは和名をオオアラセイトウといい、ショカッサイという別名もあります。 今が花の盛りです。サクラの花見も良いですが、ぜひ一面の紫色を見に行ってください。(画像をクリックすると拡大します) 道案内→クリック ※私有地(個人の土地)ですので、勝手に入ったり、花を摘んだり踏んだりしないようにしましょう。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 | |
 |  |
 |  |
 |  |
2023年3月14日(火) 春がいっぱい! 石神井川沿いのソメイヨシノもさき始めました。川岸には流れ着いたショカッサイ(ムラサキハナナ)のタネが芽を出して花をつけていました。コサギはすっかり夏羽になっていました。二本の冠羽(かんう/かんむりばね)や、背中の飾(かざ)り羽がとてもきれいです(拡大→クリック)。不思議とハシブトガラスの後ろ姿(すがた)にも春を感じます。ペアのヒドリガモ(拡大♂、拡大♀)がのんびりと水面で餌探しです。カワセミが大きなアブラハヤをつかまえて飲みこもうとしていました。(→動画) (画像と情報:スタッフのT) | |
 | |
 |  |
 |  |
2022年3月9日(木) サクラがさき始めましたね~ 善福寺公園のサクラです。ソメイヨシノなどに比べて季節的には少し早く咲いているので、品種が同定できるかと思って、様々な部分を撮影してみて、家に戻って調べてみましたが、品種の同定に至りませんでした。まぁ、春がもうそこに来ているということで。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 |  |
2023年2月28日(火) 花粉が作る「にじ」!? 日本列島が高気圧におおわれ、温かい空気が南から流れ込み一気に気温が上がったこの日は春がやってきたことを実感させる一日となりましたが、同時にスギ花粉も飛び始めたようです。今年は例年よりかなり花粉の量が多いとの予想通り、太陽を見上げると空気中の花粉の粒子(りゅうし=小さいつぶ)によって太陽のまわりに虹(にじ)のような光の輪(花粉光環=かふんこんかん)を見ることができました。花粉症の人にはつらい季節の始まりでもありますね~ ★太陽を直接見ると目をいためます。写真のように電信柱、建物などで太陽自体をさえぎった形で観察しましょう。 (28日・上石神井にて) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 |
2023年2月8日(水) 梅の花が咲いたよ! 図工室側から出て手前(西側)の梅に、一番最初の梅の花が見つかりました。いつも見ているので、多分、今日開花したばかりだと思います。 2023年2月8日に目撃しました。白くて、まだまだつぼみがいっぱいのあります。「2月下旬頃から見頃を迎える梅スポットがあるかもしれません。」と、インターネットに記載されているので、多分上小も2月下旬ごろに、満開になるでしょう。なお、調べたところ、今年は暖冬傾向なので、例年より満開時期が早まると思います。(校庭の梅の木にて) (画情報:3年生隊員のSくん) |
 |
2023年2月2日(木) 暖かくなるのが楽しみだね 冷たい風がふきぬけるたび、子供たちは『さむい〜!』とさけぶ一日でした。トンボ池に入った葉や枝(えだ)をカブクワハウスに立てかけてあったアミですくいあげていると、アミのすみに小さなカマキリの卵嚢(らんのう)を見つけました。池の水が少しかかってしまいましたが、二年生が指(ゆび)でつついても、しっかりとアミにくっついていたので大丈夫。この中から数えきれないほどのカマキリが出てくるのは、皆さんが次の学年へと進級して過ごしている4月から5月ごろです。それまで、野鳥などのごちそうとなってしまう卵嚢もありますが、ここでなら安心。春が楽しみだね! (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |
2023年1月25日(水) おいしいえさはいないかな?! 冬は野鳥(やちょう)の観察がしやすい季節(きせつ)です。大好物の虫はいないかな?とキツツキの仲間のコゲラが元気な姿(すがた)を見せていました。つついた穴(あな)の中をのぞきこむ目がしんけんです。(校庭の梅の木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |  |
2022年12月12日(月) 東門で出会えるよ~ まばゆい冬のひざしにさそわれるようにして、ミツバチが仲間と一緒におとずれていました。他にもハナバエやアリ達が、陽だまりに咲いたヤツデの花に夢中になっていました。 (左:9日・東門花だんにて) 樹木の手入れをしてくれる剪定(せんてい)屋さんが、野鳥たちのために残してくれた柿、ようやく熟してきたようです。2羽のメジロのかわいい鳴き声で気がつきましたよ。 (右:12日・東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年11月30日(水) 落ち葉じゃないよ! もしかしたらさなぎのまま冬をこすのかな? そう思いはじめていたルリタテハが、無事に羽化していましたよ。11月2日に観察してから4週間目、羽化は1週間後と思っていたので、ずいぶん時間がかかりましたが、これから寒い冬をこすのですから、何か理由があるのかもしれませんね。翅(はね)を広げると美しいるり色の模様(もよう)は、閉(と)じているとかれ葉のような、または樹皮(じゅひ)のような色あいです。『さぁて、飛んでみようかな』小刻(こきざ)みにふるえていたルリタテハでしたが、目をはなしたすきに元気にまい上がったようでした。(東門通路にて) カサカサと音のするかれ葉の上を歩いていると、サクラの葉ぐらいの大きさのクロコノマチョウが飛び立ちました。落ち葉がしきつめられた場所がお気に入りなのでしょうか、さほど遠くにはいかずに近くへとまい降ります。『とっても上手にかくれているでしょ!』と自信たっぷりのようですね。クロコノマチョウの幼虫はススキやジュズダマ、チヂミザサなど、上小ではよく見かける植物を食草としていますが、その姿(すがた)は目で確(たし)かめたくなるくらいすごくカワイイのです。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年11月17日(木) ハッとする出会いと、ワッとうれしい発見! ヤツデの花にハナバエやたくさんのアリがおとずれているなか、エメラルドグリーンの目がひときわ目立っていたモチノキハマダラミバエ。名前にあるとおり、モチノキの実の中に卵を産み、孵化(ふか)した幼虫はその中で実を食べて育つそうです。(校舎裏にて) 見つけた! オオカマキリの卵嚢(らんのう)は、アジサイのくきにありました。この中に4㎜ほどの小さな卵が100〜300個(こ)も入っているなんて、すごいですね。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年11月7日(月) じゃまをするつもりはないけれど… 学校の敷地(しきち)にある樹木(じゅもく)は、ときどききれいに整えて、健康に育つように管理されています。今日はたくさん実をつけたカキの木を切らなくてはならず、作業にきてくれた職人さんも、カキの実を食べに来ているメジロたちの様子に、枝(えだ)を切るのをためらっていました。(東門花だんにて) オオハナアブがヤツデの花にやってきていました。さわりたくなるような体毛や、複眼(ふくがん)の模様(もよう)に見入ってしまいます。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年11月2日(木) 芸術の秋 ルリタテハが蛹(さなぎ)になっていました。観察すればするほど、蛹の色や形、こまかな模様(もよう)に引きこまれてしまいます。芸術(げいじゅつ)の秋にふさわしい美しい蛹が観察できるのは一週間ほどです。(東門通路にて) 『左右確認、よし、だいじょうぶそうだ!』とカナヘビが草から顔を出し様子をうかがっているようですが、上からのぞく天敵(てんてき)には油断(ゆだん)しています。ウフフ。もうそろそろ冬眠(とうみん)にはいりますが、お腹をすかせた野鳥が一番の天敵となるようですから気をつけて過(す)ごせると良いですね。このあとやっと人間の気配に気づき、一目散ににげていきました。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月31日(月) ルリタテハの幼虫を育てたホトトギス 翅(はね)に美しい瑠璃(るり)色が見られる蝶(ちょう)、ルリタテハの幼虫が蛹(さなぎ)になろうとしていました。お尻に白い糸座(いとざ)とよばれるものが見えます。糸座は口から吐(は)いた糸を枝などにしっかりとつけたもので、ここにお尻を固定します。糸座にお尻をくっつけたあとは、体を少しのばし前蛹(ぜんよう)となっていました。このあと脱皮(だっぴ)をしてチクチクしている皮をぬぎ捨(す)てます。(東門通路にて) ルリタテハの幼虫はホトトギスの葉を食べて大きくなりました。花にはミツバチをはじめ、いろいろな仲間たちがやってきます。日本の固有種(こゆうしゅ=その地域にだけにあるもの)であるホトトギスはとても育てやすく、見る人を楽しませてくれるユリ科の植物です。(東門通路にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年10月28日(金) 秋の日の暖(あたた)かな場所 体操着(たいそうぎ)に着がえた子供たちが『さむ〜い!』と言い放ちながら校庭へ出てくると、すぐさま『あったけぇ〜!』と太陽に向かってさけんでいました。クビキリギスもちょうど草地から出てきて、じっとしていました。やっぱり『あったかぁ〜い!』と暖かさを感じていたのでしょうか。(トンボ池にて) 野鳥レストラン、ハナミズキの赤い実が野鳥を呼(よ)び寄(よ)せています。この時期になるとやっくる冬鳥のジョウビタキも、この赤い実を丸のみしてしまうほど大好きなのだそうです。でも、この実は私たち人間が食べるとお腹(なか)をこわしてしまうそうですから、口には入れないでね。(東門花だんにて) 昨日の蛹(サナギ)が気になって、キイロテントウを探してみると、すぐに見つけられました。まだ元気に活動中のようですが、これからもっと寒くなると、仲間たちと寄(よ)りそったりしながら、冬でも葉をしげらせている常緑樹(じょうりょくじゅ)の葉などで過ごしているようです。キイロテントウが集まっている様子、見てみたいですねぇ。(駐車場花だんにて) 小さなホコリかな、、いや、ちがう。そっと指先でツンツンとしてみると。ほら、やっぱり! これはクサカゲロウの幼虫で、よく見るとハサミのような顎(あご)を使って、キイロテントウの幼虫をとらえていました。キイロテントウの幼虫は、エサの菌が少ないせいか、通常の半分くらいの大きさです。どうやって食べようとしているのか、クサカゲロウの幼虫は獲物(えもの)を上下にゆさぶっていましたが、それよりも背中にのせたカモフラージュのゴミをどこで集めてきたのでしょうか、とても気になります。(キイロテントウがいた駐車場花だんの桑の木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月27日(木) 探(さが)してみよう! 中休みにおにごっこをしていた男の子たちが『わぁ!きれい』と声をあげたススキ。こんな所にあったんだとおどろきをかくせない様子でした。しげしげと観察をしながら『フワフワ!』『軽い!』などと感想を言いあっていましたよ。校庭の奥まった場所にあるヒミツの楽園はどこにあるかわかったかな? バッタも見かけるちょっとした草地、天気が良ければススキが白銀にかがやいているよ、見にきてね。(体育倉庫わきにて) 焼きとうもろこしのような蛹(さなぎ)をおぼえていますか? 梅雨時期の6月ごろ、桑(クワ)の葉では卵から幼虫、蛹、成虫とすべてを観察することが簡単(かんたん)だったキイロテントウ。秋も深まり、そろそろ桑も葉を落とすだけとなっているので、羽化までだいじょうぶかしらと心配がよぎるかもしれません。でも蛹の期間は一週間ほど、なんとか落下せずに成虫となるようです。楽しみですね!(駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月26日(水) 秋の景色(けしき)… 見つけると宝ものを探しあてたかのようにうれしくなるカラスウリ、甘くておいしそうにも感じるけれど、残念ながら赤く色づいた実は苦味がでてしまっているそうです。でも色づく前の緑色の実を見つけたら、お漬物(おつけもの)や汁物(しるもの)に入れたりして美味しくいただくことができるそうですよ。ちなみに葉っぱも天ぷらや和え物にとありました。さて、どんな味がするのかな?ぜひ楽しんでみて下さい。(校舎裏にて) まばゆい秋の日ざしのなかで、ヤマトシジミ、キチョウにモンシロチョウ、それからウラナミシジミなど、なじみの蝶がうれしそうに集まって、仲間たちと楽しげにヒラヒラとまいはじめたり、翅(はね)を広げて日向ぼっこをしたり、美味しい蜜(みつ)に夢中になっていました。 太陽が顔を出すとウキウキと元気よくしているのは私たちと同じようですね。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月25日(火) 富士山が真っ白になりました! いつの間にか富士山がすっかり真っ白になっていました。(右) 先週の木曜日に写した写真(左)ではまだこんな感じだったのに・・・ 暦の上では23日~霜降(そうこう=霜がおりる頃)。どうりで寒いわけですね。 (とも上石神井にて撮影) (画像と情報:隊員のGママさん) | |
 |  |
2022年10月24日(月) 雨の日こそお出かけ! あっ、起きてる! あいかわらずのんびりしてるカタツムリが、今日は頭を出していました。しっとりとした雨が降(ふ)って、お出かけ気分になっているようです。(東門花だんにて) 大きなクモなので、危険(きけん)な毒(どく)グモだといわれてしまうジョロウグモ。たしかに毒はもっていますが、えものをつかまえたときにマヒさせる程度(ていど)のとても少ない毒なので、人には無害です。マヒをさせて動けなくさせると、食べたいときまで、糸でぐるぐるにしておくそうですよ。ちょっと見た目がこわいクモですが、観察したり調べてみると、楽しい発見がたくさんあるようです。(駐車場脇花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月20日(木) 快適(かいてき)に過ごすには… 咲き終えた花の手入れをしようと思ったら、1㎝ほどのカタツムリがいました。近くにもう一匹が同じように草花の上部にくっついています。どちらかといえば、頭をひっこめているカタツムリは、草花の根もとにいることが多いように思いますが、土から40㎝くらいの高さの場所もまだ草花に水分を感じているのなら、過(す)ごしやすいのかもしれませんね。みなさんはどう思いますか?(東門花だんにて) オンブバッタのメスをめぐって、オスたちがはげしく争うことはありませんでした。二匹のオスはえんりょがちにメスに近づいていて、メスの様子をうかがっているような感じです。なんだか不思議な光景は半日たってもあまり変わらず、カップルとなった二匹のそばで、じゃまをせずにいるオスが一匹と、もう一匹オスがふえて、距離(きょり)をあけながらも、カップルとなった二匹を少しはなれた場所で様子を気にしているようでした。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月19日(水) ショクヨクの秋! ナナホシテントウ。草のしげみのなかを歩きまわっているのを見かけますが、今日はコンクリートの上、暖(あたた)かな日ざしがあたる場所でじっとしていましたよ。(左:校舎裏にて) 秋といえば、食欲(しょくよく)の秋! ニホントカゲが何やら大きなごちそうをくわえて、物かげへとかくれました。そっと様子をうかがうと、プリプリの幼虫を見つけたようで、それを飲みこむように食べています。喉(のど)につまりそうな獲物(えもの)を丸のみするなんて、すごい食欲ですね。また手をつかわずにダランとさせて食べる様子は意外に感じました、リラックスして食事を楽しんでいるのかな。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |
2022年10月13日(木) イナゴがいたよ! 職員(しょくいん)玄関の前、巣箱をかけていたサクラの木がなくなると、今までとはまたちがう環境(かんきょう)になっているようです。イナゴ(ハネナガイナゴ?)がいました。目がきれいですねぇ。(正門付近) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |  |
2022年10月11日(火) 顔がふたつ!? ウラナミシジミ。後翅(こうし/うしろばね)には目と触角(しょっかく)に似た模様(もよう)と突起(とっき)があります、おもしろいですね。ふたつの顔を持つと、どんな良さがあるのかな?(左:東門花だんにて) お腹がふくらんでいるオオカマキリがいました。どこで産卵するのかな?(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月4日(火) ホワホワの白い綿(わた)のようなもの… シロオビノメイガ。夜間も活動するそうですが、昼間も元気です。最近よく見かけるので調べてみると、幼虫はアカザ、ホウレンソウといったヒユ科の植物などを幅(はば)広く食草にするようです。成虫は花のみつを吸います。(左:駐車場花だんにて) これはなんだろう?、1㎝くらいの綿の玉。調べてみると、このような綿の卵をつくる虫はコマユバチなのかもしれませんが、どうかなぁ?。ホワホワ感があるさわりごごちです。ふしぎだね。(右:職員室前花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年10月3日(月) 生きものたちの姿(すがた)に秋を感じます 羽化をすると長いきょりを移動して、夏の暑い時期を山で過(す)ごし、秋になるともどってきて姿を見せてくれるアキアカネ。上小でも見かける季節(きせつ)になりました。(左:校舎裏にて) 草地の手入れをしていると、アマガエルがピョンと飛びだしました。ビックリさせちゃたね。(右:職員室前花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月30日 秋の日ざしの中で… 最初はベダリアテントウかと思いましたが、ヨツボシテントウのようです。都市部では少ないということなので、めずらしいですね。幼虫も成虫もアブラムシを食べます。(左:トンボ池にて) コノシメトンボ。秋の日ざしをたっぷりあびながら過(す)ごしていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月29日(木) おっと、おどろかせてごめんなさい… ススキなどイネ科の植物を食草とするチャバネセセリの幼虫がいました。つかまえられたことがイヤだったのか、緑色の液体をペッとはきだしていました。元気に育ってね。(左:バッタ原っぱにて) ウェルカムボードにツクツクボウシの亡骸(なきがら)がありました。『ウェルカムボードのちょうど真下でコロンとしていたので、置いたんだよ』。職員(しょくいん)のIさんがていねいに葉にのせてくれているので、ぜひ観察してみてね。(右:職員玄関前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月28日(水) いい出会いがあったかな オンブバッタにとって、秋は繁殖期(はんしょくき)です。相手を見つけるにはひたすら探検!とばかりにピョンとはねていました。もしかしたら、おいしい草のしげみで出会えるかもしれませんね。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン、一生懸命(いっしょうけんめい)に求愛ダンスを見せてくれます。年に数回の繁殖期があるそうなので、ダンスはとっても得意(とくい)なのかもしれません。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月27日(火) いましたよ!、キセル貝 『 見つけたよ!』でKさんが教えてくれたキセル貝、探検隊の資材倉庫にいましたよ!それも4匹も壁(かべ)にくっついていました!!何かこの壁には特別な良さがありそうです。(左:トンボ池にて) ニホントカゲ。りっぱな体つきですね、大好きな日向ぼっこをしながら、ときどき舌を出し、においを感じとりながら過(す)ごしているようでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月26日(月) まるで綿(わた)みたい… なんだろう?クワの木で見つけたよ。(左上:東門花だん) アオバハゴロモの幼虫でした。フワフワのロウ物質(ぶっしつ)を出して、体を守るようにつけて過(す)ごしています。(右上:東門花だんにて) キイロテントウ。植物を弱らせてしまう白い菌(きん)で、葉につく『うどんこ病菌』を食べてくれます。どうやって菌を見つけるのかな?小さな体には不思議がたくさんありますね。(左下:バッタ原っぱにて) アメリカピンクノメイガ、ブッドレアにとまりました。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月22日(木) アサザの葉の上で休息する昆虫(こんちゅう)たち 大きなカマキリが狩(かり)をしようとハナトラノオを選んで獲物(えもの)を待っているようです。逆(さか)さまになりながらもポーズをきめて、じっと待ちかまえるカマキリは、まるでヨガをきわめた昆虫のようです。ウフフ(左:東門花だんにて) アオモンイトトンボ。かいぼり前と変わらないくらい池いっぱいにアサザの葉が広がり、黄色い星の花も観察できるトンボ池。いまは、ウォーターマットのようなアサザの葉の上で休息する、小さな生きものがあとをたちません。トンボにチョウ、バッタやアリまで、このウォーターマットの良さを絶賛(ぜっさん)しています。さまざまな種類の昆虫を観察するなら一家に一株、探検隊おススメのマットです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月21日(水) アオスジアゲハの幼虫発見! ササグモがごちそうを待っているようです。『狩(かり)のコツは『待ちかまえていませんよ』って感じをただよわせると良いんだよ』、ちょっと体をななめにしてじっとしている様子、そんなふうに言っているような気がしました。アハハ(左:東門花だんにて) 昨日の雨風のせいなのか、クスノキの下に落ちていた木片にアオスジアゲハの幼虫がいました。突起(とっき)の間に黄色の線が見えるようになってきたら、そろそろ蛹(さなぎ)になるころです。楽しみですね!(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月20日(火) 木登りだってできるんだよ! 見上げるくらい高い枝(えだ)に、アマガエルがのんびり過ごしていました。木登りが得意(とくい)なアマガエル、手足の先にある吸盤(きゅうばん)をつかって上手にのぼるようようです。(左:トンボ池にて) ツマグロヒョウモンの幼虫。食草のスミレの葉を求めて旅をしていたのかな?元気にオレンジ色のチョウになってね!(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月16日(金) 休憩(きゅうけい)中も用心用心… シオカラトンボ。日向ぼっこをしながらくつろいでいました。三年生ががんばって作ってくれたプールの新しい島の様子は見てくれたかな?トンボ池を中心にして、仲間たちがたくさんおとずれています。(左上:校舎裏にて) モンシロチョウ。サツマイモの葉がしげる日かげを選んで休憩(きゅうけい)をしていました。見ると触角(しょっかく)がゆるやかに曲がっています、触角はにおいを感じる鼻(はな)の役割をしていて、なかまのにおいをたしかめたり、空気のゆれなどを感じ、敵(てき)から身を守る時にも役立っているそうです。ゆるやかに曲がっていても、そっと人が近づくのがわかっているようでした。(右上:校舎裏にて) クロウリハムシ。ナデシコの花びらがハンモックなんてうらやましい。(左下:東門花だんにて) 緑のトンボ!?と思ったらクビキリギスが勢いよく飛んできました。りっぱな成虫で口のまわりが赤くなっています。強力なアゴを持っているので、飼育する場合は食事にかたいドッグフードをあげてもよいそうです。まだ小さな個体だったら金魚のごはんかな?イネ科などの植物も食べますが、雑食性なので自然の中では小さな昆虫なども食べているそうです。教室で飼育(しいく)して観察する時に参考にしてみてね。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月15日(木) 姿(すがた)の変化も見てね! キマダラカメムシの幼虫。成虫になるまで衣装(いしょう)がえするみたいに変化を見せる、オシャレなカメムシです。(左:校舎裏にて) ヒラタアブの仲間(ミナミヒメヒラタアブ?)。アメリカタカサブロウの花にやってきていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月14日(水) てんとう虫も眠(ねむ)りから覚めて活動開始! 明日は三年生が手作りの島をプールにうかべて、トンボを呼ぶ準備をします。プールに浮かべる前の、こんもりとした草の島から、まだ小さなエビガラスズメの幼虫を見つけました。大好きなルコウソウの葉へと移(うつ)しました。(左上) 写真の向きをかえていますが、大きなカマキリは逆(さか)さまになって、プラタナスの仲間にいます。おくに見えるのは中校舎(なかこうしゃ)で、子どもたちは授業中です。(右上:西側通路にて) ヒメカメノコテントウ、植物を弱らせてしまうアブラムシを食べてくれます。夏眠(かみん)といって、落ち葉の下など涼しいところで眠っていたてんとう虫、そろそろ動き始めているようです。(左下:校舎裏にて) アシタバのハンモックで、のんびりと過ごすキアゲハの幼虫がいました。そろそろ蛹(さなぎ)になるころでしょうか?楽しみですね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月13日(火) 親子じゃないよ! 親子のように見えるけれど、仲良しカップルのオンブバッタ。大きい方がメスのバッタ、これからたくさんの卵をうむからオスよりも大きいのかな?他にもメスの方が大きい昆虫(こんちゅう)はたくさんいるよ。(左:プール裏にて) 写真の向きを変えていますが、コンクリートのかべにピッタリくっついていたキハラゴマダラヒトリ、あるいはアカハラゴマダラヒトリかもしれません。翅(はね)にかくれている腹部背面などで、キハラ(黄)かアカハラ(赤)かがわかります。そっと指を差し出すと手にのってくれたり、死んだふりが得意(とくい)だと言う人もいるんですよ、役者さんですね。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月12日(月) 仲良くしようね! ときどき、種類のちがう昆虫がいっしょにいる時があります。ヨメナの花の蜜(みつ)を楽しむヤマトシジミのそばで、カスミカメムシの仲間がいました。何かおしゃべりをしているのかもしれません。(左:東門通路にて) ヨツモンカメノコハムシの成虫。たいてい、じっとした姿(すがた)で見かけます。触角(しょっかく)を見せてもらおうとトントンとおこしてみたら、びっくりして飛んでいってしまいました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月9日(金) ビックリしないでね! わぁ〜すごい!大きなカマキリ。コムラサキシキブの葉の上で待ちかまえています、忍びよってガッツリとらえる、狩(か)りの上級者の風格(ふうかく)がただよいます。(左上:校舎裏にて) トイレに入ろうドアを開けると一匹のカマドウマがいました。思わず『キャ〜!!』と悲鳴(ひめい)をあげてしまいそうです。湿気(しっけ)の多い場所が好きなカマドウマ、元気よく飛びはねますが(ここも悲鳴のポイントですねぇ)つかまえやすく、やさしそうな顔をしているなどと、観察はしやすいです。(右上:南校舎1階トイレにて) オンブバッタ。体色を環境(かんきょう)にあわせて変えられるなんて、おもしろいね。でも、すぐにはムリだから、ときどき目立ってしまうかも。ちょっと不満げな目になっているような…ウフフ。(左下:東側通路にて) 昨日あたりからクマバチとミツバチが花の蜜(みつ)集めにせっせとおとずれています、気をつけなければいけない種類のハチもいますが、上小におとずれている、たいていのハチは人を刺すことよりも、花の蜜や獲物(えもの)を探すことに夢中になっているので、あわてず、さわがす、じゃまをしないようにしていればだいじょうぶです。どんな花が好みなのか観察してみましょう。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月8日(木) 雨がやむと… 雨がやみ、ヤマトシジミが翅(はね)を広げていました。(左:校舎裏にて) 草のしげみをピョン!オンブバッタでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月7日(水) 不思議な生きもの発見! 「さわがないでっ!『し〜っ』」ってことかな? ズボンについていたモンクロシャチホコの幼虫。幼虫は桜などの葉を食べて、大きくなると地上へおりて蛹(さなぎ)になります。無害なのであわてなくて大丈夫です。(左上:幼虫がいたのは中庭の桜のようです) 雨が降(ふ)り出しました。モンシロチョウはどこで雨やどりをするのかな?(右上:校舎裏にて) おもしろい虫みつけたよ、なんだろう。(左下:校舎裏にて) おもしろい虫の正体は、ヨツモンカメノコハムシの幼虫でした。かたそうな石のような傘(かさ)は、自分の糞(ふん)と脱皮(だっぴ)した皮のかたまりなのだそうです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年9月6日(火) 大きなごちそう オミナエシにひそんでいたアズチグモ。ヤマトシジミをとらえて、がっちりとはさみこんでいました。(左:駐車場花だんにて) エノキワタアブラムシ。エノキにつく、2㎜ほどのアブラムシ。じっと観察していると、小さなホワホワのワタが動いたり飛んだりしています。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月5日(月) 葉のしげみの中で… アオドウカネ。葉のしげみの中で上手にかくれているつもりのようです、フフフ。(左上:校庭西側花だんにて) イトトンボの仲間。葉のしげみの中でのんびりしてました。 (右上:東門脇通路にて) 自分の体より大きな獲物(えもの)をとらえるのがとくいなアズチグモ。前脚(まえあし)を広げながら待ちぶせをしているようです。(左下:東門花だんにて) ハエなどの小型の昆虫(こんちゅう)をねらうササグモ。ルドベキアの花にて、ごちそうの獲物をまっているようです。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月2日(金) 雨の中でも活動中! クモヘリカメムシ。イネを食害するそうですが、上小ではイネ科の植物が広がる草地で見かけ、近づくとヒョイヒョイとすばやくにげてしまう感じです。草地のアメンボみたい。(左上:校舎裏にて) メドーセージ(サルビア・グアラニティカ)にアメリカピンクノメイガがいました。花びらがパラソルとなって、居心地(いごこち)が良さそうですね。この花はアメリカピンクノメイガの食草でもあります、探(さが)すと幼虫がいるかもしれません。(右上:東門花だんにて) クロウリハムシ。今日はたくさん雨のしずくをつけて探検(たんけん)中です。ジンジャーリリーの甘い香りがただよう場所で、花がらに身をよせていました。(左下:西側フェンス沿いにて) ナミアゲハの幼虫。今日は一日、雨が降(ふ)り続きました。こんなにぬれてカゼをひかないのかしら?と見ているほうがくしゃみをしてしまいそうでしたが、モリモリ食べて元気に育ってね。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年9月1日(木) 自然は生きものたちのレストラン ササグモ。巣を作らずに草のしげみなどにいて、えものをつかまえます。脚(あし)の毛がよく目立ちます、移動(いどう)するのに便利そうですね。(左上:校舎裏にて) ノゲイトウの花の蜜(みつ)を楽しむヤマトシジミ。(右上:東門花だんにて) ヒラタアブ。暑さは苦手だったのかな?久しぶりに会いました。幼虫の時はアブラムシなどを食べてくれ、成虫となると、植物の受粉(じゅふん)を手伝ってくれます。(左下:校舎裏にて) ヒメジオンの花の上でくつろぐダイコンサルハムシ(ダイコンハムシ)がいました。名前にあるとおり、ダイコンの葉っぱが大好きなハムシです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年8月31日(水) 夏休み終了!子どもたちに会えるぞ! 夏休みはどんな思い出がつくれましたか?上小では小さな生きものが、毎日元気に過ごすようすが見られました。その中でも上小での観察はめずらしいハグロトンボが、夏休み中も川辺に行かずに過ごしていました。(左上:中校舎裏にて) 夏休み中もさらに活発になっていた、たくさんの小さな生きものたち。中でも探検に夢中になっていたのはモグラのようで、いろいろな場所で通ったあとが見られました。手前にある穴(あな)は、かくにんのために手で土をよけた穴ですが、小さくなって探検してみたくなるようなワクワクするトンネルが続いていました。(右上:トンボ池にて) ニホンカナヘビ。今年もたくさん生まれているようで、小さな幼体が元気にすがたを見せてくれています。かわいいね。(左下:校舎裏にて) 新学期が始まり、校庭で最初に出会えるのはトンボか、このクビキリギスかもしれませんね。夢中になってつかまえると、おどろいてかむこともあります。生きものをつかまえて観察したいときには、そっとやさしく、つかまえてみてね。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフの澁谷さん) | |
 |  |
2022年8月24日(水) 花は生きものたちの良いエサ場 キンカンの花にヤマトシジミがやってきました。少し翅(はね)を広げてみたりしながら、花の蜜(みつ)に夢中(むちゅう)になっていました。(トンボ池にて) アズチグモ。ランタナの花の蜜を吸いにやってくるこん虫をじっとまっているようです。見た目からは想像(そうぞう)しにくいですが、体よりもずっと大きな獲物(えもの)をつかまえます。(トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月23日(火) トカゲの舌(した)の秘密(ひみつ) 真正面から見たイチモンジセセリ。幼虫の食草はススキやエノコログサ、イネなど植物なので、上小でも幼虫のようすをかんたんに観察できそうですが、なかなか気づきにくいようです。(左:校舎裏にて) ニホントカゲの幼体。ひっきりなしに舌を出し入れしていました。これは口の中ににおいをかぎわけるところがあって、2つに分かれた舌(した)ににおいをつけ、口の中の左右にある、においをかぎわけるところ(ヤコブソン器官)にもっていくからだそうです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月22日(月) 葉の上のちっちゃなバナナ? ツマグロオオヨコバイ(ニックネームはバナナムシ!)の幼虫。近よると、横へと移動(いどう)しながら葉のうらにかくれたりしますが、その場でユサユサと左右に体をゆらしているバナナムシがいました。目かニコニコ、なんだか楽しそう! 成虫となったバナナムシ(ツマグロオオヨコバイ)。幼虫の時と同じ、草木の汁(しる)を吸います。(2枚ともに校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2022年8月19日(金) どこでだれに会えるかな!? ただ今、自慢(じまん)をしたいくらいに、上小のどこを歩いてもトンボに会えます。シオカラトンボも『そうだねぇ〜』と言っていると思うよ。(左上:校庭にて) オンブバッタ。体色がまだらになっているね、どんな場所で過ごしていたんだろう?ヒミツかな。(右上:バッタ原っぱにて) アカマエアオリンガ(夏型)。15㎜くらいの小さなガです。カイズカイブキの葉の上にとまりました。こぼれおちそうな大きな目、まわりの景色はどんなふうに見えているのかな?(左中:トンボ池にて) あれ?作業着にくっついてきた小さな幼虫。だれだかすぐにわかったよ、セスジスズメだね。りっぱに育つとカッコイイ新かん線のようなんだよね(8月8日観察)。食草のヤブガラシにうつしたよ。(右中:校舎裏にて) ミスジミバエ。目の色がエメラルドグリーンらしいのですが、つやのある翅(はね)がきれいでした。幼虫がウリの仲間などに被害(ひがい)を与えるため、農家さんなど野菜を育てている人にとっては迷惑な昆虫なのだそうです。(左下:校舎裏にて) さわるとかゆみや皮膚炎(ひふえん)を起こしてしまう毒針毛(どくしんもう)のあるタケノホソクロバの幼虫。成虫となると無毒ですが、食草のササ(または竹など)で幼虫を見つけたら、ぜったいにさわらないでね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月18日(木) 姿(すがた)を大きく変化させるよ! キマダラカメムシの幼虫。たえまなく触覚(しょっかく)をブルブルとさせていました。孵化(ふか)後、幼虫から成虫になるまで、体色にはっきりとした変化が見られます。オレンジ色の点は、成虫に変化するのが近づいた段階の幼虫に現れます。(左:校舎裏にて) キハラゴマダラヒトリ。白くてオシャレな蛾(が)になるなんて思えないくらい、幼虫は毛むくじゃらです。幼虫の食草はクワやサクラの他、いろいろな葉を食べますが、成虫になると口先が退化して何も食べなくなるそうです、ふしぎですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月17日(水) よく観察してみよう! テングスケバ(天狗透羽)。幼虫(8月12日観察)から成虫となると、天狗(てんぐ)のようにみえる頭の先が、さらにりっぱになったようです。他にも幼虫とはちがうところ、見つけてみてね。(左:校舎裏にて) 雨がふりはじめ、キチョウ(キタキチョウ)が雨やどりをはじめました。年に5、6回発生し、成虫のまま冬ごしします。幼虫の食草はネムノキ、ハギ類などのマメ科の植物です。(右:中庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |   |
2022年8月16日(火) 幼虫もがんばっているね アカサシガメの幼虫。まだ小さな翅(はね)が、洋服のベストのようですね。幼虫も小さなこん虫をつかまえて、ストローのような口で体液をすいます。(左:校舎裏にて) クビキリギスの幼虫。成虫は口のまわりが赤くなります。幼虫も成虫と同じように強いアゴをもっていて、イネ科などの植物のほかに、かたい植物のくきや、昆虫もつかまえて食べます。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月15日(月) オッと見つかっちゃったぜ! 水辺から元気にジャンプしていった小さなカエルたちが、ドキドキの旅をはじめて2ヶ月ほどたちました。かぞえきれないほどいた、たくさんの仲間たちはパッタリと姿を見せなくなり、本当に生きのびるのは全体のごくわずかなんだなぁと、あらためて感じていました。今日は草地の手入れをしていると、ひさしぶりに元気な姿を見せてくれましたよ。 成長したヒキガエル(アズマヒキガエル?)の体長は4㎝ほどでした。まだまだ小さいけれど、りりしくなりましたね。(2枚ともに東側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2022年8月12日(金) 暑くても生きものがたくさん! 強風がふいていた朝、舞(ま)うのが少し大変なようすのナミアゲハがいました。しばらくすると、翅(はね)を休ませにおりてきました。(左上:トンボ池) イチモンジセセリ。ちょうどよい場所を見つけたのかな、朝日をあびていました。(右上:トンボ池) コバネイナゴ。おもにイネ科の植物を食べるバッタのなかま。佃煮(つくだに)などにしておいしくいただくようですが...(左中:東門わき通路) こんな顔をして、何かをお願いするように前脚(まえあし)を合わす姿(すがた)を見たら...なかなか食べる気になれないですね。(右中:東門わき通路) 石ころにまざって、カタツムリがころがっていました。殻(から)の中が乾燥(かんそう)しないよう、膜(まく)をしっかりはって夏休み(夏眠/かみん)中です。(左下:東門花だん) テングスケバの幼虫。バッタににているね。成虫には、セミのような翅(はね)ときれいな色のストライプもようがあるんだよ。(右下:東側通路) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月10日(水) この植物を食べるのは? 東門を入ると出むかえてくれるサルスベリ、ただいま青空にむかって満開中です!(左:東門にて) 道路のわきから出てくる草には、ヤマトシジミが好きなカタバミ、バッタがよろこぶエノコログサなどありますが、こちらはスベリヒユ。さて、だれが食べるか知っていますか?。こたえは、人間!。日本では山菜、海外ではハーブ、野菜として、おひたしやサラダにしていただきます。栄養もバツグンなんですよ。(右:東側通路にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月9日(火) 見分けられるかな? ミスジチョウの仲間のちがいは、前翅(ぜんし/前側のはね)の白いラインで見わけます。上小ではこのコミスジとホシミスジが見られます。(左:校舎裏にて) アゲハの幼虫、種類はわかるかな? ヒントはミカンの葉にいたよ。(右:西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月8日(月) 休憩(きゅうけい)中かな!? ヤブガラシにセスジスズメの幼虫がいました。あざやかな黄色からオレンジ色の眼状紋(がんじょうもん/目のように見えるもよう)や先の白いアンテナのような尾角(びかく)があります。(左:校庭花だんにて) ミソハギの花にもたれかかるように、じっとしているヤマトシジミがいました。あまりにも動かないので、そっと茎をうごかしてみたり、やさしく指でツンツンとつついてみると、やっとパタパタと飛びました。蜜(みつ)を吸っているうちにねむくなっちゃたのかな?そんなことってあるのかな?ウフフ(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月5日(金) 見て見て!きれいでしょ! アメリカピンクノメイガ。幼虫の食草となるサルビア(一般的な名称はメドウセージ)にいました。ちなみにうしろでぼんやり写るるのはカメムシのなかま(幼虫)です。(左:東門花壇にて) ミドリグンバイウンカ。5㎜ほどの小さな虫ですが、蛍光(けいこう)色のような体色で目をひきます。今年はいろいろな場所でよく見かけます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月4日(木) だれが何を食べているのかな? いろいろな植物の葉を食べるスグリゾウムシ。今日はベニカナメモチの葉をおいしそうに食べていました、今まで犯人がわからなかったのですが、だれのしわざなのかやっとわかったゾ。(左:西側通路にて) イトカメムシ。ふだん植物を食べていますが、時にはアブラムシを捕食するそうです。今日はアブラムシよりも大きな昆虫を捕まえていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月2日(火) 羽化したトンボ、ネットの外の広い世界に コスカシバ。すけている翅(はね)や、腹の先にあるブラシのような毛、不思議がたくさんありますね。幼虫はサクラやウメなどの樹皮(じゅひ)の下に入って樹木を弱らせてしまうので注意も必要のようです。(左:校舎裏にて) 田んぼエリアにネットを張ってもらいました。これで野鳥や小動物がおじゃますることなく、安心してイネが育つようです。今日は田んぼゾーンですごしていたシオカラトンボのヤゴが羽化して、ネットの内側にいました。しばらく羽化が続くと思うので、見つけたらおしえてね。(右:田んぼゾーンにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年8月1日(月) 上小は、いごこちいいのかな ハグロトンボ。未熟(みじゅく)な個体は水辺からはなれて林の中などで生活するそうですが、上小では7月5日に観察してから、そろそろ1ヶ月になります。思っていたよりずっと長くいますね。もしかしたらちがう個体なのかもしれません。どちらにせよ、上小の環境(かんきょう)が気に入っているようです。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン。もともとは南方の暖かな地域に生息していたというので、暑さに強いのかなと思っていましたが、暑い日には日かげをえらび、翅(はね)をとじたまま休んでいることが多い気がします。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月28日(木) 暑くたって元気いっぱい! 大好物のアブラムシを夢中になって食べているナナホシテントウがいました。(校舎裏にて) 日向ぼっこをしていたニホントカゲ。夏の日差しをいっぱいに浴びて気持ち良さそうにしてました。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月27日(水) 今日のごちそうはなにかな? シオカラトンボのメスがいました、よく見ると食事中です。つかまえたのは、ノゲイトウにおとずれていた虫だったのかもしれませんね。(左) おいしくいただいたあとの様子。すごく満足そうな顔つきですね!(右:2枚ともに東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月26日(火) どちらの蜜(みつ)がおいしいのかな? お昼時、やまない雨にセミが待ちきれなさそうに鳴いていて、ヤマトシジミたちの楽しげに飛びかう姿がありました。シロツメクサのおいしい蜜を見つけたようです。(左:校舎裏にて) こちらからは、わたしはオミナエシの蜜を見つけたよ、と聞こえてきそうです。(右:給食室裏花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月25日(月) 暑さに負けずにがんばれ! ひっくり返っていたアブラゼミ、指をかしてあげると美しい翅(はね)を見せてくれました。セミの寿命は羽化してから1週間と思っていましたが、環境が良ければ1ヶ月くらいは生きているそうです。しばらくすると、ジージーと鳴きながら元気に飛んでいきました。(中庭にて) どこから入ってしまったのか、主事室に8㎝ほどのニホントカゲの幼体がいました。まだこわい思いをしていないのか、肩までのぼってきたり、手のひらにのせていると、ウトウトと目をとじる様子にビックリしてしまいましたが、草地にはなすと急に用心深くなっていました。元気に育ってね!(主事室にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月22日(金) それぞれ忙しく ヤブカラシの葉をモリモリと食べているコスズメ(終齢)幼虫がいました。もうすぐ土の中で蛹(さなき)となる準備をします。(左:校舎裏にて) 朝からブンブンブンと仲間たちとおとずれていたミツバチ。キンカンの甘い香りがただようなか、せわしなく蜜(みつ)を集めていました。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月21日(木) ゴーヤの蜜(みつ)は甘いかな? シジミチョウ。ゴーヤの花の蜜(みつ)を楽しんでいました。(左:中庭にて) 赤ジソの上に数匹のオンブバッタがいました。そのなかには、少し赤ジソの色になっている個体もいました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年7月20日(水) 虫たちに夏休みはないのかな? 朝食は大切。キボシカミキリがクワの葉をたんまり食べ、たっぷりウンチもしていました。元気なしょうこです。あっ!見て見て!カミキリのうしろあし近くのウンチがちょうど『フフ』になってるよ!アハッ!(左上:駐車場花だんにて) ウスバキトンボのようです、ドクダミの葉の上でひとやすみしていました。(右上:東門花だんにて) へぇ〜!すごく大きなテントウ虫、ハラグロオオテントウがいました。ふだん見るテントウ虫の2〜3倍、12㎜くらいあります。大人になると深読みしてしまう名前のハラグロですが、たしかにお腹の色が黒いです。クワの葉につくクワキジラミを食べます。(左下:東門花だんにて) 他のチョウとはちょっとちがう飛び方をするコミスジ。羽ばたいた後、翅(はね)を広げたまま紙飛行機のように滑空(かっくう)し、それを繰り返して飛びます。風をつかまえるのが上手に見えます。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月19日(火) えっ、チョウじゃないの? チョウです! イチモンジセセリ。くりんとした大きな目に引きこまれます。チョウの仲間ですが、体の特徴や生態が他のチョウたちと少し違う部分もあって、国によっては、花から花へスキップするように移動するその様子から、スキッパーズと呼んでチョウとは別の昆虫として扱われることもあるといいます。(左:バッタ原っぱにて) シジミチョウの仲間、ベニシジミがおとずれました。特にめずらしいチョウではありませんが、上小で見かけることは少ないと思います。幼虫はスイバ、ギシギシなどタデ科の植物です。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月15日(金) だれと勝負するんだ!?覆面(ふくめん)レスラー かさ立てを動かしたら下にヤモリがいて、びっくりさせてしまいました。人がいると、こんなにあわてるのに、自然の多い場所ではなく、人の生活環境によりそうのは、夜になると街灯などの明かりに集まる虫たちがヤモリの好物だからです。(左:職員玄関付近にて) キンバエの仲間です。すごい!写真を拡大してビックリしましたよ!赤茶の目のふちに銀色のかこみがありますが、その目のあいだが細い糸のようなものでクロスされているんです(ここをクリックで拡大)。まるで覆面(ふくめん)レスラーのよう!カッコイイ!!(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月14日(木) 雨のあと、探せば不思議いっぱい 雨でぬれた道をオオミスジコウガイビルがゆっくりといどうをしていました。平べったい頭には、たくさんの眼があることや、おしりと口が同じ場所にあること、コウガイビルの生態にはおどろくことばかりです。(左) その長さは50㎝くらいもありました。(レンガの上に20㎝定規を置いてみました)ナメクジやミミズ、カタツムリなどを細長い体に巻き付けて食べるそうです。見れば見るほど不思議がわいてくるコウガイビル、ぜひ観察してみてね。(右:2枚共に東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月13日(水) 本格的な夏はこれからかな 今週は雨の多い天気がつづくようですね。霧雨(きりさめ)の中、モンシロチョウが翅(はね)を休ませていました。(左:校舎裏にて) オニユリが咲き始めています。くるりとカールした花にはアゲハがおとずれるようです。よく観察してみると、葉のつけねにムカゴと呼ばれている大きく育った芽がついていますよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月12日(火) どこかで会えるといいね! 今日でヤゴの展示水槽(すいそう)もおしまい。ちょうど最後の一匹のギンヤンマが羽化しました。昨日のギンヤンマもまだ外に出ていなかったので、先生方も心配そうにトンボに話しかけていましたが、午後になって探検隊スタッフと図工室から出てきた四年生に見送られながら外へ出しました。2匹とも元気に空高く飛んでいきました。(左:職員室前にて) 先週に紹介したハグロトンボ、あれから上小の自然を気に入ってくれたようで毎日見かけています。とても用心深く、いつも木々のしげみにいて、近くによるとパタパタとはなれますが遠くに飛んでいくようすはありません。成熟(せいじゅく)し川辺へとおりるまで、元気に過ごしてほしいですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月11日(月) たくさんの生きものがいる小学校 なかなか羽化をせず、みんなに見守られていたヤゴ。りっぱなギンヤンマとなりました。(左:職員室前にて) オオシオカラトンボ。よく観察できるトンボですが、区内の学校で毎日見られるとなると、そう多くはないと思います。トンボ池を中心に、上小ではたくさんの生きものが過ごしているなぁと、あらためて感じます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月8日(金) ボクだって、休むことに夢中だよ ツチバチのなかま。オミナエシの花の蜜(みつ)に夢中になっていました。おとなしいハチですが雌は毒針をもっていて、卵を産むのにコガネムシなどの幼虫を刺し、マヒさせてから産みつけます。卵からふ化すると幼虫を食べて育つそうです。(左:駐車場花だんにて) スグリゾウムシ(5㎜くらい)。葉の裏でのんびりしていました、幼虫は土の中で根を食べながら育つそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月7日(木) どっちのモフモフがステキ? 顔がワイルドなシオヤアブ。オスにだけ、おしりにかわいいモフモフがついています。昆虫界きっての優秀(ゆうしゅう)なハンターです。(左:校舎裏にて) シラヒゲハエトリ。白いかべにサッサッとあらわれたモフモフのハエトリグモ、つぶらな瞳(ひとみ)がならんでいます。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月6日(水) 仲良しのトンボたち オオシオカラトンボ。交尾の後はオスが見守るなか、メスは腹の先を水面に打ちつけるようにしながら産卵をくりかえしていました。(左:トンボ池にて) お昼どきに、交尾と産卵でにぎわうトンボ池の様子がありました。アオモンイトトンボ、いつもの見た目とはちがい、腹の節(ふし)はよく曲がるんですね。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年7月5日(火) めずらしいお客様 カワトンボ科のハグロトンボ。成熟すると川辺へもどりますが、羽化後の若い個体は水辺から離れ、好みの薄暗い場所をえらんで生活するそうです。石神井川ではたくさん見られますが、上小では見る機会はあまりないめずらしいお客様です。上小のしぜんを気に入ってくれると良いですね。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン。もともとはアフリカなどの温暖な国で生息し、毒蝶のカバマダラに姿を似せて、天敵から身を守っていたようです。今では日本でもすっかり良く見られる蝶となりました。ヒョウ柄(がら)が素敵ですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年7月4日(月) 久しぶりの雨 ・久しぶりに雨が降った後、シランの葉の上でのんびり過ごすカナヘビがいました。よっぽど居心地がよいのか、カメラを向けても葉からおりる事なく、こちらの様子を見ていました。(左上:東側通路にて) ・ムシヒキアブ(の仲間)がニクバエ(の仲間)をとらえていました。(右上:校舎裏にて) ・水を使いながら作業をしているとオンブバッタがピョンと飛び出してきました。(左下:南校舎前にて) ・こちらも同じく、ホースからの水をさけて動きだしたダンゴムシとセアカヒラタゴミムシ。ゴミムシと言うのは、ゴミを食べにくる虫を捕まえることからついた名前だそうです。また、とても早く歩くので『歩行虫』と呼ばれる事もあります。(右下:南校舎前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年7月1日(金) あまりの暑さに「開いた口がふさがらない!」? ・今日は数頭のショウジョウトンボが飛び交うすがたがありました。観察会でもたくさん来てくれるといいですね。(左上:トンボ池にて) ・朝日をたっぷりあびながら過ごすオオシオカラトンボ。(右上:トンボ池にて) ・7月の観察会は『ヤマトシジミをさがそう』・・・身近にいる小さな美しいチョウを観察してみようです。(左下:校舎裏にて) ・今週は外遊びが中止になるほどの暑さが続きました。このところ毎日水辺をもとめてやってくるカラスも、カァカァと鳴かずに口をひらいたままです。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月30日(木) 暑い夏は寝てすごします! 暑さがやってくると、夏眠をしてしまうカタツムリ。殻(から)の中の水分がなくならないように薄(うす)い膜(まく)をはって過ごしますが、見つけた時は膜がやぶれていました。水をかけて様子を見ていると、数分後には元気なようすがわかり安心しました。(左:東門通路花だんにて) ヨコバイのなかま。幼虫のようすを見つめていると、ふしぎがたくさんです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月29日(水) ふしぎな卵 小さなハチが興味津々(きょうみしんしん)の様子でとまっているのは、マダラカメムシの卵(1.7㎜くらい)。まっ白な卵には卵蓋(らんがい)といって丸い蓋(フタ)が付いていて、幼虫はこのフタをあけて生まれ出てくるそうです。このような卵が産めるなんて、すごいですねぇ。(左:校舎裏にて) これもふしぎな卵。1㎝くらいのメレンゲみたい。シオヤアブの卵鞘(らんしょう)のようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月28日(火) 暑くたって私たちは元気ですよ~ 暑い日差しの中をチラチラと元気よく舞うヤマトシジミ。金魚草にとまり吸蜜をしはじめました。白い花と白いチョウのようすに、すずしさを感じましたよ。(左:東門花だんにて) モンシロチョウも仲良く交尾中、やさしい気持ちにつつまれるひとときです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年6月27日(月)関東地方梅雨明け トンボ池に水をくみに来たのは・・・ ・シオカラトンボ。日かげの草地でひとやすみしていました。(左上:校舎裏にて) ・ミツバチが池のふちにやってきました。気温が上がると巣内をすずしくしたり、幼虫を育てるためにも水を運ぶのだそうです。(右上:トンボ池にて) ・カタバミの葉に産卵していくチョウがいました、この卵を産んだチョウの名前は言えるかな?(左下:校庭にて) ・答えはヤマトシジミです。ここでもお腹まげながら産卵するようすが見られました。卵は一週間くらいで孵化(ふか)します。楽しみですね。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年6月24日(金) 中庭の桜 中庭で長い間、みんなを見守ってくれていた桜(ソメイヨシノ)ですが、長い年月で木が弱り、倒れる心配も出て来たことから専門家の判断により伐採されることになり、11日~18日で作業が行われました。上・中段左側は作業直前(11日午前)の様子。右側は作業終了後(24日撮影)の同じ位置からの写真です。風景がずいぶん変わりました。 下段2枚は18日のクレーン車を使った伐採作業の様子です。 ソメイヨシノは成長は早い木ですが、木自体の寿命は50~60年くらいとも言われ、最近では大きな枝が次々と枯れて、幹からキノコが生えるなどして弱ってきていることが明らかでした。ちょうど上小ができた頃植えられたとすると残念ながら寿命だったと言えるかもしれません。 切り株は残っているので、みなさんも直径を計ってみたり、年輪(それを数えると木の年齢がわかる丸い線)を数えてみたりしてみましょう。 この桜に探検隊で設置していたシジュウカラ用の巣箱は、今回の作業に伴い近くの別の木に移設する予定です。 (画像提供:スタッフのNさん) | |
 | |
 | |
2021年6月23日(木) クモをじっくり観察したことありますか? ※クモというと苦手な方もいるかもしれませんが、この美しさ、みなさんに何とかお伝えしたくて今日は大きな写真で紹介します。いや、やっぱり実物をルーペやマクロレンズでじっくり観察してほしいなぁ・・・ ・ウロコアシナガグモ。写真ではお伝えできないくらい、かがやく緑色。うっとりしてしまいます。(上:トンボ池にて) ・黄色っぽいササグモがいました。口のわきの触肢(しょくし)がふくらんでいるのはオス、ボクシンググローブをはめているみたいです。(下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年6月22日(水) 梅雨の晴れ間 校庭の小さな生きものたち ・カタツムリは土にうめこむように30〜50個ほどの卵を産むそうです。2㎜くらいの卵は乾燥しているとひからびてしまい、自然の中で孵化(ふか)するのはなかなかむずかしいそうですね。そんな中、校庭の日当たりのよい花だんの草のしげみで3㎜前後のカタツムリの赤ちゃんを見つけました。(1段目左:校庭にて) ・カマキリ。若齢(じゃくれい)で見られた脚(あし)のシマもようもなくなり、キメのポーズもかっこよくなってきました。(1段目右:東門通路にて) ・「まぶしいねぇ〜!」正午すぎに太陽が顔を出し、ハエトリグモがフキの葉の上に出てきたところ。(2段目左:トンボ池にて) ・アワフキムシのなかま(12㎜くらい)。小さなセミみたいですね、幼虫時はアワの中ですごしているよ。見たことあるかな?(2段目右:校庭西側花だんにて) ・松の木からおちてきたのかな?マツヘリカメムシ(幼虫)のようです。ずっと見てるとイボイボのところ、松ぼっくりみたい。(3段目左:校庭西側花だんにて) ・今日もかがやいています。アシナガバエ。(3段目右:校庭西側花だんにて) ・草のしげみを少しだけきれいにしたら、すごくふきげんそうなクビキリギスがいました。足元でダンゴムシがなだめているように見える・・・ごめんね。(4段目左:南校舎前花だん) ・のんびりすごすナミテントウ。なごみますねぇ。(東4段目右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年6月21日(火)夏至 みんないっしょうけんめい生きています 今日は夏至(げし=1年で一番昼間の時間が長い日)です。 ・ササグモが自分よりも大きなカノコガをトゲのある長い脚(あし)でガッチリとおさえこんでいました。見ているだけで、おなかがいっぱいになってしまいます。(上左:朝の校舎裏にて) ・歩き回っていた一羽のムクドリ。草地のしげみに入りこんで捕まえ、地面に置いたのはニホントカゲでした。この後くちばしではさみながら飛んでいきましたが、もしかすると子育て中なのかもしれませんね。みんな一生けん命、生きています。(上右:朝の校舎裏にて) ・オミナエシが咲き始めています。モンシロチョウが2頭おとずれ、朝食を楽しんでいました。(中左:駐車場花だんにて) ・アオスジアゲハ。エアコン室外機から出る水で水分ほきゅうです。よっぽど暑かったのか、この場所からなかなかはなれませんでした。(中右:南昇降口通路にて) ・コブガのなかまのようです。(アカマエアオリンガ、ベニモンアオリンガに似ています)小さくて15㎜くらいでしたが、きれいな翅(はね)の色が目にとびこんできました。(下左:校舎裏にて) ・オオシオカラトンボ。今日もこのあと、メスの産卵を見守る姿が観察できました。(下右:ンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月17日(金) おっと、見つかっちゃった いたいた!見つけた!カタツムリ。たね取りをしようと抜いた茎の下でピッタリくっついていました。カタツムリは環境の変化で、なかなか見られなくなっているようですね。昆虫ではなく軟体動物で、貝のなかまです。(左:東門花だんにて) 草地の手入れをしているとカナヘビがしげみから木にのぼり、様子をうかがっていました。「かくれ場所がなくなるから、あんまり草をとらないでね」なんて思っているのかしら?と考えると、なかなか作業はすすみません。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月16日(木) 白い斑(はん)は半透明(はんとうめい) カノコガ。幼虫はシロツメクサやタンポポ、スギナなどを食べるそうなので、草地でムラサキ色も入った、25㎜ほどの黒っぽい毛虫がいたら、ぜひ観察してみてください。また、成虫になるとさまざまな花のみつを吸うそうです。白く見えるもようは半透明(はんとうめい)になっていて、脚がすけて見えています。(左:東側通路にて) 梅雨の中休み、トンボやアゲハチョウがいそがしそうに産卵をしにやってきている中、アオモンイトトンボは、ときどきオオシオカラトンボのオスに追いやられながらも、このにぎわいに慣(な)れたかのように、のんびりと過ごしていました。(右:トンボ池にて) (画像・動画と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月15日(水) まだまだいるよ、私たちの仲間 草地の手入れをしていると、アズキノメイガ(かつてはフキノメイガと呼ばれたことも)が出てきました。夜に活動するガの翅(はね)は、自然にとけこむような目立たない色合いが多いです。理由のひとつに、昼間に活動するガと違い、はんしょく相手を見つけるのは翅の模様(もよう)からではなく、におい(フェロモン)で見分けるため目立つ必要がないからといわれています。毛におおわれている翅は、気温の下がる夜に活動するからのようですが、チョウとはちがった美しさがありますね。(左:校舎裏にて) こちらはクロモンキノメイガ。やはり草地の手入れをしていると出てきました。上小では、まだお伝えできていないさまざまなガを見かけています。チョウは好きだけど、ガは苦手だなぁとの声がとどいてくることもありますが、チョウもガも同じ鱗翅目(りんしもく)に分類される仲間なんですよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月14日(火) 虫たちが見ている世界は? 多くの昆虫(こんちゅう)は、紫外線(しがいせん)という私たちには見えない光を見ることができるそうです。モンシロチョウもその紫外線を見ることができて、私たちには白色に見えるモンシロチョウの翅(はね)も、モンシロチョウには、紫外線を吸収(きゅうしゅう)するオスの翅が暗く、紫外線を反射(はんしゃ)するメスの翅が明るく見えているそうです。(左:東門花だんにて) ウメエダシャク。うすい紙がヒラヒラとまうように飛んで、アジサイの葉にとまりました。手でえがいたような翅(はね)のもようがステキです。年に一回発生し、6月ごろに多く見られるようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月13日(月) 大きくなってね! ヒメジオンの花の上にハラビロカマキリがいました。脚(あし)がシマもようなのは若齢(じゃくれい)幼虫のときに見られるそうです。何回か脱皮をして秋ごろに立派な成虫となります。 茎(くき)についたアブラムシを見つけました。このハラビロカマキリは、まだ翅(はね)のない若齢ですが、中齢(ちゅうれい)から終齢(しゅうれい)では翅のもとになる翅芽(しが)が目立つようになるようです。ごちそうを栄養にかえて、大きくなってね!(2枚ともに校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月10日(金) ごちそうを求めて おいしい蜜(みつ)を求めて、毎日のように上小の花だんをおとずれているミツバチですが、仲間たちには蜜がある場所をダンスで教えています。「8の字ダンス」といわれているミツバチのダンスは、その名のとおり、数字の8を描くように移動しながら、体の向きで方向を教え、移動の途中で行う尻ふりとその時に出す音で蜜のある花までの距離を伝えるのだそうです。すてきな連絡(れんらく)方法ですね。見てみたいなぁ! クマバチもメドーセージの蜜(みつ)に夢中です。ブーンと大きな羽音は強そうなイメージですが、大きくてもおだやかな性格のハチです。顔(複眼の間)にクリーム色の毛が生えた部分があればオスですが、こちらはメスで、顔が真っ黒です。メスだけにある毒針(どくばり)も、なにもしなければ恐れることはありません。静かに観察をし続けると、会えるよろこびがまたひとつ、ふえると思いますよ。(2枚ともに東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年6月9日(木) トンボ池、水辺でのできごと トンボ池の水辺は1分でまわれる広さです、その小さな水辺をもとめて、トンボたちが集まってきますが、お昼どきにゆっくり過ごしていた数匹のイトトンボが、池から離れてしまうほどのにぎわいがありました。 田んぼゾーンのヒョロッとしていた稲の苗は、順調に根をはりながら元気に育っています。風にゆられながら稲をハンモックがわりにして過ごしているナミテントウがいました。(右上:田んぼゾーンにて) | |
 |  |
2022年6月8日(水) においも、楽しみかたもさまざま ナガメの幼虫がいました、ナガメなどカメムシのなかまは、油状のキツイにおいのついた液体を出して、身を守ったり、仲間どうしのれんらくに使ったりしているそうです。幼虫を撮影していると、おしりのあたりから不思議な液体が出てきました。これがにおいのもとなのかは分かりませんでしたが、なんだか透明でキレイ。 キツイにおいできらわれるカメムシのなかまたちですが、種類によってそのにおいには違いがあり、水中にすむタガメは果物の香りに似ていいるそうで、国によってはこのカメムシのなかまをさまざまな調理法でおいしくいただくそうです。(左:校舎裏にて) 見ごろをむかえているアジサイ、一番楽しんでいるのは、このナミテントウのようです。朝から昼すぎまでずっと、葉でかくれているピンクの花びらの上で、まったりとすごしていましたよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月7日(火) 思わす目がハート型!? ヨツモンカメノコハムシ(体長8㎜ほど)。頭や脚(あし)をかくして葉の上で過ごしていると、葉にかさぶたができているようにも見え、虫なのかな?とちょっとドキドキしてしまいます。近くに食草となるヒルガオがあり、おいしく食べたようすがありました。(左:トンボ池にて) 思わず目がくぎ付けになってしまいました。エサキモンキツノカメムシがいました。長い名前にあるエサキは昆虫学者の江崎氏からですが、紋黄(モンキ)はかわいい黄色のハートもようのことで、ツノは前胸の背中側の出っぱりをあらわしています。成虫のメスは卵を産むと、卵や幼虫が小さなうちは、それを守りながら過ごすそうです。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月6日(月) 雨なんか気にしない、気にしない 一日中雨がふり続きました。虫たちは葉のウラで雨やどりをしているのかなと思いましたが『これくらい平気!』とばかりに何種類かのハエがいました。これは胸に3本のたてじまが特徴のニクバエのなかま。ハエというと、あまり良いイメージがないかもしれませんが、生物の死がいや、はいせつ物などを分解してくれる、自然界では、大変重要な役割をはたしている生きものです。(左:校舎裏にて) アシナガバエのなかま(体長1㎝ほど)。長い脚も特徴のひとつですが、見とれてしまうほどに美しい体色は、小さな宝石のようだと言いあらわす人もいます。幼虫、成虫ともにダニや小さな昆虫を食べます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月3日(金) 羽化したギンヤンマ、大空へ ギンヤンマの羽化、今年もたくさん観察できているようですね。けさは4年生に呼ばれて教室をのぞいてみると、愛情たっぷりに飼育されたヤゴが、無事に羽化をして、窓辺でひとやすみしていました。このあと窓のすき間に入りこんでしまい、おおあわてをしたそうですが、T先生がわりばしで上手に救出し、みんなで大喜びしたとのこと。今ごろ気持ちよく空を飛んでいるのかもしれませんね。(左:4年生の教室にて) かわいらしい鳴き声がたくさん聞こえてくる方へカメラをむけると、小さなエナガ(全長13㎝ほど)が5羽ほどの群れでやってきているようでした。好物のアブラムシの他に、クモや小さな昆虫、木の実を食べたり、樹液も吸うそうです。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月2日(木) 翅(はね)を広げて朝のひと休み 今年はこのホシミスジを良く見かけます。タテハチョウのなかまで、幼虫の食草は上小にもあるシモツケ、ユキヤナギ、コデマリなどです。 オオシオカラトンボのオス(右)。木陰などがある少し暗い環境が好きなトンボです。なわばりをパトロールをしながら翅(はね)を休めているようでした。 (2枚ともに朝の校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年6月1日(水) トンボ池で真っ赤に日焼け?! ショウジョウトンボ(オス)。羽化してから赤くなってゆくのはオスだけです。なぜオスだけが赤くなるのか、いろいろな事が考えられていますが、オスは、なわばりを守るために、太陽の強い光をあびつづけるので、その紫外線(しがいせん)から体を守るために赤くなるようだ、という研究の結果も報告されているそうです。(左:トンボ池にて) サトキマダラヒカゲ。幼虫はササなどを食草にして育ち、成虫になると樹液(じゅえき)などを食べます。木の多い場所にいるチョウで、ふくざつなもようが美しいですね。また、卵や幼虫のようすを図鑑などで調べると、実物を目でたしかめたくなる、かわいらしいすがだです。(右:畑、探検隊の看板にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年5月31日(火) 雨上がり もう少しで雨も上がるころ、校庭の木々を飛び回りながら、二羽のコゲラがおとずれていました。電線に止まり羽を休ませる様子はちょっとだけ寒そうでしたが、すぐに元気よく飛んでいきました。(左:校庭にて) シマサシガメ(体長15㎜ほど)、脚もシマもようのサシガメです。ふだんは折りまげている口ですが、獲物(えもの)をつかまえる時はストロー状にとがった口をさしこんで、イモムシや昆虫の体液を吸います。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月30日(月) 夏のような一日 今日も暑かったですね! ショウジョウトンボ(オス)が太陽の光で体が熱くなりすぎないように、『さか立ち』をするようなポーズをしながら過ごしていましたよ。(左上:トンボ池にて) ツマグロヒョウモン(オス)。風にのって飛ぶのがとくいなようで、羽を広げたままスィースィーと飛んでは気になる場所へと着地していました。(右上:校舎うらにて) 保護中のオタマジャクシのほとんどが、尾もなくなってカエルの姿となりました。今日は水そうから旅立つ個体が多く見られました。水そうから青いネットの橋をわたり陸上へ、ドキドキの旅がはじまります。こうしてカエルになれても、その後一年間に生きのびることができるのは全体のごくわずかだそうです。また元気にトンボ池にもどって来てね!(下2枚:共にプール裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |  |
2022年5月27日(金) 大雨があがったあと 雨上がり、トンボ池に行くとイトトンボがいました。 水面にはアサザの黄色いつぼみが出ていましたよ。(左:トンボ池にて) 雨が上がるとともに、いそがしそうにやってきたモンシロチョウ。これでもない、あれでもないと草から草へと舞いおりて、あったあった!とお目当てのキャベツにたどり着き、お腹をまげながら産卵をくりかえしていました。(右:3年生の畑にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月26日(木) 鳥たちのお気に入りの枝 この木(たぶんネズミモチ)は自然に落ちた種から育ちました。今ではトンボ池の中でも目立つ高い木となり、野鳥たちにとっては、お気に入りのとまり木となっています。今日もシジュウカラがやってきました(左)。 つづいてスズメが同じ小枝にとまりました(右)。まわりのようすを見ていて、くちばしには何か虫をくわえているようです。子育て中なのかな?(上2枚:共にトンボ池にて) プール裏のかたすみに、人があまり足をふみ入れない虫たちの楽園があります。でもプールがはじまる前に草の手入れをしなくてはいけないので、クモやカメムシなどにことわりながら作業をすすめると、ヤモリがビックリしながら出てきました。かべにぺったりとはりついて、一応かくれているつもりのようです(左)。 きれいな目ですね(右)。ヤモリにはまぶたがないので、たまに舌で目をふいているそうです。また夜行性のヤモリ、暗い場所でも色彩を見る力がとてもすぐれ、上手に獲物をつかまえることができるそうです。(下2枚:共にプール裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年5月25日(水) 幼虫があの動物にそっくりなんです 「このあたりが、良さそうねぇ。」ヒラタアブがヨイショと、お腹を曲げながら産卵をしていました。葉についたアブラムシが、生まれてくる幼虫のごはんになります。3〜4日でふ化するそうです、にぎやかになりそうですね。(左:バッタ原っぱにて) タテハチョウ科のヒメジャノメ。おもしろい目玉もよう(眼状紋=がんじょうもん)は天敵をおどかすためと言われています。 さて、このヒメジャノメの幼虫はススキやササなどの葉を食べて育ちますが、幼虫の姿は まるであの動物にそっくり!さて何にそっくりなんでしょう?ぜひ、調べてみてね。きっと幼虫を探して、自分の目で見てみたくなること間違いなしですよ~(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月24日(火) 「自然のバランス」を観察しよう 今朝も数種類の野鳥の声が気持ちよく聞こえていました。小さなキツツキ、コゲラ(15㎝くらい)も木々を飛び回りながらギーギーと鳴いていました。(左上:東門花だんにて) 先週まで3匹のジャコウアゲハの幼虫を観察してきましたが、週明けに様子を見ると、なにかしらの理由でいなくなってしまいました。今は最後にふ化した幼虫が1匹いるだけとなりました、命をつないでいくのは簡単なことではないようです。(右上:校庭にて) 頭が逆三角形でかわいい、アオスジアゲハの幼虫。アゲハの天敵は鳥や昆虫とたくさんいます。でも生き物のバランスを考えると、とても自然なことです。(左下:校庭西側花だんにて) 三年生はキャベツを育て、葉に産みつけるモンシロチョウの卵を熱心に観察しているようです。チョウはそれを知っているかのように毎日楽しそうにおとずれています。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月23日(月) とらえたよ!空中での交尾 ゲッケイジュの手入れをしていると、空中で交尾をするヒラタアブが目の前にあらわれました。上のオスがホバリングをしながら移動をしています。(左上:校舎裏にて・画像クリックで拡大) ハルジオンのつぼみについたヒラタアブのさなぎ。 20日前後で羽化するそうです。花の方が先に咲くかな?(右上:中校舎裏花だんにて) アオオビハエトリ。アリに似ているように第一脚を持ち上げながら歩き、獲物をつかまえるブルーが美しいクモ。アリを捕獲(ほかく=つかまえること)しています。(左下:校舎裏にて) ユウマダラエダシャク(4㎝くらい)。幼虫はマサキなどニシキギ科の植物が食草で、同じ科のツルウメモドキが校舎裏にあります。独特な羽のもよう。よく見ると、りりしい顔をしていました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年5月20日(金) 世界ミツバチの日 児童の登校が始まる朝、めずらしい場所から気になる物音がしました。のぞきこむとカナヘビがいて、なんだかお腹が大きいような気がしました。この辺で産卵するのかな?産卵場所には落ち葉や土の中をえらぶそうですが、キク科の植物がこんもりとしげった場所は、足のふみ入れもなく安心かもしれませんね。(左:中庭花だんにて) わ〜すごい!花粉をたっぷりつけてミツバチがやってきました。どこを飛びまわってきたの?と聞きたいくらいですね!ちょうど今日、5月20日は『世界ミツバチの日』といって、農産物や植物の受粉を手伝ってくれる、ミツバチやその他の昆虫や鳥たちが、地球上の生命維持に役立ってくれている大切さを改めて認識する日なんです。英語ではこのような生き物達をポリネーター(pollinator)と言います。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月19日(木) カッコいいからマネしたくなるよね まだ小さな2㎝くらいのカマキリ、体を草木によりそわせながら、えものを待ちかまえるのが得意です。このカマキリ(漢字で書くと「蟷螂」=とうろう)の獲物を狩る動きを見て、中国では蟷螂拳(とうろうけん)という、有名な拳法(けんぽう=武術)ができたんだそうですよ。(左上:校舎裏にて) トキワツユクサ。南アメリカから昭和初期に持ち込まれた花。上小でも5〜8月頃まで、さまざまな場所で咲いています。あまり花蜂などがおとずれている様子は見られませんが、小さくてもパッと目にはいる、真っ白なツユクサのなかまです。(右上:校舎裏にて) ジャコウアゲハの幼虫が、2匹にふえていました。様子を見ながら、食草のウマノスズクサ1株に一匹ずつにしてやった方がいいかな。(左下:職員室前花だんにて) 卵があるのには気づきませんでしたが、ヤブニッケイの小さな食べあとの葉をめくると、アオスジアゲハの幼虫(3㎜ほど)が生まれていました。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月18日(水) ここにいるよ! アハハ。プランターの中に入ってしまい、出られないニホントカゲ(幼体)がいました。指先のカギ爪でコンクリートや木にのぼるのはとくいでも、ツルツルのプランターをのぼるのはむずかしくてジャンプをくり返していました。手を貸すと出られましたが、ふりむく姿からは、小さなハシゴをかけておいてやりたい気持ちになりました。ウフフ・・・(左上:畑PJエリア、Kさんのプランターにて) 今年も出ましたラミーカミキリ(12㎝くらい)。ブーンと飛んできて目の前でボトっと落下しました、ミント色が美しいですね。上小へは食草のひとつ、アオイ科のムクゲを目当てにやってくるようです。(右上:校舎裏・落下したリアカーの上にて) ジャコウアゲハ、2匹目のふ化です。こちらは1枚の葉に3個の卵(写真左側中央)が産みつけられていましたが、葉がかれてきてしまい、卵も色が変わってしまったので生まれるか心配でした。本当だったら、出てきた卵殻を食べて栄養をとりたいところですが、かれた葉にくっついた卵殻は、白っぽく、おいしそうに感じません。でも食草のウマノスズクサの茎にそって元気に歩くすがたがありますから、きっと大丈夫!(左下:職員室前花だんにて) 先週木曜日にふ化したジャコウアゲハの幼虫。ずいぶんと特徴が出てきました。今のところ、思っていたより少食で、今日も葉の裏でのんびりと過ごしています。よい夢を見ているようでもあります。(右下:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月17日(火) ふしぎの国からやって来ました!? 腹部の黒いおびもようが特ちょうのクロヒラタアブ。ノゲシの花蜜をていねいになめていました。(左上:校庭にて) そのクロヒラタアブの幼虫(12㎜くらい)。成虫は花粉や花蜜ですが、幼虫はアブラ虫を食べます。(右上:校庭にて) オオチョウバエ。4㎜ほどの小さなカに近いなかま。幼虫は下水溝などの汚泥がたまるような排水場所で育つそうですが、葉の上にとまるとモールのような触角に、羽先には点のもよう、ふしぎの国からあらわれたと思うような姿です。(左下:トンボ池にて) 星がたくさんのナミテントウ。パッと見ると、草食のニジュウヤホシテントウに似てるけれど、体がつるんとしているから見分けられるね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年5月16日(月) 葉っぱのかげで雨宿り中 雨の日は草木の葉っぱで、小さな虫たちが過ごしているのをゆっくりと見ることができます。今日はコガタシロモンノメイガがいました、羽を広げた大きさは18㎜くらいの花蜜を食べる小さなガ。モンキクロノメイガと羽もようがソックリですが、大きさがちがいます。(左) 触角(しょっかく)にコブがあるのが大きなとくちょうなのだそうです。前から見ると、よくわかるかな?(右) 他にも体の部位にこだわりがあるようで、おもしろいですね。ちなみに最初からカメラに気がついている様子でしたが、真正面からの撮影すると、パッとその場をはなれました。(2枚共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月12日(木)② ジャコウアゲハの卵がふ化! ムラサキツユクサは5月〜9月ころにかけて咲きます。そのあいだに、ミツバチなどの虫たちが花蜜や花粉をいただきにやってきます。花は虫たちにごちそうをするだけではなく、かわりにタネを作るために「おしべ」の花粉を「めしべ」につける受粉(じゅふん)を手伝ってもらいます。花と虫、種類はちがうけれど、おたがいに協力しあっているんですね。今日はヒラタアブがおとずれていました。(左上:中庭にて) 2羽のメジロが「チーチー」と鳴きながら、水を飲みにやってきていました。春ごろは校庭のツバキやウメの花蜜に夢中になっていましたが、今の時期は小さな虫などを食べているようですよ。(右上:トンボ池にて) ジャコウアゲハ。出た出た!孵化(ふか=卵から生まれること)してる!幼虫の大きさは3㎜もなくて、とっても小さい。まるで小さな虫のフンみたい!これから食草のウマノスズクサを食べて大きく育っていくんだね! 葉っぱを食べると思っていたら、まずは卵のからをムシャムシャ。ジャコウアゲハの卵はどんな味なんだろう? 出てきた場所から、きれいに食べていました。和菓子みたいで甘くておいしそうですね。(下2枚共に:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月12日(木)① クロスジギンヤンマ産卵に! 朝一番にナミテントウが羽化していました。黒い前羽にオレンジ色のもようは最初からではありません。羽化してすぐは黄色の前羽にうっすら円のもようが見えるくらいで、2時間くらいかけて羽色が変わっていきます。撮影者がうつってしまうくらい、ピッカピカの羽です。(左上:駐車場花だんにて) 隊員のGママさんが歓声をあげながら教えてくれたクロスジギンヤンマ。今日は池にうかんだ枝や、アサザの葉にとまりながら、産卵をくりかえしていました。孵化(ふか=卵から生まれ出ること)は2週間後くらい。楽しみですね!(右上) となりにはトンボ池よりも大きなプールがあるのに、クロスジギンヤンマは必ず木々にかこまれた、日かげもできるトンボ池で産卵をし、ギンヤンマは明るくひらけたプールで産卵するって知っていたかな?上手にすみわけて、自分たちの種を守っているのかもしれませんね。(左下:産卵のようすをうしろから撮影) 何回も水面におりて産卵をしていましたが、オスはいません。どこにいるのかな? 実はクロスジギンヤンマのメスは単独で産卵をしにやってきます。ギンヤンマのようにオスメスがつながっての「連結産卵」はしません。 また、クロスジギンヤンマのとくちょうは黒い腹部もありますが、胸部の黒く太いスジが名前(黒条銀蜻蜓=くろすじぎんやんま)のゆらいにもなっていて、わかりやすい目印です。(右下:3枚共にトンボ池にて)※トンボのお話しはスタッフのつとむさんより聞きました。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月11日(水) よく気づいたね! 四年生の体育の時間、「虹がでてるよぉ〜!」とたくさんの歓声が聞こえてきました。まぶしいのに、よく気づいたね!太陽のまわりにできる丸い虹を『ハロ』または『日暈(ひがさ)』と言うんだったね。(左上:校庭にて) 脚(あし)にたくさんのトゲをもつササグモ。クモは脱皮をしながら大きくなりますが、ササグモのぬけがらには、このトゲトゲもちゃんと残っているんですよ。今日はハスの葉の上で、虫がやってくるのを待っているようでした。(右上:トンボ池にて) マガリケムシヒキ(2cmくらい)。名前のゆらいは目の後ろに見える毛が、前方にまがっているからなんだとか。細かいところまで観察してついた名前だったんですね。今日はサッと飛んで、すぐにもどってくると「しとめました」とクサカゲロウのような虫を見せてくれました。(左下:校舎裏にて) クルクルとじょうずにまいたね、だれのしわざかな? いろいろ調べてみましたが、よくわからない。もしかしたら、エノキハマキホソガかもしれないけれど、もう少し様子を見ていようかな。他にもあって5個くらい見られるよ。(右下:トンボ池、実生から育つエノキにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年5月10日(火) ジャコウアゲハの卵 『ギィーギィー』と特徴のある鳴き声のコゲラ。時々おとずれる小型(15cmくらい)のキツツキです。この時期は、木の葉につく虫を食べていることが多いそうですね。今回は梅の木にきて、何かをついばんでいる様子でした。(左上:校庭にて) ササグモ(1cmくらい)。歩きまわりながら獲物を見つけるとジャンプして捕まえる活発なクモなのだそうです(今回はアリを捕獲)。ずいぶん前の話ですが、スギの植林で新芽を食べてしまうスギタマバエに対し、このササグモを大量に飼育して放したところ、とても良いこうかがあったそうです。(昭和30年代の九州でのお話しです)きっと、時間や手間がかかったと思いますが、自然や人にやさしく、安心できる方法ですね。(右上:校舎裏にて) テントウ虫の中でも小型なヒメカメノコテントウ(4㎜くらい)。幼虫、成虫ともにアブラムシを食べます。ナミテントウのように、もようがいろいろあります。(左下:トンボ池にて) ジャコウアゲハの卵(1.5㎜くらい)です。(右下)お世話になっているKさんが食草のウマノスズクサと一緒に持ってきて下さいました。トンボ池で育てている苗の大きさとあまり変わらないくらい、小さな葉が出ているだけですが、長い間観察を続けているKさんのお話では「不思議なんだけれど卵が幼虫となって草を食べ始めると草の方も育ち始めるみたい」とのこと。まだ10㎝程の大きさですが、幼虫が葉を食べはじめると、草もなくなってかれてしまわないよう、がんばってグングン成長しはじめるのかもしれません。大切に観察していきましょう。(観察しやすい場所に植える予定です) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年5月9日(月) 夜のジーーーーーーって声の正体 キクの手入れをしていると、胸部に赤いしるしが特徴のキクスイカミキリがいました。9㎜くらいの小さな虫ですが、顔を見るとカミキリムシの仲間とわかります。幼虫はキクやヨモギなど、キク科の植物の茎の中で育つそうです。(左:西側花だんにて) めいわくそうな顔しているクビキリギス。のんびり過ごしていたのをじゃましたようです。緑色の個体もあますが、幼虫時の環境が乾燥した草地だと薄茶となりそのまま成虫となっても色は変わらないそうです。夜、どこからか「ジーーーーーーーー」って音が聞こえるのはボクの声です。(右:校庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |
2022年5月6日(金) 上小の自然 GWスペシャル バラの咲く頃となりました。つぼみについたアブラムシを見つけましたが、食べてるテントウ虫の幼虫も見つけました。(校庭にて) ★校庭の自然 スペシャルアルバム第2弾(14枚) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 |
2022年5月2日(月) 食事をしながら産卵!? えっ、産卵しながら食事?ありえるかもしれません。 こちらはナミテントウ(7㎜くらい)よりも小さなダンダラテントウ(5㎜くらい)のようでした。 (東門花だんにて) ★この日Sさんが撮影してくれた写真がたくさん届いたのでアルバムを作りました (画像と情報:スタッフのSさん) |
2022年4月28日(木)② しゃがめば見つかる! しゃがんでしばらくじっと見つめていると、身近な所にも色々な生き物がいるのに気づきます。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
おぉ〜っ! おちばの上にもテントウムシの卵が! 今年はものすごいテントウ虫の産卵ラッシュですね、幼虫たちもたくさん見られます。 (駐車場花だんにて) | その近くにいたナミテントウ。ちょっと話ははずれますがナミテントウの幼虫は天敵製剤(てんてきせいざい=天敵となる生き物を農薬の代わりとして使うために増やしたもの)として売られているんですね。アブラムシのひがいは薬にたよらず幼虫にたのむ! (駐車場花だんにて) |
 |  |
「あっ。見つかっちゃった!」と体をかたまらせるクロウリハムシ(6㎜くらい)。エノキの葉を丸くかじっていました。 クロウリハムシは、このように葉を丸くくり抜いて食べる前に、そのまわりをかじって溝をつけ、苦味や有毒成分が集まらないようにして、その部分がおいしくなってから「いっただきま〜す」とばかりに食べます。その溝ほりを『トレンチ行動』というそうです。 (西側花だんにて) | 午後はなぜか2階のろうかに飛んできていたキマダラカメムシ。 虫が苦手なら「ヒャァ〜!」と声をあげてしまうかもしれない。見ごたえのある大きさで2.5㎝くらいあります。でも愛きょうのあるつぶらな目や、繊細(せんさい)な体のもよう、ゆっくり観察させてくれるおおらかさもあるから大好きになるかも。今日はステンレスの手すりにじっとしていました。すべらないんだね。 (プールにて) |
2022年4月28日(木)① 赤ちゃん次々誕生中~! 上小ではいま、校庭や畑、トンボ池などでいろんな生き物の赤ちゃんが次々と誕生中です。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
わっさわっさ!梅の木を見上げてようすを見たらテントウ虫の孵化(ふか)が始まっていました。ずいぶんにぎやかです。 (放送室前の梅の木にて) | 新芽が出てきたばかりのレモンの葉にアゲハがさっそく来ていたようです。幼虫はまだ生まれたばかりの1齢のようで、白いもようは2齢から見られます。元気に育ってね。 (校庭花だんにて) |
 |  |
新密になってる~!4月の中旬に見つけたカメムシの幼虫。よく見ると背中にぷくんとふくらんだ部分があります。なんだろうね? (西側花だんにて) | さわらないでね!2㎝くらいの小さな幼虫、ウメスカシクロバ。白い毛は毒毛、ふれるとかゆい。成虫は黒い蛾(ガ)となり、たまに見かけます(無害)。幼虫はバラ科の植物を食べます。今回は放送室前の梅についていたみたいですね。さなぎになる時は葉についたまま、繭(まゆ=体内から糸をだして体をくるみます)を作りますから、前日の強風で落ちてしまったのかな? (南校舎、昇降口にて) |
 |  |
2022年4月27日(水) 〇〇〇〇コガネ ハルジオンの花の上でのんびりしていたヒゲブトハナムグリ、春から初夏の短い期間だけ姿を見ることができるコガネムシのようです。しょっかくの形がおもしろいですね。まるでトナカイのツノのようにも見えます。みなさんだったらこのこん虫にどんな名前をつけますか?「〇〇〇〇コガネ」みたいな感じでもっとステキな名前を考えてみよう。(左:校庭にて) 月曜日に観察した卵はどうなっているかな?と見上げてみると、4齢(ふ化してから8日くらい成長している)くらいのテントウムシの幼虫がモミジの葉の裏でじっとしていました。そろそろ蛹(さなぎ)になるのかな?ちなみにふ化したてのような小さな幼虫は、元気に動きまわっていました。アブラムシがたくさんいるので、この様子はしばらく続くようです。(右:トンボ池、資材小屋前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月26日(火) トンボ池のほとりにて オレンジ色のイトトンボは、未熟個体のメスになります。成熟するにつれ色が変わります。どんな色になるのかな?(左:トンボ池にて) 葉を食べるとピリッとした辛(から)みのあるクレソン。花はアブラナ科のとくちょうで、4枚の花びらが十字形にひらきます。(右:田んぼエリアにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月25日(月) テントウムシとアブラムシ もみじの手入れをしていると、黒いアブラムシ(写真の右上)がいっぱいついていました。そして、近くにはてんとう虫の卵があります(写真の中央)。2日くらいすると生まれてくる幼虫はアブラムシをたくさん食べます。てんとう虫の親は、エサの心配がない場所をちゃんと選ぶんですね。(左:トンボ池、資材小屋前にて) てんとう虫の蛹(さなぎ)もありました。一週間くらいすると成虫になります。卵から成虫までは20日くらい、そして2ヶ月ほどの寿命です。(右:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月22日(金) 二匹はいっしょ❤ 今日は10匹ぐらいのイトトンボがいました。そしてその半分はオスがメスの首にくっついたままです。これは交尾が終わったあとのようす。その場所からはなれる時も、他のオスがじゃまをしにきても、2匹はいっしょです。おもしろいですね。(左:プールにうかんだ草のくきの上で) あれ?てんとう虫にそっくり!クロボシツツハムシです。クヌギやサクラなどの葉を食べるそうです。そして、てんとう虫はおいしくないので野鳥は食べません。なので、てんとう虫にそっくりになることで、食べられないようにしているようです。(右:図書館棟通路わきにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月21日(木) イトトンボを確認! 何日か前から見かけているイトトンボ。近づくとサッと逃げてしまうので、そ〜っと近よってみてね。(左:プールにて。★23日土曜日の観察会は10時から、一度家庭科室に集まってからトンボ池に行くよ) ドウダンツツジにいたのはユスリカのなかまのようです。幼虫は水中で過ごし、ヤゴのエサにもなってくれます。成虫となると寿命はわずか一週間ほど。口や消化器がないので、何も食べずに交尾・産卵をして、命をつないでいきます。(右:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月20日(水) 水中からフトイの芽が出てくるころです 4月20日〜5月4日は、二十四節気の6番目『穀雨(こくう)』です。 穀物(こくもつ=米や麦など)の成長に大切な雨がふる時期になります。 そして二十四節気をさらに細かく分けた七十二候(こう)では『あしはじめてしょうず』。 水辺の植物が芽をのばすころ、という意味です。 トンボ池とプールから伸びはじめたのは、葦(あし)ではなくフトイ(カルガモのおくの草)。この草を使ってヤゴがトンボへと羽化をします。(左:プールにて) ベニカナメモチの手入れをしていると、切った枝先にキイロテントウがいました。植物を弱らせるうどん粉病、その細菌を食べてくれるテントウムシです。きっと食べに来てくれたんですね。薬をまかなくても上小にはキイロテントウがいるからだいじょうぶ!(右:西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月19日(火) フジの花がさき始めました フジの花も少しずつ咲きはじめています。花のみつを楽しみにやってくるクマバチは見た目とはちがい、おだやかな性格のハナバチです。あわてずに見まもりましょう(左:校庭にて) 大きく育ったノゲシ(タンポポに似た花が咲く野草)の根もとに、カタツムリがいました。カタツムリは夜行性なので、昼間は鳥などに見つからないようにすごしているようです。あたまを出してくれなかったのは、きけんを感じたからなのかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月18日(月) トンボの羽化始まる! イトトンボのぬけがらがありました。ということは、羽化して成虫になったイトトンボがどこかで雨やどりしているのかな。いよいよ今年もトンボの季節の始まりです!(左:プールにて) カルガモが池の中でおよいだり、羽の手入れや、体を休めたりと、1時間以上もゆっくり過ごしていました。明日も来るかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |
2022年4月19日(火) 繁殖の時期を迎えたツミのメス おとなり、西東京市の公園で、ツミのメスを見かけました。長い間同じ枝にとどまっていましたが、しばらくして近くに小鳥くらいの大きさの獲物(えもの)を持ったオスがやってくると、そのオスのところに飛んでいってその獲物をもらっていました。どうも公園のとなりにある大きなお屋敷(やしき)の林の中で営巣(えいそう=を作って卵を産み、子育てをすること)しているようです。 上石神井でもツミを見かけることがありますから、いこいの森や公園など、高い木がたくさんある場所を探してみましょう。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
 |  |
2022年4月15日(金) すみれの花をさがそう 上小で観察できるスミレは3種類。これはニオイスミレかな。ドライフラワーにして楽しんだり、香料やお菓子にも使われます。ほかのスミレもあわせて探してみよう!(左:東側通路にて) ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)が花の見頃をむかえています。秋に赤い実がなり、野鳥がやってきてます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月14日(木) そろそろツバメにも会える頃です セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草) 。セリバは「セリのような葉っぱ」。ヒエン(飛燕)は「飛ぶツバメ」という意味。花がツバメが飛ぶすがたに似てるからということみたいです。ツバメの特ちょう的な二本に分かれた長い尾羽を思い出すと・・・ そうです。そろそろ飛んで来る頃です!海を渡ってやってくるツバメにもまた会えるのが楽しみですね。(左:トンボ池にて) 八重桜(やえざくら)が満開をむかえています。この桜は花を塩づけにし、お茶や料理に入れて春を楽しみます。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月13日(水) おいしい蜜がありますよ~! ハサミで切りこんだようなふちどりのあるシャガの花。絵の具で描いたようなもようは、ネクターガイドと言って『この先においしい蜜(みつ)がありますよ』と虫たちに教えるためなんですって。 (左:校舎裏にて。観察しやすいように、他の花だんにも移植中) 見すごしてしまうような1㎜ほどの小さな花ですが、水色のかわいらしいキュウリグサ。葉をもむとキュウリのようなかおりがするのが名前のゆらい。 (右:校舎裏にて。他にもいろんな場所で見られます。探して見てね) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2022年4月12日(火) この花、な~んだ? 存在感のある実の地味な花。さてこの花はなんの花でしょう? 葉っぱがヒントになるかな。いい香りのする葉っぱですよ。アゲハチョウの食草でもあります。 お花とめ花があるんだけれど、これは、お花の方です。トンボ池のバタフライゾーンでもいまちょうど咲いていますよ。 (画像と情報:隊員のGママさん) |
 |  |
 |  |
2022年4月12日(火) 「春のようせい」出現! (4枚共に、お母さんと畑の手入れに来てくれていた3年生隊員のKくんと、妹のSちゃんが見つけました。) 「つかまえたよ!」と虫かごの中にいたのは、ツマキチョウ(メス)でした。飛んでるとモンシロチョウのようで、とまると前羽が緑のまだらもよう。発生時期が短く、だから気づかれにくい[春の妖精]なんですって!もうちょっと、よく見えるように撮っていたら・・・すばやく飛んでいきました。はねの先がとがっているのがわかるかな? ミミズではないよ、コウガイビル。ちょっと気味悪い感じだけど、ニョロニョロとおもしろい。しめっぽい所にいて、カタツムリやナメクジ、ミミズや小さな昆虫を食べるそうです。Sちゃんは『かんそうに弱いんだよ』と言って、ジョウロの水をかけていました。やさしいね。 カメムシのなかま、ヒメナガメ。命をつなぐための交尾中のカップルが1、2、3 〜とたくさんいたよ! Kくんが「かわいいのがいるよ」と教えてくれたのはシロヘリツチカメムシ。他にもカメムシのなかまが2種類もいました。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2022年4月11日(月) ニホントカゲの季節です そろそろ学年ごとの畑の準備がはじまるので、かれ葉などを取りのぞいていると、元気よくニホントカゲが出てきました。もうそろそろ産卵期にはいります。1回の産卵で3〜6個の卵を産むそうですよ。卵を観察してみたいですねぇ・・・(左上:校舎裏にて) 上小でもアゲハやモンシロチョウを見かけるようになりましたね、今朝はパタパタと飛んできて、羽を休めたマエアカスカシノメイガがいました。緑色の幼虫時はネズミモチやキンモクセイなどの葉をたべるそうです。(右上:東門花だんにて) ヘビイチゴの花が満開中!ハナバチがおとずれていました。(左下:西側花だんにて) 秋になると黄色く甘い香りのするカリンの実、今は白い花びらに、ほんのりピンク色の入った、かわいらしい花が咲いています。(右下:図書館外玄関わき花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月11日(月) カエルプロジェクト 「オタマジャクシの観察をしてみませんか?」と校内で先生方によびかけることにしました。 3月中旬にヒキガエルがトンボ池で産卵をし、オタマジャクシとなりました。これから手足が出て、カエルに近くなると陸へとあがります。この様子を教室で飼育をしながら観察をしてみませんか?陸へ上がる頃は生き餌が必要となり、教室で飼い続けるのはむずかしくなるので、連休前にトンボ池へとかえし、その後は自然の中で観察していただくようになります。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月8日(金) ダイコンの花 練馬大根の花、他にもキャベツ、ブロッコリーの野菜の花もりっぱに咲いています。楽しんだあとは、どんなタネができるのかな?(左:体育館裏の畑にて) 上小には数種類のスイセンが咲きますが、これは原種(げんしゅ)といって、もともとのすがたのスイセン。 はなやかなスイセンとはちがい、ちいさくてかわいらしいです。どこにあるか見つけられるかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月7日(木) むらさき色の「三きょうだい」を探そう 桜の花びらがおりてくる中、ツグミがいました。あたりのようすを見ながら、土の中にもぐっているミミズや昆虫をさがしているようでした。(左:校舎うらにて) ムラサキケマンが咲いています。ケマンとは「華鬘」と書き、お寺などで使われる花や鳥などをデザインした丸い金ぞくでできたかざりもののことだそうです。それに形がにているということかな。強い日ざしは苦手な植物だそうで、トンボ池でも少し日かげの場所で見られます。むらさき色の三きょうだい=春に見られるよく似たむらさき色の花「ホトケノザ」「ヒメオドリコソウ」(どちらも上小にあります)とのちがいも観察してみましょう。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年4月6日(水) 上小のみんな 進級おめでとう! ハナカイドウが満開をむかえています、ミツバチが花にもぐりこんでいるようすもありました。(左:校庭にて) ステキなさえずりをしていたメジロ。校庭での始業式中も、ずっと鳴いていたんですよ。 (右:校庭・新芽をのぞかせたイチョウの木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2022年4月5日(火)~4月19日(火) 「清明」(せいめい) 4月5日~19日は、二十四節気の5番目「清明(せいめい)」。 すべてのものが清らかで生き生きと明るくかがやく様子を表しています。花が咲き、チョウが舞い、空は青くすみわたり、さわやかな風がふく頃です。 南からわたってきたツバメのすがたが見られるようになり、反対に冬を日本ですごしたガンなどの冬鳥が北へと帰っていく頃です。また空気中の水分がふえ、虹が見える日が出てくる頃ともいわれています。 今回の「清明」はちょっとむずかしいので、ポスターは先日の観察会(詳しくはこちら→)で見られた校庭の自然をイラストにしてみました。 (ポスター:玄関ウエルカムボードとトンボ池けいじ板に掲示中) (情報とポスター制作:スタッフのSさん) |
 |  |
2022年3月25日(金) 地上でも3つの星、発見! ミツボシツチカメムシ。体のふちが白くて、白い点(星)が3つ、5㎜くらいの小さなカメムシです。(左:中庭にて) ヒヨドリが桜の花にみつを吸いにおとずれていました。それから、メジロも来ていましたよ。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年3月24日(木) 学校の中でも春見っけ! レンギョウが咲いています。花のあとに実をつけ、生薬(しょうやく)に使われるそうです。どんな実ができるのかな?(左:東門花だんにて) トンボ池の今後の生態系を考えて、ヒキガエルの卵を少しだけ観察をかねて保護しました。卵をすくっていると、イトトンボのヤゴ(幼虫)が入りましたよ。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |  |
 |  |
2022年3月24日(木) 町でいろんな春を見つけたよ~ きれいなムラサキ色ですね。いろんな名前がある花です。みなさんはなんと呼んでいますか。ほかの名前も調べてみましょう。(左上) これも美しい花です。シャガ。アヤメの仲間です。(右上) 見上げるとこずえにコサギが3羽!(左下) 庭の小さな池のヒメダカも元気に泳ぎだしました。(右下) (画像と情報:隊員のGママさん) | |
  |   |
2022年3月22日(火) 雪の中で桜が開花 今日は雪もふるくらいの寒空でしたが、見上げると美しくサクラ(ソメイヨシノ)が咲き始めていました。(左:中庭にて) ヒキガエルの卵の形が変わっていました。1週間くらいで孵化(ふか=卵から出ること)するようですから、もうすぐですね!(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月18日(金) 野鳥のレストランも閉店します 二十四節気のポスターを『春分』にかえました、野鳥たちが子育てにむけて、巣をつくりはじめる頃です。楽しみですね!(左:玄関前ウェルカムボードにて) 「何かないかしら〜?」と散歩するキジバトがいました。野鳥のレストランも今週で閉店します。これからは自然のエサがたくさん出てくるから自分でおいしいものを見つけてね。(左:校庭西側にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
  |   |
2022年3月17日(木) ヒキガエルの産卵をかくにん!! さすが上小四年生!理科の授業でトンボ池を観察中に、今年初めてのヒキガエルの卵を見つけてくれました。りっぱな卵が島の近くにあります、光のかげんで見にくいかもしれませんが、よーく観察をしてみましょう。(上:トンボ池にて) ★これから池の中の「島」には、トンボの幼虫のヤゴが、羽化をしてトンボになるために使う植物『フトイ』が出てきます。島にのって遊んでいる人がいたら、やさしく声をかけて、島には乗らないように注意してあげましょう。できたら分かりやすく理由も教えてあげられると良いですね。 ヒキガエルは一度の産卵で1500個〜8000個くらいの卵を産みます。黒いツブの卵がやがてオタマジャクシになり、カエルとなります。成長が楽しみですね!(下左:トンボ池にて) おっと!鉢をどかすと、体長10㎝ほどのニホントカゲの赤ちゃん(幼体=ようたい)がいました。近くにダンゴムシがいたので、いただこうと思っていたのかな?ちょっと出入りのある場所なので、校舎うらへ連れて行きました。元気に育ってほしいですね!(下右:中庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月16日(水) コブシの花の味は? コブシの花をヒヨドリが食べていました。おいしいのかな? 調べてみると、コブシは、つぼみや花、種子を食べたり、お茶にして飲めたりするそうです。また、生薬(しょうやく)や香水(こうすい)に使われることもあるそうです。(左:駐車場・花だんにて) スミレが咲いています。校庭に咲くスミレはいくつかしゅるいがありますが、これはアメリカスミレサイシンのようです。(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月16日(水) お待たせしました! ソメイヨシノが開花しているのを見つけました!今年第1号かな。(左:関公園の手前にて) アンズの花も咲き始めています。(右:関町にて) (画像と情報:隊員のGママさん) | |
  |   |
2022年3月15日(火) ヒキガエル君、池に入る カエル好きのG(ママ)さんからの情報で、池のようすを見ていると、そ〜っと水面から顔を出すヒキガエルがいました。昨日の個体と思いますが、ときどき鳴いているのでオスのようです。(左:トンボ池にて) シジミチョウがやってきました。ルリシジミのようです。ナズナ(ぺんぺん草)の花のみつに夢中になっていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月14日(月) ヒキガエル君おはよう! ヒキガエルが!ゆっくり動いてはあたりの様子を見たり、野鳥の声にちょっと動きをとめているようでした。でも「仲間たちが来ていないね」と思ったのか、しばらくすると、またかれ草の中へともぐりこんでしまいました。(左:トンボ池にて) ハクモクレンが咲いています。あまいかおりのする花です。木の近くで『しんこきゅう』してみよう!(右:学童施設、西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |   |
2022年3月14日(月) 町の春さがし 上石神井の町を歩いて、春を探してみました。 オオイヌノフグリ(左上) 名前に似合わず、色も形もとても可憐な花です。 ミドリハコベ(右上) 〈ハコベ〉と呼ばれるものにはいくつかあります。その中でもミドリハコベとコハコベはとても見分けがむずかしいのですが、おしべの数からミドリハコベではないかと判断しました。花弁が10枚あるように見えますが、よく見ると花弁の下の方で2枚がつながっていて、実は5弁花です。 スズメノエンドウ?カスマグサ?(左下) 小葉の先を拡大して写してみました。丸くとがらず切り取ったような形をしていて中央にトゲのようなもの。スズメノエンドウでしょうか? ヒラタアブ(右下) ホソヒラタアブでしょうか。盛んにホバリングをしています。コンデジで撮影するのはとてもむずかしい被写体です。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
  |   |
  |   |
2022年3月11日(金) 黄色い羽をもったカワラヒワ 今朝、イチョウの木のずっと高い場所から、ここちよいカワラヒワの鳴き声が、ひびきわたっていました。(左上:西側花だんにて) スズメは梅のつぼみを食べるそうですが、上小ではおぎょうぎよくしています。きっと、レストランの食事にまんぞくしているんですね。今日もレストランにはみんなが持ち寄ったパンやりんご、バナナがありました。ありがとうございます。(右上:東門花だんにて) ★野鳥レストランは春分の日の3月21日までの予定です。 おっと!地面にカマキリの卵が落ちていました。かれ草のマットで見事にキャッチ!よかった!孵化(ふか=卵から出ること)するのは6月頃。肉食のカマキリは食事にこまらない時期がちゃんとわかっているんですね。(左下:校舎裏にて) 生き物たちが使うかな?とよせていたかれ草、あたたかい陽気となってきたので片付けていると「まだ使ってます・・・」とクビキリギスが出てきました。(クビキリギスは成虫で冬ごしするちょっとめずらしいバッタです。)かれ草に同化(どうか=同じように似せる事)した色になっていましたよ。なのでかれ草のベッドは片付けずに一部残したままです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月10日(木) アリ発見~ みなさんはもう見つけているかな? アリが元気に活動しはじめていますね!(左:東門花だんにて) ハクセキレイが訪れていました。ときどき首をかしげながら歩くので、不思議なことでもあるのかな?なんて思ってしまいます。でもこれは目が横にあるため、よく見たい時にとるしぐさなのだそうです。(右:プールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月9日(水) 梅の源平咲き 校庭の梅の木に1本で2色の花が咲いているナゾはとけましたか?こういうのを「源平咲き」と言うのだそうです。 梅はもともと白い花ですが、より美しい花や良い実がなるよう作りかえて、今では300種以上の品種があるそうです。でも、赤い色は、じょうけんがそろわないと白く先祖返り(せんぞがえり=もともとの姿にもどる事)してしまうこともあるのだとか。校庭の梅も、もともとはピンクか赤だったとも考えられます。(左:校庭にて) ※参考:asahi.com ののちゃんのDO科学「なぜ同じ木に2色の花が?」 鳥たちでにぎやかなレストランをのぞきに、近所のネコが来校していました。東門まで見送ると、門を上手にくぐって出ていきました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2022年3月8日(火) 渡りにそなえてしっかり食べてね! 六年生が卒業をむかえる頃、同じようにジョウビタキも北国へと旅立ちます。 探検隊からお祝いもかねてポスターを作成しました。(左上:ウエルカムボード&トンボ池掲示板にて) ツグミ。かれ草をくちばしでかきわけながら、虫を探しているようでした。ツグミも冬鳥です。もうしばらく日本で過ごしてから北へと渡ります。(右上:校舎裏にて) 観察会で用意してもらったブンタン。食べごたえがあるので、まだまだ野鳥達がかわりばんこに訪れています。ヒヨドリ(左)が「おいし〜い!」とよろこんでいました。 「ひとりじめしたいくらいおいしい!」と喜ぶメジロ(右)。(下2枚共にトンボ池にて) ※ブンタン(=ボンタン・ザボン)は大きなものは2キログラムにもなるという巨大なかんきつ(ミカン)。写真は4分の1に切ったものです。スタッフで銭湯をやっているKさんからの寄付。先日「ブンタン湯」をした時のものなんだそうです。人間が香りを楽しみ、中の身は鳥たちに楽しんでもらうという究極のSDG’s(笑) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月7日(月) オオイヌノフグリ開花 オオイヌノフグリが咲きはじめています。ミツバチが小さな白い花粉を集めにやって来るのも、そろそろですね。(左:校舎裏にて) 満開となった梅の木から、チチッチチッと小さな声が聞こえてきました。見上げて見るとメジロが花のみつに夢中になっているすがたがありました。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2022年3月5日(土) 「啓蟄」(けいちつ) 3月5日~は、二十四節気の三番目「啓蟄(けいちつ)」。 春のあたたかさにワクワクしますね! (ポスター。玄関ウエルカムボード、トンボ池にて掲示させて頂きます) (情報とポスター制作:スタッフのSさん) |
 | |
2022年3月4日(金) 落ちそうで落ちない おっと!落ちそうで落ちないメジロ。すごい!忍者みたいだねぇ・・・(トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
  |   |
  |   |
2022年3月3日(木) 生きものたちが動き出しています スノーフレーク(別名スズランスイセン)が咲きはじめました、香りはスミレに似ていることから、英語では『白いスミレ』を意味する名前がついているそうですよ。(左上:校庭にて) ヤスデなどを食べるアカシマサシガメ、かれ葉の中にいました。生き物たちが動き出していますね!(右上:校舎裏にて) ムクドリが数羽おとずれていました。以前は農作物につく虫をたくさん食べてくれる益鳥(えきちょう=人間にとってやくにたつと考えられる鳥)だったそうです。でも環境の変化で都市部で過ごすようになり、数が増えてしまうと、にぎやかな鳴き声などで、あまり歓迎されなくなってしまっているようです。そんなムクドリの歴史を知ると、いろいろと感じます。(左下:校庭にて) レストランのメニューにひまわりの種が復活してから、こまめにおとずれるシジュウカラ。種を両足ではさむ姿はかわいいのですが、近づくたびに発する警戒(けいかい)する鳴き声にはとまどいます。(右下:トンボ池にて) ※シジュウカラ語では「ピーツピ!」=警戒しろ! 「ヒヒヒ」=タカ 「ジャージャー」=ヘビ、なんだそうですね。さて、Sさんのことは鳴き声ではどう言うのでしょう? (←サイドバー・本の紹介参照) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2022年3月2日(水) そろそろ旅立ちの季節です 『ヒッヒッヒッ』と鳴くジョウビタキ。地面におりておいしいものを探しているようでした。昆虫やミミズ、ナンテンの実などを食べているそうです。冬鳥のジョウビタキはそろそろ北へと旅立つ季節。しっかり食べて旅の準備をしてほしいですね!(左上:校舎裏にて) ヒヨドリがいました。昨年モンシロチョウの観察で育てていたキャベツを、おいしそうについばんでいました。(右上:体育館裏・畑にて) 『ギーギー』と鳴き声がわかりやすいコゲラ。校庭の木をコツコツとたたきながら移動していました。今朝は一羽で行動しているようでした。(左下:校庭西側花だんにて) 昨日見つけた卵嚢(らんのう)は、うずまきが右巻きのモノアラガイのなかまのようです。(左巻きはサカマキガイ) ちなみにタニシは卵胎生(らんたいせい)といって、卵をメスがからだの中で孵化(ふか)させるので、卵ではなく稚貝(ちがい=赤ちゃん貝)を産みます。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年3月1日(火) 小さな卵がキラキラ見えてます よく「タニシ」とまちがえられるサカマキガイなど小型のまき貝の卵嚢(らんのう=卵をまもる袋)がトンボ池にありました、ぷるるんとしていそうですが、寒天くらいのかたさです。この卵嚢の中に小さな卵がいくつも入っているのが見えます。太陽光があたり卵の中がキラキラしています。キレイ!(→画像クリック・拡大) (左:トンボ池にて) ハクセキレイが校庭を歩いていました。人に警戒心(けいかいしん)があまりないようで、時々おいかけっこをさせてくれる時があります。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月28日(月) ダンゴムシではありませんよ 池の中に入った葉をすくってみたらミズムシがついていました。 かれ葉や藻(も)、死んでしまったものを食べて水質をきれいにしてくれるおそうじ屋さんです。また魚などの食事にもなってくれるんですよ。ワラジムシにています。(左:トンボ池にて) ※プールにいるカメムシのなかまのミズムシとも、足にいるあの水虫ともちがいます。甲殻類(こうかくるい=エビやカニのなかま)のミズムシ。そう、おなじみのオカダンゴムシやワラジムシのなかまで、水中にいます。 トンボ池初確認(→画像クリック・拡大) ヒヨドリがキンカンをほおばっていました。校庭でしゅうかくしたものを半分に切っておいておいたのをそのままのようですから、食べっぷりがみごとです。でも大変そうだから、次はもう少し細かく切ろうかな。(右:野鳥レストラン・トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月25日(金) シジュウカラ対カラス 香りの良い梅をながめていると、みつをもとめて虫が飛んできていました。春のたよりが次々と届きそうな陽気となりました。(左:東門花だんにて) ジュクジュクジュク!!とシジュウカラのものすごい警戒(けいかい)する声が聞こえてきました。新しい巣箱をかけたサクラの木からです。2羽のシジュウカラと2羽のカラス、1羽のカラスは大きなくちばしを上手に使って、サクラのえだを折っています。もしかすると巣作りをしたいのかもしれません。その様子をもう一羽のカラスがじっと見つめています。精いっぱい威嚇(いかく)しているシジュウカラ、しばらくすると2羽のカラスは飛んでゆきました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月24日(木) こおり作りで遊ぼう! 冷たい空気を感じるのも、あと少しとなりそうですね。最近1年生が、花だんの霜柱(しもばしら)や、トンボ池の氷を先生といっしょに観察しています。そして、プリンカップに葉や花を入れて、氷作りも楽しんでいました。楽しそうですね!(左:一番ひえこむ校舎裏にて) ずっと気になっていた場所へと忍(しの)び足で近よってみると、メジロがいました。あたたかい日差しが差しこんで、天敵もここなら入ってこられないから安心ですね。体の小さな野鳥たちがお気に入りの場所です。(右:トンボ池とプールの間・カイズカイブキの生垣【いけがき】にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月22日(火) さてなんの花でしょう? よく見ると、おもしろい!さてさて何の花?なんだかハートのくちびるに、つぶらな目、ちょっとこまったまゆげもあって、ステキなぼうしをのせて「まぶしいからサングラスがほしいわ」って言っているみたい。(左:校舎裏にて) メジロは空からきけんがやってくるかもしれない!と天敵(てき)の様子は気にするのに、人間にはあまり警戒(けいかい)しません。そのせいか、子ども達はときどき「つかまえられるかな?」とワクワクしてしまうようです。おもしろいですね。(右:野鳥レストラン・トンボ池店にて) ※花のこたえ=ホトケノザ (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月21日(月) タンポポ、半?咲き・・・ レストランにおとずれていたキジバト(左)、そこへメジロ(左)がやってきて、おたがいの様子を気にしながら食べていました。でも、キジバトは小さなメジロが気になって、メジロはキジバトのミカンが気になっているようですね。(左:野鳥レストラン・トンボ池店にて) わぁ。おもしろい!半分だけひらいたタンポポだよ。 なんでだろう、さむかったのかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2022年2月18日(金) 雪が雨にかわるころ 二十四節気の2番目、空からふるのが、雪から雨にかわり氷がとけて水になるころになる『雨水(うすい)』に入ります。この時期から、トンボ池ではカエルの産卵がはじまります、池のようすを気をつけて観察してみよう。 (左上:ウエルカムボード、職員玄関前にて) 沈丁花(ジンチョウゲ)も咲きはじめました。よいかおりがただよっています。 (右上:校庭にて) 朝日を見つめる冬鳥のジョウビタキ(メス)がいました。桜が咲くころには北へと旅立つそうです。 (左下:校庭にて) 夕方「ツツピーツツピー」と上手にさえずるシジュウカラの声がひびきわたります。中庭の巣箱はもう少ししたら新しくなるよ、まっててね。 (右下:上小と上中の間の電線にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
  |   |
2022年2月17日(木) エナガが来たよ! うわぁ・・・かわいい・・・エナガです!黒いラインの下につぶらな目、そして小さなくちばしと、ぜひ写真を大きくして見てね!シジュウカラと6・7羽の群れでおとずれていました。(左:東門花だん、ハナミズキにて) 主事のIさんが「メジロの大群がきてたよ!緑だらけだった!」と、スズメと共にレストランにメジロが来ていたようすを教えてくれました。そうぞうしただけで笑顔になってしまいますね。 少し冷え込む夕方におとずれたふくらんだヒヨドリにも、やっぱりニコニコとなります。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月16日(水) 梅が開花しました! 東門の白い梅が咲きました!木の下にいると、良いかおりがしてくるよ。(左:東門花だんにて) ※去年より15日もおそい開花ですね。やっぱり今年の冬は寒かったのかなぁ。 トンボ池でもフキノトウが出てきました。いくつあるかな?かぞえてみよう!(右:トンボにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月15日(火) カラスのカラオケ大会か? 今日はめずらしく、十数羽ほどのハシブトガラスの集会がありました。高い木にバタバタとあつまったと思えば、おいかけっこがはじまったりと少しさわがしいくらいでした。そして、のど自慢は夕方までつづき、カァカァとよく鳴いていました。(左:屋上フェンスにて) 根をのこしていたノゲシが咲いています。でも、あたたかい時期とはちがい、くきを長くのばさないで地面近くに6つも咲いています。寒い時期はこの方がよいのかな?タンポポに似ています。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月14日(月) おしゃれなマフラー 今日はメジロとスズメが仲良くならんで、いっしょにさえずる姿を見かけました。しばらくすると仲間たちがやってきて、二羽は合流して飛んでいきました。(左:写真は野鳥レストランにて夏ミカンをいただくメジロです) キジバトが歩いていました。首もとの黒と青白いシマもようは、灰色の羽でかくれていますが首の後ろまであるそうです。オシャレなマフラーですね。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月12日(土) レストラン営業中~! おとといは雨や雪で見かけなかったスズメやメジロ(左)でしたが、今日はいつも通りの大にぎわいでした。 「よいしょ、このへんかな♪」・・・メジロのファン、S先生がミカンを補給して下さっているすがたをキャッチ! (2枚共に:野鳥のレストラン・トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月10日(木) つもるかな? 夕方から雪化粧(ゆきげしょう)をしはじめました。つもるかな? みぞれまじりの雪の中、二羽のヒヨドリがレストランをおとずれていました。さむいねぇ。(2枚共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月9日(水) ふきのとうが開きはじめたよ フキノトウの花が見えてきました、フキノトウはひとつの花におしべ、めしべがあるのではなく、おしべだけを持つ雄花(おばな)をつける雄株(おかぶ)、めしべだけを持つ雌花(めばな)をつける雌株(めかぶ)と、それぞれ分かれて育つそうです。ちなみに雄株の花は黄色っぽい感じ、雌株は白い花になるそうです。(左:東門花だんにて) 真っ白なハコベの花が咲いていました。明日は雪の予報ですね、雪景色が見れるかな?足元に気をつけてください。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月8日(火) なにかないかな・・・ ひびきのよいさえずりが聞こえ、二羽のシジュウカラがなかよくトンボ池にやって来ました。地面におりて何かないかな?とうかがっているようでした。(左:トンボ池にて) 二月に入るとスズメのオス達も、さえずりや尾やおしりをあげたりするポーズでメスにアピールするそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月4日(金) 立 春 今日は二十四節気のいちばんめ、春のはじまりをしらせる立春(りっしゅん)です。 まだ氷のはるトンボ池ですが、春の便りは少しずつ届いています。 ウェルカムボードの掲示を「立春」にしました。(左:職員玄関前にて) ※次回は『雨水(うすい)2月19日〜3月4日』となります。 その頃に見られそうな自然の様子などを上のポスターを参考に、イラストや折り紙など自由に作品にして下さい。できたら事務局へお知らせ下さい。みなさんからのポスター、お待ちしております。(♪ちなみにその頃は、校庭の沈丁花(じんちょうげ)が咲き始めたり、ヒキガエルの産卵が始まったりしそうです。このコーナーの下の方、去年の今ごろを見ると参考になるよ。):事務局 放課後、のんびりくつろいでいるキジバトがいました。目がまんまる・・・そう言えば、今日の給食はメロンパンでした。朝から「今日はメロンパンだ!」とそわそわする子ども達のようすが見られました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月3日(木) 最初の一輪はいつ開くかな? 明日(2月4日)は立春。梅の開花はもうすぐ!(左:東門花だんにて) レストランは連日大盛況。最近では保健室のS先生も、みかんの差し入れをして、その様子を楽しんで下さっています。今日はそんなレストランからはなれ、学校のまわりを歩いていると、しげみのおくから鳴く声がしてきました。しばらくすると『ジュクジュク』と不思議な声もします。しげみからあらわれたのは、二羽か三羽のシジュウカラでした。その不思議な声は警戒音(けいかいおん)、私がやってきたので威嚇(いかく=おどすこと)してたんですね。もしかすると最初に聞こえた声は、オスがメスにアピール中だったのかもしれません。春が近づいてきているようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月2日(水) ヒイラギといわし 明日は「節分」。節分にはヒイラギの葉に、鰯(いわし)の頭をさした『ヒイラギ鰯』を魔除け(まよけ)として玄関先にかざる風習があります。邪気(じゃき)をはらうとされるトゲのある葉ですが、動物に大切な葉を食べられないようにくふうした結果、チクチクとしたトゲを作るようになったようです。でも成長して老木になるにつれ、葉のトゲは少なく丸くなっていくのだとか。おもしろいですね。(左:東門花だんにて) スズメの群れは冬のはじまり頃より、どんどん大きくなって20〜30羽くらいになっているようです。自然と大きくなった群れにリーダーはいません。みんなで行動することが何より安心で、食べ物も見つけやすいからだと言われています。 二十四節気の大寒から立春にかけて使われる季語『寒雀』(かんすずめ)の呼び名もおわりに近づいていますが、まだ当分の間は仲間といっしょにいるふっくらしたかわいらしい姿が見られるはずです。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年2月1日(火) ヒマワリの種見っけ! 「ごちそうがつまってる!」目をパチクリさせてペットボトル製バードフィーダー(えさやり器)の中を見つめるスズメがいました。取り出し口が見つけられず、なかなか苦戦しているようです、ウフフ。(左:トンボ池にて) 上手にバードフィーダーの中のひまわりの実を取り出せたシジュウカラは、その場からちょっとはなれ、両足の間に実をはさみ、くちばしでコンコンとたたいて、中の種を取り出していました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月31日(月) なにものじゃ! 『ほわぁ、あったかぁい・・・』モフモフのスズメがいました。(左:トンボ池にて) 『むっ、くせ者。何者じゃ!』するどい眼光をむけるメジロがおりました。(右:野鳥レストランにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月28日(金) 春の七草④ハコベ 春の七草の一つはこべら(ハコベ)は、奈良時代から野菜として食べられていたそうです。昔から歯みがきとしても利用され、ロングセラー商品にもなっているんですよ。そして作れます!きれいに洗った葉を乾燥させて、粉にして塩とまぜるとできあがりです。小さな白い花はもうすぐですね!(左:校舎裏にて) トンボ池での野鳥レストランが開店してから、子ども達はリンゴやみかん、アワを台の上に置いてくれたり、観察をしては報告をしてくれます。先日も「ゆずを置いてみたけど、食べないみたいだから夏みかん置きたい!」とその様子を心配してくれたり(ゆずもきれいに食べてましたよ、安心してね。)登校時の集合場所にあらわれる鳥達の様子を気にかけ「コゲラやヒヨドリ、オナガ、そして時々カラスもくるよ、白と黒の鳥 (シジュウカラのようです) もいる!」と、目を輝かせ話してくれたりします。 校庭のキンカンを収穫したので、メニューにキンカンがふえるよ。よろこんでくれるかな?また、楽しい知らせを待っています。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2022年1月27日(木) 冬のセミ見っけ! 長年の土がたまった溝(みぞ)に、サクラの根が入りこみ、その根の近くでセミの幼虫がすごしているのを一年前に見つけました。今年もそのままにしておいた溝から土を出す作業をしていると、3匹のセミの幼虫がいました。今回は作業の中止はできなかったので、他のサクラの根を選び、土をほぐしてそこにうつしてやりました。 セミの幼虫は土の中で過ごしている間、木の根から栄養を取ります。元気に育ってくれますように。(上:中庭にて) ※冬にはセミは死んでしまっている、と思いがちですが、それは成虫のセミの話。幼虫は冬でも地面の下でしっかり生きているのですね。セミの幼虫を見つけること自体、なかなかむずかしいことですが、コンクリート製のU字溝(こう)の中の土に入り込んだ根にいることで、毎年こうして冬の溝そうじで発見されるのですね。それにしても3匹もいっぺんに、というのはすごいなぁ。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
昼下がり、めずらしく静まりかえったレストランにメジロがやってきました。 「ヒャッホー!だれもいない!たっぷり食べれるゾ!」とよろこんで食べはじめましたが、すぐにあたりをキョロキョロ、おちつかないようすになりました。「あれ?いつものにぎやかなスズメさんたちはどうしたのかな?体の大きな鳥がおそいかかって来やしないかしら?」 おいしい夏みかんでしたが、心配になってしまったようで、見はらしのよい近くの木にとまって、あたりの様子をうかがい、飛んでいきました。また来てね。(野鳥レストラン・トンボ池店にて) | シジュウカラのさえずりが聞こえてきました。空を見上げながら声をたどっていくと、上中にいました。非常階段を上がり撮影を始めると、気がきく子でして遠くの枝の間から、近くの電線へと移動してさえずりはじめてくれました。 それも、胸をはりつつ、ちょっと首をななめにして「この歌い方イケてる」って感じにさえずってました。(中校舎非常階段より) |
  |   |
2022年1月26日(水) 春の七草②③スズシロ・セリ 春の七草の一つ、すずしろ(清白)は大根の昔の呼び名、ちなみに日本の一番古い歴史書『古事記』には、おおね(大根)と書いてあります。その名前のとおり、食べている白い部分は根っこ。上の部分の少し緑色したところは茎(くき)です。大根スパゲッティや、おでん、みそ汁にと、すずしろメニューはどれも人気です。(左:校舎裏、1年生花だんで育てている練馬大根です) セリも春の七草です。田植えで種がはこばれたのか、毎年こんもりと育ちます。セリは在来種ですが、おなじセリ科のミツバは江戸時代から栽培がはじまりました。それぞれ独特の味や香りで料理をおいしくしてくれます。(右:トンボ池・田んぼゾーンにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月25日(火) 春の七草①ナズナ 1月も残りわずか、早いねぇ〜とたいていの大人は思います。みなさんはどうですか? お正月のおわりに七草がゆをいただく風習(ふうしゅう=長年つたわる行事)が今でも残っています。短歌のリズムにのせて春の七草をおぼえたりもしますが、実物は学校探検をすると見つけることができます。そのうちのひとつ、ナズナが花を咲かせていました(左:校舎裏にて) キジバトが来ていました。正面から見ると小顔なんですねぇ。ふくらんだ羽のせいかしら?などと思いながら見ていると『マジック(手品)じゃないわよ』と言っているような視線を感じました。ちなみにマジシャンの相棒(あいぼう)はペットとして改良されたギンバトです。どちらも人になつきやすい性格なので、ときどき話しかけている人がいますね。ふと『聞き上手は愛され上手なのです』と胸を張って言っているようにも感じました。今度、話しかけてみようかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2022年1月24日(月) 黒ネクタイはシジュウカラ 2年生隊員のSさんがレストランの手伝いをしてくれました。すぐにメジロがやってきて、うれしそうにごちそうを楽しんでいましたよ。 今日はトンボ池を一面におおっていた氷はありませんでした。学校の夏みかんをあげ終わる頃には、校庭の梅も咲きはじめ、次は花蜜に夢中になるメジロのすがたが見られるようになるでしょう。まだ『大寒』を感じる時期ですが、体に気をつけて元気にすごしましょう!(左:トンボ池・野鳥レストランにて) 1時間目がはじまった頃、カワラヒワとシジュウカラのさえずりが、心地のよいハーモニーとなって、サクラの木から聞こえてきました。夕方にも黒ネクタイできめたシジュウカラはサクラの木をおとずれて、美声を聞かせてくれました。それは中学校から聞こえてくる、テンポのよいかけ声に合わせているかのように、リズムのよい鳴き声でした。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月21日(金) 今朝も冷えました 「今朝も冷えるねぇ〜チュンチュン!」と仲間たちとすごすスズメがいました。群れですごす理由のひとつは、天敵(てんてき)をいち早く見つけて、仲間に知らせるためです。群れの数が多いほど、きけんに気がつきやすいですから、時には種類のちがう鳥同士で群れをつくり、行動します。もし強い者におそわれて死んでしまっても、自然界で生きてゆくおきて(きまりごと)なので、相手をうらんだりはしません。いろいろな出来ごとをけいけんしながら、日々が探検です。「そろそろ行く?」あたたかな朝日にトキメキを感じたようで、スズメたちは元気に飛び立っていきました。(左:トンボ池にて) わぁキレイ!えいようが流れる葉脈(ようみゃく)だけがきれいに残って、レースの葉っぱになっていたよ。すごくこまかいね。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月20日(木) 校庭にキツツキが来たよ! ギィーギィーと何だか聞きなれない声がするなぁ、と見上げてみると、サクラの枝をコツコツとたたく日本最小のキツツキ、コゲラがいました。他にも4羽くらいのちがう種類の鳥たちが、木の高いところにちらばって過ごしているのが見えます。これは『カラの混群(こんぐん)』と言って、トンボ池にもやってくるシジュウカラなど、スズメよりも小さいカラ類が、はんしょく期を終えると一緒に群れとなって行動し、小型のコゲラもこのなかに入って過ごすそうです。なぜだかわかりますか?小さな鳥たちのちえを、おうえんしたくなりますよ。(左:校庭にて) 氷のあつみが1㎝くらいになっているところもあって、夕方になっても池に氷がのこるようになってきています。じんじんと感じる氷の冷たさや、静まりかえった水の中のようす、やくそくを守りながら観察していきましょう。(右:トンボ池にて・氷と水の間に入った空気が「ひょうたん」の形をしていたよ。) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月20日(木) 今日は「大寒」 今日は二十四節気の最後「大寒」(だいかん)です。大寒は1年のうちでもっとも寒い時期のことを言います。この時期になるとフキノトウがつぼみを出すと言われています。さっそくトンボ池で観察してみましょう。さて、つぼみは出ているかな?花を咲かせるのはいつごろになるかな?観察できたら、お友達や先生にも教えてあげましょう。(職員玄関・ウェルカムボード) (資料:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月19日(水) 野鳥のタネまき 小さな芽を見つけました、左は野鳥が食べた実がフンとなってまかれたマンリョウ。そしてなかよく出てきたのは・・・はて何だろう?同じような芽がほかの所からも出てきています。どこからやって来たのかな?(左:トンボ池にて) メジロがカイズカイブキの枝にとまりながらツンツンとしています。この木は葉がそのまま花になったような小さな花と、開花した後にできる青白い実があります。その実を食べる野鳥もいるそうですが、メジロの様子は、探検隊お手製のバードフィーダー(写真右)に入ったひまわりの種をねらっているのかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月18日(火) 春のかおり発見! ビワの花(左)と白いウメの花(右)がさいていたよ! ※ビワの花は地味ですが、とてもよい香りがします。見つけたらぜひ立ち止まってかいでみましょう。こんな寒い時期に咲くのですね。梅は今年初めてのおたよりです。寒い季節にさく花は、よい香りがするものが多いようです。その香りにさそわれて、冬でも活動するわずかな虫や、メジロなどの鳥が集まります。 (画像と情報:隊員のおとうとさんNくん) | |
  |   |
2022年1月18日(火) 夏みかんとフキノトウ 昨日からトンボ池の夏みかんが野鳥レストランにならんでいます。先週まではスタッフのつとむさんが差し入れてくれたあまいみかんでしたが、酸味(さんみ=すっぱさ)のある夏みかんになったので「おいしいけれど、ちょっとスッパイね・・・」とあまいもの好きのメジロさんは少し、とまどっているようでした。ちなみに秋の終わる頃には色付く夏みかんですが、すっぱさがぬけて食べごろになるのは初夏の頃なので「夏みかん」と言うのだそうです。(左:トンボ池・野鳥レストランにて) そろそろ二十四節気最後の『大寒』(だいかん=1月20日~)です。もう少しこまかく分けて季節のようすを短文にした七十二候(しちじゅうにこう)には「そろそろフキノトウがつぼみを出す頃」とあります。フキノトウは花を咲かせる前につみとり、天ぷらやふきみそにして、少しほろ苦い自然の味をたのしむ山菜です。これからトンボ池でも観察できるようになります、見つけたら友達や先生にも教えてあげましょう。(右:給食調理室うらにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月17日(月) 鳥たちにもそれぞれの性格があるようです 野鳥レストランにスズメの群れがやって来ているのが、楽しそうな鳴き声でわかりました。でもそれは、少しはなれた場所からのようです。この時テーブルについていたのは1羽のヒヨドリで、スズメ達は少しはなれた場所から木々の中を行ったり来たり、プールでもレストランの様子を気にかけながら過ごすスズメがいて「そろそろかわってくれないかしら。」「まだ、おやつは残っているかな?」そんなヒソヒソ話しが聞こえてくるようでした。(左:プールにて) レストランにくるヒヨドリは用心深くて、すぐにはテーブルにおりてこない感じがします。でも、ミカンに夢中になっているメジロがいたので、もしかすると順番待ちで、メジロの様子を見ているのかな?とも思ってしまいます。メジロよりもずっと大きなな体ですが、このヒヨドリは、ひかえめでやさしい性格なのかもしれませんね。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2022年1月15日(土) そして日の入りです 日の出は動画で確認すると6:54くらいでしたかね。暦の上では東京の日の出は6:50となっていましたが、地平線に見える建物や雲、見る場所の高さなどによっても実際の見え方は変わるのですね。 ということで、日の入りも観察してみました。16:38の画像です。まだ、富士山頂の左=南寄りに沈むことがわかりました。この冬2回目の上石神井からのダイヤモンド富士も、もうすぐみたいです。 この時期、日の出が早くなるのは比較的ゆっくりですが、日の入りは毎日1分ずつくらいどんどん遅くなり、月末には17:00を過ぎても太陽を見ることができるくらいになります。太陽を観察していると春はすぐそこまで来ていることが実感できます。みなさん、寒さやコロナに負けず、がんばりましょう。 (上石神井・自宅ベランダより 画像:隊員のGママさん) |
 | |
2022年1月15日(土) 上石神井の今日の日の出です! 本日予定していた「上石神井の日の出を見る会」は大変残念ながら中止とさせていただきましたが、上石神井の空は今日もいつもと変わらぬ日の出をむかえたようです。その様子をさっそく隊員さんが送って下さいました。日の出直前の美しい空のグラデーション、西の地平線に見える白い富士山が刻刻と色を変えていく様子、来年こそはぜひみなさんでいっしょにながめたいですね。 日の出前後の6:35~7:01を100秒に縮めたタイムラプス動画も撮影して下さいました。 今朝の上石神井の日の出は何時何分だったか、動画で確認してみましょう。 日の出を見ると、今日の日の入りも気になります。今日の日の入りは何時頃でしょうか。 寒い日が続きますが、この週末は日の出や日の入りを観察しやすい場所を探して、ちょっと観察してみるのもいいですね。写真など撮れたら送ってください。 (上石神井・自宅ベランダより 動画と写真:隊員のGママさん) | |
  |   |
6:52 東の空 | 6:52 西の空 |
  |   |
| 6:19 東の空 | 6:19 西の空 |
  |   |
おいし〜い、しあわせだぁ〜(しみじみ) | リンゴ、大人気!! |
2022年1月14日(金) 野鳥のレストランだより 冬の冷えこむ朝、もう少し寝ていたい気持ちはみなさんにもおぼえがあることでしょう。今朝ふと見上げると、二羽の野鳥が高い木の上にいました。下の写真左はヒヨドリが寒さにまけないよう、体をふくらませながら羽根の手入れをしているんだね!とわかりますが、もう一羽の近くにいた鳥(下右)は、もっと大きく風船のようにふくらんで、まるでぷっくりした魚のフグみたい。さらに写真を広げると、首をすぼめ目をギュッととじています。足元から朝日がじわじわととどきはじめ「あったかぁ〜い、まだ動きたくなぁ〜い、ずっとこうしていたぁ〜い。」なんて思っているのかもしれませんね。やがて先に身じたくを終えたヒヨドリが朝日の方へと鳴きながら飛びはじめると、もう一羽もすぐさま追いかけるように飛び立っていきました。今日も探検がはじまったようです。(学校のおとなりの高い木、図書館棟の出入り口から撮影) 三年生隊員Kくんが野鳥レストランのテーブルにワイルドに切ったリンゴをのせてくれました。(上右)いったいどれだけの野鳥がおとずれたのでしょうか。次の朝には小さなクチバシの跡(あと)がたくさん見られ、昼休みをすぎるとすっかりなくなりました。これには担任の先生もビックリされて『鳥達の様子を見てみたい』とはずんだ声で言われていました。冬の間だけは野鳥におやつを用意して良いことにしています。野鳥と仲良くなれ、可愛らしいしぐさを近くで見られるチャンスです。(上左:さいごまでリンゴを食べていたメジロ)そして楽しい観察が続けられるように、おやつを置いたりした後は、手洗いうがいも忘れずに。(上の二枚共に野鳥レストラン、トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2022年1月13日(木) 氷の華(はな)見つけた! 朝の冷えこみが続き、トンボ池も氷が観察できるようになっています。今日の氷のあつみは4ミリくらい、昼休みまでにはすっかりとけてしまいます。それくらい氷がうすいとわかっていても『この上にのれそうだと、夢をえがいてしまうようです・・・』と困ったような、でも少し笑顔をのぞかせて、保健の先生が話してくれました。先生はそのあと、校内放送でトンボ池でのすごし方をていねいに話され、ちゅういをよびかけました。(右:トンボ池にて) ※先生方、ご指導ありがとうございます。雪や氷を直接さわってその冷たさを体感することは子ども達にとってとても大切なことだと考えて、トンボ池には、あえて柵などを設けないできています。ただし、安全には十分に気を付けてやくそくを守って観察してくださいね。氷を池の外に持ち出したり、石などを投げ入れるのもやめましょう。 冬の寒い朝に見られる『氷花(華)=ひょうか』はトンボ池にもある植物、シモバシラから見られることでゆうめいです。植物のシモバシラは花が咲いた後にやがてかれてゆきますが、根は土の水分をすい上げて茎(くき)に水をとおしつづけます。冬のとても寒い日となると茎のまわりで氷となり、やがて美しい氷の花のようになります。 今朝はそれと同じげんしょうを見つけました〜!根っこをぬかずに残しておいた植物から、羽根のような氷が出ていたのです。(左)地面のまわりの気温が0℃より下だったしょうこです。朝日がとどきはじめると、魔法のようにとけてゆきました。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月12日(水) 冬はひとりが好きなんです みなさんが家で朝ごはんを食べているころ、野鳥レストランにはすでに、さまざまな野鳥がやって来ているようです。昨日見かけたツグミも、今朝はトンボ池にやってきて、他の種類の鳥たちと過ごしていました。 ツグミは秋になると大きな群れ(むれ)となって、シベリアから日本に渡ってくる冬鳥です。日本にやってくると、群れを小さくしながら各地にちらばり、冬になる頃にはひとり行動をすることが多いそうです。果実や地面におりてミミズ等を食べます。子育ての時期にはふたたび日本をはなれてシベリアに帰ってしまうことから、この名前がつけられたようです。(え?どういうこと?なんで帰ってしまうと「つぐみ」という名前になるの?・・・名前の由来、自分で調べてみてね。)さて、今日はどこへ行こうかな?それとも、仲間たちは元気にしてるかな?なんて思っているのかもしれませんね。(左:トンボ池から屋上に上がったところを撮影) ツグミと同じく、ひとりが好き(?)なヒヨドリが来ていました。でも、こちらの様子が気になるのか、なかなかエサ台へ上がれないようです。そのうちこんなかわいらしいポーズを決めてくれました、キュンとします。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2022年1月11日(火) ツグミもやってきました 今朝は学校に着くと、かわいらしい声がツバキのつややかな葉のしげみから聞こえてきました。鳥が好きなみなさんなら、すぐにピンッときましたね。そうです、ツバキの花のみつが大好きなメジロが、小雨がふる中おとずれていました。毎年ツバキには、毒のあるチャドクガの幼虫が葉にびっしりとついてしまうのですが、今はたくさんのつぼみをつけて、何事もなかったように美しく咲きはじめています。(左:西側正門側花だんにて) う〜ん。うまく撮れていないなぁ・・・と写真をかく大すると、ツグミのような感じがします。よくおとずれるヒヨドリくらいの大きさで、一羽で来ていました。何を思っているんでしょうか?あっ!開店した野鳥レストランのうわさを聞いてやってきたのかな!? お店はとんぼ池にありますよ。(右:東側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2022年1月9日(日) 野鳥のレストラン完売御礼! 昨日の活動で設置した野鳥レストランですが、今日の校庭開放時に見てみると、ほぼ完食されていました。(上2枚) 家からおかわりを持ってきて設置すると、すぐにお客様(メジロさん)がご来店されました!(下2枚)これからも時おり様子を見ていきたいです。 ★あんなにたくさんのミカンやリンゴをたった一日で完食とは!皮しか残っていないですね。鳥さんたち、やっぱりおなかをへらして、開店を待っていたのですね~。冬の間、レストランが品切れにならないようみなさんでメニューの補給、よろしくお願いします。 (画像と情報:2年生隊員のRちゃん&ママ) | |
  |   |
2022年1月8日(土) メジロのむれが来たよ ミカンの木にメジロのむれが来ました。いくつかのむれがまじっているのか、メジロどうしが追いかけっこに夢中でした。中には2羽がもつれ合って落ちてくるものも。そばでじっとして観察しているとにげずに、すぐ目の前で観察できました。トンボ池のミカンのレストランにもたくさんのメジロが来てくれるといいですね。みなさんもそっと観察してみてください。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 | |
2022年1月4日(火) 日なたと日かげ 「しぶんぎ座流星群」は見られましたか。昨夜から今朝は冷えこみは少しゆるんだものの、それでも畑の土に一面に霜(しも)が降りていました。朝太陽が出ると、太陽の光の当たったところの霜は溶け、家の形の影(かげ)の部分だけに白い霜がのこっていました。太陽は少しずつ動いていくので、影もそれに合わせて動きます。さっきまで影だった場所は太陽の光が当たってもすぐには温まらずしばらくは白い霜が残って、ふちどりのようになっているのがおもしろいですね。 「寒さ」や「あたたかさ」はふつうは目には見えませんが、こんな形で見ることもできるのですね。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
  |   |
2022年1月2日(日) どんな初夢見れたかな 初夢とは、新年最初に見る夢。その初夢に見るとよいとされるものはむかしから「一富士・二鷹・三茄子(いちふじ にたか さんなすび)」と言われています。上左は1日の朝、初日の出に照らされた上石神井から見えた紅富士(べにふじ=赤い富士山)。右は同じく1日の初・日の入り(?)と富士山のシルエット(かげ)です。これを見てから寝たらいい初夢が見られるかな。 よい夢を見るには、七福神(しちふくじん)の乗っている宝船の絵に「長き夜の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな」(なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな)という前から読んでも、うしろから読んでも同じ文になる「回文(かいぶん)」の歌を書いたものをまくらの下に入れて眠るとよいとも言われています。 初夢とは、2日の夜に見る夢とされていますが、お正月の間に見た夢、と広く考えてもよいかもしれません。夕べいい夢を見られなかった人は、今からでも宝船の絵と回文、書いてみてはどうでしょう。そうそう、富士山も自分の目でよく見ておくといいですよ~見える場所を探してみましょう。(※高いビルなどでなくても、道路から見える場所もあります。千川通り、関東バスの車庫の少し西、立野橋のあたりから西を見ると見えるよ、という情報が届いています。ほかにも見つけたら教えて下さい!) (情報:事務局 画像:隊員のGママさん) | |
 | |
2022年1月1日(土) あけましておめでとうございます 今年もみなさんで身近な自然を楽しみましょう。 「いっしゅんでこおる水」↓できましたか?この実験には最高の寒さが東京でもしばらく続きそうです。うまくできたら報告、写真など送ってください。 (上小屋上からの日の出2020:スタッフのつとむさん撮影) |
 | |
2021年12月29日(水) 年末年始はすごく冷えそうです 一瞬(いっしゅん)でこおる水!? =「過冷却」(かれいきゃく)の実験をしよう 水がこおるのには、ふつうは、それなりの時間がかかりますよね。 ところが、ちょっとかき回したり、ふったりしただけで「一瞬でこおる水」が作れます。 まずは、動画(→クリック)を見てみましょう。 翌朝の気温が氷点下(0℃以下)まで下がる予想が出た日がこの実験のチャンスです。 今年はちょうど大みそかの夜あたりがそうなりそうです。 用意するのは水道水を入れたペットボトルだけ。 これを前の日のうちに、なるべく寒くなりそうな場所(家の外の地面の上)に置いておきます。 朝になって、まわりの地面などには霜(しも)や氷ができているのに、ペットボトルの水が凍(こお)っていなかったら、たぶん成功です。 ペットボトルをそっと持ち上げて、強くふってみましょう。(あるいは、そっとフタを外して中に小さな氷のつぶを落とし入れてもおもしろいです。) 今の季節限定の楽しい実験です。ちょうど冬休みですし、特別な道具もいりませんから、ぜひ、ためしてみてください。 (ふだんだったらイヤ~な「朝の寒さ」が待ち遠しくなっちゃうことまちがいなし!) そして、なぜ、こんなことがおきるのか・・・おうちの人といっしょに調べてみましょう。 2021.1.10記事一部編集再掲載 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
  |   |
2021年12月24日(金) 冬のみのり 鼻を近づけるとさわやかなキンカンの香りが広がります。今年もすずなりに実をつけていますよ。(左:校庭にて) マンリョウ。秋から冬にかけて赤い実を付け、縁起の良い植物としてお正月かざりに使われます。仲間に一両・十両(=ヤブコウジ)・百両・千両があり、これは「万両」。(「両」は昔のお金や重さの単位)野鳥がタネを運んでくれ、いろんな場所から出てきています。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月22日(水) さて、ワタシはどこでしょう? トンボ池のほとりでかわいいわた毛( 正式名称『冠毛 』かんもう )を見つけました。冠毛はタンポポと同じように、たねを飛ばすのに役立っています。いい風がふいてくるのをじっと待っているのでしょう。さて、この小さなわた毛はなんの花のあとにできたのかな。(左:トンボ池にて) 「うーん、まだ開店しないのか・・・」と、ミカンの木のしげみから、野鳥のレストラン(トンボ池店)の様子をうかがうメジロがいました。探検隊では、自然界のエサが少なくなる冬だけ限定で、トンボ池にバードフィーダー(えさ台=野鳥のレストラン)を開店します。メジロさん、1月の観察会まで、もう少し待っててね。(右:トンボ池にて) ★ところで、ワタシがどこにいるかわかった?写真を広げて見つけてみてね。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月20日(月) スイセンのあまいかおり あまいかおりがする方へと目を向けてみると、ニホンスイセンが咲いていました。ほかの場所にあるスイセンは、まだ咲くじゅんびをしているところ。いつもより早い開花で楽しませてくれています。(左:校庭西側花だんにて) まつぼっくりが落ちてきてよろこんでいると、ピタッとおくにもぐりこんでいる幼虫がいました。マツカレハではないみたいですが、なにかほかのガの幼虫かな?(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月20日(月) しもばしらができていました お楽しみのトンボ池の氷はまだでしたが、校舎のうらでは、サクサクの霜柱(しもばしら)が見られました。霜柱になっているのを見るのはこの冬初めてかな。飴細工(あめざいく)のような美しさでした。(左:北校舎うらの畑にて) さて、22日(水)は「冬至(とうじ)」です。むかしから冬至には、ゆず湯に入ったり、カボチャを食べたりしますが、どんな日か知っていますか。しょくいんげんかんのところにポスター(写真右)を作って出しておきましたので、見てくださいね。(いっしょにユズのリースも作っちゃいました!) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月17日(金) つぶらなひとみの雪虫に会えました お昼どき、元気なスズメの群れが飛び去り、すっかり静まり返ったトンボ池を歩くと、小さな雪虫が足もとで飛んでいました。写真には色が出ませんでしたが、飛んでいる時はやさしい色のブルーグレイ。雪虫と呼ばれるアブラムシの成虫は数種類いるようですから、11月中旬に出会ったものとは種類が違うかもしれません。 アブラムシは単為生殖(たんいせいしょく)といって、メスのみで子を作っていていますが(おなじみのゴキブリも場合によっては単為生殖の方法をとる種があるそうですよ!)冬ごしする卵を産むために、秋の終わりから翅(はね)をもつオスとメスの成虫が発生します。交尾をして越冬卵(えっとうらん=冬の寒さにたえるたまご)を残すまでを、およそ一週間の命の間にやりとげるそうです。 この後、ピンっと翅を立たせるように広げて元気に飛んでいきました。(二枚共トンボ池にて撮影。写真右、正面から顔を見ると、つぶらな目が並んでかわいいです。) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年12月15日(水) 初霜(はつしも)がおりました 昨晩、一昨晩、流れ星は見られましたか? 昨夜10時頃、うちのあたりは雲が広がり見られませんでしたので、今朝は早起きして自宅のベランダから大きくてまぶしい流れ星1個と小粒の流れ星を2.3個、見ました。3時頃でしたが、意外なほど冬の星座がキラリ、キラリと良く見え、得した気分になりました 通勤中、石神井川では川霧(かわぎり)が見られましたよ。川の水の温度より、空気の温度の方が低くなったのですね。 その今朝の気温は2度。落ち葉の葉脈(ようみゃく=葉にとおるすじ)には霜(しも)がなぞるようについて、とてもきれいでした。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |
 | |
2021年12月13日(月) 巨大トンボ出現!! リース教室の時にあまったクズのつるを活用して、スタッフのSさんが、ステンドグラス風トンボのオブジェ、作ってくれました。冬の間も「トンボ池」をしっかり見守ってくれそうなやさしい目のトンボですね~ |
  |   |
2021年12月10日(金) あれ?冬はこれからなんだけど・・・ アジサイの冬芽をかんさつしてみると、あれ?落葉もしていないのに、春を待たずに『バンザイ!』をしています。今年は二度咲きを見せてくれたキンモクセイをはじめ、いつもよりずいぶんと早く、月桂樹(げっけいじゅ)の花のつぼみも出てきています。温暖化となりつつあるので、植物もそれに合わせ芽ぶき時期などを変えてきているのかもしれませんね。(東門花だんにて) ヤツデの開花期は長く、雄花(おばな)の後に雌花(めばな)が咲きます。香りで虫達を呼び、雄花から雌花へと受粉をしてもらいます。今日はミツバチがおとずれていました。ところで、ヤツデの花のかおりってかいだことありますか?(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月9日(木) えさはどこに残っているかな・・・ スズメ達が体の大きなヒヨドリ、ムクドリの群れについて行動しているように見えました。(野鳥のレストラン東門カキの木店にて) 寒い日をむかえるたびに生き物の数も少なくなってきていますが、ヤツデの花に元気なヒラタアブがやってきていました。冬でも日差しがあるとブーンと気ままにやってくるようです。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月3日(金) 天気がよい日は日なたぼっこ~ カナヘビが日なたぼっこをしてました。火曜日に会った赤ちゃんよりも少し大きい個体でした。カナヘビの産卵は5月頃から9月あたりにかけて3〜4回(1回の産卵で2~6個)するそうです。もしかすると今年はたくさん生まれていたのかもしれません。(左:校舎裏にて) リース作りの準備をしていると、フタホシテントウが出てきました。そのようすから、樹木の枝を切っている時からいたようで、針のような葉の間にすっぽりと入っていました。同じ樹木に帰したので、また葉の間にはさまって過ごしているかもしれませんね。(右:体育館にて、樹木枝は校舎裏より採取) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年12月3日(金) リース教室・じゅんびはOK! 夕方から体育館で明日のリース教室の準備をしました。隊員やスタッフ、協力者のみなさんがそれぞれに集めた材料を持ち寄り、種類ごとにならべて会場準備。写真はSさんとお父さんが日ごろから公園などで集めたといういろいろな木の実。どれもきれいですね!ほかにもいろいろな葉や実、手作りオーナメントなどがそろいました。わからないものはスマホで調べて名前のラベルを付けていきました。明日は参加者のみなさんに、自分で持ってきた材料以外にも、これらの中から好きな材料を選んで使ってもらう予定です。お楽しみに!! | |
手作りリース じゅんびのヒント集 (下に追加情報あり) 4日のリース作りに向けて、材料集めを始めている方が多いと思います。今年初めて参加される方からどんなものを集めたらいいのかわからないのでヒントがほしい、というお声がありましたので、過去の作品や情報をいくつか紹介します。でも、例にとらわれずまったく新しいものを自由に作って楽しんで下さいね。(木の実や葉っぱなどの一部は探検隊で用意して提供したものです。) | ||
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
  |   |   |
空き地などに生えているヨウシュヤマゴボウの紫色の実をベランダで干したもの。色も形も案外きれいですね。 (情報提供:Gママさん) | 公園で見つけたムクロジの実。緑色のも乾かしたらセルロイドのようになりました。これもきれい。 (情報提供:Gママさん) | マツボックリをラメ入りのノリでデコってみました。色が入るとキラキラ感も出てきれですね! (情報提供:2年生隊員のKさん) |
  |   |   |
木の枝、ストロー、ススキのくきで星を作ってみました。落ち葉や花びら、お菓子のカラフルな包みを使ったり、ヒモのかわりに布を細く切って使っても楽しいですね! (情報提供:スタッフのSさん) | 家にあったリボンを使って、リボンのかざりを作ってたら楽しくなって親子でいっぱい作っちゃった!当日、持って行くね。 (情報提供:OBのナオ) | イチョウの葉は集めやすく工作もしやすいのでおすすめです。バラの花を思い出しながら一枚ずつテープでとめるとくずれにくいですよ。チョウは小枝を体にしてつけています。 |
  |   |   |
| ツル植物のオニドコロのさや(=種をつつんでいる『から』)を川ぞいのフェンスで見つけました。形を観察しながら、ちょと厚めの紙でまねして作ってみました。あさがおなどいろいろな種を思い出しながら自由に想像して作るのも楽しいよ。 | 枝とエノキの実を見つけました。枝のようすを見ながら、枝がわかれるところにヒモをまいて顔にし、実を目にしてトナカイにしてみました。小さな実ですが、使わなくなった布などをまいて飾りに使っても楽しいです。 | 厚紙にハートや鳥の形を切りとり、枝をつけます。パズルみたいで楽しく作れます。枝のかわりに葉っぱ等でもおもしろいです。 ペットボトルキャップをテッシュ4枚くらいで包み、てんとう虫にしてみました。色をつけ、小枝やお菓子の包みなどをかざれば、できあがりです。 |
  |   |   |
| 松ぼっくりをさかさまにして、小人さんを作りました。鼻はジュズダマ、ヒゲはセンニンソウ(石神井川沿いにも咲いていた白い花のツル植物)、ぼうしはツタの葉っぱ2枚を使ってみました。 | 都内の紅葉がきれいな時期です。落ち葉をひろって来て本の間にはさんでおもしをして押し葉にしただけです。(かんそうざいのシリカゲルを使うと色がきれいに残るそうです。) | 2枚くらいのテッシュを使い、まん中をつまみながらねじって『じく』を作り、そのままの流れで『かさ』の円形を作っていきます。仕上げに『かさ』にテッシュをかぶせながらまとめてゆき、のりで整えます。ペンで色をぬり、まるく切った紙をはりました。 |
  |   |
2021年12月2日(木) 実やタネのかんさつ ユズリハの実にはヒヨドリやメジロがやってくるようです。ユズリハは春の若葉が出てくると、それまでついていた葉が、ゆずるように落葉することから名前がつけられたそうです。お正月のおそなえの飾りとしても使われます。(左:校舎裏にて) キキョウの実を見ていると、クサギカメムシがいました。(どこだかわかる?右側の実にいるよ) カメムシは成虫のまま冬をこし、春の繁殖期を終えるまで、一年半くらいの一生とされています。この時期はあたたかい場所を見つけながらすごしているようです。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年12月1日(水) 月桂樹のしげみで見つけたよ 月桂樹(ゲッケイジュ=ローリエ)の生けがきの手入れをしていると、雨や風をしのげるくらい葉がしげっているのが良かったのか、アカホシテントウ(左)や、種類のちがうテントウ虫が過ごしていました。 オオカマキリの卵鞘(らんしょう=たまごのかたまり)もありました(右)。(2枚共に校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月30日(火) そろそろ冬眠だね おやすみ~! 片づけをするとよいことがあると言いますが、かわいいカナヘビの赤ちゃんがいましたよ。かれ葉の中にいたのを起こされたので、最初はビックリしていましたが、石の上にのせると、トロンと目をとじてしまうくらい眠いようでした。そろそろ冬眠(とうみん)だね。見つけた場所にもどし、たっぷりの葉でおおいました。(左:園芸倉庫前にて) お昼時、スズメとメジロが10羽くらいの群れとなって過ごしていました。とまらないおしゃべりを聞きながら追いかけてみると、トンボ池から野鳥のレストラン、東門店へと向かっていました。そろそろトンボ池でも開店準備をしたいですね。(右:野鳥のレストラン東門カキの木店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月24日(水) 春からくり返し咲いています タビラコ(コオニタビラコとも言う)は春から咲きはじめ、綿毛のついた種を風に運んでもらいながら、くりかえし咲き、今の時期でもカタバミといっしょによく咲いています。今日は花粉だらけになっているハナバチが来ていました。(右:校庭にて) 本日の野鳥のレストラン東門店ではムクドリ数羽と、スズメの団体さんでにぎわいを見せていました。(左:東門のカキの木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月25日(木) リースのかざりを探そう・作ろう! 南天(なんてん)。のどあめでおなじみの薬用植物。 「難(なん)を転(てん)じて福となす(むずかしい事がおきても、そこから学んで、よりよくすること)」という言葉にかけて、えんぎが良い植物とされているようです。この時期に色づく赤い実はヒヨドリやジョウビタキなどの野鳥が好んで食べます。リースかざりにも入れたくなりますね。(左:東側フェンスにて) リース作りにむけて、木の枝、ストロー、ススキのくきで星を作ってみした。今回は家にある物をつけましたが、落ち葉、実、花びらを使ったり、お菓子のカラフルな包みを切ってはりつけたり、ヒモのかわりに布を細く切って使っても楽しいですね! みなさんも「こんなふうに作ったよ!」というものを知らせてくれるとうれしいです。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年11月23日(火) 野鳥のレストラン・カキの木店の夕ぐれ 夕暮れ(ゆうぐれ)どきの庭のカキの木です。 今日やって来たのは、左上から時計回りにシジュウカラ・スズメ・メジロ・ヒヨドリでした。 葉が落ちて、野鳥の観察はしやすくなる季節ですが、そろそろ自然界のエサが少なくなり、鳥たちには、きびしい冬がやって来ます。 昨日は二十四節気の「小雪(しょうせつ)」本格的に寒くなり、北国では雪もふり始める頃です。 天気のよい日は夕やけ空を見るのも楽しみです。今日は動画を撮ってみました。(→こちら) (4枚とも自宅にて) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
  |   |
2021年11月22日(月) バナナ虫カクレミノの葉にかくれる ツヤのある3つにわかれた葉をもつカクレミノは、中型の野鳥、ヒヨドリなどが好む実をつけます。野鳥が食べた実や種(たね)はフンとなって落ち、かんきょうが合えば芽を出します。 このカクレミノもそんなふうに野鳥がはこび、大きくなったようです。 名前の由来は、天狗(てんぐ)のお話に出てくる持ち物『かくれみの』に葉の形がにていることだそうです。 今日は葉のうらを見るとツマグロオオヨコバイ(通称バナナ虫)がのんびりと、雨宿りかねて上手にかくれていました。(2枚共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年11月19日(金) やっぱり学校が好き!? 校舎の2階にいたカマドウマの赤ちゃんに[上小に入りたい子は、まずは校長室へ]とまつせん(事務局)がコメントした(↓9月27日)次の日、本当に校長室そばにある職員玄関に来ていました。作り話と思われそうだとヒミツにしていましたが、やっぱりカマドウマは上小が大好きのようです。その後も別名のゆらいとなっているトイレでくつろいでいたり、今日も『ここもおそうじしてね』と言わんばかりに、かさ立ての下からホコリをつけて出て来たりしていました。かさ立てからでてきたカマドウマは足をケガしてしまったようで、しずかな校舎裏の草地にはなしました。成虫のまま冬ごししますが、5℃くらいになれば冬眠するそうです。(中校舎、昇降口にて) ★そう、別名「べんじょこおろぎ」などともよばれるカマドウマですが、古くは『いとど』とよばれ、秋を表す「季語」(きご=はいくなどで、季節を表す言葉)でもあるんですよ。芭蕉(ばしょう)の俳句(はいく)にも『海士の屋は 小海老にまじる いとどかな』(あまのやは こえびにまじる いとどかな)とあります。「さなかとりのまずしい家に入ったところ、とりたての小エビのカゴの中でカマドウマも一緒にとびはねていた」というくらいの意味でしょうか。 (画像と情報:スタッフのSさん) |
 | |
2021年11月18日(木) 角度そくてい中!? 「アゲハの幼虫をみつけたよ!」と言って、ふで箱の中からそっと取り出し「レモンの木についていたよ。」とうれしそうに話すKくん。まだいるんですね。 それにしても、分度器にのって登場のアゲハの幼虫はそうめったにいませんね。 「脱皮が見られたら最高だ!」と元気に話してくれました。 本当に脱皮が見られたら最高ですね!アゲハは5回の脱皮をくり返して蛹(さなぎ)になります。そして、この時期の蛹は夏とはちがい、寒い冬をのりこえる特べつなつくりとなるようです。脱皮を見られたら絵をかいてね、と約束してわかれる時には、ふでばこに大切にしまわれていた幼虫は、そのあと担任のA先生が用意して下さったプラ容器の中に、ちゃんとレモンの葉といっしょに入れられていました。(校内にて:ジュニア隊員2年生のKくんより) (画像と情報:スタッフのSさん) |
  |   |
2021年11月17日(水) ヒノキのようないいかおり かぎに来てみて トンボ池とプールの間には、じょうぶな木のカイヅカイブキが20本以上うえてあり、生垣(いけがき)と言って木のかべになっています。手入れをしていると、ずいぶん高い所にカタツムリ(左)がいました。カラが少しこわれていましたが、葉にぎゅっとくっついているので、休んでいるようです。この場所は冬でも晴れた日はとてもあたたかいのですが、カタツムリはふつうは落ち葉や石の下にもぐりこんで、寒さや敵から体をまもるようですから、手入れがすんだら生垣の下に、もう少し落ち葉をひいておこうと思っています。 キタキチョウ(右)がやってきて羽を休ませていました。カイヅカイブキはイブキ(別名ビャクシン)という海岸のがけ地などで育つ樹木の変種とされています。イブキはヒノキ科の植物なので、カイヅカイブキも手入れをしていると、ヒノキのようなよい香りが洋服などにもつきます。ちなみにその香りにはリラックス(安心感)やリフレッシュ(清涼感)など、気持ちにはたらきかけるこうかがあるのだとか。キタキチョウも、もしかしたらそんな香りにさそわれて、やってきたのかな。(2枚共にトンボ池プール側にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月16日(火) 雪虫飛ぶ!⇒冬が来るよ~ 自転車にのっていると、洋服のそで口に雪虫がくっついていました。 アブラムシの一種が冬ごしする前に白いホワホワしたもの(体から出すロウ物質だそうです)をつけて飛ぶのを、地いきによっては「雪虫」とか「しろばんば」などと呼び、秋の終わりの風物詩(ふうぶつし=その季節を感じさせるもの)とされています。そのすがたはまさに雪のようです。「冬がやってくるよ~」と知らせているようにも感じます。(朝の通勤中の路上にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月16日(火) 野鳥のレストラン「東門店」 営業中 今日もチィーチィーとなかまどうしよび合いながらメジロがやって来ていました。 「これは食べごろだね」と、いっしょに来ていたスズメたちと食事を楽しんでいると、体の大きいムクドリの団体さんがやって来て「さぁさぁ、どいてどいて」とおいやられてしまいました。 冬でも葉の色を変えずに、ツヤのある葉のモッコク。野鳥たちは一年中、この木によく集まっています。この時期は赤い実をつけ、おいしいおやつとなっているようです。食べているようすはわかりにくいのですが、実のカラの音なのか、あたりでパチ、パチ、とかわいた音がしてきます。校門を通る時は、ちょっと立ち止まって耳をすませてみよう。(2枚共東門にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年11月15日(月) このカキ、食べごろかな? まだ渋(しぶ)いかな?体をグイっとのばして、ようすをうかがうメジロがいました。 鳥はいっぱんに、視力(しりょく=見わける力)はすぐれているものの、においをかぐ力は弱いと考えられています。でももしかすると、メジロは色だけでなく、くちばしを使ってかたさをたしかめたり、私たちと同じように鼻を近づけてにおいをかぎ、カキの食べごろをかぎ分けたりしているのかもしれない・・・と思いました。(東門・カキの木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) ★鳥がにおいをかぐ力についてはまだあまり研究が進んでいないようです。鳥の種類によってもだいぶちがいがあるという報告もあるようです。身近な野鳥、メジロはどうなんでしょう。インターネットで調べていくと「メジロの好物のミカンの近くに、メジロがふつうは近づくことのないバラにハチミツをぬって置いてどうなるか」実験してみたなんていう話も出ていました。みなさんだったらどんな実験を考えますか?冬はえさ台などを設置して身近に野鳥を観察できる季節です。いろいろ実験や観察をしてみましょう。 |
 | |
2021年11月15日(月) 私はブタクサではありません 秋になると、ブタクサによる花粉症(かふんしょう)が話題になりますね。時々ブタクサとまちがわれる植物として開花時期や姿(すがた)がそっくりなセイタカアワダチソウがあります。これは、セイタカアワダチソウ。セイタカアワダチソウはすっとした葉っぱ、ブタクサはギザギザの葉っぱです。 セイタカアワダチソウは、みつをとったり、花を楽しんだりするために北アメリカから日本に持ちこまれた植物です。原産地では薬草として大切にされていて、漢方薬でも一枝黄花(いっしこうか)という名前で使われているそうです。(バッタ原っぱにて) (画像と情報:スタッフのSさん) ★ブタクサは風媒花(ふうばいか)といって、風でたくさんの花粉を飛ばし、秋の花粉症の原因の一つとも言われる植物ですが、セイタカアワダチソウは、虫に花粉を運んでもらう花(虫媒花=ちゅうばいか)なので、たくさんの花粉を飛ばすことはないのですね。みなさんが見る秋の黄色い花は、どっちかな?立ち止まってかくにんしてみよう。 |
 | |
2021年11月12日(金) 初記録! ツバメのしっぽみたいでしょ ムラサキツバメ。上小初記録です。 後羽の尾状突起(びじょうとっき=しっぽのようなでっぱり)をツバメの尾羽に見立てたのでしょう。(このしっぽがないムラサキシジミというチョウもいます。) ヒラヒラと舞うたびに深いムラサキ色がかがやきます。羽を広げた様子は見られませんでしたが、とじた羽のうらがわも何色も色をかさねたような味わい深い羽色です。 この種はもともと南方系のチョウでしたが、温暖化の影響や、街路樹や庭木に食草となるマテバシイがさかんに植えられたことで関東でも見られるようになってきたと考えられているそうです。(上:東門花だんにて) |
  |   |
こちらは、ウラナミシジミ。日本以外にも広く分布するシジミチョウの仲間。春より世代をくりかえしながら北上してきますが、寒い冬は越せずに死んでしまいます。でも西日本の暖かい地域では一年を通して見られ、関東でも房総半島南端では越冬するそうです。翅(はね)の下をよく見ると、目のような黒い点と、翅からつき出たところが触角(しょっかく)のようにも見えます。これは翅のもようを頭部に似せて、敵の目をだますためではないかと考えられています。さらによく見ると翅の黒い目の上はキラキラさせて、下のほほにはオレンジ色をのせています。(上左) 翅を広げると(上右)ヤマトシジミに似ていますが、大きさにちがいがあり、ウラナミシジミの方が少し大きいです。 幼虫の食草はマメ科植物で、クズもその中に入ります。リース作りに参加するとクズのツルとりをしますから、もしかすると観察できるかもしれません。(2枚共に東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月12日(金) ヒルガオのつるに来てたのはだれ? からまったヒルガオのツルをとっているとオオカマキリの卵鞘(らんしょう=たまごのかたまり)がありました!(左)この中には卵が200〜300個もあるそうですから、気がついてよかったです。 そのヒルガオの葉はずいぶん虫くいだらけで、だれのしわざかしら?と思いながら作業をすすめていると、どうやらホオズキカメムシだったようです。キラキラした卵のカラ(右)がありました。(2枚共に電気設備のフェンスにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月10日(水) バラの実・・・リースのかざりに使えそう! 上小のバラは、花が咲き終わると次の開花時期に向けて切ります。でも、うっかり残しておくと、野ばらと同じようにぷっくりと赤い実をつけて目を楽しませてくれます。リースのかざりにしてもよいですね。リース作りの申し込みは今週の土曜日がしめきりです。(左:校舎裏にて) アシタバレストランがひっそりとしてきたこともあり、たおれたくきなどを手入れしていると、からまっていたカラスウリの葉に来ていたのかクロウリハムシがいました。葉に円形にキズをつけ、円形の中の部分をたべる『トレンチ行動』という食事方法をとります。キズを入れることにより、植物が虫たちに食べられないように出す、にがみやネバリの物質をさけることができるのだそうです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月9日(火) カタツムリにもいろんな種類がいるよ あまり見かけない黒いカタツムリがいました。『カタツムリ同定』で検索すると、日本自然保護協会のサイトがあり、そこで殻(から)の特ちょうを見分けるとウスカワマイマイという種類かなと思われます。でも正確に見分けるのはむずかしいようです。日本にすむカタツムリは700種くらいもいるそうです。(左:東門花だんにて) 別名『テングのうちわ』=ヤツデの花が咲いています。花のかおりで虫たちをよびよせて、咲きおえてからゆっくり黒い実となるのは鳥たちが子育てをはじめる5月ごろ。上手に野鳥をまねいて食べてもらい、たねをまいてもらいます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月8日(月) 「ツマグロ」のなかまたち ヨメナの花には毎日のようにさまざまなハナアブ、ハナバエがやってきてどちらも植物の受粉の手伝いをしてくれます。今日は他の個体より、ずいぶん小さなホソヒラタアブが花びらの上で脚をスリスリしながら身づくろいをしていました(写真左) スジもようの入った青緑色の目と、のびた口が特徴のツマグロギンバエ(写真右)。 ツマグロと言えばチョウのツマグロヒョウモンを思いうかべますが、そのほかにもツマグロとつく名前の生き物が、身近にいろいろといます。パッとうかんだのは黄みどり色の虫、名前は「バナナ虫!」と親しみをこめて思わず言ってしまいますが、正式にはツマグロオオヨコバイ。そのほかツマグロと名前につく生物は、体の先端(せんたん)部分が黒いことからつけられているそうです。ちなみに海にはツマグロと言う、ヒレの先端が黒いサメの一種も生息しています。(トンボ池・プール側から撮影) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年11月6日(土) イラスト日記 トンボ池ミニ観察会 (左上から時計まわりで) コモまきをすると、さっそく様子を見にきたのはクモだったようです。 プール観察ではアキアカネがいました。メスの個体には赤くないものもいます。 クヌギの木の下で大きなフン発見。1㎝くらいの大きさですから、大きな幼虫なんだろうなぁ・・・もしかしたら、オオミズアオの幼虫かな? なんてそうぞうしながらみんなでクヌギのこずえを見上げたけれど発見できず。でも楽しみですね! 海をこえてやってくるウスバキトンボ。冬はこせずに死んでしまいますが、新天地をもとめて毎年やってきます。 虫にはそれぞれ得意わざがあるのです。それは死んだふり!?だったりすることもあります。きれいな緑色にかがやくアオドウガネ。 (イラストと情報:スタッフのSさん) |
  |   |
2021年11月5日(金) 冬ごしするチョウです 成虫のまま冬ごしするキタキチョウ(キチョウ)。幼虫の食草はハギなどマメ科の植物です。 草かげに休んで休んことも多く、冬もそのようにして、じっと春をまつそうです。(左:東門花だんにて) ハナミズキの赤い実を食べおえ、一緒にきた仲間とさえずるシジュウカラ。これもおいしいよ!って伝えているのかもしれません。黒のネクタイもようが太いとオスで、細めはメスと見分けるそうです。(右:東門・ハナミズキの木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年11月4日(木) 冬が来る前におなかをいっぱいに 渋柿(しぶがき)がみのる柿の木ですが、実がトロトロにやわらかくなってくるころにはあまくなるようです。さまざまな野鳥がよろこんでやってきています。昼どきはスズメの団体さん(5.6羽)がおとずれていました。ちなみに渋柿は、ほし柿にしてもおいしいですが、ヘタの部分に焼酎(しょうちゅう=アルコール分35度くらいの強いお酒の一種)をかけてから、ビニル袋に入れてとじて数日おきます。すると渋さがぬけおいしくなるそうです。これはお酒を使うので、大人と相談してためしてね。(左:東門の柿の木にて) モモスズメガの幼虫。この個体はとびっきり大きくて10㎝以上ありました。蛹(さなぎ)になるため地上に下り、もぐる場所をさがしていたようです。見つけた場所の近くにあるバラ科の梅の木の葉をたっぷり食べて、すくすく成長したのでは?と思います。(モモなど「バラ科」の植物を食草にしているのでこの名前)成虫はこげ茶色のかれ葉をマントにしたような姿です。(右:トンボ池前・梅の木のそばにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月28日(木) 太陽がまぶしぃ~!? 気持ちのよい秋晴れでした。ヤマトシジミが羽を広げて体をあたためている様子がよく見られるようになりました。黒っぽい羽なのでメスのようです。(左:プールにて) 「太陽がまぶしぃ〜」っていうしぐさは人間といっしょ!?いえいえ、ちがいます。 日なたぼっこをしていたアキアカネ。ときおり両前足で頭をかくような感じで、くつろいでいました・・・ん?やっぱり「まぶしぃ~」って事なのかな!?(右:プールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月27日(水) 鳥でもあり飛行機でもある お昼どき、花バエやナミテントウがススキの葉にとまりのんびりしていました。食事は終わったのでしょうか。気持ち良さそうな後ろすがたです。(左:トンボ池にて) ブドウトリバ(葡萄鳥羽)、15mmくらいの不思議なすがたをしているガの仲間です。羽に細かい毛が生えていて、ひろげてみると鳥の羽のように見えます。幼虫はヤブガラシ、ツタなどのブドウ科の花や葉などを食べるそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
※ブドウトリバ。影を見るとどこかのアニメに出てくる飛行機のようではありませんか。写真ではちょっとわかりにくいですが、かくれている3枚の後羽はまさに鳥の羽毛のようです。円を描きながら飛ぶ様子が「タケコプターみたいだった」などと言っている人もいました。ちょっと見てみたいですよね。くわしくは「ブトウトリバ・羽」で検索して「千葉 県立博物館」のページなどにわかりやすい写真があります。 (画像提供:隊員のGママさん・10月15日) | |
  |   |
2021年10月26日(火) 「前の方が赤い透きとおった羽」っていう意味だよ マエアカスカシノメイガ(前赤透 野螟蛾)。秋の七草のひとつフジバカマの花みつを吸っていました。幼虫はネズミモチやキンモクセイなど、モクセイ科の葉を食べるそうです。(主事室前にて) 「ちょっと来て〜!」とよばれて行くと、ペタっとタイルにはりつくヤモリがいました。 かわいい・・・「これからせんざいをまくからひなんしようね」と、うらの草地へ連れて行きました。(中校舎1階 トイレにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月25日(月) 見つかったらたいへんだ・・・ はち植えのキンカンの枝で、じっとしているマユタテアカネ(左)。今日はこれから雨がふるから、早めの雨やどりかな?とも思いましたが、プールをのぞくとハクセキレイ(右)がいました。ハクセキレイはプールのまわりを歩きながら、おいしいえものを探しているようでした。 もしかしたら、マユタテアカネはプールではのんびりできなくて、ひなんしてきたのかもしれませんね。(トンボ池わき「バタフライゾーン」とプールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年10月22日(金) ざんねん!ハエにやられた! 9月のたんけん隊活動日に、主事のSさんからもらったセスジスズメの幼虫を育てていました。ヤブカラシの葉をむしゃむしゃと食べ、まるまると太って、入れた土の中で無事さなぎになりました。羽化は来春か、と思いながらも時々のぞいていました。先日ようすを見ると、異変が・・・! なんとイエバエににた大きなハエが4匹も土からはい出しているではありませんか。 さなぎをほり出してみると、やはり大きなあながあいていて、なかみは空っぽでした。 この大き目のハエ、イエバエににているのですが、ヤドリバエの仲間かなあ、と思います。さなぎをつくる前から、幼虫のからだにたまごがうみつけられていたものと思われます。アゲハの仲間にもつく寄生(きせい)バエです。来春の羽化をまたずにセスジスズメが死んでしまうのは悲しい結末です。 スズメガを中心に考えればそうですが、これも自然の営み(いとなみ)で仕方のないことですね。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |
  |   |
2021年10月21日(木) 秋の花々をもとめて うしろ脚(あし)の太さがとくちょうのアシブトハナアブ。ミツバチやチョウと同じで、さまざまな花の花粉や花蜜をいただきにやってくる花アブです。(左:トンボ池にて) トンボ池からプールへと顔を出して咲くのはヨメナ。あびる日差しのちがいで花のふいんきも変わります。今日はヤマトシジミがおとずれて、羽を広げていました。あたたかい日差しが心地よく感じる季節です。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月20日(水) 秋になるとまっ赤になります コノシメトンボ。秋の日差しをまんきつ中です。秋の風物詩(ふうぶつし=そのきせつを感じさせてくれる代表的な生き物、食べ物など)「赤とんぼ」ですが、アカトンボという種類のトンボはいません。このコノシメトンボなど、秋になると体が赤くなるトンボをまとめて「赤とんぼ」とよんでいます。(左:プールにて) キンケハラナガツチバチ。ツチバチの仲間は土の中にもぐり、コガネムシの幼虫などに産卵します。見た目とちがい、おとなしいハチです。(右:トンボ池アシタバレストランにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月19日(火) わたしたち「黄色」グループです 上小には10本以上のクワの木がありますが、手入れをしていると、よく出会えるのがキイロテントウです。葉につく菌を食べてくれるパトロール隊員でもあります。(左:駐車場花だんにて) キアゲハの幼虫(中齢)がいました。今からだとさなぎになって越冬(えっとう=冬ごし)するのかな?と思います。元気に育ってくれるといいですね。(右:トンボ池・バタフライゾーン食草のアシタバにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月18日(月) あたたかい秋の日ざしの中で アキアカネ。あたたかい日差しをたっぷりあびながら過ごしていました。 (左:バタフライゾーン・開花後のブッドレアにて) 10月中旬の気温が下がるころになると、オンブバッタの繁殖期(はんしょくき=たまごを産む時期)が始まるそうです。交尾のあとメスは土の中に卵を産み付けます、卵は来年の梅雨時期あたりに孵化(ふか=たまごからかえること)し、命をつなげていきます。やくわりをはたして、たいていのオスは交尾後、メスも冬を越さずに死んでいきます。(右:「バッタ原っぱ」にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月15日(金) クワの葉で見つけた小さな星空★ クワ科の植物が好きなキボシ(黄星)カミキリ。体長は3㎝くらいなのですが、触覚(しょっかく)の長さが体の2倍くらいあります。トンボ池にもあるイチジクもクワ科の植物ですから、時々おとずれているかもしれませんね。(左:東門花だん・クワの木にて) よくひびく声で秋の夜をにぎわすオスのアオマツムシ。中国からの外来種で、日本の在来種のマツムシとは反対に生息数が増えているようですよ。(右:東門花だん・落葉広葉樹ハナミズキにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年10月14日(木) 「焼きとうもろこし」見っけ! お昼時、コノシメトンボ(左上)と、後からアキアカネのメス(右上)がおとずれました。(プールにて) クワの木ではキイロテントウの幼虫やさなぎ、そして成虫がそれぞれすごしていました。さなぎ(左下)は、焼きとうもろこしのような感じがしませんか? ほかにもクサカゲロウのまゆのようなもの(右下)もありました。大きさはとても小さくて5㎜くらいです、じょうずに作るんですね。(校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年10月13日(水) 南の国から来ました 小雨のふる9時頃にプールへ行くとウスバキトンボがいました。 羽化したてのようです。(左上) ウスバキトンボの幼虫はとても成長が早く、卵から1か月ほどで羽化します。近くには、ツヤのあるぬけがらがありました。(右上) もともと南の国、熱帯のトンボです。春になると集団でやってきて、世代交代(成虫のじゅみょうは1~2か月くらいのようです)をくり返しながら、日本を北上していきます。 1時間後に見にいくと、羽をひろげていました。(下の2枚) 風にのって長距離移動をするためにうしろの羽がはば広いのが特徴。 南の国のトンボですから、温暖化していると言われてはいても日本では冬は越せずに命をまっとうしていきます。広い海をわたり冒険をしにやってくるウスバキトンボ。毎年あきらめず日本にやってくるくらいですから、きっと雨の初飛行でも、ワクワクしているのではないでしょうか?(4枚共にプールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月13日(水) 雨宿りはネズミモチの葉のうらで 雨の日、虫たちはたいてい葉のうらなどで静かに過ごしているようです。ネズミモチの木の葉をめくるとナミテントウの幼虫がいました。(左) その木の下にはカタツムリ(右)がいましたよ。(2枚ともプールわきの「バッタ原っぱ」にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月12日(火) 雨のふり始めの校庭で・・・ ポツリと雨がふりはじめたお昼ごろ。 草の手入れをしているとオンブバッタがしげみの中から出てきました。どうする?またもどろうか?などと話しているようでした。メスがオスをオンブしていますが、食事の時は下りるそうです。(左:プールわき・バッタ原っぱにて) ギンメッキゴミグモ。5㎜くらいの大きさです。かけた網(あみ)のまん中で脚(あし)をたたんでじっとしていますが、ちょっと網がゆれると、えものが引っかかったゾ!っとすばやく脚を広げるようすが見られます。どうやら今回のゆれは雨つぶだったようです。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年10月11日(月) 日本でただ一つ?ギンヤンマのいる「教室」 3年生の先生から「プールにヤゴがいましたよ!」との知らせをもらったので、教室で観察中の水そうをのぞいてみると、米つぶくらいの、ギンヤンマの赤ちゃんヤゴがいました。みどり色のやじるしの先に目があります。上小は毎年の3年生のとりくみにより東京ではめずらしいギンヤンマがいる学校ですが、この季節に教室でギンヤンマのヤゴを観察しているのは、たぶん日本中でもここだけなのではないでしょうか!?(左上:3年生の教室にて) アシタバレストラン本店にて。メニューの『葉っぱ』はキアゲハの幼虫の定番。おなかいっぱい食べて、そろそろサナギになるじゅんびかな。(右上) ヤマトシジミ。こちらのメニューは『花みつ』です。どんな味なのか、気になりますね。(左下) おとずれてみたけれど、あまりそそられないようすのクロウリハムシ(右下)。大好物はキュウリなどのウリ科の植物ですが、キキョウやナデシコなどの花にもこっそりやってきます。ひみつですが、セリ科のアシタバレストランには、うらメニューの『キュウケイ』があるんです。(3枚共にトンボ池・アシタバレストラン本店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月8日(金) プールが生き物たちの楽園に 最近、トンボ池でトンボを見かけないなぁ・・・と思ったら、プールにコノシメトンボのオス(左)とイトトンボ(右)がいました。プールは広くてまわりもよく見えます。しずめたコンテナから生える草は特にトンボたちのお気に入りの場所のようです。 また三年生が作ってくれたうき島には、小さな虫たちも来ていますし、3年生が放流してくれたクロメダカも小さな目をキラキラさせて元気に泳いでいます。 プールが「生き物たちの楽園」になっているようです。(上小プールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月7日(木) 「やっちまったぁ・・・」のポーズ あたまに手をのせて「やっちまったぁ〜!」って感じのオンブバッタ。草地をはなれて、なぜか自転車おきばに来ていました。ここにいるとあぶないので、校舎のうらへつれて行きました。(左:職員自転車置き場にて) 豆柿(マメガキ)。1~2㎝くらいの小さな柿です。 まだ青いうちに実をつぶして発酵熟成(はっこうせいじゅく)させたものを柿渋(かきしぶ)と言って、木材を長持ちさせるための塗料(とりょう=ペンキなど)や、布を染(そ)める染料(せんりょう)、せっけんなどに入れて抗菌(こうきん)にも使われてきました。( 2020年には、渋柿からとれる柿渋に、新型コロナウィルスを無害化させる作用があることが、奈良県立医科大により発見されたそうです ) マメガキは渋柿(しぶがき)で、食用というより柿渋を取るための木ですが、黒く熟してくると甘くなります。(右:校庭にて) ※上小には、東門やジャングルジムのそばなどに学校に植えられる木としてはめずらしいマメガキの木があります。開校当時、校庭に植える木が足りなかった時、地域の方々がお庭などにあった木を寄付して植えた下さったと聞いています。上石神井では柿渋を取るために古くから農家さんのお庭などにマメガキが植えられて活用されていたことが想像されます。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年10月6日(水) 朝ごはんだよ~ 朝日をあびながら、メマツヨイグサの花のみつに夢中になるミナミヒメヒラタアブがいました。マツヨイグサのなかまは、夕方から開き、朝になるとしぼんでしまう夜の花ですが、秋が深まってくるとお昼くらいまで開いていることもあるようです。(左:校舎裏にて) ヤマトシジミ(チョウ)が、ヒロハホウキギクをおとずれていました。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年10月5日(火) アオギリコーヒー作ってみました 9月30日の「見つけたよ!」コーナーで紹介したアオギリの実が、食べ物がなかった戦争中、コーヒー豆の代用品(=代わりの品)として使われたこともあると聞き、さっそくためしてみることにしました。 先日の台風で折れた枝を公園でもらってきました。種だけにして約50g、洗って乾燥(かんそう)させたものをコーヒー屋さんのにおいになるくらいまで炒(い)って、確か一杯分10gくらいだったはず、とコーヒーミルで挽(ひ)いて淹(い)れたら薄(うす)い「コーヒーのようなもの」ができあがりました。 【アオギリコーヒー試飲(しいん)感想】 ・これはコーヒーではない。 ・代用としてはそれっぽい。 ・苦いけど酸味(さんみ)がなくてわりと好き。 ・苦い、渋(しぶ)い(炒りすぎた?) ・さとうとミルクを入れるとおいしい。 ※すぐに試してみるところは、さすが探検隊員さんですね。コーヒー好きの人は戦争中もそこまでしてもコーヒーを飲んだのかぁ・・・ ★自然のものを口に入れる実験・体験は、大人の指導の下で安全性をよく確かめた上で行うようにしましょう。 (情報と画像:隊員のGママさん) |
 | |
2021年10月5日(火) かくれんぼはとくいです! 中休みに2年生隊員のKくんから教えてもらったアゲハのさなぎ。Kくんが「コンクリートに擬態(ぎたい=色や形を別のものににせて、敵に見つからないようにすること)してるみたい。」と教えてくれました。(上:西側の登校門近くにて) 「なるほどね〜」と感心しながら、まわりをそっと囲い、説明を付けておきました。(下) このサナギは昨日までは幼虫で、最初の発見者、同じく2年生隊員のSさんがじっくり観察していたようです。 アゲハの種類はちょっとハッキリしていないのですが、子ども達の観察力にビックリです。 (情報:2年生隊員のKくん&Sさん・画像:スタッフのSさん) | |
 |  |
  |   |
2021年10月4日(月) 野鳥に食べられないよう気を付けてね チャバネアオカメムシの幼虫。むらさき色の小さな実をつけるコムラサキにいました。 きけんを感じたりするとにおいを出すカメムシですが、そっと指にのせたりして観察できる昆虫です。今日ものんびりしていましたが、この場所はコムラサキの実を食べに、野鳥がやってきます。あまりのんびりしていると小さなカメムシは野鳥のごちそうなので、お腹に入ってしまうよ〜(左:北園芸倉庫前にて) キタキチョウがヨメナをおとずれていました。幼虫の食草はネムノキ、ハギ類などのマメ科の植物で、若葉や新芽にたまごを一個ずつていねいに産み付けるそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月30日(木) 人気店「アシタバレストラン」へようこそ! ツマグロオオヨコバイ(通称バナナムシ)はカメムシのなかまで、セミにちかい昆虫。ストローのような口をさまざまな植物の茎(くき)や葉にさして汁(しる)を吸います。 セミと同じ発声器官(はっせいきかん=声を出すしくみ)をもっていて、人には聞きとることができない音で仲間たちと過ごしているようです。虫達のおしゃべり、聞いてみたいですね。(右:トンボ池にて) コアオハナムグリ(小青花潜)。幼虫は植物の根など、成虫は花粉などを食べます。 今日は人気のアシタバレストラン2号店へおとずれ、お食事を楽しんでいました。(左:2号店場所、校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月29日(水) 3時のおやつだよ~ よいしょ!ナミテントウの幼虫が脱皮して、さなぎになっていくところ。このあと、からだをススキの葉にピッタリとつけていました。(左:プールわきの草地「バッタ原っぱ」にて) 『3時のおひめ様』のほかにもかわいらしい呼び名をもっているハゼラン。3時ごろになると咲きはじめる花を、アリも楽しみにしているのかな?南アメリカから来た外来種です。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月28日(火) ビロードって知ってる? ビロードモウズイカ。ビロードっていうのはソファーなどに使われる手ざわりのよい布(ぬの)の名前。じっさいに葉っぱをさわればなっとくするよ。大きなふわふわの葉っぱから、アメリカ中西部では「カウボーイのトイレットペーパー」なんてよび名もあるんだって。ほかにもたくさんのよび名がある植物。薬草にもなるといわれていますが、外来種です。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン(オス)。最近、赤いラインの入った黒い幼虫を見つけては『害虫が出たよ!』と伝えにきてくれる人がいますが、どくはなく、チョウの幼虫だと伝えるとみんなびっくりします。あの毛虫がこんなオレンジ色のチョウになるなんて、そうぞうしにくいですよね。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月27日(月) たんけん隊に入りたい!? たんけん隊のけいじ板にいた5㎝くらいのヤモリの赤ちゃん。きょうみしんしん、目がキラキラしています。んっ?もしかしたら、たんけん隊に入りたいってことかな?トカゲの石積みがある「バッタ原っぱ」(=プールわきの草地)にはなしました。(左:トンボ池にて) ※たんけん隊に入りたいヤモリや人間の子どもは、上の「問い合わせ」ページから①学年②クラス③お名前を知らせてね! カマドウマの赤ちゃん。1㎝くらいの体につぶらな目がかわいい!2階のろうかにいました。どこからきたのかな?もしかしたら、上小に入りたいってことかな?(右:中校舎にて) ※上小に入りたいカマドウマや人間の子どもは、まずは校長しつへ! (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月24日(金) おなかの中は卵でいっぱい? 2年生が見つけたカマキリ。おなかが大きくて、はちきれそうです。寄生虫じゃない?と心配してくれましたが、産卵場所を探していたのかな?校舎うらへつれていきました。ちなみに寄生虫(ハリガネムシ)かな?と分からない時には、ちょっとだけ、おしりの先を水につけてみるとよいそうです。(左:中庭、手洗い場の下にて発見!) ヨメナ。うすむらさき色の野菊には、ヒラタアブなど小さな虫がおとずれます。春には若葉をヨメナごはんにしたりと、おいしいくいただくことができます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月21日(火) 秋の七草、いえるかな? お月見におそなえするススキ。ススキの穂(ほ)が動物のおっぽににていることから、尾花(おばな)とも言われ「秋の七草」のひとつです。(左:校庭にて) ①「秋の七草を覚えよう」(→1分間動画) ②「秋の七草を覚えよう」(→PDFファイル) ん!ごちそう・・・ナナホシテントウとヒゲナガアブラムシのなかまのようです。でも、朝食はすませました、とそのまま枝の先をめざすナナホシテントウでした。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月20日(月) アオスジアゲハの産卵 今日はとてもいい天気なので校庭開放に行きました。 校庭の、百葉箱(ひゃくようばこ)のとなりの木に、アオスジアゲハが卵を産んでいました。 近寄っても逃げず(左)、いくつも小さな卵を産み付けていました。(右) どんな幼虫が孵化(ふか)するか、楽しみです。(写真はいずれも校庭にて) (写真と情報:2年生隊員のSさん) ※アオスジアゲハはとても美しいアゲハですが、ふだんは木のこずえの高いところを早いスピードでとんでいて、なかなか観察したり、つかまえたりするのがむずかしいチョウです。でも、産卵の時はこんなに間近に観察できるのですね。この木はアオスジアゲハが好きなクスの木のなかまのヤブニッケイかなと思われます。葉っぱをもんでにおいをかぐと、どくとくのよいかおりがします。低いところにも葉が出ているので、アオスジアゲハの卵や幼虫を間近に観察できてありがたい木です。右の写真、かく大してたまごがいくつあるかわかりますか? | |
  |   |
  |   |
  |   |
  |   |
2021年9月19日(日) 探して→写真に撮って→送ろう! 「クワの葉コレクション!」 学校内、ちゅう車場、川ぞいの道、公園、緑地・・・鳥のしわざか、いろいろなところでお目にかかるクワの木です。上小には探検隊が卒業記念樹として植えたものもありますね。 秋ですが、まだまだみずみずしい緑色をした葉があります。 クワの葉にはいろいろな形のものがありますね。 1本のクワの木でも、場所や育ち具合によってもちがうものがあるようです。 このクワの葉(写真・左上)は、切れこみが葉の左右(上下)に1か所ずつあります。 さがすとまだまだいろいろな形の葉が見つかるはずです。 このクワの葉とちがった形の葉をさがしてみましょう。 見つけたら写真をとって、写真と見つけた場所を書いて事務局に送ってください。いったい何パターンくらいあるのでしょうか。みなさんのおうぼをお待ちしています! ※トンボ池観察会でたくさん見つけました。同じクワなのに切れこみが0個~11個のものまでありました。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |
  |   |
2021年9月17日(金) キンモクセイに実ができないわけ キンモクセイが香りをとどけてくれています。でもこの香りにある成分、虫たちは苦手なので近づきません。 ところが上小でも観察できるホソヒラタアブだけは、キンモクセイの香り成分にふくまれるガンマーデカラクトンを好み、オスの木から実のなるメスの木へと、短い開花のあいだに手ぎわよく受粉をしてくれるのだそうです。 でも日本ではメスよりも花付きが良く、香り高いオスの木が、江戸期に原産地の中国から持ち込まれただけで、メスのキンモクセイは育てていないそうです。 キンモクセイは香りを楽しむ樹木として、お酒や、シロップ、香水、生薬として生活の中にとけこんでいます。(左:図書室外玄関前にて) ミドリグンバイウンカ。相撲(すもう)で使われる軍配(ぐんばい=うちわのような道具)に似ていることから名前がついたそうです。5㎜くらいの大きで、さまざまな植物の汁などを吸います。今日の食事はアシタバにきめたのでしょうか、とてものんびりしていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月16日(木) 空中にできるヤマイモだよ ヤマイモの赤ちゃん、ムカゴ。お米といっしょに炊(た)いたり、バターでいためたり、おいしい食べ方がいろいろあります。地面の下のヤマイモを育てるには数年かかりますが、ムカゴは毎年収穫できます。栄養価も高く、縄文(じょうもん)時代から食べられていたようです。(左:校舎裏にて) いろいろな場所でニホントカゲの幼体に出会います。足音を消すように歩いていると、日なたぼっこをしている姿を見ることができますが、たいていはサッサッっと足早にかくれてしまいます。よっぽど心地よくて油断(ゆだん)をしていたのか、二匹の幼体がいました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月15日(水) サングラスでキメてみたぜ んっ!エノキの葉にとまり、まったりしているアカボシゴマダラを発見! 気のせいか、大きなサングラスをかけて、ビシッとチョイ悪(わる)にキメているような感じです。(顔をアップにしてみてください!)このまま数が増えて生息場所(せいそくばしょ=生活するところ)も広がると、同じエノキを食草としている在来種のゴマダラチョウ、オオムラサキ、テングチョウやヤマトタマムシがこまるので、バランスをくずしすぎない程度におさまると良いですね。(左:トンボ池にて) わっ!デカイ〜!迫力(はくりょく)のある大きなカマキリがいました。春にひとつの卵鞘(らんしょう)から生まれる数百匹の赤ちゃんの中から、無事に成虫になれるのは数匹だけです。交尾、産卵の大切な時期に入っています。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月14日(火) ひがん花がさきました ヒガンバナが見ごろをむかえています。彼岸(ひがん)の時期に合わせて咲く不思議さもあって、びっくりする別名がたくさんあります。生活にとけこんでいる花のしょうこですね。ちなみにヒガンバナ科の植物には野菜の玉ねぎも入ります。(左:トンボ池にて) ヒメジオンにおとずれたツマグロアオカスミカメ。さまざまな植物の汁を吸う、5㎜ほどの少しすけた緑色のカメムシのなかまです。ニオイはするのかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年9月13日(月) るり色って知ってる?見せてあげようか ホトトギスやユリに産卵するルリタテハ。昼間はトンボ池におとずれていましたが、夕方にも駐車場あたりをヒラヒラまうすがたがありました。そして何度もとまりにきたのは黄色の帽子をかぶったコタジーの頭です。黄色がよっぽど好きなのか、それともさそわれる香りがあるのかしら?と楽しいひとときでした。 羽はとじていると、かれ葉のようなシブい模様(もよう・上左)ですが、広げると瑠璃色(ルリ色=ムラサキの入った濃い青色・上右)の美しいチョウです。(どちらも西側、駐車場にて) マユタテアカネ(オス)のようです。眉状斑(びじょうはん)と言って、顔にある2つのもようが眉(まゆ)のように見えたことが、名前のゆらいだそうです。(下左:トンボ池にて) ヒキガエル。昨年アオダイショウを校庭で見つけたころには、すっかり減ってしまいましたが、また数が戻りつつあるようです。(下右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月10日(金) 私、鳥と同じなまえなんです イチモンジセセリ。(じみな色から「ガ」だと思っている人が時々いますが、りっぱなチョウです!) 幼虫の食草はイネ科の植物です。チョウになると、さまざまな花のみつを楽しみ、お花屋さんでもおいしそうにみつをすうすがたが、『これ、おいしいよ〜』とオススメの花を案内してくれているように感じます。(左:トンボ池にて) ホトトギスが咲きはじめています。どくとくなもようは野鳥のホトトギス(夏鳥)のもように似ていることからこの名前がついたそうです。これからミツバチがみつを集めにやってきたり、チョウのルリタテハが産卵におとずれると思いますよ。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月9日(木) 雨上がりが待ちどおしい 雨がこぶりになってくると、イトトンボ達が合図をしたかのように出てきていました。その中にちょっと黄色っぽいイトトンボがいました。いつものアオモンイトトンボはちがうようでしたが、細部まで撮ることをすっかり忘れてしまいました!明日も見かけたら観察してみようと思います。(左:バッタ原っぱにて) 手のひらにのる大きさのカラスウリ、リース作りのかざりに人気です。中国では生薬(しょうやく)として使われているだけあって、食べると苦味があるそうですが、漬物(つけもの)にしていただくこともあるようです。熟すと赤く変わります。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月8日(水) 「てんぐ」に見えるかい? 秋に見られるテングスケバ(天狗透け羽)、天狗のような頭と、羽がすけていることが名前の由来(ゆらい)です。イネ科の植物がある原っぱ等で見つけやすいそうですよ。(発見場所でたくさん育てているジュズダマもイネ科の植物です)体長は12mmくらい。(左:校舎裏にて) モンシロチョウがみつを吸いにやってきました。東門花だんには2種類のマリーゴールドがありますが、観察していると、チョウ達は手を加えられた品種よりも、原種(げんしゅ=もとの野性種)の方を好むようです。(右:東側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月7日(火) 秋の雲ですね~ 9月7日あたりは二十四節気(せっき)の一つ「白露」(はくろ)。昔の人は草の葉などにおりた露(つゆ)が白く見えることを、夏から秋へと季節がうつり変わっていく目印の一つにしたようです。 二十四節気というのは、1年を太陽の動きを元に春夏秋冬の4つに分け、さらにそれぞれを6つに分けた昔からの暦(こよみ=カレンダー)です。白露は秋の3番目の節気。 この日、久しぶりに雨が上がった東京では、夕暮れに秋らしい雲が見られました。(石神井川・上石神井団地付近にて) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
  |   |
2021年9月7日(火) 見つけることができるかな クスノキにアオスジアゲハの幼虫です。アオスジアゲハは上石神井でも見ることのできる大変美しいアゲハですが、その幼虫にはなかなか出会えません。でも、どの木にいるのか覚えると見つけることもできますよ。9月に産まれた幼虫はサナギのまま越冬して、春を待つそうです。(左:校庭西側植え込みにて) 仮面(かめん)のようなもようがユニークなアズチグモ。花におとずれる獲物(えもの)を待ちかまえているようです。自分よりも大きな獲物も、第1、第2脚ががっちりと長いので、つかまえるのが上手なんですね。花はケイトウのなかまセロシア、みつを吸いにチョウなどがやってきます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月6日(月) バンビのもようだよ ヤマトシジミ。蜜(みつ)がよっぽどあるのか、ずっとはなれずに、マリーゴールドに夢中でした。(左:東門花だんにて) 鹿(シカ)のようなもようが名前の由来(ゆらい)のカノコガ(かのこ=鹿の子)。成虫は果樹の花蜜を好み、幼虫はシロツメクサやタンポポなどの葉を食べるそうです。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月3日(金) ピンクと青 アメリカピンクノメイガ。食草はサルビア(シソ科)の葉だそうです。中庭と東門花だんに通称メドーセージ(サルビア ガラニチカ)があるからなのか、ときどき出会います。(左:校舎裏にて) アオモンイトトンボ。雨が弱まるとすがたを見せてくれました。生息場所からあまりはなれないそうなので顔なじみの個体なのかもしれません。(右:バッタ原っぱにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月2日(木) レモンが大人気です! 昨年の6年生が卒業記念に植えてくれたレモンのなえ木に、大小さまざまな8匹ほどナミアゲハの幼虫がすごしているのを給食栄養士のMさんが見つけて知らせてくれました。事務室のみなさんが見守る中、ツンツンして臭角(しゅうかく=においを出すオレンジ色のつの)を出させるイタズラをしちゃいましたが、元気にすごしています。(左:事務室前の花だんにて) ザクロがほんのり色づいてきました。 ザクロの原産地はイランやトルコなどの中近東で、気候のちがいから皮がうすく、果汁や甘みもあり、タネまで食べられる栄養(えいよう)の高いくだものなのだそうですよ。環境(かんきょう)のちがいでずいぶん変わるんですね。(右:校庭西にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年9月1日(水) キアゲハが大好き「セリ科」の野菜 植物のビーズ、ジュズダマ。これから色づくのが楽しみです。(左・トンボ池資材小屋近くにて) 日本ではこの1種類をジュズダマとよんでいますが、ジュズダマのなかまは世界にぜんぶで7種類もあり、そのうちの1種類は栽培によってできた変種のハトムギです、夏におなじみのあのお茶の原料ですね。 アシタバにキアゲハの幼虫がいました。(右:トンボ池・バタフライゾーンにて) キアゲハの幼虫が好むのはセリ科の植物です。 アシタバの他にセリ科には『パ〇〇』『〇ン〇ン』『〇ツバ』などの野菜があり、どれもキアゲハの大好物。 〇の中の文字はすぐにわかったかな? (画像と情報:スタッフのSさん) | |
2021年8月30日(月) 秋の鳴く虫クイズ この声はだれの声でしょう? 昼間はまだまだ暑い日が続いていますが、夜になると外では虫の声が日に日に大きくなってきたようです。そこで、今日は秋の鳴く虫クイズです。 次の虫の声を聞いて、それが下の写真のどの虫の声か当ててください。 上石神井でもよく聞けるものもあるし、名前はよく聞くけれど実さいには聞くチャンスが少ないものもあります。 問題1 虫の声(その1)★クリック★ 問題2 虫の声(その2)★クリック★ 問題3 虫の声(その3)★クリック★ 問題4 虫の声(その4)★クリック★ (虫の声の録音と写真:スタッフのつとむさん) | |
  |   |
| ①エンマコオロギ | ②クツワムシ |
  |   |
| ③アオマツムシ | ④オケラ(ケラ) |
  |   |
| ⑤キリギリス | ⑥トノサマバッタ |
| ★さあ、いくつわかったかな? 答えはこちら(⇒クリック) | |
 | |
2021年8月19日(木) 久しぶりの月ですね 昨日(18日)の月です。季節はずれの大雨が続きましたが、ようやく空が晴れてきました。 22日の満月に向けて少しずつふくらみを増してきた月が夕刻の南の空によく見えます。 外に出て空を見上げてみましょう。少し蒸しますが、風があるので気持ちいいですよ。月のそばには木星と土星も見えるでしょうか。(木星・土星情報→こちら) (情報と写真:スタッフのつとむさん) |
  |   |
  |   |
2021年8月12日(木) 夏休み 生き物さんぽ 石神井川沿いを歩きました。天気が悪いためかギンヤンマの数は少なかったです。 ハグロトンボ(左上)がヒラヒラと飛んでは休み…風が強いため必死に水草につかまっていました。 この辺では見た記憶がないのですが(気にしていなかっただけ)ガガイモ(右上)の花が咲いていました。 ガガイモの近くにはアオドウガネ(左下)。 スズメバチ(右下)は水面の水草に降りて水を飲んでいるのでしょうか。 みなさんからの「夏休み生き物さんぽ」情報募集中! (情報と写真・動画:スタッフのつとむさん) | |
  |   |
2021年8月8日(日) 夏休みのトンボ池 さいきん、池のまわりが静かだな。え?「夏休み」、なにそれ?なんでこんなすてきな季節に人間たちは休んじゃうのかなぁ。暑くって気持ちいいのに~ ショウジョウトンボ。まぶしい日差しをたっぷりあびていました。(左:トンボ池にて) ニホントカゲ(幼体)、たんけん中のようでしたよ。(右:自転車おきばにて) (写真と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| 羽化したばかり。未成熟体のトンボのようです。 このあと元気に飛び立ちました。(2枚ともトンボ池、田んぼゾーンにて) | |
  |   |
| シオカラトンボ♂(左)とオオシオカラトンボ♂(右) くらべてみると、ちがうのがわかりますね。(トンボ池にて) | |
  |   |
| どちらもアブラゼミですが、少し赤っぽい個体(右)もいました。寿命(じゅみょう)が近づくにつれ、色のへんかがあるという説もありますがどうなんでしょう・・・(どちらもトンボ池にて) | |
 |  |
2021年8月1日(日) ヒスイのようなグリーン! 明日の観察会には参加できないのですが、昨夕子どもとセミの羽化を見ることができました。場所は上石神井団地の公園です。(上石神井第三保育園の隣)ここはセミがとても多い公園です。 19時過ぎに、ツルツルのさくに登って落ちそうになっている幼虫を発見。 家のベランダに連れて帰ると、羽化が始まりました。 ミンミンゼミの幼虫でした。 子どもの頃、アブラゼミの羽化は毎年見ていましたが、ミンミンゼミは初めてでした。 翡翠(ヒスイ)のようなグリーンが、とてもきれいで、子どもたちも大喜びでした。 朝見ると、無事に飛び立って行ってくれていて、安心しました。 (画像と情報:2年生隊員Rさんのお母さん) ★ミンミンゼミ、東京では以前より増えた印象がありますね。それにしても美しい羽化です。今はちょうどセミの羽化ラッシュの時期。観察会ではなくてもちょっと探せば身近な公園などで幼虫を見つけることができます。ぜひじっくり観察してみましょう。子どもの頃に生で見た感動は一生の宝ものになること、間違いなしです。 | |
  |   |
2021年7月29日(木) ヤモリくん、オリンピックに出るんだって!? 職員玄関のわきの花だんで草の手入れをしていると、 『あれ〜!?もう出番ですかぁ〜??』っとあらわれたヤモリくん。よく聞いてみると、上小オリンピックが人知れず開催(かいさい)されているんだって!しらなかった〜っ! では、ここで問題!ヤモリくんはどの種目にでるのでしょうか?ひとつではないですよ。 カッコの中はヤモリくんのコメントをもらいましたがウソかもしれませんよ。 ※ちなみにヤモリくんは夜の出番なので、もう少し休むそうです。(写真右。) 1。水泳25cm自由型 4。走りはばとび 5。ウェイトリフティング こたえと説明→(クリック) (情報と画像:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年7月28日(水) 「ちびオナ」のベッドかな? 公園のオナガの巣に親鳥が入り、じっとしているのを見るようになってからがそろそろ2週間がたちます。台風の大風もさほどふかなったので、安心しています。今日は、白いわた毛のようなものを巣に運びこんでいました。生まれくる「ちびオナ」のベッドでしょうか。 1分動画はこちら(→クリック) (情報と画像:スタッフのコタジー) |
  |   |
2021年7月22日(木) オオシオカラトンボの産卵 トンボ池でオオシオカラトンボの産卵行動が観察されています。トンボ池を自分のなわばりにして他のオスが来ると追いはらっていたオス(水色の方)は、メス(黄色と黒)が自分のなわばりにやってくると、すかさず交尾をします。(上の2枚) メスはすぐに池で産卵を始めました。オスはメスのすぐそばを飛んで、ほかのオスがやって来ないようにメスを守っていました。 (写真・動画とも:トンボ池にて 撮影 スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年7月21日(水) セミはかせになろう! セミのぬけがらを目にすることがふえました。 セミは身近なこん虫ですが、あんがい知られていないこともあるようです。 それでは、今日も〇✕クイズ〜! クイズに答えて、セミはかせになろう。 第1問 セミのぬけがらは、食べるとあまくてパリッとしていて、けっこうおいしい? 第2問 セミのぬけがらは、発熱などの病気にききめのある生薬として使われている? 第3問 セミのぬけがらから出ている白い糸は、 第4問 セミの幼虫は木の根から汁(しる)をすって生きている? 第5問 セミはどくとくの『におい』でゆうめいな、カメムシのなかま? こたえと説明→(クリック) (情報と画像:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年7月20日(火) ピンクの蛾(が)だよ~ メジロの黄緑色のきれいな羽は、食べ物などのバランスによって、色合いが多少かわるようです。この子の色はどうかな? (左:トンボ池にて) アメリカピンクノメイガ。花びらのようなピンク色の1㎝くらいのガです。 (右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
2021年7月20日(火) オナガの巣(す)を見つけたよ! オナガは、市街地でもよく見かける鳥です。ギャーとかギーッとかギョエギョエ・・と、なき声は、けっこううるさいのですが、すがたは、黒いぼうしに、ブルーグレイの上品な体で、都会的?なフォルムが目を引きます。 近所の公園で、オナガの巣を見つけました。はじめは何の鳥の巣かわからなかったのですが、ある日その巣から、ながーーーい尾がのびているのを見つけてそれとわかりました。 ※西東京市にて:300㎜望遠レンズに2倍のテレコンバーター使用して撮影 | |
  |   |
| 近所の公園のケヤキの高いところに見つけました。あれは、何の鳥の巣でしょうか?木の枝をたくさん集めて作られています。中には白いスズランテープも見えています。 | 待っていると、ついに親鳥がやってきました。はたして、オナガでした。 |
  |   |
| こずえからおりて、これから巣に入るところです。足が見えています。 | 巣からにょきっとオナガの尾がのびています。尾の先は白っぽいです。尾の方向はいつも決まっています。方角でいうと西南西(たまたまですが・・)です。卵をあたためるのにおさまりのいいからだの方向ってあるようです。 |
それでは、ここで「オナガ〇✕クイズ」 全5問! (情報と画像:スタッフのコタジー) | |
  |   |
2021年7月19日(月) いるのがわかるかな? わかった?イボバッタがいるよ!(左:校舎裏にて) 草のしげみにいるのはカマキリです。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年7月16日(金) キャベツの上がお気に入り 草の手入れをしていると、ひょこっと顔を出したニホンカナヘビ。収穫期をむかえているキャベツですが、ちょうどよいヒンヤリ感があるのでしょうか?この姿を見てしまうと、収穫はなかなかできません! かわいいので、もう一枚。(2枚ともに校舎裏の畑にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
ヒルガオに小さなハナバチがおとずれました。 (トンボ池にて) | 千日紅(せんにちこう)の花蜜をあじわうヤマトシジミ。ストロー(くち)に花粉がたっぷりついています。(東門花だんにて) |
  |   |
くつろぐアオモンイトトンボ。 (トンボ池にて) | 朝日をたっぷりあびるオオシオカラトンボ。 (トンボ池にて) |
  |   |
セミの抜けがらを見つけました! (校舎裏にて) | ルルルルル〜と鳴くカンタンのようです。まだ1.5㎝くらいの幼虫ですが、ピョンピョンと元気にはねます。 (校舎裏にて) |
  |   |
2021年7月15日(木) 雨があがるの待っていました ブンブンと大きな音を出して、ずっしりとした体でやってくるクマバチ。迫力(はくりょく)はありますが、とてもおだやかなハナバチです。メドーセージがお気に入りのようで、よくおとずれています。 (東門花だんにて) 雨上がり、さっそくオオシオカラトンボがやって来ました。大きな水たまりができた東門あたりにも、めずらしくおとずれていました。水辺が好きなんですね。 (トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年7月15日(木) 葉っぱのうらにキラッキラのビーズ発見! 今朝はカメムシが、わが家の琉球朝顔(リュウキュウアサガオ)に産卵してました。 昨日のカタツムリ(左の「見つけたよ!」コーナー参照)に続いて、卵ラッシュ(笑) 親は地味なのに、まるでビーズのようなキラキラ感のある卵です。 (画像と情報:2年生隊員のKさん) |
  |   |
2021年7月14日(水) こんどは・・・オンブバッタくんのトイレタイム トイレタイムが続いて失礼。今日はオンブバッタ。 おしりから黒いうんちが出ています。じょうずにピンっ!と飛ばすんですよ。 (左:校舎裏にて) ただ今、いろいろな場所でうどん粉病が発生中ですが、キイロテントウがたくさん来て食べてくれています。たすかる〜! (右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
ヒメジオンの花蜜にシロモンノメイガも夢中です。 (校舎裏にて) | ツマクロヒョウモンはブッドレアの花蜜を見つけていました。 (トンボ池・バタフライゾーンにて) |
  |   |
ホリカワクシヒゲガガンボ。おしりをあげてとまります。黒と黄色のもようなどから、ハチに似て刺すように見えますが、性格はおとなしいそうです。 (トンボ池にて) | サキグロムシヒキ。白いヒゲがおだやかそうにも見えますが、自分より大きなセミなどの昆虫も平気で捕まえるそうです。体長は2.5㎝くらい。 (トンボ池にて) |
  |   |
2021年7月13日(火) アズチグモ「全集中の狩り」が見たい! 自分より倍もあるアブやハチなどをとらえるアズチグモ。 以前は(6月7日)メドーセージの花の中に入って待ちかまえていましたが、花より大きなアズチグモは花の下でそっと待ちかまえているようでした。(左上:東門花だんにて) アズチグモは数日かけて体色を変えることもできるそうです。(右上:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| ハナバチのなかま。ヒメジオンの花蜜に夢中です。(校舎裏にて) | ナス科のつる性植物ヒヨドリジョウゴ(日本在来種)の小さな花が咲いていました、秋になると赤い実をつけます。(東門花だんにて) |
  |   |
2021年7月12日(月) ちょっと失礼・・・カタツムリさんのトイレタイム ガマの葉にカタツムリがいました。ちょうどウンチをしているところ。なんと、あたまの近くに肛門(こうもん)があるんですね。ゆっく~り、出していました。(左上:トンボ池にて) ヤモリ。空洞化(くうどうか=中がからっぽになること)の進んだ木の中に、ずいぶん前から住み着いているんですよ。(右上:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| ヘリグロテントウノミハムシ。ヒイラギ、ネズミモチなどの葉を好むようです、葉っぱの先がクシュっと茶色になってしまっていたら、このハムシがのんびり過ごしているのかもしれません。 (プールわき・バッタ原っぱにて) | 草のしげみの中で過ごしていたナナホシテントウ。 (中庭にて) |
  |   |
| オオシオカラトンボ。今日は二年生の教室にも入ってきたそうです。(トンボ池にて) | フトイにシロテンハナムグリがいました。 (トンボ池にて) |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年7月12日(月) イチジクのふしぎ 花はどこにある? 「トンボ池のイチジクがすずなり!」(7/2 Sさん情報)と聞いて、ちょうど庭のイチジクの実が熟(じゅく)してきたのを思い出しました。 イチジクは、漢字で書くと「無花果」です。花の無い果実(かじつ=くだもの)、花がさかないのにいきなり実がなる、そんな意味でしょうか。 さっそくじゅくした庭のイチジクをとってきて、花をさがしてみました。中をわってみると、細かいものがたくさん密集しているのが見えます。(上左)数えた人によると、ざっと1800本ほどあったそうです。5本ほど取り出してみました。(上右)つぶつぶしたこれ1つ1つがイチジクの花です。 ではここでさっそく「イチジク〇✕クイズ!」にいきましょう。 問1)イチジクの木によくつくこん虫は、 ゾウムシである。(〇✕) 問2)イチジクの花にも、花びらがある。(〇✕) 問3)食べているイチジクは、げんみつにいうと くだものでもやさいでもない。(〇✕) 問4)イチジクが受粉(じゅふん)するためには、 イチジクコバチの働きが必要である。(〇✕) 問5)イチジクコバチのオスはイチジクの雄花の中で、 外の光を見ることもなく一生を終える。(〇✕) さて、かんたんでしたか? イチジクコバチのお話は、いろいろ調べてみてください。ただ、日本には南の島々をのぞいて、本土にはイチジクコバチはいないようです。(ほとんどが、海外) 今の日本には、受粉をしなくても実がふくらむイチジクの種類をさし木でふやしたクローンが多いようです。できるのは、みんな雌花(めばな)。だからあのつぶつぶには「めしべ」がついているはずです。中には、雄花(おばな)雌花に分かれるものもあるそうですが、イチジクの雄花って食べられるのでしょうか。花たくの大きくなった部分(果肉ではない)を食べるのだから、雄花でもいけそうな気がしますが、見たこともないので何ともいえません。 (情報と画像:スタッフのコタジー) | |
 | |||||
2021年7月11日(日) 雹(ひょう)がふりました!ヒョウ~!! 梅雨(つゆ)ももうおしまいでしょうか。天気予報どおりに今日は昼までむし暑かったですね。 お空は急に暗くなりに雷(かみなり)と雹(ひょう)。上石神井に住んでもう30年ほどですが、こんなに大きい雹は初めてです。 ひょう(雹)とあられ(霰)のちがいは、その大きさによって区別されます。 ひょう(雹)は直径5ミリ以上の氷のつぶが大きくなった氷のかたまりで、氷のつぶが積乱雲(せきらんうん=かみなり雲)の中で上にいったり下にいったりをくり返して大きくなり、ある程度の重さになると落下していきます。 あられ(霰)は直径5ミリ未満の氷の粒です。(動画①→)(動画②→) (画像と情報:スタッフのおおさわさん)(動画②:つとむさん) | |||||
  |   | ||||
 | 公園が池になっちゃってました すごい雨と雹(ひょう)でしたね。平成公園が、池になっていました。めずらしいので、写真を送ります。 左のくつの写っている写真は、石垣の上から水たまりに映った空の写真です。 (画像と情報:スタッフのくるしまさん) |
雨のあとは虹と夕焼けがきれいでした 雨があがると、東の空に虹(にじ)が出ました。この季節は太陽がしずむのが西よりだいぶ北よりです。西から北にかけて夕焼けがいつまでもきれいでした。 (画像と情報:関町付近にて・スタッフのつとむさん) | |
  |   |   |
 | |
2021年7月11日(日) ギンヤンマが羽化しました! えさを食べなくなって4日ほど。毎日水面から出たり入ったりをくり返していましたが、先日無事に羽化してくれました。 夜中に羽化し、元気に飛び立って行ってくれて、ホッとしました。 残されたぬけがらの観察も、楽しかったです。 (画像と情報:2年生隊員Rさんのお母さん) |
  |   |
2021年7月10日(土) 羽のかがやき ヒラタアブの小さな翅(はね)のかがやきにウットリ。まるっこい触覚(しょっかく)もかわいいです。(プールわき・バッタ原っぱにて) オオシオカラトンボのメス。(尾っぽの方にある、腹部第8節目が太めなことと、さきっぽのツメのような突起(とっき)の間にみじかい突起が出ていることでメスとわかります) (トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
イボバッタかな? (給食室前にて) | ショウブヨトウのなかまかな?と思います。ドクダミのしげみから、よいしょ。。っと、のそっと登場。 んっ!よく見ると、ハートマークがある〜っ! (校舎裏にて) |
  |   |
2021年7月9日(金) 葉っぱ、ゲット! きのう、しょうかいしたカップルのヒメグモを観察しに行くと、コナラの葉が引っかかっていました。もしかしたら、もしかすると・・・ わぁ〜!本当だぁ〜!ヒメグモがいますよ〜!! でも不思議。どうやって葉をもってきたのでしょうか?おもしろいですね〜! (2枚ともトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
ヒラタアブがハキダメギクをおとずれていました。 (校舎裏にて) | ヒメジオンのくきにカマキリがかくれていました。 (校舎裏にて) |
  |   |
♪出~たぁ 出~たぁ 月がぁ〜♪ と、月ではなくてジュズダマのまぁるい実が出てきました。 (校舎裏にて) | くもり空の下、メスのヤマトシジミチョウが翅(はね)を広げて休んでいました。 (校舎裏にて) |
  |   |
ヤブミョウガの花に夢中なミツバチ。 後ろ足につけてる丸くて黄色いものは『花粉だんご』。みつをすっている間に、体の毛につく花粉が、花粉かごのある後ろ足にあつまります。巣に持ち帰った花粉だんごはミツバチの保存食となるそうです。 (東門花だんにて) | ハナバチのなかまかと思います。 まったく動かないので、思わずトントンとかるくさわると、ねぼけたようなしぐさをしていました。ウフフ。 (東門花だんにて) |
  |   |
2021年7月8日(木) わらっているわけではないのですが・・・ ヒメグモ。上のオレンジ色の目立つ方がオス、おなかをかかえて笑っているみたい(!)にしているのがメスです。6〜7月ごろにオスはメスの網(あみ)にやってきて、メスが成体になるのを待ちます。メスは成体になると枯れ葉をつるすように網にくくりつけ、その葉で過ごし産卵をします。親グモは子グモに口から液体を出しあたえ子育てをするそうです。(左:トンボ池にて) 朝一番にのぞいてみると、ススキの葉の上でくつろぐヤマトシジミがいました。 (右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
ひさしぶり!元気なアマガエルがいました。体長は2㎝くらいで小さいです。もしかすると、プールからトンボ池にはなしたオタマジャクシ(5月31日)かな? (トンボ池にて) | アオモンイトトンボ 「プールにも入ってくるんですよ〜」と、生き物が大好きなH先生がニコニコと話してくれました。 (プールわき・トカゲ原っぱにて) |
 | |
2021年7月7日(水)★たなばた★ 赤ジソの橋をわたってようやく会えたね♡ いいえ。たなばたは関係ありません。 君たち、毎日ここで会ってるでしょ! なぜだかバッタの幼虫に人気の赤ジソ。今日も6匹くらい来ています。仲間どうしで情報こうかんしているのかも!(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| チョウのなかま、イチモンジセセリ。幼虫の食草にはイネやススキ等のイネ科の植物も入っています。もしかすると、田んぼゾーンのイネをチェックしにきたのかな?(トンボ池にて) | くきから白い乳汁のでるコニシキソウの葉にカタツムリの赤ちゃんがいました。卵からかえったばかりのようで、2㎜くらいです。 (東門花だんにて) |
  |
キイロテントウ (プールわき・バッタ原っぱにて) |
 |  |
2021年7月6日(火) 梅雨の晴れ間 今日はひなたぼっこかな あっ!いたっ!と思う間に、いつもならサッと身をかくすニホンカナヘビ。でも今日はのんびり。なんでかな?口もとを指でツンとしたら『んっ!』としたけど、やっぱりのんびりしてました。(左:校舎裏にて) エビやカニと同じ仲間のダンゴムシ。金色のもようがある方がメスですが、オスにも真っ黒だけではなく金色のもようが見られることもあるそうです。おしり裏の生殖器(せいしょくき)で見分けられるそうですが、なかよくキャッキャと過ごしているようでしたので、またこんどにしました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
ムシトリナデシコにやってきたヒラタアブ。ムシトリナデシコはくきの一部に両面テープのようなベトベトがあるから「虫取り」ナデシコ。さわってごらん。 (東門花だんにて) | キオビツチバチのメス。せわしなく動きまわり、落ち葉のかさなる土の中へもぐりこんだりしていました。もしかするとコガネムシの幼虫を探し、卵をうみつけたいのかもしれません。 (校舎裏にて) |
  |   |
ヒメグモのなかまのようです。黒いブーツをはいている5㎜くらいの小さなクモ。 (トンボ池にて) | クサギカメムシ5齢幼虫。葉っぱのうらでのんびりしていました。 (プールわき、バッタ原っぱにて) |
  |   |
ジュズダマの花がもうすぐさきます。イネ科の植物です。 (校舎裏にて) | バッタの赤ちゃん、うんちも小さい。 (トンボ池にて) |
  |   |
| アオモンイトトンボ。昨日はどこで過ごしていたのでしょうか?今日は元気なすがたがありました。(トンボ池にて) | わかいメスのアオモンイトトンボもいました。 (プールわき・トカゲ原っぱにて) |
  |   |
2021年7月5日(月) キノコが元気です! 梅雨の時期はキノコが元気に育つようです。名前はわかりませんが、この白いキノコがほかにも2つありました。(左) こちらはシイタケのようなキノコでした、白いキノコのそばにありました。(右:共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
サキグロムシヒキのようです。 (プールわき・バッタ原っぱにて) | ヒラタアブ。メハジキ(ヤクモソウ)におとずれていました。(プールわき・バッタ原っぱにて) |
  |   |
セマダラコガネ。セイヨウタンポポのとくちょうで、花の下の緑色のそりかえっている部分に入りこみ、きゅうけい中のようです。 (校舎裏にて) | コガネ虫のなかまに近づくと、時どきピーンと足を伸ばす姿がおもしろいと思っていたら、天敵におそわれそうになった時、すぐに飛べるようにするため、なのだそうです。リラッ クスしてるのではなく、けいかいしていたんですね!(校舎裏にて) |
  |   |
アシナガバエのなかま。5㎜くらいと小さくても、キラっとしているので目にとまりやすいです。ダニなど極小の虫を捕食します。 (トンボ池にて) | 植物を弱らせる菌をキイロテントウが食べてくれるおかげで、農薬を使わずに葉がいきいきしています。 (トンボ池・ミカンの木にて) |
  |   |
咲きはじめたマツヨイグサのなかま。夕方から咲く一日花ですが、くもり空でしたら朝から観察できるようです。アリがおとずれていました。 (プールわき・バッタ原っぱにて) | 雨上がりの昼時には見かけるかな?と思いましたが、いつもいるイトトンボはいませんでした。でも、オオシオカラトンボが気ままに過ごしていたのと、クロアゲハがヒラヒラと舞うすがたを観察できました。 (トンボ池にて) |
  |   |
2021年7月2日(金) 「雨の日探検」してみたら・・・みんな元気です! イネ。田植えから2か月。40㎝くらいになっています。(左:トンボ池・田んぼゾーンにて) イチヂク。すずなりです!(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| 雨の日もパッと明るく咲いていたセイヨウタンポポにヤマトシジミと花粉を食べに黒くて小さなルリマルノミハムシがおとずれていました。(校舎裏にて) | 雨でも元気なヤマトシジミ。咲きはじめたメハジキ(ヤクモソウ)をおとずれていました。 (プールわき・バッタ原っぱにて) |
  |   |
雨宿りをしているヤマトシジミ。翅(はね)をおおっている鱗粉(りんぷん)が、雨をはじいてくれます。鱗粉はとれてしまうと再生(さいせい)できません。チョウを手でつかまえるときは、チョウが翅をとじている時にやさしくピースサイン(人差し指と中指)で、はさみましょう。 (校舎裏にて) | 雨でねてしまった菜の花でまったりしているナガメ。ピンっと立った触角(しょっかく)に、もしかして空と交信中?なぁ〜んて思いましたが・・・虫の触角はいろいろなものを感じるすぐれたセンサーのようですから、私達よりずっと、たくさんのことを知っているのかもしれません。 (東門花だんにて) |
  |   |
これくらいの雨ならへいき!とアオモンイトトンボ。とまっているのはフトイのくき。細いのになぜフトイ? (トンボ池にて) | わかいメスのアオモンイトトンボ。ふわっふわっと移動(いどう)しながら過ごしていました。 (校庭まわりのコンクリートかべにて) |
  |   |
おぉっ!肉食カマキリ(左)と草食ショウリョウバッタ(右)がのんびり過ごしています。 雨音と、マダラスズがジー ジー と鳴いているのが聞こえます。 (校舎裏にて) | ススキの葉のうらにも小さな虫がいました。風のない小ぶりの雨なら、カサをさしての観察も楽しいです。まわりに注意して、みなさんもぜひ「雨の日探検」してみましょう! (トンボ池にて) |
  |   |
2021年7月1日(木) 今年も出たよ 昨年から東門正面花だんに出現したキノコ(マンネンタケと思われる)。雨水をたっぷり吸って今年もちゃんと育っています!(左) 昨年見つけた右どなりの赤いキノコと同じくらいになっています。(右) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| ★初記録★赤いしょっかくが目をひく5㎜くらいのイネホソミドリカスミカメムシ。(以前はアカヒゲホソミドリカスミカメムシと呼ばれていたそうです。)名前にもあるようにイネ科の植物が好きっ!田んぼゾーンのお米をねらう小さな生き物です。(トンボ池・田んぼゾーンにて) | アジアイトトンボかな?と思いました。オスは腹が青色、複眼の後ろの青く小さい点が特徴です。メスは大人になるとオレンジ色から緑色に変化します。(トンボ池にて) |
  |   |
| 雨上がり、聞こえてきたのはヒヨドリの声でした。ヒーヨッ!と鳴くからヒヨドリ。(校庭にて) | おいしいね!なかよくみつをすっていたヤマトシジミ。(東門花だんにて) |
  |   |
2021年6月30日(水) ストローのひみつ くるくるんとまいている口をのばして、花のみつをすうチョウたち。ストローには目では見えないヒミツがあって、外側にはこまかいシワがならび、それによってストローはのびちぢみができます。そして内側にはやわらかい筋肉と、その中に毛のようなものがあり、そこで味を感じるそうです。 (ヤマトシジミ(左)とモンシロチョウ(右):ともに東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
『おいしいみつはあるかなぁ』ミツバチはこのあと、ブッドレアの花のみつに夢中になっていました。(トンボ池にて) | アシタバにツマグロオオヨコバイ(通称バナナ虫)の幼虫が6匹くらいいました。成虫と同じで、いろいろな植物の汁(しる)を吸います。 (トンボ池にて) |
  |   |
2021年6月29日(火) 「スターにしてくれ!」 ジュニア隊員のKくんから「カタツムリがいたよ!」と情報をもらったので、かけつけてみると・・・いました、いました!(上左) おやっ?なんだろう・・・何か見つけたかな? ムムッ!(右上の写真をよ~く見てください) おわかりいただけましたか?『スターにしてくれ』とアピールしたかったのですね!! (2枚ともにトンボ池、アサザ(水草)の掲示板にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
アオモンイトトンボ。わかいメスは青ではなくて、オレンジ色。ときどきしか観察できないので、記念にアップの写真も。(右) (2枚ともにトンボ池にて) | |
  |   |
| ★初記録★ベダリアテントウ。(4㎜くらい)オーストラリアのてんとう虫。柑橘類(かんきつるい=みかんのなかま)につくカイガラ虫の害虫対策で世界中で導入(どうにゅう)されたてんとう虫なのだそうです。こういうのを「生物農薬」というのだそうでです。(トンボ池・チョウの庭ゾーンにて) | スグリゾウムシ。(5㎜くらい)ミカンや他のいろいろな葉を食べます。幼虫は植物の根を食べて育ちます。(トンボ池・チョウの庭ゾーンにて) |
  |   |
| 小型スズムシのマダラスズ。まだ成虫にはなっていないようです。(5㎜くらいかな?)えんそう会がはじまるのかと思ったくらい10匹近くいました。(校舎裏にて) | ルリヒラタゴミムシ。(8㎜くらい)きれいなメタリックブルーです。(校舎裏にて) |
  |   |
2021年6月28日(月) 雨があがったら会いに来てね すっきりしないお天気が続きますが、日の差す時間もけっこうあります。 休み時間や放課後、身近な生き物たちに会いに行きましょう。 ◇ヤマトシジミ。ときどき翅(はね)を広げながら、朝日をあびていました。(上左:朝のトンボ池にて) ◇ツマグロヒョウモン。「みつは残っていないかしら?」と、大好きなビオラの花の中をのぞいていました。(上右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
| ハムシのなかまのようです。ちょうど、うんちをしたところです。スッキリ!(校庭にて) | ナガメ。小さい方がオスで、大きい方がメスです。どっちがどっちかな?(校舎うらにて) |
  |   |
| シオヤアブ。メスにはない白い毛がオスにはあります。写真にはとれませんでしたが、顔にも、もじゃもじゃの毛が生えています。ときには、スズメバチをつかまえて食べてしまうこともあるそうです。(校庭にて) | ギンメッキゴミグモ。はらの部分が銀メッキをしたようにピカピカ光るクモ。いそがしそうに、ぐるぐるとまわりながら巣を作っていました。(校庭にて) |
  |   |
| 6センチくらいのカマキリ。おなかがいっぱいのようで、のんびりすごしていました。(校舎裏にて) | オンブバッタの赤ちゃん。赤ジソの葉にいましたが、ほかにも10匹くらい赤ジソの葉の上ですごしていました。(校舎裏にて) |
  |   |
  |   |
2021年6月25日(金) ただいま狩(か)りの修行(しゅぎょう)中 ①まだまだ小さな3㎝くらいのハラビロカマキリ、アジサイの葉の上で過ごしていたので、少し観察してみると・・・(左上) ②んっ!アシナガバエ!(右上) ③おしりを上げて、威嚇(いかく)をするハラビロカマキリでしたが・・・ アシナガバエはサッとその場をはなれてしまいました。 ハラビロカマキリはめげることなく、注意深くまわりの様子をうかがいます。 次の獲物(えもの)を見つけたっ!?(左下) ④つかまえたっ!「今度はうまくいったゾ!!」っと、思っていましたが・・・(右下) | |
  | またしても残念! (すべてトンボ池・資材小屋前にて) |
 | |
2021年6月25日(金) 顔まで真っ赤 ショウジョウトンボ ぼくの名前はショウジョウトンボ。「ショウジョウ(猩々)」っていうのは、中国の昔話に出てくるお酒が大好きなサルの名前なんだって。よっぱらって顔まで真っ赤・・・って思われているのかな。からだは真っ赤だけれど、実は「赤トンボ(アカネ)」のなかまではないんだ。まちがえないでね。 それにしても梅雨といっても今日みたいに晴れると暑いね。こうやっておしりを持ち上げているのは、太陽の光で体が熱くなりすぎないようにする「避暑(ひしょ=あつさをさけること)」のポーズなんだよ。 あー、少しはすずしいな。みんなもあつい日はぼくみたいに「さか立ち」してみたらどうかな。 (トンボ池にて) (下6枚と共に撮影と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
こちらはオオシオカラトンボ。今日も休けいしたり、ショウジョウトンボとブンブンと場所とりをし合ったり・・・本当はケンカするほど仲がよい?(トンボ池にて) | 観察中のキアゲハの幼虫(3齢)。 (トンボ池、キアゲハ食草のアシタバにて) |
  |   |
ハエトリグモの赤ちゃん! (トンボ池にて) | 害虫などを食べてくれるアシナガグモ。下がオスで上にメス。おたがいの巣はならんでいます。子グモがどのように観察できるのか楽しみですね。(トンボ池にて) |
  |   |
アカホシカスミカメムシ。5㎜くらい。 (校庭にて) | ダイミョウセセリ。写真よりも、本当はもう少し黒っぽいです。食草はヤマノイモ、ナガイモだそうです。 (トンボ池にて) |
  |   |
  |   |
2021年6月24日(木) ここはぼくの場所です! トンボ池にショウジョウトンボ(左上)がいました。 後から来たオオシオカラトンボ(右上)となわばり争いでしょうか?時おりブンブンとはげしく飛び回っていました。 それをよそに、水辺近くにいたアオモンイトトンボ(左下)。のどかな時間が流れていました (トンボ池にて) キンカンに訪れていたミツバチ。花の中に頭をつっこみながら、いそがしそうにしていました。(校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月23日(水) 梅雨の晴れ間 虫たちのランチタイム② テントウムシダマシと呼ばれているニジュウヤホシテントウ。28個の黒星が名前のゆらい。ほかのてんとう虫のツヤのある体とはちがい、ちょっとさわりたくなるような短い毛がびっしりはえています。おなじみのテントウムシやナミテントウがアブラムシなどを食べる肉食性なのに対して、こちらはナス科の植物を食べるので畑ではきらわれ者です。(左:校舎裏、畑にて) キンカンのさわやかな香りの白い花が咲きはじめ、シジミチョウやキオビツヤハナバチなど、小さな生き物が花蜜に夢中になっていました。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年6月22日(火) 黄色いちっちゃいテントウムシ見っけ! クワの手入れをしていると、葉につく細菌を食べてくれるキイロテントウ(成虫:左上)観察を観察できました。 キイロテントウの幼虫(右上) キイロテントウのさなぎ(左下) キイロテントウの交尾(右下)左がわ・上にいるのがオス、右の下がメスです。これから卵の観察も楽しみです。(4枚とも校庭の桑の木で撮影) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年6月21日(月) シジュウカラが巣立ちました! ★巣立ちの瞬間→(50秒動画・クリック) 本日、子ども達の授業がはじまったころから、シジュウカラ親子のにぎやかな巣立ちが始まったようでした。(左上:中庭巣箱にて) 巣立ちをうながしながら、ごはん運びも!いそがしいのに、親鳥は本当に虫とり名人!(右上:中庭巣箱にて・左が親鳥・右がヒナ) シジュウカラのとくちょう黒いネクタイは、まだ子どもサイズです。(左下:中庭にて・ヒナ) 子ども達が見守る中、最後までがんばりました。短い命でしたが、教えられることは大きかったです。(右下:中庭にて・親とはぐれて衰弱してしまった最後に巣だったヒナ) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月20日(日) 昼間が長くてうれしい季節 明日は1年で1番昼が長い「夏至(げし)」ですね。夏至から数えて11日目の頃を「半夏生(はんげしょう)」と言い、その頃に咲く花(写真・左)なのでハンゲショウ(半夏生、または葉が半分だけ白いので半化粧)だそうです。気候の変化もあり一週間前くらいから見ごろをむかえています。ドクダミの仲間でドクダミと同じように葉全体に独特の香りがあります。(14日・トンボ池にて) ハチの仲間のようで、食事中でした。ハチを見つけた時はさわがずに、そっとはなれましょう。(右:15日・東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年6月18日(金) 私の目には「紫外線」が見えるんですよ 今日もナミアゲハがおとずれていました。チョウは太陽からとどく光のうち、人間には見えない紫外線(しがいせん)を見ることができ、それによって蜜があるところがわかるそうです。 虹(にじ=太陽の光が空気中の水分を通りぬける時に色が分かれて見えるげんしょう)は、人間にはだいたい七色に見えますが、それは光の波長(はちょう)のちがいよるものです。波長の長いじゅんに、赤、だいだい、黄、みどり、青、あい、むらさきの光となるのですが、むらさき(紫)よりさらに波長の短い光、紫の外がわの光のことを「紫外線」と言います。 アゲハの目にはどんな色の風景が見えているのでしょうね。(左:トンボ池にて) アシタバの葉にキアゲハの幼虫(2齢)がいました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年6月17日(木) 梅雨の晴れ間 虫たちのランチタイム ムシヒキアブの仲間サキグロムシヒキ。25㎜くらいの体に、長めのじょうぶそうな足をもっています。人は刺しませんが、自分より大きな昆虫をとらえるのがとくいのようです。この時はハエのような虫を食べていました。(左:校舎裏にて) チョウが大好きな花のブッドレアが咲き始め、ナミアゲハがおとずれていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月16日(水) ヤマトシジミの足のひみつ アサザの蜜をいただきに、そ〜っと花びらをおりてゆくヤマトシジミ(メス)がいました。 何となく見ていたのですが、人間だったらつるんとすべりそうですね。足にヒミツがあるのか調べてみると、ヤマトシジミのメスにはオスでは退化(たいか=なくなること)してしまった前足の爪(つめ)や、その両足2つずつの爪の間に、接着する役割もある爪間盤(そうかんばん)があるそうです。(中足、後足にもこれらがあります、オスは中足と後足にあり前足にはありません。)だから蜜を吸いにじょうずにおりていけるのでしょうか?正確にはわかりませんが、バランスをとりながら、わざわざ花の中へと入ってゆくのですから、もしかするとアサザにもヒミツがあるのかもしれません。(左:トンボ池にて) ときどきやってくるカラス。今日は2羽で訪れていました。そのせいなのかアオモンイトトンボはプールサイドにひなんしているように見えました。(右:プールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年6月15日(火) 中庭の巣箱でシジュウカラが子育て中!! 中庭1年4組前のサクラの木に取り付けてある巣箱でシジュウカラが子育てをしているのがかくにんできました。親鳥がひっきりなしにエサを運んできています。親鳥の気配がすると巣箱の中からたくさんのヒナたちの元気な声が外まで聞こえています。 無事、巣立つことができるようみなさんでやさしく見まもってあげてください。 (画像と情報:事務局スタッフM) | |
 |  |
巣箱の中にはすでにだいぶ大きく育ったヒナがこんなに! さて、何羽いるでしょう? | エサを運んで来た親鳥が、出て行く時にくわえている白いものはヒナが出したフン。巣の中はいつもせいけつなんだね。 |
 |  |
| 巣箱の中には小型のカメラが取り付けてあるので、巣の中のようすは、理科室前のモニターテレビでライブ(生=なま)で観察できますよ。親鳥が何分くらいごとにエサを持ってくるかなど、ぜひ自分で観察してみてください。 | 校内展示していたヤゴがすべて羽化してトンボになったので、今年の隊による飼育サポート活動は本日で終了。 写真は1本の枝に4つもついたヤゴのぬけがら。(受付でしばらく展示します。) |
  |   |
2021年6月15日(火) ドクガだって大事なえさなんです! わっ!妖精(ようせい)さんだぁ〜っ!っと絶対につまえないで下さいね。 (たしかによ~く見ると、つぶらなひとみはそんな感じでかわいいですが・・・) 日本を代表する毒蛾(ドクガ)、チャドクガ(2.5㎝)です。 ツバキ科の植物が食草なので見つけやすく、たいていは幼虫のとき駆除(くじょ=とりのぞくこと)されます。毛虫だけでなく、成虫(じゅみょうは約1週間)となっても強いかゆみを残す毒があるので注意が必要ですが、シジュウカラをはじめ数種の野鳥は毒針毛のあるチャドクガも捕食(ほしょく=つかまえて食べること)します。ほかにはクモやハチも捕食者です。(左:トンボ池にて) オオシオカラトンボがおとずれていました。メス(↓6月8日参照)はあざやかな黄色と黒でしたが、成熟したオスはこれまたきりっとしたブルーと黒でよく目立ちます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年6月14日(月) ちっちゃいけれどジャンプはするよ! 花だんの手入れをしていると、数匹のオンブバッタの赤ちゃんがいました。 ①そのうちの1匹。(左上) ②大きさは1㎝くらい、カタバミの葉にピョンとジャンプ!(右上) ③さらにジャンプ! ありゃりゃ!クモの網(あみ)に引っかかっちゃった!(左下) ④まわりのようすを見ると、網をしかけたクモはいません。それならばと、引っ付いている網から、はなしてやりました。ホッ!(右下:4枚すべて東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月11日(金) もっと知りたいカメムシ カメムシも産卵時期に入っています。独特なにおいで苦手との声もありますが、野鳥やカマキリ、クモなどカメムシを捕食する者にとっては、ありがたい存在と思います。そして、ふしぎな模様(もよう)、つぶらな目を観察していると、もっとカメムシを知りたくなるかもしれません。左はキマダラカメムシ(トンボ池にて) 右はホオズキカメムシ(東側フェンス沿いにて:1年生が発見♪)の卵です。 2種とも草食性のカメムシで、好きな食草はあると思いますが、今回、写真とは別種の植物からも観察できました。なので、これでなきゃ!というこだわりもないような・・・見方を変えると相当なグルメなのだ!という気もします。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月11日(金) 今年も出てきた気になるキノコ 昨年10月に見つけたキノコ。もしかしたら縁起の良いキノコ、マンネンタケ(霊芝=レイシ)なのでは?とウキウキしました。結果的に同定(どうてい=何であるかを見きわめること)はむずかしかったのですが、今年もすぐそばにニョキと出てきました!(左上)ヤッホー!! これから形がどう変わっていくのか観察していきましょう! 右上の写真はまだ残っている昨年のキノコ(右側)と一緒に撮りました。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月11日(金) ブランコ毛虫 つかまえるとギイギイと警戒音を出し続けるゴマダラカミキリ。手にのせると鳴きながらのぼってきます。人なつっこいなんて喜んでいると、足先に細かな毛が密生している付節(ふせつ)と鉤爪(かぎつめ)のせいで、服からはなすのがちょっと大変なので、ヒィ〜っとこちらが悲鳴をあげそうになります・・・(左:西門付近にて) マイマイガの幼虫。黒い目のような模様がおどろかないでネ、と言っているようです。ツバキ等につくチャドクガと同じ仲間ですが、毒はありません。ただしモサモサの毛は指にささると痛みを感じることもあるようです。 孵化(ふか=たまごから出ること)すると、糸をはいて枝からぶらさがり、風にのって移動(いどう)することから「ブランコケムシ」とも呼ばれるそうです。おもしろいですね! ちなみに食草はこだわりがなく、いろいろな葉を食べるそうです。(右:東側フェンス沿いにて) (画像と情報:スタッフのSさん&用務主事チーム=チームY) | |
  |   |
2021年6月10日(木) トンボ池のフトイのくきで 池からたくさん出ているフトイを観察していると・・・ アオモンイトトンボ。今日は2匹いました。(上左:トンボ池にて) オオシオカラトンボ。黄色がよく目立ちます。トンボの目は複眼(ふくがん)と言って、一万個以上の小さな目が集まっているそうです。トンボの複眼は色覚能力がすごく高く、色があふれるように超多彩に見えているようです。トンボのメガネで見てみたいですね!(上右:トンボ池にて) (画像と情報:下4枚と共にスタッフのSさん) | |
  |   |
フトイの太さはちょうどよい?ホソヒラタアブが休んでいるようでした。よく見ると花粉が目についています。食事後のようです。 (トンボ池にて) | ん!行き止まり・・・ クロウリハムシもフトイにのぼって探検中。 (トンボ池にて) |
 |  |
ヤマトシジミ。やっぱりカタバミの蜜が一番おいしくて好き!なんですね。 (トンボ池にて) | ナミスジチビヒメシャク。グリーンカーテンのため、花だんのドクダミの手入れをしていると、バサッと葉っぱにとまりました。2㎝もないくらいの小さな蛾ですが、目がクリンとしています。でも、暑さにバテたかのようにふせたままだったので、そっとしておきました。この後、元気に活動する夜行性。(中庭にて) |
  |   |
  |   |
2021年6月9日(水) 昆虫がよくいる場所にはちゃんと意味があります シオカラトンボのようでした。成虫になっても肉食性のトンボは、ガガンボ、カ、ハエ、チョウ、トンボ、ハチなどの昆虫を捕食するそうです。この場所が気に入っているのか、カメラのシャッター音などで離れても、また何度ももどってきていました。 (左上:校舎裏、ヤブカンゾウ?が密集している場所にて) シジミチョウの仲間は世界に四千〜六千種類ほどいるそうです。ヤマトシジミのヤマト(大和)とは、日本という意味。カタバミの葉の上でよく見られるのはなぜかな。(右上:校舎裏にて) 菜の花につく亀虫(かめむし)、ナガメがストックのタネさやにいました。ストックも菜の花と同じアブラナ科の花、ナガメはどうやってアブラナ科の植物を見分けるのでしょうか?他にも一匹いました。(左下:東門花だんにて) アブラムシの被害が多い梅の木ですが、今年はてんとう虫のおかげでイキイキとした葉がしげり、日差しの強い日はちょうど良い日かげになっています。ナミテントウのさなぎが観察できました。(右下:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年6月8日(火) ギンヤンマもソーシャル・ディスタンス? 今朝は一気に3匹のギンヤンマが羽化しました。トンボもソーシャルディスタンスでしょうか、ほどよいきょりをたもちつつ窓を開けてもらうのを待っていました。えらい!! (2年生教室前の観察コーナーにて) (画像と情報:下2枚と共にスタッフのSさん) | |
  |   |
オオシオカラトンボのようでした。大きな音をたてながらおとずれていました。産卵の様子は動画でどうぞ(→1分間動画) (トンボ池にて) | アオモンイトトンボ。よく似てるアジアイトトンボは腹部第9〜10節が水色、アオモンは第8〜9節が水色。 (トンボ池にて) |
 | |
2021年6月8日(火) 美しきハンター アシナガバエのなかま。体長は5ミリくらいですが、ハッとするかがやきです。 ダニや極小の虫を捕食する、小さな美しいハンターです。(校庭にて) (画像と情報:下2枚と共にスタッフのSさん) | |
  |   |
シロテンハナムグリ。 | 廊下にいたよ!っとヤモリを受けとりました。少し手足をケガしているようでしたが、ひとみはキラキラと元気でした。校庭裏ではなしました。(校舎内にて) |
  |   |
  |   |
2021年6月7日(月) メドーセージとみつばち メドーセージが咲き始めました。ミツバチの大好きな蜜源(みつげん)のようで、何匹かおとずれていました。(左上:東門花だんにて) でも、気をつけて!アズチグモが待ちかまえていたようです!アズチグモには毒はありません、自分よりも大きなチョウやハチを捕まえることが多いそうです。すごい!!(右上:東門花だんにて) しばらくの間、せっせと蜜をあつめるミツバチの姿が観察できるようです。おだやかな性格ですが、はなれて観察するようにしましょう。(左下:東門花だんにて) 2週間くらい前からカマキリやバッタの赤ちゃんが観察できています。小さくて元気に動くので、なかなか撮影できなかったのですが、アジサイの葉の上にただずむ、まだ2㎝にもとどかないくらいのカマキリの赤ちゃんがいました。(右下:第二音楽室南側通路にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年6月6日(日) これが八重のドクダミ! 八重(やえ)ザクラ、八重のムクゲ、八重のチューリップ・・特に園芸用の植物のほとんどに八重咲きのものがあるそうです。花びらのボリュームがあればその分きれいですから。 この時期よく見るのが八重のアジサイでしょうか。いま花ざかりのドクダミにも八重があると聞いて、それをさがしていました。自然に生えているのを散歩のとちゅうでついに見つけました。ドクダミは、花びらではなく、苞(ほう)と呼ばれる部分が八重になっています。スタッフのつとむさん情報によると、その苞がふつうは4枚ですが、よく探すと5枚や6枚のが見つかるそうです。ぜひ探してさい。幸運の四つ葉のクローバーならぬ、幸せを呼ぶ5苞のドクダミ、見つけたら写真を事務局に送ってください。(西東京市田無町にて) (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2021年6月5日(土) わが家は羽化ラッシュです! こんにちは。先週から次々とカブトムシが羽化してきています。(左) もう十匹以上います。まだまだ羽化しそうで、ケースの用意が大変です。 今度は、トンボです。(右) 今朝、起きたらトンボが羽化していました。 アカネ系はいつも失敗していたので、無事羽化してよかったです。 (画像と情報:OB隊員中1のNくん・5年生隊員のS君) | |
  |   |
2021年6月4日(金) 雨の校庭で ヒメジャノメは花の蜜よりも樹液などが好きで、じゅくした果実にも集まるそうです。幼虫の食草は、ススキなどイネ科の植物です。(左:トンボ池にて) 今年はモンシロチョウの数が多く、ヒラヒラ舞うすがたを間近で楽しむことができます。雨の日の今日も、気ままに過ごしているようでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年6月3日(木) 赤星のないアカボシゴマダラ アカボシゴマダラ(春型または白化型)。 幼虫の食樹は在来種のゴマダラチョウと同じエノキ。 いやがらずに撮影させてくれました。(2枚共に校舎裏にて) (下2枚と共に画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
| カイコがつくるマユは白だけじゃないんですね。中でうっすらと、カイコが動いていているのが見えました。2~3日かけてマユが完成するそうですよ。(3年生教室にて) | オオシオカラトンボのオスでしょうか。ハチに似た音を出しながら高速で飛んでいました。 (トンボ池にて) |
  |   |
  |   |
2021年6月2日(水) 朝の学校で 生き物いろいろ 窓のレールにうずくまる、羽化したばかりのギンヤンマがいました。つかまえてみると元気でひと安心。よく見るとギンヤンマもホッとした目をしてる気がします。(左上:2年生教室にて) モモスズメ。学童ようごさんが見つけてくれました!幼虫はモモやサクラ、梅などの、さまざまな樹木の葉を食べるそうです。オス(下)とメス(上)がわかりやすいよう写したので、体はかれ葉のように見えますが、とてもかわいい顔をしているんですよ。朝見つけて、夕方まで観察できました。夜行性です。(右上:西門にて) ★三年生の教室では、ヤゴをはじめアゲハやカイコなどさまざまな生き物を飼育しています。担任の先生が声をはずませながら知らせてくれるので、一部ですが紹介します。 羽化したキアゲハ、外ではなかなか近づくことができませんが、筆でえがいたような美しい模様をじっくり観察することができました。(左下:3年生教室にて) カイコの幼虫、大きな箱で飼育した方が成長が早いようですよ。耳をすますとクワの葉を食べる音が聞こえるくらい大きくなりました。(右下:3年生教室にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
2021年6月1日(火) ラミーカミキリ 初登場 ラミーカミキリ。おもしろい虫を見つけました(上小初記録)。見つけた場所の近くには食草のひとつで、白い花が咲く花木のムクゲがあります。体が大きいのがメス、後ろの水色の顔がオスです。(左上:校舎裏にて) シジミチョウ。だいすきなカタバミの葉の上で、休んでいまし(右上:トンボ池にて) 今日は教室の窓ガラスの間に、はさまってしまったギンヤンマを救出してきました。しばらく指にとまっていたので写真を撮りました。キレイな色ですね。(左下:トンボ池から空にはなしました) アオモンイトトンボのメスのようです。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
2021年5月31日(月) プールにアマガエルのオタマジャクシ 20日に行われたヤゴ救出の後、一度水を抜いて新しい水を少しだけ張っておいたプール。今日が業者さんによる清掃の日だったのですが、その前に一応かくにんしたところ、なんとアマガエルのオタマジャクシがいっぱいいました!金曜日に確認した時にはわからなかったのですが、すでに産卵はされていたのでしょう。ヒキガエルのオタマジャクシは黒いのですが、アマガエルのオタマジャクシは色がちがいます。中にはゼリー状のから出るとちゅうのもいました。業者さんによる清掃が始まるぎりぎりまでかかって、左の写真のバケツくらいの数×4~5杯分をトンボ池にひなんさせることができました。 (下2枚と共に画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
| アマガエル。葉っぱ→小枝→葉っぱ→小枝と、ピョンピョン上手にいどうをしていました。(トンボ池にて) | アオモンイトトンボ。オスはなわばりを持ち、時々水面を低く飛びながらパトロールをしているそうです。(トンボ池にて) |
  |   |
2021年5月28日(金) しっぽのにじ色がきれいでしょ! つみあげていたかれ草をかたづけていると、ゴソゴソとニホントカゲの幼体(ようたい)が出てきました。あわてて土の中にもぐろうとする所をちょっとだけ捕獲(ほかく)して写真をとりました。 しっぽがきれいなにじ色だから「にじ色トカゲ」なんてよばれることもあるけれど、しっぽがにじ色なのは子ども(幼体)の時だけだよ。(2枚ともに校舎裏にて) (下4枚と共に画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
| ニホンカナヘビの幼体も同じ場所で出てきました。いそいでかれ草の中へ入ろうとするところをちょっとだけ捕獲してみましたが、捕まえられた事に不満そうだったので、すぐに放しました。ちなみにその後、カナヘビらしき他の2匹がよこぎり、昨年よりも増えているような感じがしてなりませんでした。(校舎裏にて) | 交尾中のガガンボ。 左の大きい方がメス、右の小さいのがオスです。 (トンボ池にて) |
  |   |
| アジサイの花はガクアジサイとちがい、吸蜜ができないので蝶が訪れる事はあまりないようですが、今日はココで撮ってほしいと言わんばかりに、モンシロチョウが葉の上にとまりました。(校庭にて) | ナミテントウがいました。足に無数の吸盤(きゅうばん)をもっているので、飼育ケースもかんたんにのぼれます。 (駐車場花だんにて) |
  |   |
2021年5月27日(木) 教室でギンヤンマが羽化しました!② 今日は一匹の羽化がありました。(左:朝に撮影) 外が雨だとわかるのか、窓へ向かわずこの姿勢(しせい)のまま、ずっと天井(てんじょう)で過ごしていたそうです。(右:夕方に撮影) これから獲物(えもの)をとらえる脚(あし)は、とてもじょうぶなようです。 (1年生教室にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
| 高木のタイサンボク、見上げると20㎝くらいの花がいくつか咲いています。花軸にめしべ(上部)と、少しずつとれているおしべが、大きくて厚みのある花びらにたまっています。それから、とても良い香りがします。(校庭にて) | 雨の日はとじているアサザの花ですが、雨でも『星』がかくにんできます! (トンボ池にて) |
  |   |
植物の手入れをしていると、モンシロチョウが出てきました。葉の裏でぶら下がるように過ごしていたようです。しばらく小雨にあたりながら過ごしていました。 (校舎裏にて) | ナミテントウ。 ちょうど良い雨宿り場所を見つけていました。 (東側フェンスにて) |
  |   |
| ヤサガタアシナガグモ。水面近くにいます。雨の日は羽をもつ昆虫は低めに飛ぶようなので、ごちそうがやってきやすいのかもしれません。(トンボ池にて) | カルガモの親子、元気です!親鳥は雨で増水した川の流れを読みながら、7羽の子ガモを反対側の岸辺にいどうさせたりしていました。ハラハラする場面でしたが、子ガモ達は声をかけ合っているかのように上手に渡っていました。(石神井川にて) |
  |   |
2021年5月26日(水) 教室でギンヤンマが羽化しました! 今朝は二年生の教室から2匹のヤゴ(ギンヤンマ)が羽化していました。 また、なかなか羽化できずにいたヤゴもいて、皆でおうえんをしてくれたようです。羽をひろげることなく命を終えてしまっても、自然の中ではその命をありがたくいただいて、命をつないでいくのですから、空に放つことができなくても、さまざまなすがたを観察できたことに感謝してすごしてくださいね。(上2枚:二年生の観察場にて) イトトンボ(どちらもアオモンイトトンボのようでした)。成虫になっても肉食性。小さな蚊(カ)や蛾(ガ)が食事となるそうです。右のイトトンボは少し羽がまがっていましたが、元気に過ごしていました。(下2枚:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
  |   |
  |   |
  |   |
2021年5月26日(水) トンボ池の黄色いスター(星) 単色のイトトンボがいました。調べるとモートンイトトンボにも似ているようですが・・・また会えたら良いです。(左上:トンボ池にて) アサザが咲きはじめました。(右上:トンボ池にて) トンボを撮影していると、うでにとまったり、足にとまったりしてきたサトキマダラヒカゲ(チョウ)。幼虫の食草はタケやササなど。(左下:トンボ池にて) 最初はムシトリナデシコにとまり、吸蜜していたモンシロチョウ。しぶしぶ撮影に協力をしてくれました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年5月25日(火) 巣立ったよ にぎやかに鳴いているなぁと見上げてみると、まだ羽のそろっていない元気な子どものスズメのようでした。その後、にぎやかな鳴き声はトンボ池の高木から聞こえ、仲間と過ごしているような感じでした。(左:校庭にて) カタツムリがいました。カタツムリは土の中に卵を産みつけます、卵から出てきた時にはもう殻(から)をもっていて、敵からの危険を感じたとき、乾燥してからだがひからびないようにするため、そして冬の寒さから身を守るため殻の中に入ります。便利ですね。(右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月24日(月) 朝から長いやつ発見! 朝からニョロニョロ〜と、2mくらいのヘビが泳いでいました。アオダイショウかな?と思いましたが、シマヘビかな。(左上:石神井川にて) ウメスカシクロバ。1㎝くらいのガの仲間。成虫には毒はありませんが、梅や桜などのバラ科の植物が食草の幼虫には毒毛があります。わからない毛虫がいた時は素手でさわらないようにしましょう。(右上:東門花だんにて) アオスジアゲハ。4齢幼虫のしるし、黄色の線が出ていました。(左下:校庭にて) アマガエル。元気にすごしています。(右下:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月21日(金) 葉っぱ上の小さな世界 アカマダラカゲロウ。長い尾毛を左右にパサパサとさせながら過ごしていました。(左上:西側駐車場花だんにて) ドウガネサルハムシ。4㎜くらいの小さな虫です。かがやきがきれいです。(右上:校舎裏にて) 三年生が飼育しているカイコの食草、クワの木を観察すると、白いふわふわした糸のようなものが見られる事があります。これはクワキジラミの幼虫が、とりすぎた糖(とう)をロウ物質に変えて出し、身をかくすために利用しているそうです。その中から出てきた幼虫がいました。(左下:東門花だんにて) クワキジラミの成虫。4㎜くらい。(右下:西側駐車場花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
2021年5月21日(木) プールのヤゴを救出しました~1080匹を救出!~ プールの水がぬかれる前に、3年生によるヤゴ(トンボの幼虫)の救出(きゅうしゅつ)活動を行いました。今年は密(みつ)にならないように2クラスずつに分かれて行いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1クラスをさらに2つのグループに分けて救出。 | かごですくった落ち葉の中からヤゴをさがします。 | 種類ごとに分けて大きな入れものにうつします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きなギンヤンマ。これがいるのが上小のじまん! | たくさん見つかったイトトンボのヤゴ。(過去最高記録) | 種類ごとに数を記録して集計していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この時期に水をぬくと、羽化(うか)寸前まで育っているヤゴがみんな死んでします。 この日は、来週に予定されている清そう作業に先立ち、水をへらしたプールから子ども達がヤゴを救出しました。 今年は春の気温が高かったため、すでにトンボになって飛び立っていったものもだいぶいたようでしたが、それでも東京ではめずらしいギンヤンマのヤゴ約500匹をはじめ、過去最高数の130匹ものイトトンボ。さらにアカトンボ・シオカラトンボのなかまのヤゴ、クロメダカ、ヌマエビなどたくさんの生き物を救出することができました。 ギンヤンマやイトトンボは草に卵を産むトンボなので、ふつう、学校のプールでは見ることができません。しかし、上小では毎年秋に3年生が「トンボの産卵おたすけ作戦」として、プールに草を浮かべる活動に取り組んでいるおかげで見ることができるものです。 また秋に3年生が放流したクロメダカもたくさんの子どもを産んで大きく育っていたので、それらもすくい上げました。 ヤゴは3年生の教室で飼育するほか、ヤゴに親しんでもらうために低学年の教室や職員室前でも展示します。また自宅での飼育を希望する子ども達にも配布される予定です。 クロメダカは教材として理科室などで活用されます。 飼育しきれないヤゴやメダカは、おとなりのトンボ池に引っ越ししてもらう予定です。 大きなギンヤンマのヤゴがトンボへと変身する羽化(うか)の様子は、一度見たら忘れられないすばらしい光景です。ヤゴの飼育観察を通して、一人でも多くの子どもたち&大人のみなさんがそれを実際に自分の目で見る体験をしてくれるとうれしいです。 羽化はふつう、夜に行われるので学校では観察ができません。ぜひ自宅で飼育・観察してみましょう。 ★かんたんなヤゴの飼い方プリント(こちら→クリック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |
2021年5月20日(木) カルガモの子育て カルガモが子育てを始めています。可愛さあふれる子ども達や、親鳥の愛情がいっぱいのまなざしに、道行く人達も足をとめて観察していました。(左:石神井川にて) 上小を歩けば必ず会える!?ナミテントウの幼虫です。菜の花のサヤにいました。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月19日(水) アオスジアゲハの幼虫発見! クスノキにアオスジアゲハの幼虫がいました、そろそろ蛹(さなぎ)になりそうな感じもします。(左上)少しカメラを近づけてシャッターを押していると、きけんを感じたのか、ニョキっと臭角(しゅうかく)を出して、くさいにおいを出してきました。(右上:いずれも校庭にて) ユスラウメ。童話『魔女の宅急便』ではユスラウメのジュースがでてくるそうですね。(左下:校舎裏にて) 草のつゆや、花の蜜を吸いながらすごすガガンボ。(右下:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月18日(火) 白いイチゴ赤くなる イチゴが太陽の光をあびて、赤くなりました。(左上:校舎裏にて) ウリ科の植物が大好きなウリハムシ。草花の葉の裏で雨やどりしているようでした。(右上:東門花だんにて) ナノハナにおとずれたモンシロチョウ。(左下:校舎裏にて) ヒラタアブもやってきました。(右下:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年5月17日(月) カタツムリ君登場の季節です ほかの生き物もいっぱい! カタツムリがいました。さいしょはコンクリートの上にいました。からだを守るじょうぶな殻(から)を作るためにコンクリート食べカルシウムをとると言われています。(1段目左:東門ふきんにて) ナナホシテントウ。草の先まであがり、飛ぶところです。固くて赤い前ばねの中に、すばやく折りたたみできる、やわらかい後ろばねがあります。どこに行くのかな?(1段目右:トンボ池にて) ナミホシヒラタアブのようです。吸蜜中でした。(2段目左:東門花だんにて) クサカゲロウの卵が、ニゲラ(草花)の細い葉にもありました。(2段目右:東門花だんにて) ガの種類はたくさんあって、時々名前がわかりませんが、おとなしくしている様子を観察したり、ふくざつな羽のもようを見るのも楽しいです。(3段目左:西側花だんにて) モンシロチョウ。上がオスで下はメス、最初はタンポポの吸蜜をするオスに気がつきました。よく見ると、メスと一緒にいます。その後、交尾をしたまま飛んでいると、他のオスがじゃましに入り、もめていました(そのせいなのかわかりませんが、オスの羽にほころびがあります)でも離れません!その後、ムラサキシキブの葉にとまり休息すると、また仲良く飛んでいきました。(3段目右:校舎裏にて) プールに入れたガマやフトイのコンテナを引き上げると、イトトンボやギンヤンマなどのヤゴが元気に過ごしていました。先に救出したヤゴは羽化に困らないようトンボ池に入れました。(4段目:ヤゴ救出授業の準備中にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年5月16日(日) いやーーな雑草も 利用してみると! 今年も、ドクダミの花が咲くころになりました。トンボ池周辺にもかなり生えていることでしょう。ぬいてもぬいても生えてくる、くさくて手におえないヤツ。ときらわれものの雑草ですが、利用価値は、かなり広いみたいですよ。ドクダミ茶をつくってみました。①~⑧までそんなに手はかかりません。 ① 花や茎ごと、かりとります。 ② ボール(バケツ)に水を入れ、水洗いします。 ③たばねて2~3日、日に当てます。その後1週間ほどかげぼしします。 ④ カサカサになったら、20gほど計りとります。 ⑤ ハサミでてきとうに細かく切ります。 ⑥ 水600ccほど入れて、ふっとうしてから15~20分くらい煮出します。 ⑦ 茶こしでこして。 ⑧ はい!いい色に出来上がりました。どうぞ召し上がれ。 味は、若干のあのにおいが残っていますが、苦くもなくおいしくいただけるぶるいに入るでしょうか。とある「園芸」のYOUTUBEチャンネル「駆除してはいけない雑草第一位」が「ドクダミ」になっていました。というか、駆除できないですよね。 十薬といわれるこのドクダミにはどんな効能があるのでしょうか。調べてみてください。 ★どなたか「八重のドクダミ」を観賞用に育てている人はいませんか。分けてくださいませんか。 【注意!】 * 煮だすときのなべは、鉄製のものでなく、ガラスかホーローがいいそうです。ドクダミの成分が鉄と結びつき、変質するようです。(今回は磁石のつかない種類のステンレスなのですが、やはり鉄製かな) * 腎臓の悪い人、その薬をのんでいる人は、飲まない方がいいそうです。 * 飲みすぎに注意!下痢をするおそれがあるようです。「良薬もすぎてはダメ」ということですね。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) | |
 |  |
 |  |
2021年5月14日(金) 白いイチゴ!? アマガエルはどこでもよじのぼれる吸盤(きゅうばん)が前足は4本、後足は5本の指先についています。全部で18の吸盤をもっているんですね。(左上:トンボ池にて) イチゴがほんのり色づきはじめていました、種から赤くなるとは!(右上:校舎裏にて) ヒルガオが咲きました。薬草なんですね。皆さんは知っていましたか?(左下:東側フェンスにて) イネ。くきがしっかりしてきました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年5月13日(木) 「ガガンボ」って知ってるかい? 真っ赤になったヘビイチゴ。茎(くき)をのばしながらふえていきますが、アリもせっせと種を運んでいるようです。いろいろな場所で観察できます。(左:校庭にて) エゾホソガガンボ。アメンボみたいな長い手脚、ふわふわ〜と飛んできました。見ていると、6本あるはずの手脚(あし)がたりません。ガガンホは敵(てき)におそわれあしをつかまれると、あしをはずして逃げる方法をとります。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月12日(水) アブラムシたいじのために集結! 今日はラカンマキ(樹木)のあちらこちらに植物の汁を吸って木を弱らせてしまうアブラムシがビッシリついていましたが、ありがたいことに、もうナミテントウの成虫(左上)幼虫(右上)がいそがしそうに、また、まんぷく気味にしていました。そして卵(左下)もあります。このぶんだとアブラムシがいやがる酢(す)をまいたりしなくても大丈夫そうです。 よく観察してみると『ウドンゲの花』と呼ばれるクサカゲロウの卵(右下)もありました。 (全部東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年5月11日(火) このピンクの玉、な~んだ? 咲き終えたノバラの手入れをしていると、大小さまざまなピンク色のつぶがありました。(1ミリ~10ミリくらい)これはバラハタマフシと言う虫コブでした。バラハタマバチが卵を産みつけると、バラがはんのうしてフシ(コブ)を作るそうです。フシには幼虫が一匹ずついて、しばらくすると葉から落ち、冬をこして翌春にコブに穴をあけて出てきます。そしてまたノイバラの新芽に産卵するそうです。(上左:東側外通路にて) バッタの食草になるイヌムギ(イネ科)に花が咲いていました。(上右:原っぱゾーンにて) 今日はくもり空、なかなか日差しがとどかないことにふまんそうなアマガエルでした。(中左:トンボ池にて) ニワゼキショウ。1㎝くらいの小さな花、くるんとまいた蕾(つぼみ)もかわいいですね。(中右:校庭にて) カイコの観察をはじめた三年生、カイコはさなぎになるまでクワの葉をたくさん食べます。クワの木のようすを見ると、キイロテントウがいました。クワの葉についてしまうことの多いうどんこ病などの菌を食べてくれるので、上小のたくさんのクワの木はどれも健康状態良好!(下左:駐車場・西側花だんにて) テントウムシのおかげでアブラムシのひがいがなく、小さなバラもきれいに咲きました。(下右:西門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年5月10日(月) カエルにも個性があるようです アシタバの葉がお気に入りのアマガエルを2週間くらい観察できませんでした。久しぶりに会うと緑色になっていました。(4月27日に観察した白っぽいカエルと、今日のカエルが同じかは正確ではありませんが作業中にカエルと出会うのはたいてい同じ場所。)なんとなくカエルにもテリトリー(なわばり)と言うか、しっくりくる場所があるのかなぁと感じます。ちなみに、主(ぬし)と思うのは、東門の花だんと職員室前花だんに一匹ずつ。もしかしたら木々もあるので複数いるかもしれませんが。そしてアシタバのカエルと違い、近よるとピョンっとすばやいです。(左:トンボ池にて) コアオハナムグリ。花粉を食べるのに夢中になっていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年5月7日(金) 寄生(きせい)植物って知ってる? ナミアゲハの幼虫がいました。元気に大きくなれ〜っ(左上:トンボ池にて) クワキヨコバイ。体長は8㎜くらい、時々ピョンっとはねるのでバッタみたいですがバナナ虫(ツマグロオオヨコバイ)の仲間です。(右上:校舎裏にて) マエベニノメイガかな?と思いましたが、アメリカピンクノメイガのようです。体長は2㎝くらい、きれいな色の小さなガです。(左下:探検隊倉庫付近にて) ツクシみたいにニョキっと出てきたヤセウツボ、もともと日本にはなかった植物で、他の植物のえいようをもらいながら育つ寄生(きせい)植物です。もうしばらく観察したら、ぬこうと思います。(右下:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
2021年5月6日(木) 「立夏・・・蛙はじめて鳴く」 昨日5月5日は「立夏」(りっか)。暦(こよみ)の上では夏の始まりで、春分と夏至(げし)のちょうど中間にあたります。七十二候では「蛙(かわず=カエルのこと)はじめて鳴く」。学校のそばに住む隊員さんからの報告によると今日あたりすでに夜はアマガエルの合唱が聞こえているそうです。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
ニホンカナヘビ。ひなたぼっこをしていたようです。上から見ると、おなかが大きいような感じがしました。(校舎裏にて) | |
 |  |
西側花だん、西門側のツツジの木では、ナミテントウの幼虫とさなぎが見られます。今日は成虫も観察できました。よく見かけるナミテントウの二紋型(にもんがた) | これもナミテントウ。 ナミテントウには、いろいろな種類の模様があります。 |
 |  |
| ナミテントウ幼虫 | これは?ツツジのすぐそば、フェンスにからまり始めている葉(スイカズラ)にいました。 1㎝くらいで頭にハサミがあります。同じくアブラムシを食べるクサカゲロウの幼虫か? |
 |  |
校舎裏の畑では・・・モンシロチョウ。 | ヒメジョオンの蜜をいただくモンシロチョウ。 |
 |  |
菜の花につくカメムシとして名がつけられたナ(菜)ガメ。菜の花(西洋カラシ菜)の葉の上でじっとしていました。 | クサギカメムシ。 翅(はね)を広げるようすが撮れました。 |
 |  |
2021年5月3日(月) 「虻蜂(あぶはち)取らず」・・・って? さなぎから無事に羽化しました。(←「見つけたよ!」コーナー5月1日参照) ホソヒラタアブのようでした。しばらく葉の上で過ごし(左)、さっそく吸蜜していました。(右) (画像と情報提供:スタッフのSさん) ※しずくのようなさなぎから出てきたのは、やっぱりアブだったのですね。ところで「アブ」と「ハチ」ってどうちがうか知っていますか?花に来ているこのハナアブのなかまは、体の色もハチににせて、黄色と黒のしまもようなので、よくハチとまちがえられてこわがられます。でもよく観察してみましょう。 ①羽の数は何枚かな? ②おしりに針(はり)はある? ③ハチはヘリコプターみたいに空中で止まって飛ぶこと(ホバリング)ができるけどアブはどうだろう? ④ハチはアリの仲間だから体にアリみたいな「くびれ」があるんだけど、アブはどう?アブは何のなかまかも調べてごらん。 アブとハチ。両方つかまえてじっくり観察できれば一番いいんだけれど、よくばって二つのものを一度に手に入れようとして、けっきょくどちらも手に入れられないことを「〇〇〇〇とらず」って言うんだって。残念! | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年5月2日(日) 野菜のめばえ当てクイズ! 野菜の種をまきました。 「コマツナ」「インゲンマメ」「パセリ」「ニラ」「モロヘイヤ」「シソ」の6種です。 1週間から10日ほどで芽が出てきています。どれがどの野菜のめばえなのか当てて下さい。 めばえだけで名前を当てるのは超難問ですが・・・。2つはすぐに区別できるでしょう。あとは、ヒントを参考にすればわかると思います。 【ヒント】アは「〇アゲハ」の食草・エは、さやや種には強い毒が・オは、ふた葉ではない。元気の出る定食あり・ カはハーブの仲間 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) | |
 |  |
 |  |
2021年4月30日(金) クワ、ワクワク・・・ クワの実が色づいています、ワクワク・・・(左上:校庭にて) 人間と虫達の好みのちがいがハッキリわかる大輪のバラですが、ステキに咲きはじめています。(右上:校庭にて) かわいいオレンジ色の花のナガミヒナゲシ(写真はつぼみ)ですが、ほかの植物をよせつけない繁殖力(はんしょくりょく)がある外来種なので増やさないように管理しています。でも、キレイな花なので人気もあり、観察用に一時的に残しておくこともあります。また、ナミテントウの幼虫がいたりした時もしばらくそのままにしています。(左下:校庭にて) 今年はてんとう虫の観察がよくできます。こちらはナナホシテントウの成虫と、幼虫がいます。雑草と呼ばれる草花であっても、昆虫用にのこしておくと楽しいです。ちょうど三年生が種まき作業をしていたので、一緒に観察しました。(右下:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年4月28日(水) ★初めての発見!ヨツボシトンボ★ トンボ池で見かけないトンボを見つけました。 藤だなのせん定作業中に主事のIさんが「あっ、変なのが飛んできたぞ!」って教えてくれたのです。羽化したてなのかふわ〜って飛んで、ボテっと着地する印象でこれまでトンボ池で見てきたトンボとは何かちがう。記録のために写真に撮影。前からも撮ろうとすると、ふわ〜んと行ってしまい、ちょっと追いかけてみたのですが今回は後ろからの2枚だけしか撮れませんでした。ちなみに、2匹いたような感じでした。 後でスタッフとも確認したところ「ヨツボシ(四つ星)トンボ」ではないかと思われます。羽の上端に4つの黒い模様(星)があるのが特徴のようです。全体にがっしりした感じのトンボです。 トンボ池は、できてから今年で22年目の夏をむかえますが、ヨツボシトンボは初めての発見です。ヨツボシトンボは東京都区部では絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)とされている珍しいトンボです。(東京都レッドデータリストRL(区部):絶滅危惧ⅠB類(EN)) この時期、池から羽化しているようなので、みなさんもぜひ観察してみてください。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) |
 | |
 |  |
2021年4月28日(水) 知らん?いや「紫(し=むらさき)蘭(ラン)」です! シラン。あまいみつや香りのないシランですが、花粉をはこんでもらえるよう、くふうされています。虫の気持ちになって花をかんさつすると、気になる入り口が見られます。(上:校庭にて) ノバラ。小さなバラが元気よく咲きはじめています。香りも楽しめます。(下左:東側外通路にて) イチジク。今年も楽しみですね。(下右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月27日(火) ★銀メッキのかがやき! ギンメッキゴミグモ。出入り口のマットをどかすと、米つぶくらいのクモが歩いていました。ギンメッキのかがやきが目をひきます。(左:図書館棟出入り口にて) ノメイガの仲間かな?体長が8㎜くらいです。(右:校庭にて) | |
 |  |
 |  |
カワラヒワ。仲間と水浴びをしに、おとずれていました。(左上:トンボ池にて) チュウレンジハバチ。体長は2㎝くらいですがオレンジ色がよく目立ちます。(右上:トンボ池にて) アマガエル。たっぷり日光浴をしているようですが、まだ白っぽいです。変色にかかる時間はさまざまのようです。(左下:トンボ池にて) コミスジ(チョウ)。幼虫の食草はフジやハギなどのマメ科の植物です。観察できると良いですね。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月26日(月) しゃがんでみると見つかるもの ヒメフウロのようです。おとなりの草地あたりから広がりかわいらしい姿を見せてくれています。(左:東側の外通路にて) 草をぬいているとアマガエルがころがりました。夜行性なので、昼間は寝ていたり、しずかに過ごしているようですが、小さいので気づかず、おたがいビックリしてしまいます。(右:東側花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月23日(金) 葦(あし)はじめて生(しょう)ず 1年を24の季節に分けた「二十四節季」。それらをさらに3つずつに分けた「七十二候(こう)」は、昔の人々が考えたものですが、自然のうつりゆく姿をよくとらえていて感心させられます。今の時期は「立春」から数えて6番目の「穀雨(こくう)」。その最初の候で「あしはじめてしょうず」です。(4月20日~24日頃)水辺の植物が芽をのばすころ、という意味です。 トンボ池には「葦」(あし=よしとも言う)はありませんが、写真はフトイという植物です。冬の間は枯れていますが、この季節になると急にのびはじめ、ヤゴはこのくきを上ってトンボへと羽化するのでトンボ池には大切な植物の一つです。(左:トンボ池にて) 最近、学校のまわりをよく飛んでいるカラス。高い木の上に巣を作るのですが、高い木がどんどんへってきているので場所探しも大変なようです。仕方なく電信柱に巣を作ってしまい問題になることもあります。よく見るとクチバシが細いので都会ではめずらしいハシボソガラスでしょうか。(右:校庭フェンスにて) | |
 |  |
 |  |
アマガエルがアシタバの葉の上で日光浴をしていました。どこで過ごしていたのか、ずいぶん白く、そしてふっくらしています。アマガエルの産卵期は4月〜7月、大切に見守っていきましょう。(左上:トンボ池にて) ナナホシテントウのさなぎを見つけました。(右上:校舎裏にて) バナナ虫(ツマグロオオヨコバイ)、手先をよく見るとピースサインしているんですね。(左下:東門花だんにて) 顔なじみとなってきた2羽のカルガモが訪れ、1羽はプール、もう1羽は日光浴をしています。すると途中からハクセキレイも訪れ、羽づくろいをはじめました。(右下:プールにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月22日(木) 校庭の生き物たちの春のドラマ 昼時にやってきたカルガモを「今日は一羽だなぁ」と観察していると、後から2羽のカルガモがグワァグワァとにぎやかに飛んできました。でも、おだやかではない様子の二羽は、お互いに追いかけまわすようにすぐに飛びさりました。 最初の1羽はその様子を気にかけることもなく、気持ちよさそうに過ごしていました。(左:プールにて) ボールよけのフェンスがあるので、人の出入りがほとんどなく、アマガエルにとって自由きままに過ごせる場所になっているようです。(右:職員室前花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月21日(水) テントウムシじゃないのはど~れだ? てんとう虫は20日くらいで成虫になるそうです。 ナミテントウの幼虫を見つけました。(左上:校庭西側にて) こちらはさなぎですが、ナナホシテントウのようでした。おしりは葉に固定されていています。さなぎになって1週間くらいで羽化するそうです。卵は葉の裏で産むようですが、さなぎになる時は葉の表面、お天道さまにあたりながらのようです。(右上:校庭西側にて) かれた草をとっていると、ナナホシテントウがあわてて出てきました。(左下:校舎裏にて) てんとう虫と同じくらいの大きさのナガメ。『菜の花につくカメムシ』と言ういみ。菜の花のなかま、オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)に訪れていました。(右下:東門花だんにて) | |
 |  |
 |  |
水上の忍者、アメンボです。いろいろ調べてみるとおもしろいですよ。(左上:トンボ池にて) ヤマトシジミ。チョウの触角(しょっかく)は人間の鼻と同じにおいを感じる所。シマシマもようがステキです。(右上:東側花だんにて) カルガモがおとずれていました。仲良く歩いたり、ひなたぼっこしたりと、おだやかな昼時でした。(左下:プールにて) シジュウカラも鳴きマネをするのでしょうか?かすれた自転車の音がするなぁ。。と見上げると、かすれた声ではあるけれど、元気に飛びまわっていました。(右下:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年4月21日(水) 菜の花(コマツナ)の奇形(きけい) このコーナーでもたびたび紹介されている菜の花の話題です。 菜の花が種の時期をむかえたので、種とりをしていると・・・。明らかにとても変わった形をしたものを見つけました。毎年のように必ず見られます。数十に一つくらいはあるようです。奇形(きけい)とは、めずらしい形という意味です。左はふつうのもの。右が奇形です。奇形のものをよく見ると、めしべが大きくとびだしたような花が左右に見えます。花びらもぶあつく色もうすく、ふつうのものとくらべて、見た目がかなりちがいます。 四つ葉のクローバーも奇形の一つです。皆さんも、身の回りに奇形と思われる植物があったら写真にとって見せてください。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |
 |  |
 |  |
2021年4月20日(火) 名前の由来(ゆらい)を想像してみよう コバンソウ(左上:トンボ池にて) マミジロハエトリのオス(右上:トンボ池にて) ナナホシテントウ(左下:中庭にて) トキワツユクサ(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |
2021年4月19日(月) WELCOMEボード完成 職員玄関わきにフラワーボックス型のウェルカムボードを設置しました。これはしぜん探検隊のジュニア隊員さんの卒業記念制作として春休みに制作したものです。昨年度の卒業生隊員さんと、コロナ禍で卒業記念の活動ができないまま卒業をむかえてしまった一昨年度の卒業生隊員さんがこの春協同して企画制作したものです。 材料には、体育で使うハードルのこわれたものから取った板の部分や、廃品のミニ黒板などを加工して使っています。「WELCOME」の文字は校庭の木から剪定(せんてい)した枝を組み合わせて作りました。 季節の花々を飾れるように作られており、今後隊員有志で花の入れ替えなどの管理をしていくつもりです。 学校においでの際は、ぜひごらんください。 |
 |  |
2021年4月19日(月) カタツムリの殻(から)のひみつ かんそうしないようにでしょうか?石にくっついているカタツムリを見つけました。カタツムリの殻(から)の表面は、ヨゴレがこびりつかないミゾやシワの模様で作られているそうです。これをヒントに、建物の外壁材(がいへきざい)など、私達のくらしに役立てているそうです。(左:校庭にて) 何か見つけたのでしょうか?ハクセキレイがおとずれていました。(右:プールにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月16日(金) しぜんがつくる形と色のおもしろさ アメリカフウロ。タネが入っている鞘(さや)はアラジンの宮殿(きゅうでん)のような形です。(左上:校庭にて) ナナホシテントウ。安心してすごせる場所なのか、寝ているのかも?それくらい動かず、のんびりしていました。(右上:図工室前の花だん・アジサイの下にて) キンバエ。メタリックグリーンがかがやいています。人間にとっては衛生面で気をつけなければいけませんが、自然界ではとても大切な分解者です。(左下:東門花だんにて) アミガサタケのようです。学校のしきち内でよく見かけるキノコ。しげったドクダミの間にありました。(右下:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月15日(木) 風のおとしもの カタバミのみつをすうヤマトシジミ。天気のよい日は必ず観察できる季節となりました。(左上:東門花だんにて) ナノハナにおとずれていたのはゴボウハマキモドキのようでした。次はキレイに撮りたいと思わせる、羽のもようでした。(左下:校庭にて) 昨日の風のおとしもの、松の雄花(おばな)でした。(右上:校庭にて) ユスラウメの実がほんのり色づいてきました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月14日(水) 雨の日の校庭で・・・ バナナ虫(ツマグロオオヨコバイ)、雨の日は葉のうらで過ごすのがおちつくようです。(左上:東門花だんにて) 天気によってとじている花もありますが、雨の日も元気に咲いてる菜の花。(右上:校庭にて) 幼虫だったクロヒラタアブは、野バラの葉のうらでさなぎになっていました。(左下:東門花だんにて) ヨトウガ。幼虫はイネ科以外の植物を食べてしまうのでいやがられますが、2㎝くらいの成虫はそっと指を差し出すと、のっかってくれる人なつっこさもあり、にくめません。(右下:中庭主事倉庫前) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月13日(火) 待ち遠しいのはお日様?それとも雨? キイロテントウ。植物が弱ってしまう菌をよろこんで食べてくれるたのもしい昆虫。(左上:校舎裏、ゲッケイジュの手入れ中に出てきました。) ツツジ。今年は花々の早めの開花におどろかされます。(右上:東門花だんにて) アマガエル。草のしげみからピョンっと出てきました。(左下:職員室前の花だんにて) 水浴びをしに訪れる野鳥を時々見かけます、今日はシジュウカラが来ていました。(右下:昼時のトンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月12日(月) 虫メガネで見てみよう 昨日の観察会で首に虫メガネをかけて参加している探検隊員がいました。タチイヌノフグリの花は、虫メガネで見るのにちょうど良い小さな花です。(左:校庭にて) コデマリ。しらべてみると、小さな虫が好む花のようです。よく見ると左の花に訪れています。こちらも虫メガネが必要です。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年4月11日(日) ギンヤンマの羽化が始まりました!! プールでギンヤンマの羽化が始まっています。例年4月下旬頃から見られることがありますが、今年はこれまでで一番早い記録です。 毎年9月に3年生が総合の授業で「トンボの産卵お助け大作戦」に取り組み、プールにギンヤンマが卵を産むために必要な植物をたくさん入れて、さらに卵からかえったヤゴのえさになるようにとメダカを放流するなどして、かんきょうをととのえる活動にとりくんでくれているおかげで、上小のプールはギンヤンマにとって、とてもよい「池」になっているのですね。 それにしても今年はこんなに早くからギンヤンマの羽化が見られるのは、どうしてでしょう。いくつか理由が考えられるかもしれません。みなさんも考えてみてください。 (画像と情報:スタッフのSさん) |
 | |
2021年4月11日(日) 春探し写真クイズ2021 ここはどこでしょう?⑥ 白い花がブドウの房(ふさ)のようにたれ下がっています。いいかおりもしています。 藤(ふじ)の花です。本当は左に藤色(=うすむらさき色)の花がさく木もあるのですが、今年は右の白い花が咲く木の方だけに花がついています。でも今年は、かつてないほどのみごとな花の数です。もうすぐ満開です。さて、ここはどこでしょう? この問題のヒント: 上小の子どもならだれでもよく知っている場所です。 (画像提供:スタッフのWパパさん) この写真の場所を見つけた人は事務局までメールで①学年②お名前③答え(場所をコトバで説明してもよいし、写真を撮って見つけた証拠にしてもらってもいいです。幼児さん~大人まで隊員以外の方も参加できます) (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。 (しめきり4月18日) |
 | |
2021年4月11日(日) 春探し写真クイズ2021 ここはどこでしょう?⑤ 新緑の緑が美しい畑の風景です。うしろのお寺さんのかわら屋根も春の日差しをやさしく照り返しています。畑で作られている作物がなんだかわかりますか? この問題のヒント: ①西武新宿線の線路のすぐ南側です。学区域の西側です。 ②この畑のすぐとなりに下の写真の児童遊園があります。入り口にあるピンクのハナミズキの木がめじるしになるかな。 (出題者:スタッフのMさん) この写真の場所を見つけた人は事務局までメールで①学年②お名前③答え(場所をコトバで説明してもよいし、写真を撮って見つけた証拠にしてもらってもいいです。幼児さん~大人まで、隊員以外の方も参加できます。) (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。 (しめきり4月18日) | |
 |  |
 | |
2021年4月10日(土) 春探し写真クイズ2021 ここはどこでしょう?④ むらさきの次は、赤に黄色です。『上石神井オランダ村』でとりました。写真左のすみで農作業をしているおじさんに撮影許可をいただきました。 「チューリップきれいですね。ちょっととってもいいですか。」 「うーん、いいよーー。もう終わりだけどさ・・・」 どこまでものどかな風景が広がっています。 この問題のヒント: ①学区域の東側ぎりぎりです。 ②フェンスの柱や白い建物は、とある学校のものですよ。 (出題者:スタッフのコタジー) この写真の場所を見つけた人は事務局までメールで解答を。 (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。 (しめきり4月18日) |
 |  |
2021年4月9日(金) 背中に「お面」を背負ってます 草の手入れをしていると、オオホシカメムシがキクの葉の上でのんびりしていました。小昆虫など、いろいろ食べるそうですが、これから実をつけはじめたクワにもおとずれそうです。(左:校庭にて) フエフキスイセンが咲いていました。ラッパスイセンの原種(もともとのすがた)です。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年4月8日(木) 小さくて地味だけど私たちも上小の住人です! 野バラについたアブラムシを捕食しているクロヒラタアブの幼虫を発見!他にも4匹くらいいました。(左上:東門花だんにて) カブラハバチ。ハチのなかまですが、刺しません。(右上:トンボ池にて) カタバミの蜜(みつ)をすうヤマトシジミ(左下:校庭にて) ヤガ科、フタテンアツバ。大きさは2㎝くらいです。(右下:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月7日(水) 上小の住人です。見つけてね! ハクセキレイ。近すぎるのはイヤがっても、あまり人をこわがらないようです。(左:プールにて) ヤマトシジミ。太陽であたたかくなった石の上が気に入っているようでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月6日(火) 早くも花から実へ ユスラウメ、実をつけはじめていました。(左:トンボ池にて) ナナホシテントウ。赤くて、かたい羽(さや羽)の中に、とぶ時に使う羽(後ろ羽)をおりたたんでしまっています。(右:中庭、花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
 | |
2021年4月6日(火) 春探し写真クイズ2021 これは何の木の葉でしょう?③ 木々の新緑が目にあざやかな季節がやってきました。春を探して上石神井の町を探検してみましょう。今回はこれが何の木の葉かあててみてください。すぐわかるのもありますが、ちょいと難しいのもあります。まわりのギザギザ(きょし)のあるなしや、葉脈(ようみゃく=葉のすじのような部分)の入り方などもくらべるといいですよ。「カ」以外は、落葉樹(らくようじゅ)です。 この問題のヒント: ア・・・葉のつけねにある二つの小さなコブがみつせんです。 ♪ 今さきほこる・・ イ・・・国ちょうオオムラサキの幼虫が食べる葉。ギザギザが葉の半分にはありません。 ウ・・・歌姫がよく歌うあの曲の題名。今まさに花ざかりです。 エ・・・武蔵野の・・ オ・・・4月5日のGママさん出題のクイズが大ヒント! カ・・・新芽が赤いとは。色素が中を守っているそうな。冬でも葉を落とさないので、いけがきによく使われています。(出題者:スタッフのコタジー) この写真の葉の木の名前がわかった人は、事務局までメールで解答を。 (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。 (しめきり4月18日) |
 |  |
2021年4月5日(月) 草花のずかんを持って外に出よう! セキショウの花が咲いています。石菖根(セキショウコン)と言って、根が生薬(しょうやく=自然の植物などを使ったくすり)に使われています。(左:トンボ池にて) ナヨクサフジのようです。緑肥(リョクヒ=緑の草をそのまま土にすきこむ肥料)利用などの理由で海外から渡ってきた植物だそうです。フジの花に似て、みごたえがあります。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年4月5日(月) 春探し写真クイズ2021 ここはどこでしょう?② 春を探して上石神井の町を探検してみましょう。 第2問も一面のムラサキ色。23区内とは思えない「上石神井遺産」に認定したい美しい風景ですね。ムラサキハナナ・ショカツサイ・オオアラセイトウなどいろいろな呼び名があるようです。柿の若葉とのコントラストも美しい。(出題者:隊員のGママさん) この写真の場所を見つけた人は、事務局までメールで解答を。 (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。(しめきり4月18日) この問題のヒント:①学区域の西側です。②近くに「いこいの森」がありますよ。 |
 | |
2021年4月4日(日) 春探し写真クイズ2021 ここはどこでしょう?① 春を探して上石神井の町を探検してみましょう。 この写真の場所を見つけた人は、事務局までメールでお知らせ下さい。 (事務局アドレスはページの一番下にあります) ★正解者には探検隊オリジナルグッズを差し上げます。(しめきり4月18日) この問題のヒント:①学区域の南側です。②近くにバス停がありますよ。 (出題者:スタッフのくるしまママ) また、みなさんからも問題を募集しています。上石神井の春を見つけたら、ぜひ写真を送ってください。ホームページでクイズとして紹介します。子どもも大人もこぞってご参加下さい! ※上石神井小の学区域内で、場所があるていど特定できる写真をお願いします。 ※個人のお庭等はプライバシーへの配慮をお願いします。 |
 | |
2021年4月4日(日) スズメとカラス 神学院の道ぎわにいっしょに生えているところがありました。 スズメノエンドウ(右)とカラスノエンドウ(左) (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) |
 |  |
2021年4月2日(金) カゲロウとついていますが・・・ パッと目をひく虫がいました。いろいろ調べてみたのですが、もしかしたらヤマトクサカゲロウの越冬型なのかな?と思いました。ちなみに、からだは1.5㎝くらいだったような感じです。(トンボ池にて) ※クサカゲロウの仲間は名前にカゲロウと付きますが、プールでよく幼虫が見つかる「カゲロウ」とも、幼虫がアリジゴクを作る「ウスバカゲロウ」とも違う昆虫です。さてクサカゲロウは何を食べるでしょう? (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年4月1日(木) アゲハチョウもさなぎから出てきました 一日に100匹くらいのアブラムシを食べるナナホシテントウ。学校の植物が元気に育つのを手伝ってくれています。(左:校庭にて) ナミアゲハ。ヒラヒラと舞い上がってはヤツデの葉にもどり、春の日差しをあびていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月31日(水) ハネはないけど大きなハサミがあります 湿っぽいしげみにいました。身近に観察できるハサミムシは、翅(ハネ)がしだいに無くなった種類。日本には20種くらいのハサミムシがいて、翅のある種類などさまざまな特徴があるようです。(左:トンボ池にて) うえきばちの中からピョーンと飛びだしたアマガエル。冬眠から間もないからなのか、白っぽいです。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月30日(火) お久しぶり!動き出したよ~ 仕事道具を持ち上げると、ヤモリがチョロチョロっと出てきました。家のそばにすみ、人がいやがる小さな虫を食べてくれるので、昔の人は家を守ってくれると、ヤモリ(家守)と名付けたそうです。(左:中庭、主事倉庫前にて) しげった草の手入れをしていると、ナナホシテントウがいました。(右:中庭花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年3月29日(月) 生き物いっぱい春の上小ビオトープ 昨日から卒業記念制作のために集まってくれたOB、6年生隊員が小さな生き物達をヒョイヒョイとつかまえては、名前を教えてくれたおかげで、春のようすを見る事ができました。紹介からはもれてしまいましたが、他にも観察できた生き物がたくさん。それから花の後に小さな梅の実も見つけることができました。 アマガエル。久しぶりの再会に皆でよろこびましたが、よく見るとキケンな事もあったようですね。(右手の先に注目)でも水の中に入れるとスイスイと元気に泳いでいました。他にも合計で8匹もアマガエルの確認ができました。(左上:トンボ池にて) ギンヤンマのヤゴは1㎝位の小さなのもいれば、もうこのように終齢(しゅうれい=成虫あるいはサナギになる前の事)となっているヤゴもいました。(右上) シオカラトンボのヤゴ(左中) イトトンボのヤゴ(右中) アズマヒキガエルのおたまじゃくし(左下:すべてプールにて) ニホントカゲ。クヌギの下にいるのをマツセンが発見!すると隊員全員いちもくさんに集まり、かこっているネットの下から救出していました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年3月28日(日) アマガエル君、おはよう! 強い風と雨で、桜が早くも散り始めました。(上段:中庭にて) スギナのしげみで今年初めてアマガエルを発見。よく探したら同じ場所だけで8匹もいました。(下左:トンボ池にて) そのしげみになぜか鳥の卵が1個無傷のまま落ちていました。落としたのはだれ?(下右:トンボ池にて) | |
 |  |
2021年3月26日(金) 春休みは旅立ちの準備の時 明治時代に岩石を使った庭作りをするため、日本にやってきたヒメツルソバ。今では道ばたでも見かけるようになりました。(左:校庭にて) 春休みがはじまり、新学期に向けて準備期間ですね。ノボロギクも新天地へ行くところです。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月25日(木) 卒業式は満開の桜の下で 校庭の桜(ソメイヨシノ)も満開をむかえました。 (左:体育館裏にて) 和名はオオマツユキソウ。その他、スノーフレーク等いくつかの名前で親しまれているヒガンバナ科の植物です。(右:校庭でも観察できます、撮影は体育館裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月24日(水) 「やまぶき色」はこの花の色です ヤマブキが咲きました。ヤマブキ色を草木染めで出したい時はヤマブキではなく、玉ねぎの皮がオススメのようです。(左:校舎裏にて) ハナニラ(イフェイオン)は『春の星の花』と呼ばれたり、いくつかある花言葉のひとつには『星に願いを』とあったりするのですが、星の出る夜はとじています。太陽の光が大好きな植物です。(右:校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月23日(火) 満開は桜だけじゃないですよ~ アシブトハナアブの幼虫は水中で育ちます。シュノーケルのように、呼吸をするための筒を水面に出してすごすようです。(左:東門花だんにて、キク科ノースポールによく訪れています) 身近な薬草、ヘビイチゴの花が咲いていました。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月22日(月) かわいい花なのですが・・・ アケビの花が咲きました。まん中にあるシベ(花粉のやりとりをして、実をつける所)が丸まっているのが雄花(オバナ)、少し大きめに咲いてシベがひらいている方が雌花(メバナ)です。 (左:トンボ池、プール側より撮影) ナガミヒナゲシはかわいい花ですが、他の植物と一緒にいると、いずれはナガミヒナゲシだらけになってしまうほど、はんしょくりょくの強すぎる花です。元々日本にはなかった植物(外来種)なので、ツボミができる前にそっと抜いてあげるのが一番良い方法かもしれません。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月19日(金) 地上に咲いた星 昼休みに写真を撮っていると、児童がキレイだね〜っと、ハナカイドウの華やかさに見とれていました。バラ科の植物です。(左:図工室前の花だんにて) ハコベ。学名はステラリラ(学名=学問上の世界共通の名前)と言って「星」の意味があるそうです。小さなかわいい星です。(校舎裏にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月18日(木) 上石神井のツバメ・・・ ムラサキケマン。畑の様子を見に訪れたスタッフのつとむさんによると、種をパッとはじきとばす様子がおもしろいそうですよ。(左:校舎裏にて) セリバヒエンソウ。漢字で書くと『芹葉飛燕草』で、花が飛ぶツバメ(燕)に似てるからなのだそうです。じっと観察してると見えてくると思います。(右:トンボ池、カブクワハウス前にて) ★ツバメといえば、本日隊員のGママさんから「青梅街道でツバメを見ました」という報告がありました。この春最初の報告です。かつては上石神井の駅でも見られたツバメの巣、最近はめっきりへってしまいました。「ツバメの巣ここにあるよ」という情報がありましたら、ぜひお寄せください。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月17日(水) サクラ開花! 桜(ソメイヨシノ)が咲き始めました。(左:西側正門にて) 花屋さんで売られていたシンバラリア(ツタバウンランなど、他にも呼び名があります)ですが、いつの間にか道ばたでも、上小でも見つけられるようになりました。次はどこへ行こうかと、ワクワクしているように見えます。(右:中庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月16日(火) 草花の名前しらべもおもしろい 正式な和名はオオアラセイトウ。私達の生活に身近にあったので、ムラサキハナナ、ムラサキ大根などたくさんの別名が付けられてきたようです(左:東門、ドウダンツツジの並ぶ花だんから出てきました) ノボロギク。これからひらくのかな?って思わせる花がおもしろいです、小さな虫がおとずれていました。(右:東門花だん前、コンクリートのすきまにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月15日(月) …カエルのたまご成長中…… 丸いままの卵、白くなってしまった卵もありましたが、変化がみられる卵もありました。(左:プールにて) アシブトハナアブのようです、このストロー状の口で花蜜や花粉を食べるんですね。(右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年3月14日(日) 花粉がつくる虹 雨が上がり、気温が上がっています。強い風もふいて、どうやら空中には大量の花粉が飛んでいるようです。その花粉によって太陽のまわりに虹(にじ)のような輪が見えていました。 これを花粉光環(かふんこうかん)といいます。空中に舞った花粉の粒に光が当たった時、色によって光の散らばり方がちがうため虹色が見えるそうです。(これを光の回折=かいせつ=といいます) カメラや肉眼で直接太陽を見ると目をいためるので、下の写真のように建物などで太陽の光がうまくかくれるようにして見ると、虹色が見えます。写真に撮るには、手動で明るさ(露出)を調整するときれいに撮れると思います。観察にちょうせんしてみましょう。 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) | |
 |  |
 |  |
2021年3月12日(金) キュウリとバナナ キュウリグサ。かわいい花に野菜の名前?草をもむとキュウリの香りがするからなのです。(左:校舎裏の畑にて) バナナ虫(ツマグロオオヨコバイ)。三匹もいました。(右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月11日(木) 白い花はメス・黄色い花はオスのフキ ひょっこり出ていたフキノトウですが、そのあとグングンと太めのクキをのばして花を咲かせています。(左:トンボ池にて) バナナみたいな花、レンギョウが咲きました。(右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2021年3月10日(水) プールでも発見!カエルのたまご ヤゴネットを持ち上げてみると…産卵しに来てくれていました! タネのような卵の大きさはトンボ池と同じくらいです。成長が楽しみですね!(上:プールにて) 大きい!西洋ミツバチの女王バチに似ています。・・・ジンチョウゲの花蜜に夢中でした。(中左:校庭にて) ※その後、スタッフOBのNさんから「これはヒメハラナガツチバチのメスの越冬個体ではないか」と教えていただきました。オスは夏ごろ発生し、触覚は長く全体に細身。また、地中のコガネムシ類に寄生するそうです。似たハチに、体毛が黄褐色のキンケハラナガツチバチもいるそうです。 ツマグロヒョウモンの食草=スミレがいっせいに咲き始めました。(中右:東門花だんにて) 赤い実も待ち遠しい!ユスラウメ、開花しました!(下左:トンボ池にて) 成虫は蜜や花粉を食べ、幼虫はアブラムシを食べてくれる花アブの仲間フタホシヒラタアブ。(下右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月9日(火) こんなところにも春が・・・ アケビにツボミができていました。うしろにボンヤリ写っているのはカマキリの卵、楽しみがいっぱいですね。(左:トンボ池、プール側から撮影) こぼれ種から育ったサクラ草、花だんからずいぶんはなれた場所で咲きました。アリが運んでくれたのかもしれません。(右:古紙リサイクル倉庫の近くにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月8日(月) ひと雨ごとに春が進みます フッキソウ(またはキチジソウ)の花が咲きました。 (左:西側正門花だんにて) シデコブシ(またはヒメコブシ)と言われる種類のようでした。 リボンのような花びらです。(右:玉川沿いにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年3月7日(日) トンボ池でヒキガエルが産卵! 観察会などの活動がなかなか思うようにできない状況が続いていますが、そんな中でも毎日熱心にトンボ池で観察を続けてくれている子ども達がいます。トンボ池が大好きな1年生グループ、先日もスタッフのコモ外し作業をお手伝いしてくれましたが、今日はトンボ池にヒキガエルが来て産卵しているのを発見して、U君が知らせてくれました。聞けば「昨日から産卵していた!」とのこと。池の中にはすでにゼリー状の卵もかくにんできました。 昨年の産卵確認は2月24日でしたので、今年は10日ほどおそいことになります。なかなか来ないので心配していましたが、よかったです。 ヒキガエルはふだんは陸上でばらばらに生活し、産卵の時だけいっせいに池に集まります。1匹で数千個以上の卵を産むと言われています。 産卵シーズンはしばらく続くと思われます。みなさんでやさしく見守ってあげてくださいね。 (画像と情報提供:スタッフのいとうママ) | |
 |
 | |
2021年3月6日(土) いやーーなヤツ見っけ! 数日前から、目がかゆくなってきたので、スギの花粉をとらえてみました。ワセリンやポマードがなかったので、セロハンテープのねんちゃく面を上にして、板の上にはって表に6時間ほど出しておきました。倍りつは200倍ほどです。コンデジで接眼レンズをのぞくようにしてとりました。スケールがないので、1平方センチにどのくらいの数があるのかはわかりませんが、多い時だと、1日あたり数百個もつかまるようです。真ん中左にあるのはゴミです。 これからしばらくの間、花粉の飛ぶ量がピークをむかえるようで、花粉症の人にとってはつらいですね。お大事に。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |
 |  |
2021年3月5日(金) 今日は「啓蟄」(けいちつ) 冬眠していた虫などの生き物が春のおとずれを感じて出てくる頃。 タンポポも咲きはじめ、虫達をまっていますよ〜。(左:校庭にて) フワフワのコートをぬいで、ステキなすがたを見せてくれていました。(右:武蔵関公園にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月4日(木) ショカツサイも開花しました 三羽の仲間同士で訪れていたカワラヒワ。 落ちているサワラの実をついばむ姿も見られました。(左:中庭にて) ショカツサイ(紫花菜・オオアラセイトウ・花大根)が咲いていました。 チョウが食草として利用するそうです。(右:武蔵関公園にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月3日(水) ホトケノザも開花しました 昨日から強風でしたが、梅の花はまだいっぱい! 仲良くメジロが訪れていました。(左:東門花だんにて) 石のすきまから出てきたホトケノザ。 小さな花からほんのり甘いみつが楽しめます。(右:トンボ池、トカゲエリアにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月2日(火) この鳴き声を覚えてね お昼時に『キリッリィリィリィ』っと心地良い鳴き声をきかせてくれた2羽のカワラヒワ、仲良く飛びたってゆきました。(左:中庭西側、桜の木を訪れていました) 稲の種を水につける頃、田んぼにたくさん咲いている事からタネツケバナと言う名前がついたそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年3月1日(月) ヒメオドリコソウが開花しました つがいのメジロ、仲良く羽づくろいしながら過ごしていました。(トンボ池前のフジ棚にて) ヒメオドリコソウ。スミレと同じ、アリに種を運んでもらいながら生息場所を広げるそうです。(トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月26日(金) 春、めじろおし・・・・? 満開の梅の蜜をいただくメジロ。そう言えば、もりだくさんの時などに使う言葉『めじろおし』とは、メジロが仲間どおしでギュッと寄せ合いながら枝に並ぶ姿からきている言葉なのだそうです。(左:東門花だんにて) シジュウカラが『ツピーツピー』っとなわばり宣言をしていました。(右:玉川上水沿いにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月25日(木) オオイヌノフグリが開花しました きれいなコバルトブルーですね!オオイヌノフグリ。(左:トンボ池、カブクワハウスの脇にて) 最近は梅の蜜に夢中のメジロです。今日もあたりのようすをうかがいながら、せわしなく飛びまわっていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月24日(水) ツクシからのスギナ 田んぼゾーンのスギナ。ムーミンのニョロニョロみたいです。(左:トンボ池にて) ナガミヒナゲシの草とりをしていたら、ヒメグモが通りました。ずらした鉢の下にいたのかもしれません。(右:中庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年2月23日(火) ツクシ見っけ! 新青梅街道沿いでツクシ、見つけました。 ★この春一番のツクシの便りです。最近は上石神井でツクシの生える場所もだいぶ減ってきてしまいましたが、探せばあるのですね~。ほかにもこんなところで見つけたよ、という情報があったらぜひご連絡ください。 (画像と情報提供:隊員のGママさん) |
 |  |
2021年2月22日(月) 春の野草が咲きはじめています 植物の花粉を運んでくれるヒラタアブが、ナズナ(ペンペン草)におとずれていました。(左:校舎裏の畑にて) カタバミの小さな花が咲いていました、シジミチョウがおとずれるのが楽しみです。(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年2月21日(日) 春探しのお散歩に出かけました 厚労省上石神井庁舎脇をお散歩中に見つけました。 あたたかいせいかナナホシテントウがたくさんいて(左上)、チョウも飛んでました。(タテハチョウのなかま・右上)。脱皮したてのバナナ虫(=ツマグロオオヨコバイ・左下)も発見。カマキリの卵(右下)は植込みのツバキの高さ70センチくらいのところで見つけました。ふ化はまだもう少し先かな。 たぶんジョウビタキと思われる鳥も鳴いていたし、テントウムシはもう産卵をしているのもいましたよ。 (画像と情報提供:隊員のGママさん) | |
 |  |
2021年2月19日(金) フキノトウが開きはじめました 今日は晴天!「富士山がきれいに見えてるよ〜」との情報をいただいたので、昼時に上小ビュースポットへ、雪化粧の富士山がきれいに見えました。(左:中校舎屋上から撮影) つぼみだったフキノトウがひらきはじめました。開く直前ごろに、天ぷらやフキ味噌にして早春を味わいますが、このほろ苦さや、香りを楽しめるのは大人になってからかもしれません。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月18日(木) 今日は「雨水」(うすい=二十四節気の一つ) 「雪は雨に、氷は溶けて水になる」・・・という日ですが、今日は寒の戻りで、トンボ池いちめんに氷がはっていました。が、校庭を歩けば、やっぱり春! スイセン、ウメ、ジンチョウゲが香りを届けてくれていました。(左:放送室前の花だんにて) 土砂のたまる溝の中で、この殻(から)をいくつも見つけることがあります。キセルガイの殻なのかなと思います。キセルガイはカタツムリやナメクジの仲間、木の幹(みき)や落ち葉の下などで過ごしているようです。見つけたこと、ありますか?(右:校庭の溝にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年2月17日(水) オケラ 大好評につき再登場 水陸両用なんだよねっ!って理科室にいた児童が、しげしげと観察していました。 昨日のオケラと同じ個体かもしれませんが、ひょこっと出てきましたので、今日はアップ写真で登場です!(上:トンボ池近くの溝にて) ★さすが、上小の子ども達はよく知っていますね。そうです。オケラは水の中も上手に泳げるのです。今日は発見したものを理科室で子ども達に広く見てもらえたとのこと。生きたオケラが観察できたなんて子ども達もラッキーでしたね。 うれしい再会です!昨年ヒキガエルは、アオダイショウのお腹へと次々入ってしまったようでしたが、作業中にゴロンと出てきたのは少し小柄、丸まっている姿は12センチ位の大きさです。 『まだ絶対に起きませんから!』っとの主張がありありと見てとれたので、ふんわり土砂をもどしました。(下:トンボ池近くの溝にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |
 |  |
2021年2月16日(火) オケラ発見!! 童謡『手のひらを太陽に』に出てくるオケラ!大きさは2センチくらい、とびきり元気!すぐさま土の中へともぐって行きました。(左:放送室前にて、溝の砂土すくい作業中に) ★すごい!上小の敷地内でオケラが発見されたのは、探検隊発足以来初めてのことです。「虫ケラ」などという言葉からもわかるように、昔の人には田畑などを耕すといくらでもいる普通の生き物だったようですが、今は東京ではめったに見られない貴重な生き物。いても土の中だし、動きは素早いし、そう簡単につかまえられるものではないようです。すごいラッキーでしたね。前脚がモグラの手そっくりのとってもかわいいヤツです。会いたかったな~。いることがわかったので、今度みんなで探しましょう! 昨年はチャドクガの被害を受けて、枝をたくさん切る事になってしまったツバキですが、見上げると残った枝にツボミをつけながら咲いています。(右:西側正門近くにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月15日(月) ジンチョウゲが開きはじめました 今日はまとまった雨が降りました。そんな中でも開きはじめたジンチョウゲからは、春のおとずれを感じる、心おどる香りがしてきました。(左:職員室前花だんにて) 夕方は魔法のように、雨がやみました。空には大きな虹がかかった雨上がりの校庭に、一番のりしたのはムクドリでした。(右:西門から撮影)※←「見つけたよ!」に虹情報 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年2月13日(土) ふきのとう トンボ池のまわりに今年も春を知らせるフキノトウが出てきました。 この日は午後には気温が14℃まで上がり、まさしく春のような陽気の中、スタッフによる校庭の樹木管理(農薬を使わない昔ながらの方法によるマツカレハの毛虫退治)が行われました。→活動日誌のページ |
 |  |
2021年2月12日(金) メジロの全力アピール メジロは「梅の蜜はとても美味しいですっ!」って全力アピールしているのだと、、思います。(左:トンボ池から、お隣にある梅の木を撮らせてもらいました。) じっと川を見つめるカワセミ、魚をねらって真剣なんだろうけど、、どうしても、かわいい。(右:石神井川にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月10日(水) しもばしらのサクサクを楽しむ子ども達 コロコロとここち良く鳴くカワラヒワもスズメ達と一緒に訪れていたようです。今朝、トンボ池をのぞくと、スズメ達は近くの高木へ、カワラヒワは校舎の屋上へと勢いよ飛び立ちました。朝日が高木に届きはじめた所でした。(左:朝のトンボ池にて) まだ氷がはる池では、中休みになると、氷で遊ぶ子ども達と、はしゃぎすぎを注意する先生の声でにぎやかでした。そんな中、シモバシラで盛り上がった土をふみながら、サクサクの感覚を楽しむ子も。泥だらけのクツはまだしばらく続くようです。(右:朝のトンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月9日(火) トンボ池の野鳥メンバー いつもの野鳥メンバーの中から、少し違う声がする!そ〜っとのぞいてみると、カワラヒワもそ〜っとこちらを見ていました。(左:トンボ池にて) いつもの野鳥メンバーのヒヨドリ、つぶらな目がかわいいです。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年2月8日(月) 草のバッタ わっ!わっ!わっ! バッタがいるっ!草のバッタ、リアル〜っ!! 子ども達もスゲーっ!(男の子)とか、きも〜っ!(女の子)など、さまざまに楽しく反応していたようです。 手の込んだ贈り物、どうもありがとうございます。 (左:職員玄関受付にて・写真には入っていませんが4匹もいるんですよ〜!) 梅の木におとずれたシジュウカラ。ツピーツピーっと鳴いていると、もう一羽やってきました。蜜を吸うにはまだ小さかったかな?仲良く飛んでゆきました。(右:東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年2月5日(金) 毎朝見上げてしまうモクレン モクレン。フサフサの冬芽の時期から華(はな)やかなふん囲気がただよっています。(左上:上中南側校庭、道路から撮影) カマキリの卵。やっぱり2m以上の高さで発見です。卵の時期は寄生虫と鳥が天敵だそうですが、鳥がとまれそうにない細い枝にあるので、す、が。葉がなくなる事までは気にしてなかったんで、す、ね。(右上:東門花だん、落葉したモミジにあります) カワラヒワです。昨日、植木屋さんが枝切り作業をしてくれていたので、何か見つけたのかもしれません、スズメもきていました。(左下:中庭西門の花だんにて) とっても良い香りがするよ!っと聞いていたビワの花を見つけました。小さな花がかわいいです。(右下:玉川上水沿いにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年2月4日(木) 春 一 番 春一番がやってきましたね!立春から春分(今年は3月20日)の間に、その年に初めて吹く、南よりの強い風を『春一番』と呼びますが、今年は早かったですね! スイセンも満開、見ごろをむかえています。(左上:東門花だんにて) おとといあたりから、外では小さな虫が集団で飛びかう姿が見られるようになりました。屋内でパトロールしてくれるアダンソンハエトリも、そろそろいそがしくなるぞ〜っと久しぶりの再会です。ただ、明日の朝に悲鳴があがると困るので、外へ出しました。(右上:一年生の教室前、廊下にて) ピシッとまっすぐ、りりしい表情のヒヨドリ。空にいる仲間でしょうか、甲高い鳴き声のやり取りの後、飛んでゆきました。春の知らせを聞きつけたのかもしれません。(左下:トンボ池にて) 『この種、どうやってとるのぉ〜?』『ここから、とるんだよ〜』スズメ達はいつも5羽以上の仲間で、にぎやかに訪れます。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年2月3日(水) 【クイズ】 何羽いるでしょう? 石神井川の橋の上から撮った写真です。大きな葉っぱのようなものはコサギです。みんなで仲良く眠っています。さて、何羽いるでしょう? (画像と情報:隊員のGママさん) |
 |  |
2021年2月3日(水) 立 春 立春の朝は気持ち良く晴れましたね、月もきれいに見えました。あっ!そういえば、卵は立ちましたか?(左:職員玄関前から7時30分頃に撮影) どぶさらいの作業中、ふたをあけるとヒメアカタテハがいました!暖かい場所では、成虫のまま越冬するようですが、、あおむけになって寝ているような感じの動きをしていました。 とりあえずその場所はそのままそっとフタをとじました。(右:校庭のよく日があたる場所の溝にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年2月3日(水)立春・・・(はまだ明日ですが) 立春には、卵が立つって本当?! 今から70年ほど前に、立春には卵が立つらしい、といううわさが世間に広がり、実際に上海やアメリカで実験に成功した!というニュースが話題になったそうです。 やってみました。立ちました。心を「全集中」すると、30秒くらいで立たせることもできます。ただ集中が切れると、一度立った卵でもなかなか立ってくれません。あれれ??今日は、実は立春の前の日2月2日(火)ですよ。おかしいなあ・・・・・。立春の前の日なのに。 とりあえず、やってみてください。塩もいりません。ごつんとわるのもなしですよ。写真(理科室の机の上にて) (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
 |  |
2021年2月2日(火) 今日は節分 今日は節分。鬼はヒイラギの葉のトゲが苦手だとか、でも、このチクチクが痛いと思う鬼は、本当はやさしいのかも。。しれませんよ。(左上:東門花だんにて) どんぶらこ〜 どんぶらこ〜 っと流れついていたのは、カマキリのふ化後の卵でした。風や雨によって、とれたようですよ。(右上:トンボ池にて) 考えるヒヨドリさん。もうミカン食べ終えちゃたんですね。(左下:トンボ池にて) ミカンをよけた後は、スズメのにぎやかな食事会となっていました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年2月1日(月) 梅が開きはじめました! ウメ。さいしょの一輪がひらきはじめました。(左上:東門花だんにて) ナズナ。少しずつ野草もでてきています。(右上:校舎裏の畑にて) メジロ、ヒヨドリはミカンが好きすぎてなのか、けいかいしつつも、長居をしてくれます。 (下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月29日(金) 冬のセミ 雨水が流れる場所は、気がつくと砂や土、葉っぱ等がたまります。そこには必ずミミズがいます。ミミズ以外にも、時には。。(どちらも中庭、自転車置き場あたりの溝にて) (左)セミの幼虫のようです。たまった土砂に1センチ位の穴があり、そっと土砂をすくってゆくと、15㎝位の場所でモゾモゾと動いていました。目は小さく光っているように見えました。砂をすくう作業は中断して、できるだけふんわりと砂をもどしました。 (右)スズメガのさなぎ。この土砂をすくう作業をしていると必ずいます!撮影後は溝のへ。春になったら出てくるのかな? (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2021年1月28日(木) 授業中、トンボ池ではメジロが・・・ ① ダぁル〜マぁ〜さぁんがァ〜(モグモグ)。。 ② ころんだっっ!! …このように、ステキな時間を過ごしています。(上:トンボ池にて) 雪だぁ〜っ!!歓声がたくさん聞こえてきました。(下左:中庭・渡り廊下から撮影) みぞれまじりの帰宅中、前から歩いてきたハクセキレイ。 しばらくついていくと『とまれ』が読めた?(下:武蔵関駅北口・郵便局の通りにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月27日(水) カマキリが卵を産む高さのなぞ ヒヨドリは日本での生息数が一番多いことから、日本の鳥とされているそうです。そして、今は原則としてできませんが、平安時代には貴族の間で飼う事が流行り(はやり)だった記録もあるそうですよ。(左:トンボ池にて) ふ化後のカマキリの卵がありました。あった場所は2m位の高さで、今年6月頃に孵化(ふか)予定のプールから観察できる卵と同じ位の高さです。カマキリはその年にふる雪を予測して卵を産むとも言われていますが、もしかしたら人の手が届かない場所を選んでるのでは?なんてことを思いました。(右:体育館西側、カリンの枝を切る作業中での事) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月26日(火) 梅一輪 一輪ほどの・・・ 野鳥に大人気だった豆柿ですが、今はながめの良い、きゅうけい場所で人気です。ヒヨドリがおとずれていました。(左:東門花だんにて) 上小の梅はまだ小さなつぼみですが、早咲きの梅は少しずつ咲いています。(右:玉川上水沿いにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月25日(月) 田んぼゾーンのオレンジ色の宝石 冬になるとおとずれる、ジョウビタキがきていました。田んぼエリアで気持ち良さそうに水浴びをして、小枝でちょっとひとやすみ(左:トンボ池にて) カワセミにもお気に入りの小枝があるようです。(右:石神井川にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年1月21日(木) 「あっ、もう ずれている!」 Gママさんの「ダイヤモンド富士」(←「見つけたよ!」コーナー参照)からほぼ1週間後、1月21日(木)の日没です。1週間でこんなに北側にずれるんですね。富士の火口と太陽の直径を比べると、ちょうど見かけ同じくらいであることがわかります。 太陽の連続写真は、NDフィルタで減光し、10秒ごとに1つずつ太陽を連写し、それを200枚ほどつなぎました。夕焼けの背景は、日没後に撮影し、それを合成しています。本当は、火口付近に沈む太陽を撮りたかったのですが・・・。あと10か月ほど待ってまた挑戦したいと思います。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2021年1月22日(金) 石神井川の青い宝石 いつも辺りの様子をうかがいながら、用心深くおとずれるシジュウカラ。エサ場すべてをまわり、ここにしようかなぁ〜と決めたようです。(左:トンボ池にて) 冬景色をながめながらの帰宅中、パッと目にとびこんできたのは、青い宝石とも言われるカワセミ。川の水で羽をととのえ、くつろいでいる様子でした。(右:石神井川にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月21日(木) じっと春を待っています 待ち遠しい梅の開花は、もう少しのようです。 花をめでた後は『梅染め』をしてみたいですね。(左:東門花だんにて) 古い切り株を割って中の様子を見てみると、ペタンとはりついて冬眠しているワラジムシが1匹いました。しばらくすると、ちょっとあわてた様子で、落ち葉の中へもぐってゆきました。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月20日(水) 大寒の朝 『大寒』(だいかん=1年を24に分けた二十四節気の最後の節気)の今朝は、川の氷が白くなっていました。 ゆっくり凍ると透明な氷が作られ、白い氷は短時間で凍ると空気のあわが残ってしまうから。ってことは、昨日つめたい風がふきあれていたから白くなったのかな?(左:石神井川にて) カイヅカイブキの樹液(じゅえき)、氷のツブのようにキラキラ。さわると、お菓子のグミのようにプニプニとしていました。 甘くはないようですが、ヒノキ科の植物から生まれた樹木なので、とかすとヒノキの香りを感じられるかも!(右:トンボ池とプールの間) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月19日(火) ビロードって知ってるかい? 氷が気になるのは子ども達だけではないようです。雨が降らないからなのか、水量がへった川辺の氷をセキレイがコンコンコンッとつつく様子が見られました。(左:石神井川にて) さわるとフサフサ、気持ちの良いかんしょくが楽しめるビロードモウズイカのようです。 いろんな国を旅しては根づいているそうで、日本へは明治時代あたりに来たそうです。 薬草や染色などに使われているようですが、黄色い花をつける夏頃には1〜2mくらいになります。(右:校舎裏の西側すみっこにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月18日(月) 桜はすでに開花準備中 週末の強風のせいでしょうか、冬芽(トウガ)のついた桜の小枝をひろいました。 夏頃にツボミを作り終え、秋頃にツボミが冬の寒さを乗りこえられるよう、コート着こむそうです。(左:校庭にて) リュウノヒゲ(ジャノヒゲ)のツヤのある青い実。(右:校舎うらにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月15日(金) ロウ細工のようなロウバイの花 香りにさそわれると、ロウバイが咲いていました。小さな花ですが、つややかな花びらが冬空にはえます。(左:玉川上水沿いにて) んっ!? 何か動いてる!そ〜っと葉っぱの中をのぞいてみると・・・ここにも『いますぅ〜』っとクビキリギスでした。(右:トンボ池、ミカンの木の下にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月14日(木) いいかおりだよ~本物をかいで確かめてみて! 水仙(スイセン)が咲き始めました。しばらくの間、かおりを楽しみながら過ごせますね。(左:東門花だんにて) つみ上げていたジュズダマのかれ草を少しずつ処分していたら、クビキリギスが『います〜』っと出てきました。なので残りのかれ草は春までそのままにします。(右:校舎裏の畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月13日(水) 石神井川の川霧 朝は昨日の雨もあり、氷点下の冷え込みでした。川霧(かわぎり)とも言われる現象が見られました。(左:石神井川にて) 昨日よりも + 6度もあたたかい陽気でした。ナミテントウがツツジの葉の上で日向ぼっこをしていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月12日(火) 冬色のトンボ池にて シジュウカラがおとずれていました。ひまわりの種の入ったバードフィーダーに行きたいようすで、一緒におとずれた仲間と『ツピ、ツピ』っとかわいい鳴き声を聞かせてくれていました。(左:トンボ池にて) ヤブソテツは常緑のシダの仲間(常緑とは、一年中、緑の葉が見られる植物の事)。お花と一緒に生けて、楽しむこともあります。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年1月10日(日) 氷の花「シモバシラ」が咲きました シモバシラはシソ科の多年草。冬には地上のくきは枯れますが、地面の下の根は生きていて水分を吸い上げ続けているのだとか。今朝のように寒い日には吸い上げた水分が地上部のくきからしみ出して冷たい空気にふれて、氷になります。これを「シモバシラの花」とよぶことがあります。水が氷になるのは0℃以下ですから、この花が咲いたということは、気温が0℃より下がったということですね。 東京では高尾山などがのシモバシラが有名で、この季節ニュースによく出ますが、元々はどこにでも自生していた日本の在来種ですから観察用にトンボ池にもあったらいいですね。 ※ちなみにシモバシラは夏に白い小さな花が集まった本物の花を咲かせます。これもきれいです。 (画像と情報:スタッフのまつせん) |
 | |
2021年1月10日(日) 一瞬でこおる水「過冷却」(かれいきゃく)の実験をしよう 水がこおるのには、ふつうは、それなりの時間がかかりますよね。 ところが、ちょっとかき回したり、ふったりしただけで「一瞬でこおる」水が作れます。 まずは、動画(→クリック)を見てみましょう。 翌朝の気温が氷点下(0℃以下)まで下がる予想が出た日がこの実験のチャンスです。 用意するのは水道水を入れたペットボトルだけ。 これを前の日のうちに、なるべく寒くなりそうな場所(家の外の地面の上)に置いておきます。 朝になって、まわりの地面などには霜(しも)や氷ができているのに、ペットボトルの水が凍(こお)っていなかったら、たぶん成功です。 ペットボトルをそっと持ち上げて、強くふってみましょう。(あるいは、そっとフタを外して中に小さな氷のつぶを落とし入れてもおもしろいです。) 今の季節限定の楽しい実験です。 ぜひ、ちょうせんしてみてください。 (ふだんだったらイヤ~な「朝の寒さ」が待ち遠しくなっちゃうことまちがいなし!) そして、なぜ、こんなことがおきるのか・・・おうちの人や先生といっしょに調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
 |  |
2021年1月9日(土) トンボ池に氷がはりました 今朝、トンボ池を見てきました。 島周辺(上2枚)とハスのコンテナ(下)にうす氷が張っていました。 メダカと小さな魚、下で冬眠(?)ですね。(トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのKママさん) | |
 | |
 |  |
2021年1月8日(金) 強風の次の朝 風が吹いた後は、楽しい拾い物がたくさんありますね。今朝は昨日の強風で、松ぼっくりやモミジバフウの実がたくさん落ちていました。(左:武蔵関公園にて) トンボ池に氷がはって、一年生が大はしゃぎでした。ガマやススキの種が氷の中に入りました。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2021年1月7日(木) 東門で待ってます スイセンの花芽が出てきました。(左:東門、花だんにて) 身近な花を観察すると、仲間をふやすためのオシベとメシベが見られます。 テングのうちわ=ヤツデの花の場合は、先にオバナが花びらと一緒に出て(この時の花は昨年11月9日の写真を見てね)その後、小さかった5本のメシベがのびてあらわれるのです。白いところから蜜(みつ)が出ているようで、今日はハナバエがおとずれていました。(右:東門、花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2021年1月6日(水) 一番早く太陽がしずむのはどこ? 初日の出が平地で一番早く見られる千葉県銚子(ちょうし)で見た 『初日の入り』の写真です。銚子の屛風ヶ浦(びょうぶがうら)の駐車場から撮影しました。元日の16時30分すぎでした。人がたくさん集まってきて、さかんにスマホやデジカメを向けていました。日の入りも日の出と同じように人気でした。 そこでちょっとしたぎもんがうかびました。 「初日の出が一番早く見られるところでは、初日の入りも一番早いのだろうか??」 日の出は、冬は南東から光がさしこんできますから、日本列島の一番南東に位置する千葉県が先というのがわかります。日の入りを考えると、太陽は南西にしずみますから、その反対側から夜の影がやって来ることになります。 さあ、ここまで書けば、答えはわかりますね。日本で一番はやく太陽がしずむのは〇〇〇ですよ。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 | |
2021年1月4日(月) 冬こそバード・ウォッチング! かわいい鳥たちですね。この季節、東京でもちょっと探せば出会うことのできる自然の鳥=野鳥の写真を集めてみました。 冬は北国から渡ってくる野鳥や、エサを求めて比較的ヒトに近い所までやって来る野鳥も増えます。葉が落ちる木が多いので鳥の姿を見つけやすいということもあります。 わざわざ遠くまで行く必要もありません。近くの公園やちょっとした木立ち、水辺など待っていれば、鳥たちの方から必ず姿を見せてくれます。 最初から特別な知識や道具はいりません。まずは、鳥の声や姿を意識して探すところから。「あれ、スズメより大きい鳥だな」とか「きれいな色だな」「ちょっと面白い動きをしているぞ」・・・そんなことに気が付いたら少しずつ図鑑などで調べていくと、すぐに身近な10種類くらいの野鳥がわかるようになります。そうなると楽しいですよ。 冬こそ、バードウォッチング! (画像提供:スタッフのつとむさん) |
 | |
2021年1月1日(金) 明けましておめでとうございます 2020年は自然と人間の関係についてもいろいろと考えさせられた年でした。 そんな中で、みなさんと(たとえ離れた場所からでも)一緒に同じ空を見上げたり、身近な自然の情報交換し合う楽しさに、ずいぶんと救われた気もしました。 まだしばらくは遠出はできませんが、子どもも大人も、すぐそこにある身近なしぜんを楽しみながらこの状況を乗り越えていきたいものです。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 (画像提供:隊員のGさん・元旦の上石神井の日の出) |
 |  |
2022年2月12日(土) レストラン営業中~! おとといは雨や雪で見かけなかったスズメやメジロ(左)でしたが、今日はいつも通りの大にぎわいでした。 「よいしょ、このへんかな♪」・・・メジロのファン、S先生がミカンを補給して下さっているすがたをキャッチ! (2枚共に:野鳥のレストラン・トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |
見つけたよ! ★身近な発見や情報をメールで事務局までお知らせ下さい。  9月21日(土) おしゃれなサギ君 石神井川の下流、練馬高野台駅付近で、撮った写真です。 サギの仲間が橋の下で毛づくろいをしているようでした。 どうして、そんなに毛が気になるんだろう? (画像と情報:6年生隊員のHくんより) ★川をのぞきこむといろいろ発見がありますね。石神井川によくいるコサギのようです。エサを取るだけでなくいろいろな仕草をするところを観察するのも楽しいですね。  9月21日(土) どこから入ってきたの? 起きたときに母の悲鳴が聞こえて、見てみたら、寝室のカーテンにバッタがいました。家の中にどうしてこんなに生き物が入ってくるんだろう。 (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★生き物は、新たなすみかを探して常に旅をしているのだといいいますが、このバッタはどうやらまちがって人間のすみかに入ってきてしまったようですね。ここにはおいしいエサはありませんよ!  7月31日(水) 増水時の石神井川 HP(右)を見て思い出しました。7月31日19:00東京に記録的短時間大雨情報が出た日の石神井川です。 武蔵関へ行ったら雨で帰れなくなり、警報も鳴りました。雨がやんでも川はここまで増水していました。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★たまたま通りかかったので記録として残しておいた写真とのこと。右の「上石神井のしぜん最新情報」の8月19日の一番下の写真と同じ場所から撮影したと思われますが、遊歩道部分の手すりがほぼ完全に水没しており、この時よりさらに増水した状態であったことがわかる貴重な記録写真です。  7月28日(日) どこに行きたいの?カマキリ君 ベランダに干した洗濯物を取り入れようとしたら、壁に子どものカマキリがいました。カマキリを家の中に入れないよう、別の窓から家に入りました。カマキリは、涼しい家の中に入りたかったのかな? (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★暑い日が続きますね。カマキリだってこんなに暑いと涼しい家の中に入りたくなるのかな?それにしても思いがけなくベランダで生き物観察ができちゃいましたね!  7月23日(月) クマゼミ クマゼミ(クリック拡大)が鳴き始めました。もともとは南方の暖かい地域のセミですが、最近では関東地方でも数をふやしているといわれます。おもに、日の出からお昼前くらいの午前中に盛んに鳴きます。 (画像と情報:しぜん探検隊) 7月19日(金) 人工衛星(えいせい)の木!? 町なかであまり見たことのない花を見つけました。調べてみると、タニワタリノキとありました。どれが花びらで、どれがおしべなんだか?「じんこうえいせいの木」ともよばれるみたいです。 コロナウイルスの木でもよさそうですが・・・。南の国では大きな木になるようです。 (画像と情報:しぜん探検隊)  7月6日(土) シーズン到来! 昨日初めて善福寺公園に虫取りに行ったらもうカブトムシやクワガタがいました。予想していたよりも多くカブトムシやクワガタがいました。(クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員のNくん) ★カブトムシ観察のシーズン到来ですね。身近なところにも意外にいますよ。みなさんもぜひ探しに行ってみましょう! 6月22日(土) 孵化の瞬間! トンボ池バタフライゾーンのウマノスズクサに産み付けられたジャコウアゲの卵。(→右ページ参照)観察していたら、ちょうど卵から1匹目の幼虫が生まれる孵化(ふか)の瞬間(しゅんかん)を見ることができました!(クリック→拡大) (画像と情報:5年生隊員のSくん) ★運がいいですね~!飼育していても孵化の瞬間はなかなか見ることができず、まして野外で孵化の瞬間をカメラで撮影するのはとても難しいことです。しかもそれがただのアゲハチョウではなく、珍しいジャコウアゲハの孵化の瞬間とは!!ウマノスズクサの葉の形や生えている場所(学校)までもが1枚でよくわかる素晴らしい写真です。 6月1日(土) タマムシの羽を発見! 6月はじめのしぜん探検隊の集まりの日、近くの自然を観察していたら、地面に、タマムシの羽が片方落ちてしました。自分が思うに、これは上石神井小学校にもタマムシが生息しているひとつの証拠となるのでしょうか。いつかは、上石神井小学校にタマムシが現れるときが来るかもしれません。(クリック→拡大) (画像と情報:6年生隊員のHくん) ★鋭い考察ですね。確かに羽が落ちているということは、その近くに実際にタマムシが生息している何よりの証拠と考えられます。アリの巣穴の外で見つけたということでしたから、アリが運んできたものの、羽は大きすぎるからか穴の中まで運び込べなかったということでしょうかね。いろいろ想像もふくらみます。タマムシの食草(食べる植物)や成虫の発生時期などを調べて観察を続けることで、本当に「上小のタマムシ」に出会える日も遠くないかもしれませんよ。  6月13日(木) 街中のキノコ探し 街で見つけたキノコ(学区外だけど千川通り沿いです)ひとつめ(上)は街路樹の桜の木に生えていたベッコウタケ。これが生えると残念ながら枯れて倒れてしまうので伐採されることが多いそうです。 ふたつめ(下)はシュロの切り株に生えているキクラゲ。ちょっとおしゃれ。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★街でもできるキノコ探し。ちょっとおもしろそうですね。キノコというと秋のイメージですが、雨の多くなるこの季節。案外見つけることができたりしますね。みなさんもおもしろいキノコを見つけたら教えてください。  5月24日(金) 水泳の授業開始! 上小の水泳の授業はまだですが、日差しの強さ、暖かさにつられてか、気持ちよさそうに泳ぐアオダイショウを見かけました。場所は、東伏見近くの石神井川です。(クリック→動画) (画像と情報:しぜん探検隊)  5月23日(木) ゴイサギの狩り 石神井公園でゴイサギの幼鳥がエサのザリガニかカニ?をとったところです。 氷川神社の前でジャコウアゲハらしき蝶も見ましたが、上小にはまだきませんか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★あちこちでいろいろな生き物のヒナに出会える季節ですね。巣立っても自分でエサをとって生きていける一人前の大人になるまで修行が続きます。 ジャコウアゲハは、バタフライゾーンに食草のウマノスズクサが植えてあるので次回の観察会で探してみましょう! 5月22日(水) カルガモのヒナだよ 駅にほど近いビルの植え込みの中でピヨピヨとかわいい声がするので見てみると、カルガモのヒナ3匹がうろうろしているのを見つけました。親鳥のすがたは見えませんでした。まわりに水辺はないので、石神井川に移動するときにはぐれてしまったのでしょうか。 (画像と情報:しぜん探検隊)  5月20日(月) 森の音楽家見つけた! 近所の公園で、キツツキがケヤキの幹(みき)を口ばしでたたいている音が聞こえてきました。この公園では初めて聞く音です。時々見かけるアオゲラだと思われます。肉眼では見えましたが、ざんねんながらさつえいはできませんでした。 (画像と情報:しぜん探検隊)  4月26日(金) タンポポのビン詰め タンポポの綿毛がふくらむ季節です。開く前の綿毛を取って、上手にペットボトルやビンに入れて乾燥させると、中で綿毛が開いて素敵なタンポポのビン詰めが出来上がり! (画像と情報:隊員のGママさん)  4月16日(火) 緑色の桜ミッケ! 花びらが緑色の珍しい桜「御衣黄」(ぎょいこう)を見つけました。公園とかで見ることはありますが、今回は意外にも学区内で見つけましたよ。さて、ここはどこでしょう。ヒント:駅のすぐ北側。線路のそばですよ! (画像と情報:隊員のGママさん)  1月8日(月) キイロスズメバチの巣発見! 雑木林の中で発見。たぶんキイロスズメバチの巣だと思われます。この時期は中は空き家のはず。次回観察会に持って行きますね~ (画像と情報:隊員のおおさわさん) ★2月の観察会でさっそく「解体ショー」やりましょう! 12月4日(火) アンテナをつらぬくISS 12月4日に、ISS(国際宇宙ステーション)が夜空をつうかするようすがとてもよく見えました。すごく明るかったのが、ゆっくりゆっくり暗くなっていく様子がなんともふしぎでしたね。これからよく見えるのは 6日(水)17:51ごろ 南西の高い空 7日(木)17:02ごろ 真上(天頂) です。くわしくは・・・・ をさんこうにしてください。  10月29日(日) ナナフシの脱皮殻発見! ぐんま昆虫の森の温室で、たくさんいたナナフシの中で初めて抜け殻を見つけました。 (画像と情報:OB隊員のN君) ★夏にやった「夜の森観察会」ではナナフシを発見したN君。今度はその脱皮殻かぁ。よく見つけましたね!!  9月19日(火) 狩りをするスズメバチ 石神井公園(三宝寺池)でセミを捕まえたスズメバチを見かけました。しつこく撮影していたら、獲物をしっかり抱え込んで運び去っていきました。(クリック→動画)  9月12日(火) どんぐりミッケ! 大きなどんぐりが落ち始めましたよ。どんぐり拾いなら今がチャンスです! (画像と情報:隊員のGママさん) 9月7日(木) 空を見上げなはれ! 18:07の上石神井から西の空です。 ご多忙なみなさんもたまには空を見上げなはれ! (画像と情報:OB隊員Nさん) ★みごとな夕焼けですね。空気中の水蒸気やチリが多いと赤色以外の光は散乱してしまい、このようにより赤く鮮やかな夕焼けになるんだそうです。この時期、夕暮れの西の空から目が離せませんね~  8月14日(月) 石神井公園でタウナギ捕獲! かねてより、タウナギを飼育してみたいと思っていて、14日の夜に石神井公園へガサガサをしに出かけました。 水路を見回ったところ、大きなタウナギがゆっくりと泳いでいるのを見つけました。最初は素手でつかもうとしましたが、思った以上にぬめりが強くて素手で捕まえるのは無理だと考え、網ですくうことにしました。何度か取り逃しましたが、何とか捕まえることができ、家で飼育することにしました。体長は70cmほどでした。 (画像と情報:卒業生の通りすがりのシャムネコさん)  8月13日(日) 流星見ながら羽化したよ! ペルセウス座流星群。極大となる今晩は微妙ですが昨晩は見ることができました。よかったです。写真は流星を見ながら羽化したアブラゼミです。 (画像と情報:OB隊員さん) ★昨晩は雲の間に結構星が見えましたからね。今晩はどうかなぁ・・・  8月9日(水) 8月9日(水)積乱雲の発達と移動 昨日のOB隊員さんからの情報に引き続きまた雲の話題を… 夏といえば積乱雲(入道雲)。雷はイヤですが(実は大好き。ワクワクします)、じっと見ていると積乱雲は実にダイナミックな動きをしています。時間を短縮して撮影するとその動きがよくわかります。→動画 (画像と情報:スタッフのつとむ)   8月8日(火) 空から目が離せません! 台風が近づいてきているようです。長いこと雲一つない青空続きでしたが、ここへ来て雲の変化、気象の変化がおもしろいです。上は太陽の両側に明るく虹色に光る点(「幻日」(げんじつ)が見えています!その下は富士山と幻日です。下の写真は雲の一部が虹色に輝いて見える「彩雲」です。 (画像と情報:OB隊員さん) ★雲の変化が面白いですね!朝夕の急な雨の後には虹が出ることもあります。みなさんも空を見上げてみましょう。   8月7日(月) ついに会えた!念願の・・・ ついに念願の水棲昆虫に会えました。ゲンゴロウです!(→画像拡大) (画像と情報:OB隊員中1のS君) ★S君はゲンゴロウに会いたくて計画を立ててはお父さんと日本各地のため池などを回り、ようやく4年ごしで出会うことができたのだそうです。探して回る中でアメリカザリガニなどの外来種が入り込んでしまって生態系がくずれてしまった地域が多いことにも気づいたと話してくれました。  8月6日(日) ミンミンゼミが羽化しました! 昨日のセミの羽化観察会で持ち帰った幼虫が無事羽化しました。ミンミンゼミでした! (画像と情報:4年生隊員のS君) 8月5日(土) ミノムシくんを見つけたよ 朝おきて家のドアーをあけると、なにやらぶらぶらしたものが目に入りました。ミノムシでした。朝のごあいさつをしにきたのかな?朝から暑いのに、あんなのをからだにまとってだいじょうぶ? (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月31日(月) さてこのトンボは・・・? 静岡県伊東市にて。宿泊先のプールで泳いでいたら、黄色いトンボの大群が飛んでいて、そのうちの一匹が駐車場内で休憩している所を発見しました。シオヤトンボ?? (画像と情報:4年生隊員のS君) ★上石神井ではあまり見ないトンボ?ですね。あれれ・・・よく見るとチョウみたいに長い触覚(しょっかく)がありませんか?(→画像拡大) もしかしてトンボによく似たツノトンボかな?  7月29日(土) どうか逃げないで! 帰宅してドアを開けようと思ったら、交尾をしているムシヒキアブが! どうか逃げないでと思いながら急いで撮影しました。 (画像と情報:4年生隊員のS君) 5月1日(月) 白い花のアカバナユウゲショウを見つけた! 町中を歩いていて、白い花をつけているアカバナユウゲショウを初めて見つけました。単にユウゲショウと呼ぶこともあります。シロバナアカバナユウゲショウなんてちょっとへんな呼び名ですね。シロバナユウゲショウでもいいみたいです。ならべて比べると、アカバナの方は茎は赤茶色をしていますが、シロバナの方は、葉の色と同じ緑色のままです。 アカバナユウゲショウの中に白い花がまじっていないかどうか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月13日(木) 黄砂(こうさ)のえいきょうかな? 夕日をとろうと西の空にカメラを向けてみました。風が強い日なのに、今日ばかりは山かげもどんよりぼんやり見えています。真上はきれいな青空ですが。やはり黄砂のえいきょうでしょうか? (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月12日(水) にげ出した植物 ~石神井川で見つけたよ~ 寒い時期からついこのごろまで、水のない 石神井川の底に黄色く目立つ花がさいています。『キクザキリュウキンカ』というヨーロッパからやってきた花です。どこかの庭先からにげだしたようで、かなり広がりを見せています。ちぎれた根からかんたんにふえるので、野生化するとやっかいです。ヒメリュウキンカ(クリック)との区別がまだしっかりとされていないようです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月6日(木) 4月6日(木)巨大なシロツメクサを発見しました。 場所は、石神井井川沿い、東伏見の早稲田大学グラウンドの、石神井川を挟んだ南側「下野谷 遺跡公園」です。葉もとても大きいのですが、花も大きく、直径3cmくらいあったでしょうか。まるで葱坊主(ネギの花:クリック)のようでした。 (画像と情報:スタッフのMさん)  3月31日(金) エドヒガン桜がやってきた! みなさんにおしまれつつも、幹の中に空洞(くうどう)ができてしまったために切り倒された桜(ソメイヨシノ)に代わり、西門わきに新しい桜の木がやってきました。新しい桜はエドヒガン桜という品種で、ソメイヨシノより少し早く咲く桜です。今回植樹されたエドヒガンはすでに凛(りん)と若葉を出している状態です。花をつけるまで何年かかかるようですが咲いた時の皆さん喜ぶ姿が今から楽しみです (画像と情報:スタッフのSさん) ★上石神井小学校の桜は図書室北側にあるオオシマザクラ以外はソメイヨシノでしたが、開校当初植えられたものは学校と同じくらいの年と考えると樹齢70年を超え、幹が老化して近年次々と切り倒されてしまっています。(ソメイヨシノはひかくてき寿命が短い樹木だそうです)新しく植えられたエドヒガン桜は寿命が長い桜で、中には樹齢数百年と言われているものもあるくらいですから今後も長く上小のシンボルとなっていくといいですね。生物多様性という観点からもソメイヨシノばかりでないというのはよいことだと思われます。 ジョウビタキ 石神井川に沿った都営上石神井アパートの一角。ジョウビタキのメスがいました。冬鳥の季節は終わり、このメスのジョウビタキもそろそろ旅支度でしょうか。(→画像拡大) (画像と情報」:スタッフのT) 3月10日(金) ムクドリの水浴び 春本番のような暖かさに、夕方、たくさんのムクドリが石神井川で水浴びをしていました。ねぐらに帰る前の入浴タイムでしょうか。(→動画)  3月9日(木) 冬眠終了! 一気に春めいた暖かな陽気に誘われて、ニホントカゲも冬眠から目覚め、日向ぼっこを始めたようです。〈上石神井第4踏切と第5踏切(閉鎖中)の間の線路ぎわ〉 (画像と情報:スタッフのつとむさん)  3月8日(水) 幼虫めっけ! 春から育てていた綿が枯れたので、植木鉢の土を空けたら、中から大きな幼虫が4匹も出てきました。コガネムシ?でしょうか。 園芸用の土で大きく育っていて驚きました。 せっかくなので腐葉土を入れたケースに移し替えて、様子を見ることにしました。 (画像と情報:3年生隊員のSさん) ★うえきばちから出てきたというこの幼虫。さてさなぎになって羽化したらいったい何になるのでしょう?ケースに移して飼育して、自分の目で確認するというのはとてもいいとりくみですね!結果がわかったらぜひまた写真を撮って報告してください。 3月2日(木) 見えた!木星と金星の大接近 (画像と情報:隊員のGママさん) 2月23日(木) 夕方の絶景をパチリ! 23日の夕方、家の2階から家族で見ました。とてもきれいでした! はじめはスマホを使ったのですが、手ブレがひどく、次にデジカメでねらいました。すると三きゃくなしでもうまくとれました。(画像クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★いろいろな機材を使ってみたのがいいですね。3つの天体(月・木星・金星)が並んでいる様子がよくわかります。3月の大接近の様子もぜひとってみてください。 2月22日(水) 毎日見てます! 22日の夕方、18:51。古田島先生からの宿題(→こちら)に挑戦中。毎日同じ場所から同じ設定で撮影してみようと思います。(画像クリック→拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★22日と23日の比較画像が届きました。この先も2日の大接近までの変化が楽しみですね。  2月22日(水) 春めっけ!② こんにちは。しぜん探検隊で頂いたサクラソウが綺麗に咲きました!写真を送ります。 (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★スタッフのコタジーが毎年取ったタネから育てた苗を秋に分けてくれているものですね。次々とつぼみが上がってきているようですから、これからもしばらく楽しめそうですね。     2月15日(水) 春めっけ! 先週、三浦海岸に行ってきました。そこではもう春がやって来ていて、ハコベ、タンポポ、オオイヌノフグリ等が咲き、カメムシかな?出てきていました。 (画像と情報:スタッフのKさん) ★恒例「春さがし」の今年の第1報ですね。春はもうすぐそこまで来ているのですね。みなさんもそろそろ冬ごもりを終わりにして外に春を探しに出かけましょう。週末は暖かくなるようですよ~  1月24日(火) 石けんの実、ミッケ! 前に観察会で遊んだ「ムクロジの実」がいっぱい落ちているのを見つけました。(写真・上)まわりの半透明の部分はぬらせばアワがいっぱい出て石鹸遊びができたんですよね。そのまわりの部分を取ると、中から硬くて黒いタネが出てきます。(写真・下)これが、羽根つきの羽根の黒い玉の部分。  見つけたのは、石神井公園。上を見るとまだいっぱいなっていて思わず「ムクロジパーティーだぁ!」  (画像と情報:OB隊員のN&Rちゃん) ★この実をひろえるのは、ちょうど今の季節なんですね。集めておいたら次のリース作りの時のいい材料にもなりそう・・・  1月21日(土) 日の入りも見たよ! 学校の屋上から日の出を見たので、夕方は日の入りも観察してみました。16:56とのことでしたが、ちょうど西の方角に雲があり、太陽が雲にかくれたのは16:29でした。西に雲があるということは、これから天気、悪くなるのかな。 (画像と情報:隊員のGママさん)  1月12日(木) 月齢19の昼間の月 昼間の月がよく見えていました。月齢19だから上石神井の電車の車庫の同じ19番線の上に出ているように撮れたら面白いかなと思ったけど、なぜか19番線だけ表示がない(汗!) (画像と情報:隊員のGママさん)  1月6日(金) 暈と幻日 太陽に巻層雲がかかると、そのまわりに色のついた光の輪や強く光る場所が現れたりすることがあります。今日は丸い輪とその両脇に虹色に光る「幻日}(げんじつ)が見えていました(矢印の下)。左右両側に、はっきり見えていましたが出先にいたのが残念。真ん中の太陽を隠すようにして撮らないとまぶしすぎて暈や幻日がうまく写らないのですが・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) 1月1日(日) 初日の出と初日の入り あけましておめでとうございます。 元日は、風はさほどないのに、とてもすんだ空にめぐまれました。 南東の空から日の出の時こくの数分後には太陽が見えてきました。わずかに広がる低い雲が光をうけて、それ刻々と増していくようすは神々しいものでした。 矢印の先に都庁やドコモタワーが見えています。 日の入りは、富士山の火口のすぐ南がわでした。あと1週間足らずで火口に重なりそうです。 ★初日の出16秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) 12月26日(月) 1時間以内で全部見えた! 日月火水木金土全部を最短時間で見るチャレンジ。1時間以内で全部見られました!! 上から太陽(日):26日16:24撮影・火星:26日17:03撮影・土星・月・水星・金星:26日17:13撮影・木星・土星・月:26日17:13撮影 (→それぞれ画像クリックで拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★すごい。古田島先生もびっくりの最短記録でしょうか。こんな「惑星パレード」は次は2061ねんまで見られないそうです。みなさんもぜひ西の空に注目!(コタジーの記事はこちら・クリック)  12月22日(木) 12月8日(金) 月のくしざし! 天気が悪く、年内のダイヤモンド富士がとれなかったので「タワーくしざし満月」をとってみました。 12月8日は、満月のすぐそばに本当は明るい火星が見えていたですが、さらに明るい月の明るさに合わせてとったので写っていません。 タワーの頂上の部分がぴったり満月の中に入りました。17時半くらいから5分おきにとったものを後で合わせました。 月の軌跡(きせき=動いたあと)を見ると、ずいぶんと地面から立っているのがわかります。 冬の満月の動きは、この時期の太陽とは反対に、天の高いところを通ることがわかります。でもこれは満月の時だけで、月の形がかわると通る高さもかわります。冬では、新月になるほど高さが低くなります。(冬の太陽と同じになる) 夏はこの反対で、満月は低く、新月に近くなるほど高くなります。太陽は、何か月もかかって高さがかわっていきますが、月は2週間くらいの間に、高くなったり低くなったりしているというわけです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  12月4日(日) 桜草咲いた! 先日の観察会で、こたじま先生から頂いた桜草に、花が咲きました。去年はピンク、今年は白でした。今年は二株頂いていて、もう一株もつぼみが出てきたので、何色が咲くか楽しみです。 (画像と情報:4年生隊員のSさん) ★寒くて花の少ない時期にもきれいに咲き続ける桜草(=プリムラマラコイデス)うれしいですね。みなさんのところでは何色が咲くかな。  11月27日(日) 大根できたよ~! 畑プロジェクトで種から育てた大根。できました! (画像と情報:畑プロジェクトメンバー) ★某農大の有名な「大根おどり」を思い起こしました。大根ってできると思わずにぎりしめて踊り出したくなるものみたいですね。わかるわかる。  11月26日(土) バッタのソフト食べたぞ! イナゴが突き刺さったソフトクリーム。長野県の諏訪湖で発見。思わず挑戦しちゃいました。 「ソフトクリームの甘い味にイナゴのしょっぱいところが合っておいしかった。でもちょっと見た目がグロかったよ」(本人談) (画像と情報:4年生隊員のK君) ★地球を救う「昆虫食」がちょっとしたブームとか。イナゴは日本ではひかくてきポピュラーな食べ物みたいですが、ソフトに合わせるとは!隊員なら挑戦したくなるよね~  11月20日(日) 11月20日(日)木の実を拾いに公園に行こう! リースづくりのためのつるとりも終わり、いよいよ12月3日はリースづくり本番。みなさんも、各自で木の実や木の枝など、リースづくりに使えそうな材料集めをしましょう。 11月12日(土) フヨウはふよう?(不要) いいえ、リースに みなさんリース作りの材料は集めていますか?フヨウの実がリース作りに使えるというので、近所の鉄道にそう道や石神井川ぞいの道で見つけたので集めてきました。12/3にもっていきますね。 (画像と情報:スタッフのコタジー) ムクドリの大群 ムクドリの繁殖期は春から夏にかけてで、それが終わると親鳥も巣立った子どもも一緒になって群れを作るようになります。秋から冬にはその群れは大きくなって、何百、何千、場合によってはそれを超える数のムクドリが群れを作るそうです。この時期、上石神井周辺でも、夕方にムクドリの群れを見ることができます。ムクドリは群れでねぐらに集まって寝るそうですが、おもしろいのは、寝ぐらに向かう前に、一回、どこかに集まることです。写真は、夕方、高圧線の鉄塔に集まったムクドリです。こうして集まったあと、何かをきっかけに、群れはねぐらに向かって飛び去っていきます。いくつかの群れが集まっているようで、見ていると、電線に残っているムクドリもいて、すべてのムクドリがいっぺんにねぐらに向かうのではないようです。それでも暗くなる前には、鉄塔や電線には一羽のムクドリもいなくなります。 →画像クリックで拡大 →動画(クリック) 10月27日(木) カノープス見えた! 南の低い空に見ることのできるカノープス。見えました!ただし午前3:23。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★シリウスに次いで明るい星ですが、日本では高度が低いため(東京で約2度)なかなか見ることができない星です。南がよく開けた場所を探して、星座アプリなどで見える時刻(けっこう限られた時間です)を確認して、みなさんもこの冬はカノープス探しにちょうせんしてみましょう。  10月26日(水) 綿の実ができました! 畑に植えた綿(わた)に実ができました! (画像と情報:隊員のKママ) ★白いフワフワの綿の実。このフワフワからみなさんが着るいろいろな服やタオルなどの綿(コットン)製品ができるのですね。このままリースなどの飾りとして使ってもすてきですね。来年はみんなでもっとたくさん育ててみたいですね~  10月23日(日) 虹色の雲発見! 虹色の雲(彩雲=さいうん)が出ていました。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) ★太陽のそばにある高積雲などの端が美しく虹色にかがやく現象です。古くからとても縁起(えんぎ)がよいものとされています。何かいいことあるかな・・・  10月14日(金) 「石神井川そばのソバ 」 ~ にげ出したソバ ~ 西東京市の石神井川は、水が少な目で、川ぞこにたまった土には多くの野草が生えています。 このところ川べりを歩いていてやたら目につくのが、白い小さな花をたくさんさかせているつる性の野草です。大きな群れをなしてさきほこっています。葉は、かどのとれた三角形です。 『シャクチリソバ』というソバの仲間でした。にがくてまずいけれどからだいいいことで有名なダッタンソバの親せきです。昔、小石川植物園に外国から薬草としてもちこまれたものがにげ出して全国に広がったようです。ふえすぎてやっかいものあつかいされてもい ます。 ソバ粉にしてソバをつくってもにがくてまずく、むしろ若い葉を野菜にするということです。 薬草というからには、どんなこうかがあるのか調べてみましょう。(野草をやたらに食べたりしないように (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月12日(水) よっぱらったフヨウだ! 「よっぱらった?フヨウ」を見つけました。「スイフヨウ(酔芙蓉)」といい、街角でふつうに見かける花です。さきはじめた朝は花びらが白いのですが、時がたつにつれて、しぼみながらピンク→赤とかわっていきます。そのようすをよっぱらって顔が赤くなることにたとえたのですね。どうして色がかわるのか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月8日(土) 十三夜の月と木星 雲の合間から見えました! (画像と情報:隊員のGママさん)  10月2日(日) 関公園にて 関公園で出会いました。ヒバカリかな?と思ったけれどアオダイショウ? (画像と情報:隊員のGママさん) 光をあてて拡大してみると!! 浴室や洗面所など水回りでときどき見かけるオオチョウバエ。ただ地味でうっとうしいヤツと思っていましたが、ストロボで光を回して拡大撮影してみると…。  9月24日(土) 小さな細長い貝発見! 画像悪いですが、先ほど初めてキセル貝を見つけました! (画像と情報:隊員のKママ) ★陸にすむ貝はカタツムリだけではないんですよね。よく探すとこのような細長い小さな貝を見つけることがあります。キセル貝は左巻きですが、オカチョウジガイという右巻きのもいます。死んだ貝殻のように見えても水をかけると写真のように動き出すことがあります。探してみましょう!かわいいよ~  9月16日(金) 上小のヒガンバナも咲き始めました この時期になると、すぅ〜っとのびて、パッと花火のように咲くヒガンバナ。トンボ池でも咲きはじめています。 (画像と情報:スタッフのSさん)  9月15日(木) カマキリ釣りにちょうせん! 自宅で子ども文庫を開いている知人に、探検隊の本を寄付しましたところ、利用者の少年が、早速【釣れた】報告を下さったそうです。 (画像と情報:スタッフのMさん) ★探検隊の本から、身近な自然遊びが広がっていっているようでうれしいですね。みなさんもいろいろ挑戦してぜひ報告を聞かせてください。  9月12日(日) 黄色のヒガンバナ見つけた! ヒガンバナが咲き始めています。上小の駐車場わきのはどうですか? 近所に黄色のヒガンバナがあるのに気が付きました。プランター植えです。ヒガンバナは真っ赤、ピンク 白 などがあると思っていたら、黄色のもあるんですね。 黄色いのはショウキズイセンという名でもよばれています。ほかにどんな色のヒガンバナがあるのかさがしてみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  9月9日(金) トチの実 トチの実の季節になりました!公園にたくさん落ちていました。今年はリース教室やるんですか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★風の吹いた次の日、早朝のお散歩のごほうびですね~ピッカピカのトチの実、拾うとうれしくなりますね。リース教室、まだ確定ではないですが今年もやりたいなぁと考えています。みなさんも材料集め始めましょう。  9月8日(木) オケラ発見!! 露天風呂でオケラ発見!近くに田んぼもないのに・・・ (画像と情報:スタッフのKママさん) ★田んぼのような場所で見つけるイメージですが、都内にもいるんですね~。上小でもトンボ池横の側溝でスタッフのSさんが見つけた記録があります。 ※「露天風呂」というのはKママさんのおうちはお風呂屋さんだからです。 ちなみにオケラは泳ぐの得意だそうですよ。  9月7日(水) レンゲショウマ SNSで人気のレンゲショウマ。石神井公園、いろいろありますね。映えないケド・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) ★御岳山まで行かなくても身近なところでも見られるのですね~  9月4日(日) ・・・ドクターブラック・・・ 家の前の道路を黒いきれいなイモムシが3匹も歩いていました! ★頭の部分がななめの流線形。黒いボディーにオレンジ色と黄色の丸い窓みたいなもよう。おしりにはとがったアンテナが1本。新幹線にドクターイエローっていう車両があるけれど、まさにそのブラックバージョン!ということで私は「ドクターブラック」って呼んでいます。 (→資料) この時期、食草のヤブガラシから下りて地面の下でさなぎになります。身近に出会える美しい生き物ベスト3に入ると思いますよ。ちなみにとげはにせもの。さわってもだいじょうぶです。 (画像と情報:隊員のりっちゃん&ママ) 8月19日(金) 夏のオリオン 昨晩から今朝にかけては風が変わりましたね。光にもかすかな秋が感じられます。早朝の上石神井の空には冬の星座オリオンが見えていました。(19日3:38撮影) (画像と情報:隊員のGママさん)  8月13日(土) 昼間からうじゃうじゃカブトムシ 近所の民家(緑が多いところですが、広い緑地は近くにはありません)に、昼間からカブトムシが元気に動き回っている木を見つけました。 シマトネリコという木のことをテレビで紹介しているのを思い出しました。カブトムシというと、夜クヌギなどの木にやってきてじっくりと樹液を吸っているというイメージですが、シマトネリコにやってくるものは、様子がかなり違います。 昼間なのにとにかくよく動きまわり元気です。ブンブン飛び回るものもいます。この木とカブトムシの関係は、まだわからないことも多いみたいですが、埼玉県の小学生の研究も参考にしていろいろと調べてみてください。 50秒動画(→こちら) ★シマトネリコという木になぜかカブトムシが集まるという情報、聞いてはいましたがまだ見たことがありません。このシマトネリコという木は最近、庭木として人気なのだそうですが上石神井にはありますかね。どんな木が調べておいて登下校やお散歩の時などに探してみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  8月10日(水) 街路樹を見上げてみれば いま、あちこちで鳥のヒナが鳴いていますね。新青梅街道の街路樹にも鳥の巣がありました。(写真左上)青梅街道の街路樹にも何かの巣があったし、街路樹って巣作りしやすいんですかね? ★昼夜を問わず人やクルマが絶えず通る場所は、天敵におそわれにくいというようなことがあるのでしょうか。都会に暮らす鳥たちのしたたかな知恵ですね。 (画像と情報:隊員のGママさん)  8月6日(土) 夏のモフモフ 昆虫界のアイドル、セダカシャチホコ? 数日間外廊下の天井にいましたが、とうとう力尽きたご様子。 暑くないのか心配になるほどのモフモフっぷり! (画像と情報:隊員のGママさん) 8月1日(月) 上石神井駅の日の出(夏) 暑い日が続きます。早朝5時の駅から見た東の空。 冬バージョン(2月23日・クリック→動画)とくらべてみてください。 ★暑い暑い・・・と文句言ってないで、ちょっと早起きして空を楽しむのもいいですね~ ちなみに下の空の動画も素敵です。こちらも撮影はGママさん。7月27日。ほかでもない上石神井の空です。 (画像と情報:隊員のGママさん)   7月21日(木) 7月の発見いろいろ 7月に見つけた自然いろいろ。 上・石神井公園内の売店「豊島屋」さんで見つけたタマムシ(7月8日) 中・石神井公園のモミジの木に生えていたキノコ。とてもおいしいキノコなのかハムシがたくさんいました。(7月5日) 下・井草の森公園のアオギリの花。そろそろ開花です。(7月5日) ★今年は梅雨明けが早く、すぐに暑くなったためタマムシはずいぶん早くから見られた気がします。石神井公園にもいるのですね。 みなさんも見つけた夏の自然を教えてください。 (画像と情報:隊員のGママさん)  7月9日(土) オナガの子育て2022(巣立ち編) オナガのヒナたちですが、生まれたのは4羽。そのうち落ちてしまい死んでしまったのが1羽、8日の段階でかなり大きく(巣の中で羽をばたつかせている)育ってきたヒナが3羽が巣の中に確認できました。翌日9日は朝少し早め6時ころに見に行きました。ヒナはもう巣の外に出ていて、一羽は数m下のカエデの木に乗っています。もう1匹はなかなか見つからなかったですが、声をたよりに探してみると巣の真下の低木(アオキやクマザサ)の葉陰にかくれるようにとまっていました。いずれも、何羽もの親鳥がギーギーいきかい、エサを時々やりにきていました。ヒナに近づこうものなら、頭をつつかれそうないきおいでした。残る1羽のヒナはついに見つけられませんでした。ツミの声や姿がよく見らるので、1羽は捕食されてしまったのかもしれません。生きているのはどちらも飛ぶのはかなりおぼつかないヒナです。ちょっと、「巣立ち」が早かったのでしょうか。親からエサをもらっているので、そのうちしっかりしてくると思いますが、なにしろ外敵がけっこういそうなのでちょっと心配です。 5分09秒動画(→こちら)  7月5日(火) オナガの子育て 2022 5月末に近くの公園のけやきの木に巣を見つけてから、3週間以上かかってやっとオナガのヒナがふ化しました。 去年は、どういうわけか親鳥がとちゅうで巣をあきらめてしまったようですが、今年はめでたくヒナのたん生を目にすることができました。ヒナは今はすくすく育っているようですが、途中悲しいこともありました。 同じ園内にいるツミにおそわれそうになる場面もありましたが、なんとか切りぬけられたようです。今は台風の大風や大雨が心配ですが、無事に巣立ってくれるとうれしいです。高い木のななめ下からの撮影ですが、ひなはどんどん大きくなるので、そこそこ中の様子をうかがうことができます。ひなの鳴き声も聞こえます。強拡大するために望遠鏡のレンズを使いました。 2分40秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月2日(土) 10円玉みがきやってみました 探検隊で(カタバミの葉で)10円玉を磨いてから、帰って5円玉も磨いてみました。5円玉は10円玉と違ってそこまで綺麗に光らなかったです。磨いてしばらくするとまた錆びてきてしまいました。 ★今日の観察会でやった「カタバミの葉っぱ」を使った10円玉みがきをさっそく家で発展させて実験してみたんだね。こんなふうに別のものでもいろいろ試してみるとおもしろい発見もあるね。台所にあるお酢などの調味料、庭の別の葉っぱなども試してみたそうですね。こんど結果を詳しく聞かせてください。 (画像と情報:OB隊員中2のNくん)  6月23日(木) なんのまゆかな? 学校のクワの木で見つけました! ★大きな繭(まゆ)ですね。クワの木で見つけたということは、カイコの原種と言われるクワコでしょうか。しっかり糸で繭を作り、中のさなぎが鳥などに食べられないようにガードしているのですね。この糸だけを集めて布を作ろうと考えた昔の人もすごいなぁ。 (画像と情報:隊員のGママさん)   6月22日(水) 見たことあるかい? こんにちは! ハラグロオオテントウ(上)とビロードハマキ(下)です。 ハラグロオオテントウは関町で飛んでいたものです。1.2センチほどあります。 ビロードハマキは石神井公園の旧内田家住宅にいました。図鑑の絵は、はねがひらいて描いてあったので、気がつきませんでした。 どちらもツマグロヒョウモンやアカボシゴマダラ、ナガサキアゲハ、ジャコウアゲハなどと同じように近年北上してきた昆虫ですね。数年前は房総で見つかったとニュースになっていたのに、そこらへんで見られるようになりましたよね。 ★このHPではどちらも初登場の新顔さんです。練馬区内にいるのですね!ハラグロオオテントウはその名の通りの大きさであることが1円玉とのひかくでよくわかります。 (画像と情報:隊員のGママさん)  6月13日(月)ソバの花 市内の新青梅街道そばにソバの花を見つけました。がいろじゅのすぐわきに、いったいだれがまいたのでしょうか? ソバは、年に二回(夏と秋)とれるそうです。▲の形をした種を見たことがありますか? あざやかな赤い花をつける種類もあるそうです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  6月10日(金) キアゲハの幼虫 3齢までの、まだ体全体が黒っぽいうちは数多くいても、緑色が多くなった4齢の幼虫になると、なぜか数を減らしてしまうような気がします。このキアゲハの幼虫は久しぶりに見つけたビッグサイズので、もうじきサナギになるのではないかな。 (画像と情報:スタッフのSさん)  |