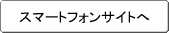トンボ池・上石神井のしぜん最新情報(2020) |
 |  |
2020年12月25日(金) 校庭のクリスマスカラー アオキの赤い実。つやつや、クリスマス色です。(西側正門にて) ジンチョウゲも花芽をつけて、春をまっています。(西側正門にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月24日(木) じっと春を待っています② 真っ赤な実をつけていたハナミズキは、来年に向けてつぼみをつけていました。(東門花だんにて) 香りの良いスイセンも、花芽がふくらんできています。楽しみですね(東門花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年12月23日(水) 駐車場花だんの住人たち 花だんの手入れをしていると、木の根もと近くでくつろぐツマグロオオヨコバイ(通称バナナ虫)がいました(左上:駐車場花だんにて) 葉っぱの中にもいます、寿命は9ヶ月くらいだそうです。冬の間はのんびりと過ごしているようです。(右上:駐車場花だんにて) 少し大きな石をどけると、石にくっついているキイロテントウがいました(左下:駐車場花だんにて) たくさんの幼虫観察をさせてもらったクワの手入れをしていると、クワコのものだったのかもしれないマユがありました。(右下:駐車場花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月23日(火) じっと春を待っています コブシの冬芽。春になると芽をひらかせて、花のツボミが顔を出すそうです。それまでフサフサのコートを着ています。(左:玉川上水沿いにて) 集めた落ち葉が入った袋の中から、クビキリギス!とても元気!良かった!(右:落ち葉回収置き場にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年12月21日(月) ヒマワリの種、もうすぐ売り切れ トンボ池のバードフィーダーには、かわいいお客さまでにぎわっています。左のすみにはメジロもいます。鳥達はおぎょうぎ良く、じゅんばんこに、いただいているようです。(左上:トンボ池にて) ときどきヒラヒラと姿を見せてくれるヤマトシジ。(右上:校庭にて) 木の手入れをしていると、ナナホシテントウがおとずれました。寒い日は落ち葉の下などで静かにしていても、天気の良い日が続くと、遊びに出てくるようです。(左下:プールにて) カマキリの卵(卵嚢=らんのう)です。2メートル以上上の、アケビのツルにありました。(右下:プールにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年12月19日(土) ヒマラヤスギの上で会いましょう いよいよ近づいてきました。今日からは、100倍くらいの望遠鏡の視野に2つの惑星を見ることができるようになっています。近所の学校のヒマラヤスギの上にちょうどやってきたところです。木星のガリレオ衛星も4つ写っています。その中には、内部海といわれる液体の海があり、生命が生まれる環境があるのでは?と研究が進んでいるようです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2020年12月18日(金) 冬の生き物たち アダンソンハエトリグモのメスのようです。(わかりづらい写真ですが、身近によくいるクモです。)ハエトリグモは『くもの巣』を作らず、えものを見つけるとジャンプしてとるのだそうです。ジャンピング スパイダーとも呼ばれています。(左:プール脇の生垣にて) 昨日、ひなたぼっこをしているイモムシがいるよ〜っと聞きつけ行ってみると、、エダシャクガの幼虫のような気がします、今日は壁にへばりついていました。(右:上小西側道路沿いの壁にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
 | |
2020年12月17日(木) 五円玉の穴にすっぽり入る木星と土星 本日夕暮れどきに見られた木星(右下)と土星(左上)と三日月の接近。(上:上中北のちびっこ広場にて) 21日の大接近に向けて日々その見かけ上の距離をちぢめてきた木星と土星ですが、すでに腕を伸ばした先に持った5円玉のあな(約0.5度=ほぼ月の視直径)以内におさまっているのをとらえました。(下:上石神井にて撮影) (画像と情報:上=スタッフのいとうパパ・下=隊員のGさん) |
 |  |
2020年12月17日(木) トンボ池に初氷! 今朝はアオサギがいました。カメラのレンズがすぐにくもってしまうくらいの冷え込みでしたが、アオサギは『へちゃらよ〜ん』って感じでした。(右:石神井川にて) ハスを育てている水そうで初氷です!(左:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年12月16日(水) いよいよです・・・5円玉を用意しましょう 16日の夕方の木星、土星です。もうすでにうでをのばして持った5円玉のあなに入るようです。左の写真は、望遠鏡30倍で撮影したものです。同じ視野の中に木星土星をいっしょに見るのは、初めての経験です。木星(下の明るい星)におともしている小さな星は、ガリレオが発見した4つの衛星です。(ガリレオ衛星) 西にすぐに低くなってしまうので、早めに(17時くらいから)観察しましょう。 17日夕方は、三日月が華(はな)をそえますので、見事な光景になることでしょう。万人がいただける空からのちょいと早いクリスマスプレゼントです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2020年12月16日(水) 落ち葉の中の生き物たち 落ち葉の上で作業をしていたら、なんだ、なんだ!?なに事だ?と小さな生き物が出てきました。通称バナナ虫のツマグロオオヨコバイ(左)と、T字形のヒルガオトリバガ(=昼顔鳥羽蛾)(右)かなと思います。(プールとトンボ池の間) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月15日(火) 完食!野鳥のレストラン とても上手に完食です!なかなか食べている姿を見せてくれませんが、集団で遊びにきているスズメをよく見かけます。(左:トンボ池にて) ヒラタアブがいました。セミの抜けガラにある成分と同じで、昆虫の翅(はね)もキチン質でできているそうです。このキチンですが、とても万能な成分で、主にカニのキチンを医、食、農、衣など、さまざまなところで使われているそうです。(右:校舎裏の畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月14日(月) 空に巨大なのり巻き! 今朝は長くて、つつ状の雲が何本か出ていました。ロール雲、うね雲と言われる層積雲(そうせきうん)なのかなぁと思いました。(左:石神井川遊歩道にて撮影) イチョウの落ち葉と一緒に、セミのぬけガラもありました。殻(から)にはカニやエビの殻と同じ、キチンと呼ばれる成分があり、中医学ではスジアカクマゼミの殻を乾燥したものを生薬として、発熱、ジンマシンの時に使われているそうですよ。ちなみに日本産はおもにアブラゼミ、クマゼミの殻を利用するようです。(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年12月13日(日) テーマは五輪! 今年は自分達でリースを作ってみました。テーマは、オリンピックの五輪です。 家族4人で、1人1つ輪を作りました。来年は、みんなで作れるといいなと思いました。 (画像と情報:4年生隊員のSくん) |
 | |
2020年12月13日(日) 見れたぞ「大接近」★(ぱおん) 本日早朝の細い月と金星の大接近。ベランダから楽しみました! ★月の「地球照」もきれいに撮れていますね。月や惑星は自宅に居ながらにして、しかも特別な機材がなくてもこうして十分に観察や撮影が楽しめるのがいいですね。この写真はスマホで写したものです。6時ころから雲が出始めてしまいましたが、早いうちはよく見えました。「空を見上げよう」のページにコタジーからの報告もUPしています。 (画像と情報:隊員のGさん) |
 |  |
2020年12月12日(土) メスは一生ミノの中(ぴえん) ミノムシがぶら下がる光景は昔は普通に見られたのだと思いますが、今はめずらしいと感じてしまいます。ミノガのオスは蛾となり飛んでゆきますが、メスは最後までミノの中で過ごすそうです。(左:あきる野市にて) 農産物屋さんで買ってきた、みずみずしい白菜の中にいました。農家さんには悩みどころかもしれませんが、おいしい証拠ですよね。ヨトウムシ類の幼虫かなと思います。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月11日(金) 天気は下り坂? うす雲と呼ばれる、巻層雲(けんそううん)のようでした。このベールのような雲が出ると天気は下り坂になることが多いのだとか。たしかにその後、空には雲が広がりました。まん中あたりの白いのは飛行機です。(左:東門から撮影) シュロの葉の裏にアリグモの巣がありました。アリグモは無害で、アリ、蚊、ハエ、アブラムシなど人が嫌がる虫を食べてくれるそうですよ。(右:プールわきの生垣にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月10日(木) 寒い朝でも元気なカルガモ 足からの冷えた血液は、足の付け根あたりにあるワンダーネットと呼ばれる熱のこうかん場所であたためられてから体内にもどるのだそうですよ。(左:石神井川にて) キラキラ!カメムシの卵だと思います。みかんの木にからまるアケビの葉の裏にあり、カメムシの種類は孵化(ふか)したらのお楽しみ。(右:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年12月9日(水) 木星と土星の大接近を見よう! 11月19日のGママの投稿にしげきされて、夕方、ISS(国際宇宙ステーション)と接近中の木星と土星をさつえいしてみました。 すでにアナウンスもありましたが、17日の夕空の中の月・木星・土星接近、21・22日の「木星・土星の歴史的大接近」(!)は、見のがすわけにはいきません。これほど近づくのは、江戸初期以来、やく400年ぶりだとか。目で見て、分かれて見えるのか?も実さいに見てみないとわかりません。望遠鏡で200倍の視野の中にもよゆうでおさまるようです。 双眼鏡では、どんな見え方をするのでしょうか。双眼鏡や望遠鏡をもっている人は、機材を事前にチェックしておきましょう。双眼鏡がない人は、ちょうど時期がいいので、クリスマスプレゼントでおねだりしてみるのもいいかもしれませんよ。(星を見るには、7倍×50mmが標準とよくいわれます。小学生低学年にはちょいと大きいかもしれませんが、三脚に付けられるねじがあるものを選ぶとよいでしょう。) 明日は、ISSはもっと高度があります。17:06 北西→17:09東 高度82°→17:12南東 明るさー3.8等 ほぼ真上を通過します。ISSの中で活動をしている野口さんに、エールを送ってください。条件◎です。火星といっしょに撮影できるでしょうか。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2020年12月9日(水) 成虫で冬ごしするバッタです クビキリギスは1.2年くらいの寿命で成虫のまま冬を過ごすそうです。緑色と茶色の2タイプがいますが、どちらも同じクビキリギス。 カイヅカイブキの剪定(せんてい=木のえだを切って形をととのえること)中に出てきました。(左:プールとトンボ池の間にて) 集めた落ち葉の中から出てきました。安心して過ごせる場所へ移動してもらいました。(右:西側正門、外の植えこみにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月8日(火) メジロが来ています 古いツルを取りのぞいていたら、コロンと蛹(さなぎ)が出てきました。食草のヤブガラシがあった事もあり、セスジスズメの蛹かなと思います。 5月頃から羽化するようですよ。(左:プール脇、バッタ原っぱにて) 柿をいただきに訪れたメジロ。観察会で作ったエサ台のくだものにも小さなクチバシの跡(あと)が残っていますよ。(右:東門にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月7日(月) 12月の色いろいろ 野鳥が種子を運んでくれたようです。フェンスのすき間からセンリョウが出てきて、赤い実をつけています。(左:体育倉庫前にて) 翅(ハネ)をとじていると灰色の蝶なのですが、翅を広げるとハッとするくらい美しい色をもっていて、とてもビックリします。ムラサキシジミ(右:校舎裏、畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年12月6日(日) 木星と土星が接近中 宵(よい)の空でかがやいていた土星と木星がだんだんと高度を下げ、同時に接近中。 21日(月)の夕方には、木星が土星の南に大接近します。小型の望遠鏡なら同一視野で木星と土星が並んだすがたを見ることができるはず。木星と土星がこんなに大接近するのは20年に一度のことですから、ぜひ夕暮れの西の空を観察していきましょう。 13日明け方には月齢28の細い逆向きの三日月の西にマイナス4等の明るい金星が大接近、14日は新月前日の暗い空でふたご座流星群。12月も空から目がはなせません! (画像は本日の木星と土星(円内)提供:隊員のGさん) |
 | |
 |  |
2020年12月5日(土) 上石神井でも見られるタカ 「たぶんツミとかそんな感じのタカが飛ぶ姿を東門から見ることができました!あたふたして、ズームして撮れなかったのですが、写真中心あたりに小さく飛ぶ姿が写っています。」(上:4日 学校の東門付近にて) ★ワシやタカなど猛禽類(もうきんるい)と呼ばれる肉食の鳥は、生態系のピラミッドの頂点とも言われ、バランスのとれた豊かな自然がなくては生きていかれません。東京では見ることはないと思っているかもしれませんが、近年オオタカ・ツミ・ハヤブサなどの猛禽類が東京でも見られるようになってきているようです。今回の情報は上の写真だけからは種類までは特定できませんが、スマホでとらえたのはさすがです。いることは確かという証拠になります。参考までにツミの写真を下に掲載しておきます。みなさんも空や木の梢(こずえ)を見上げてみてください。出会える可能性は十分です。 (画像と情報提供:スタッフのSさん・つとむさん) | |
 |  |
2020年12月4日(金) 3日ぶりの晴天 今朝は月がキレイに見えていました。(左) 今日は3日ぶりの晴天でした。気持ち良さそうにくつろぐヤマトシジミ。(右:校舎裏の畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年12月3日(木) 今日も曇り空 電線に集まってきたシラサギ(コサギ)。『今日も曇り空ね〜』って話してるんですかね。(左上:石神井川遊歩道から撮影) アシタバにナミテントウがいました。寒くなると、仲間どうしで集まってすごすようですが、まだ寒くないのかな?(右上:校舎裏の畑にて) 同じアシタバにアオモンツノカメムシの幼虫もいました。それも、良く見れば5匹くらい!上手にかくれているつもりなのかな?(左下:校舎裏の畑にて) 真っ赤に紅葉するモミジが多いですが、楽しく紅葉するモミジもあります。(右下:体育倉庫前にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年12月2日(水) 上を見上げて見つけたよ 曇り空を見上げてたら、木にからまるすごく大きな実を見つけました!野球ボールくらいなんですよ。キカラスウリのようです。(左上:石神井川遊歩道にて) 鳥は寒い時期になると、羽毛の中に空気をたくわえて寒さから身を守るのだそう。 グラウンドから聞こえる『カキーン』に仲良く反応するキジバト。(右上:石神井川遊歩道、早大グランド前にて) イイギリの赤い実。(左下:石神井川遊歩道にて) トキワサンザシの赤い実。(右下:武蔵関公園にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年12月1日(火) 今朝の朝日 太陽の表面からの光が地球に届くまでの時間は、およそ8分19秒。 まぶしぃーい!(左:中校舎屋上にて) カキの木には、さまざまな野鳥がおとずれています。 ムクドリが撮れました。(右:東門の花だんにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年11月30日(月) 霜(しも)がおりていました 今朝、6時頃の練馬区の気温は4℃でした。 草地は霜(しも)がおりていましたよ。(左:石神井川遊歩道にて) こまかい雲がたくさん集まっているのが特徴のうろこ雲=巻積雲(けんせきうん)かなぁ・・・(右:校庭にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 | |
2020年11月30日(月) 朝の空に彩雲(さいうん)! 朝9時くらいから30分間ほど、彩雲(さいうん)が見えていました。 彩雲とは、太陽の近くの雲が、太陽の光を受けて虹色に輝く現象です。雲は形やその色を少しずつ変えとても美しく輝き、ずっとながめていても飽きませんでした。 (上石神井小学校付近にて) (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月29日(日) 石神井川で発見「ツミ」? 午前中、野鳥を探してみようかと団地の石神井川沿いに行ったところ、こんなものがいました。 撮影時にはチョウゲンボウかと思ったのですが、写した写真を見ると、ツミのオスかなと思うのですが・・・ なぜか顔がハトっぽいです。(石神井川沿い・上石神井団地付近にて) (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月28日(土) 玉川上水で見つけたよ 秋も深まり、玉川上水沿いでも楽しい発見がたくさんあります。(ちなみに、撮影場所の上水桜通りですがこの辺りは桜の木が多く植えられたそうです。その理由の一つが『桜の花びらが水質を浄化する』と信じられていたからなのだそうです。ステキな想いが込められた通りですね) クマシデの果穂(かすい)。種子を包んでミノムシみたいになっている様子がおもしろい。(左上) ぷっくり咲くのはツバキ。(右上) ひらたく咲くのはサザンカ。(左下) ネズミモチの実。野鳥が好みますが、リースの素材にも好評です。(右下) (全て玉川上水、上水桜通りにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月27日(金) ひつじ雲/高積雲(こうせきうん)? それとも層積雲(そうせきうん) 雲は10種雲形(じゅっしゅうんけい)と言って高さや形から10種類に分けられているそうです。今朝の空にはこんな雲が・・・ひつじ雲の高積雲(こうせきうん)?、それとも層積雲でしょうか?(左上:石神井川沿い、早稲田大学グランド前にて) 雨水の通る溝でカタツムリが冬眠しているようです。冬眠場所は乾燥せず、暖かい所を好むようなので少し意外でしたが、もう一匹いましたよ。(右上:東門、北側外通路にて) キンカン。良い色になっていますよ〜っ(左下:トンボ池にて) 葉蘭(ハラン)は日本料理で器や飾りとして使われる、抗菌力のある植物です。お花をかざる時にも使われていますね。(右下:トンボ池にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年11月26日(木) 昨日より7℃も高い19℃(練馬の最高気温) 今朝は靄(もや)がかかっていましたね。 石神井川にダイサギがいましたよ。(左:早稲田大学グランド前) 気温も上がり、晴れたからでしょうか。カナヘビが出てきていましたよ。(右:校舎裏の畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月22日(日) 富士山と日の入り よいお天気が続き、空を見るのが楽しいですね。富士山と日の入りを見てみました。この日(撮影は11月21日)の東京の日の入りは16:31。富士山の少し右(北)側に太陽が沈んでいるのがわかります。冬至(とうじ=12月21日)までは、太陽が沈む位置は少しずつ左(南)に動いていきますから、あと少しでちょうど富士山の向こうに太陽が沈むように見える日が来ます。これが最近話題の「ダイヤモンド富士」。もちろん見る場所によってそう見える日時は違うのですが、計算すると上石神井小からだとたぶん25日(水)頃に見られるはずです。 今日から数日は、日の入りが見えるよい観察ポイントを見つけて、夕暮れの空を観察してみましょう。 ちなみに、日の入りの時刻が一番早いのは冬至かと思うと、東京では冬至の日の日の入りは16:32で1か月も前の今(11月22日は16:30)より遅いのですね。あれ?なぜでしょう。日の出の時刻も調べて考えてみましょう。 (画像提供:隊員のGさん) |
 |  |
 |  |
2020年11月20日(金) 小春びよりの校庭で⑤ 昨日からの風でサワラ(椹)の小さな実がたくさん落ちていました。(左上:職員、来客玄関前にて) 野ばらに似た、かわいらしいバラの種(右上:東側のフェンスにて) ヒラタアブの仲間。目は複眼(ふくがん)といって、小さな目がたくさん集まって上下左右、ほぼ360度、見えるのだそう。(左下:東門の美化委員花だんにて) イチゴ。元気です!明日から寒さが戻ってくるようですが、イチゴは寒さに強いのだそうです。(右下:校舎裏の探検隊畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月19日(木) 小春びよりの校庭で④ みかん。次回の観察会の時にはちょうど良い収穫日となりそうですね。(左上:トンボ池にて) さまざまな生き物がおとずれていたホトトギス。たくさん種をつけています。(右上:トンボ池にて) さまざまな生き物がおとずれていたクワ。黄葉し、葉脈(ヨウミャク=葉のすじ)がよくわかります。(左下:トンボ池にて) ピョンと出てきたオンブバッタ。今日も日差しがたっぷりでした。(右下:校舎裏の畑にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月19日(木) 国際宇宙ステーション(ISS)と月・木星・土星 月・木星・土星の大集合にISSも参加してました! 本日17:33。上石神井より南西を望む。 (画像と情報提供:隊員のGさん) |
 | |
2020年11月19日(木) 月と木星と土星が集合! 今日は夕暮れの西の空で月と木星と土星がぐっと集まります。 ※上の写真は昨晩の様子です。今日とくらべてみましょう。 月の入りは20:18。それまでの間にぜひ観察してみましょう。明るい方が木星です。 東に目を移せば、火星も赤くかがやいています。今日は11月とは思えないあたたかい南風。観察にはありがたいですね。 (画像提供:スタッフのつとむさん) |
 |  |
 |  |
2020年11月18日(水) 小春びよりの校庭で③ 赤とんぼのなかま。日光浴をしているようでした。(左上:プールサイドにて) ヤマイモ。10月頃にむかごを実らせていましたが、今は秋色を楽しませてくれています。(右上:プールのフェンスにて) トンボ池のヨメナは日かげに咲きやさしい雰囲気の花ですが、プール側に顔を出したヨメナは太陽があたるので、少し大きめです。ヤマトシジミがおとずれていました。(左下:プールにて) 南天(ナンテン)の実、野鳥たちが好んで食べているようです。(右下:東側のフェンスにて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月18日(水) 四日目の月 今日は昨日より少し長い時間、見られましたね。それでも秋の月の通り道は地平線に対して寝ているので、西の空の月の高度は低く、ちょっと見つけにくかったかな。画像の左上には木星と土星も見えています。 (画像提供:隊員のGさん) |
 |  |
2020年11月17日(火) 細い細い月、見っけ! 日没が早くなりました。16時半くらいには太陽が沈み、急速に暗くなる南西の空に昼間は見えなかった細い細い月が見えてきました。今日は三日月。(新月から3日目の月のことです。この本当の三日月は一般に思い描く三日月の形よりずっとスマートですね。)18時過ぎには太陽をおいかけるように沈んでしまうので、見られる時間はわずかです。地平線にはうっすら富士山も見えています。 右の写真は、スマホ用の簡易望遠レンズを使ってみました。うっすらと地球照の丸い形も写すことができました。 (画像と情報提供:隊員のGさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月17日(火) 小春びよりの校庭で② タイサンボクの実。6月頃に白い大きな花を咲かせた後、マイクのような花軸(手前)を残し、その中で赤いたねを作ります。(左上:体育倉庫前にて) オンブバッタ。正面から、のぞくように見たところ。(右上:校舎裏の畑にて) ヒメアカタテハ。正面からカタバミの花にとまり吸蜜しているところ。(左下:校舎裏の畑にて) イヌホオズキ。有毒成分をもつ植物ですが、正しく加工して生薬として利用されているそうです。(右下:校舎裏の電気設備周辺にて) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月16日(月) 小春びよりの校庭で ヘクソカズラの実。ちぎっても、どくとくな香りはもうしません。 かざりに使うと、とてもステキです。(左上) 今日は小春日和※。日光浴をしていたカナヘビに会いました。(右上) ※こはるびより=冬に近づく前に春のようにあたたかい日が続くこと。 バラの花が咲いた後の実。この実(=ローズヒップ)ができる品種は原種に近く、強いそうです。(左下) ヨメナにおとずれた、ヒラタアブの仲間。お腹が平たい事が名前のゆらい。観察すると、ペッタンコなのでわかりやすい。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月15日(日) カノープスを見て長生きしよう!? 天気がよいので、一足早く、カノープスを見に行ってきました。「南極老人星」(なんきょくろうじんぼし)とか「南極寿老人」(なんきょくじゅろうじん)ともよばれ、一度見ると長生きができるというえんぎのよい星です。 シリウスに次いで2番目に明るいのですが、南にある星なので、東京では高度2°くらいにしかならず、気象の条件のよい時をねらわないと、なかなかお目にかかることができないレアーな星です。シリウスの南、オリオン座の冬の大三角1つと半分くらいのところにあります。 星座早見で見ると、11月中ごろは、午前2時半ごろ南中するので、時間をあわせて東伏見公園のすべり台の上でねらいました。(すべり台からはカノープスが見えると、スタッフのつとむさんから情報をもらいました)15日の日曜日は、風があまりなく、湿度は少しありましたが、見つけることができました。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |
 | |
2時58分から2分間かけて、カノープスの動きを線にしたものです。右下がりの曲線なので、もう南中をすぎたことがわかります。露出は2秒ほどで、連写したものをつなげています。少し左上(東より)にあるのが「ほ座」のユプシロン星1.8等です。「ほ座」なんてあまりなじみがない星座ですが「ニセ十字」とよばれる星の2つの星が入っている星座が、ほ座です。 | |
 |
 | |
2020年11月14日(土) 月齢28の月と金星・スピカ なかなか見ることができない月齢28の細い細い月。向きが三日月の逆ですね。 今朝の夜明け直前の東の空です。月は光っている方の反対側の形もうっすら見えています。これは一度地球に当たった太陽の光が地球に反射して月の暗い部分にも当たってその形を映し出している「地球照」という現象です。 月のそばには水星、右上には明るい金星とその右下にスピカも見えています。すばらしいコラボレーションですね。 地平線の少し下には太陽があり、太陽が出れば明るさに負けてこれらは見えなくなってしまいます。 明日15日(日)は新月。 来週からは今度は夕方の西の空で少しずつふくらんでいく月を見ることができます。 三日月は17日(火)。太陽を追いかけるように18時頃には沈んでしまうので日没(16:33)前後に忘れずに西の空を見上げてみましょう。 上石神井近辺では、25日(水)頃には太陽がちょうど富士山の頂上付近に沈んでいく「ダイヤモンド富士」も見られるはず。しばらく空から目が離せませんね。 (画像と情報:隊員のGさん) |
 |  |
 |  |
2020年11月13日(金) プールサイドの日だまりで② いつ見てもなごみます。カタバミとヤマトシジミ。(左上) ハキダメギクと名付けられ同情されるのはとても愛らしいから!(右上) ヨメナにおとずれたキンケハラナガツチバチ(左下) ヒメアカタテハ(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月12日(木) おしりのブラシがおもしろいですね ウリ科の植物を育てていた中庭でワタヘリクロノメイガを見つけました。 | |
 |  |
 |  |
冬はそっとしておいてね! 作業中に鉢(はち)をずらしていたらまたまたカナヘビに会いました。 今日は小さなカナヘビも! なんだか赤い虫もいる!! 見つかりましたか?(左上) 大きい方のカナヘビ、作業手袋の上にのってもらいました。(右上) (季節探しをしていた数名の四年生と観察ができました。) 近くで撮れなかったのですが赤い虫はカメムシの仲間アカシマサシガメ。 ヤスデ類などを食べるそうです。(左下) 3匹並んで記念ショット。すばしっこいカナヘビも、寒空の下ではしぶしぶ?撮影に協力してくれました。その後は3匹にはたっぷりの落ち葉をかけましたが、また鉢の下にもぐっているかもしれません。(右下) ※カナヘビは冬眠する生き物です。見つけても冬の飼育はとてもむずかしいそうです。そっと観察させてもらいましょう。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月11日(水) プールサイドの日だまりで プールで羽化殻(うかがら)を見つけました。成虫で越冬するイトトンボの仲間ではなく、ヤンマ科のトンボのもののようでした。(左上) 満開のヨメナは、貴重な蜜源(みつげん)となっています。 オオチャバネセセリ(右上) ヤマトシジミ(左下) ミツバチ(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月10日(火) この花がさくとよいことがある!? ほとんどのトンボが一年一世代と言って一年で一生を終えます。アカネ属のトンボも卵を残す、大切な時期となっています。(左上) チャバネアオカメムシ。黄緑色ではないのは越冬(えっとう)型だから。実をつけたヘクソカズラにいました。(右上) ヨメナに訪れたヤマトシジミ。羽化する時期によって、低温期型と高温期型があり、はねのちがいが見られるそうです。(左下) 昔の中国では、めったに花が咲かないと思われていたので、花が咲くとよい事があると信じられ、そこから吉祥草(キチジョウソウ)の名前がついたそうです。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月9日(月) 秋から冬へ テングのうちわ、ヤツデの花が咲きはじめています。花の蜜(みつ)を吸いに小さな虫達があつまります。(左上) 鉢(はち)を整とんしてたら、カナヘビがいました。 『冬眠するところなの、じゃましないで。』って顔されてしまいました。了解ですっ!(右上) モッコク(東門花だん)の赤い実の中には赤い種があります。どんな野鳥がやってくるのか、楽しみです。(左下) キハラゴマダラヒトリの幼虫と思われます。クワなどを食草として、サナギになる前に一部の毛が落ち、その毛を使ってマユを作るのだそうです。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
 |  |
2020年11月7日(土) 野川公園で秋探し リンドウ。根は生薬(しょうやく)として使われているようです。(左上) マユミの木にキバラヘリカメムシがいました。(右上) ミナミアオカメムシの幼虫。成虫になると緑色の一色になります。(左中) コバネイナゴ。ついつい子どもの頃に田舎(いなか)から佃煮(つくだに)になったのが届いていたのを思い出します・・・(右中) ムサシアブミの実。トウモロコシみたいなつぶがビッシリ。これから真っ赤になっていきます。(左下) カルガモものんびり散歩中。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年11月6日(金) 東門 ハナミズキだより ハナミズキの真っ赤な実(左)を食べにさまざまな野鳥が訪れています。 そのハナミズキの落ち葉に、ピッタリくっついていたカタツムリを2匹も見つけました。(右) しばらくするとカラから出てきましたが、ちょっと、ねぼけまなこ?起こしちゃたみたい、ごめんね。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月5日(木) 秋の日差しの中で② 小さいのにパッと目に飛び込んでくるナナホシテントウは『食べても苦いです』とアピールするための体色だそうですね。(左上) カタバミの蜜(みつ)を吸いにやってくるヤマトシジミ。(右上) カマキリは春から秋にかけて活動し、だいたい半年くらいの寿命。たくさんの宿題をやり終えたような感じがしました。(左下) 満開のヨメナにおとずれたのはキゴシハナアブ。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月4日(水) 秋の日差しの中で 太陽光が横方向となる秋の日差しはまぶしいですね。 上小のバラは6月頃と10月あたりからの2度咲きです。(左上) クビキリギス、茶色の成虫。緑色だと口のあたりは赤色ですがオレンジ色でした。(右上) ホトトギスは花の下に距(キョ)と言う蜜(みつ)をためている3つのコブがあり、ミツバチが夢中になっています。(左下) ホソヒラタアブ。幼虫はテントウ虫と同じく、アブラムシを食べるそうです。花から花へと飛んでいます。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年11月2日(月) この色、見て見て!! 羽化したてのヤマトシジミを見つけました。(左上)カタバミ(幼虫の食草)の小さなしげみから出てきました。(右上の写真は作業用手袋の指先にのってくれたところ) 翅(はね)がまだピンとせず、やわらかい。 水路からピョンっととびだしたのは、くっきりとマダラ模様のアマガエル。(左下) 落ち葉(イチジク)にジャンプ!(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年11月1日(日) クイズ 何羽いるでしょう? 足立生物園(竹の塚)に行った帰り、団地横の電線と木々の一帯にヒヨドリ(ムクドリ?)の大群がいて、目が回るほど飛び交っていました。ジュニア隊員Nの説明では、寝床を探しているらしいですが、なかなか決まらないのか、何度も何度も集まり直していました。習性を調べてみるのも、面白そうですね。 (画像と情報提供:N君パパ) ★すごい数ですね。ぱっと見てどのくらいか予想してみましょう。(時間のある人、画面を拡大して電線にとまっている鳥だけでも数えてみてはどうでしょう。)※私は数えましたよ! |
 |  |
2020年10月31日(土) 立野公園に行ってきました 立野公園に、遊びに行きました。池で遊んでいたら、カエルがいました。兄に聞いてみるとヒキガエルだそうです。(左) (画像と情報提供:4年生隊員のS君) 立野公園でモノサシトンボを捕まえました。(右)トンボ池でも飛んでいました。 (画像と情報提供:6年生隊員のN君) ★大きなヒキガエルを見つけましたね!小さなオタマジャクシからここまで育つのにどのくらいかかるのでしょう。そろそろ冬眠の準備かな。次に会えるのは何月でしょう。 ★モノサシトンボ。たしかに腹の線がモノサシのめもりみたいだね。成虫で冬ごしするトンボですね。トンボ池でも見たとの情報だから次の観察会でみんなも見られるといいね。 | |
 |  |
2020年10月30日(金) ドラキュラ参上! 明日はハロウィンですね、ドラキュラのマントのような翅(はね)を持つスズメガの仲間が訪れていたんですよ。チョウや他のガとちがって、高速で飛ぶそうです。さわっても、毒はありません。 (左)ふと視線を感じ、その先にはっ!!・・・こんなにスゴイ目力はなかなかありません。(数匹の幼虫もいた事もありセスジスズメと思われます) (右)SF映画のワンシーン・・・ではなくて校舎の外壁でのショット!(シモフリスズメのような感じです) (学校敷地内にて9月頃撮影・画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月29日(木) 今日は十三夜 またしてもっ!先をこされてしまったイチジク(左)ですが、見えているのは『花』の部分である事をご存知でしたか? 花を包み込む形で、実になるんですね。実の中では、白くて小さな花びらのない花がそれぞれ実をつけます。口の中で感じられるツブツブは花の後の痩果(そうか)と呼ばれる実なのだそうです。だから、一つの実の中でたくさん花をつけて実になって、そのたくさんの実をいただいているという、文にすると、ややこしいけどとても美味しい果実。 今日は十三夜、中国の神話ではヒキガエルとなった女性が、月の中に住んでいると言うお話があるのだそうです。ちなみに上小のアマガエルは、アシタバに住んでいます。(右) (トンボ池周辺にて・画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月28日(水) 農家さんの味方です イトトンボのなかま(左)とナナホシテントウ(右)。どちらもみんなの人気者。 そして、どちらも肉食性。農家さんが困ってしまう害虫をおいしくいただいてくれます。 (トンボ池周辺にて・画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月27日(火) パンチのきいたにおい イチョウは恐竜時代からあったそうですね。 イチョウの実、ぎんなんのニオイは恐竜を引き寄せて、食べてもらうためのイチョウの作戦だったようです。それにしても、パンチのきいたニオイです。(左) アオモンツノカメムシの幼虫(右) カメムシもニオイがありますね。いやがられることが多いのですが、実は香水(こうすい)に欠かせない成分を持っていて実際に使われているそうですよ。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月26日(月) 赤ジソ色!? ホトトギスを食草とするルリタテハの幼虫を見つけました。(左) ・・・卵やさなぎは、ツマグロヒョウモンのさなぎのように『光』が見られるそうですよ。 枯れてきた赤ジソを抜いていたらカマキリに会いました。(右) ・・・赤ジソ色だっ!って思ったのは気のせいかな? (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月25日(日) 学校の外にも自然がいっぱい! 写真は、石神井川沿いで見つけた植物です。 左上の写真はチヂミザサというイネ科の植物です。葉がササ(笹)に似ていますが、ちぢんだようになっているためチヂミザサというそうです。 右上の写真は、マメアサガオという植物のタネです。帰化植物(外国から持ち込まれた植物)で、小さなアサガオのような花を咲かせます。タネもアサガオにそっくりですね。 左下の写真はシャクチリソバという植物の花です。これも帰化植物で、薬にするために外国から持ち込まれ、現在では道端や草原に野生化しています。ソバの仲間の植物ですが、種子は食用にならないそうです。 右下の写真は、ノブドウの実です。もともと実は白い色をしています。虫が寄生すると青色や紫色に美しく色づくとされていますが、実際のところは詳しくわかっていないようです。ためしに青や紫に色づいた実を7個ほど開いて見ましたが、ちゃんと種子が成長していて、虫らしきものが入っているものはありませんでした。 (画像と情報提供:田中つとむ) |
 |  |
 |  |
2020年10月22日(木) ホトトギス満開のトンボ池で コガネムシの仲間、アオドウガネがいました。(左上) 西洋ミツバチのようです。・・・ホトトギスの蜜に夢中です。(右上) ヒメセマダライエバエのオス・・・パッと目をひく、楽しい模様です。(左下) ボトンって何か落ちてきた!・・・見てみるとアマガエルでした。新しい登場の仕方⁉(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月21日(水) トンボ池、色、いろいろ チャバネアオカメムシの幼虫(左上)・・・成虫になると、まったく違う色。 ツマグロヒョウモンがきていました。左上のハナバエ一族も、毎日きています。(右上) 光のかげんでグリーンが入りましたが白に模様の入った小さなガ、クワノメイガ。(左下) ・・・幼虫の食草はクワ。 しばらく顔を出さないなぁと思ったらあらら! ・・・マダラ模様になっていました!茂みの中で過ごしていたようです。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月20日(火) 変 身 ! 昨日観察したアゲハチョウの幼虫が、終齢幼虫へと変身していました!(左) プールに遊びに来ていたハクセキレイ。なんだか、ステキな予感がします。(右) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月19日(月) うつりゆく色 10月6日に紹介しているアゲハの幼虫の白いところがミント色になっていました。 順調に少しずつ成長しているようです。(左) 10月8日に紹介しているツマグロヒョウモンのサナギの金色のツブツブがメタルブルーに!!とてもきれい。(右) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月16日(金) 久々の気持ちのよい晴れ間・トンボ池にて アカトンボのなかま・・・カメラ目線がかわいいです。(左上) ナナホシテントウを見つけました。(右上) ツマグロキンバエはよく観察できます。 ・・・食べものや汚物(おぶつ)には、たからず、花のみつをすう小さなハエ。(左下) 秋晴れ満喫(まんきつ)中です。・・・アマガエル。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月15日(木) トンボ池ものがたり〜 ①はげしくケンカをするアリ達に出会ってしまったのは、ナミテントウの幼虫。 ②「こりゃたまらん!」と退散(たいさん)です。 ③「いつになったら翅(はね)が出てくるのかしら?」 キアゲハの幼虫が、おとずれたガにそうだんしているよう。 ④「よく食べ、よくねることです。」とアマガエルがそっとアドバイス。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月14日(水) トンボ池の小さな住人たち クサギカメムシ・・・こまかいもようが楽しいです。(左上) シロモンノメイガ・・・かわいいもようですねっ!(右上) イトトンボのなかま・・ネットが気にいったのかな?(左下) アマガエル・・・アシタバが、とてもお気に入り。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月13日(火) チョウの庭の生き物たち 百日草のみつを吸いにやってきたよ・・・モンシロチョウ(左上) うしろすがたなんですけど・・・ヒメアカボシテントウ(かな?)(右上) 白蜘蛛(クモ)っているんですね・・・アズチグモ(左下) 日差しにウットリ?・・・アマガエル(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月12日(月) トンボ池の田んぼで育った稲(イネ)を職員室前と、受け付けに飾っています。(上2枚) 余った稲の葉で、三つ編みをしながら、ミニリースを作りました。(左下) かざりはハナミズキの赤い実と椿(ツバキ)の種と、その種をつつんでいた殻(から)です。 帰り道で拾った葉っぱはハロウィンに向けて、オバケにしました。 秋の夜長の工作にいかがでしょうか^ ^ そして、お花は来年になりますが、観察会で時間切れになってしまってできなかった「秋の七草」の一つオミナエシの植え付けも、日当たりの良さそうな三ヶ所に今日植え付けました。探してみて下さいね。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月12日(月) 観察会、楽しかったですね! 今日もアマガエル(フフッ、なにかな?目の下に赤い虫がついてます)をはじめ、(左上) 同じく昨日の観察会で人気者だったクビキリギスが顔を出し、(右上) たくさんのチョウ(写真はキアゲハ)の幼虫が元気に成長しています。(左下) ヤブランのとなりでオニタビラコを見つけました。 名前のいんしょうとちがって、かわいいお花です。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月11日(日) 秋の色いろいろ イチジクが実りました。中はきれいなルビー色。 え、イチジク食べたことない?・・・この秋はぜひ試してみよう。(左上) ジュズ玉がいっぱい取れました。糸でつないでアクセサリーを作ろう!(右上) 秋の陽をあびてツマグロヒョウモン(チョウ)の幼虫のお散歩。 黒とオレンジが10月っぽいでしょ。トゲトゲは実はやわらかい。毒もないよ。(左下) コムラサキシキブの実。鳥たちの好物。どんな鳥が食べに来るのかな。(右下) (トンボ池観察会より) | |
 |  |
 |  |
2020年10月9日(金) 〜雨の日たんけん隊の巻〜 校庭で色々な葉っぱや小枝を拾えました。 マメガキは、おっ!っとうれしいおとしもの。(左上) 洗って、紙に広げるとすぐにかわくので糸をとおして〜^ ^ 風が入ると小さな秋がユラユラ、クルクル。(右上) ちなみに上のブドウは宝の地図をかくのに実をとった後のヨウシュヤマゴボウで、そのタネが目になってる下のウサギはエノコログサ(ねこじゃらし)で作ってます。 拾ったクワなどの大きめの葉っぱもは、持ち帰り。 コースターにして、1〜2日は楽しめます^ ^(左下) なぞのキノコはこうして保護中。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年10月8日(木) 宝の地図 校庭で発見されたなぞのキノコ(10月6日の「見つけたよ!」コーナー参照) 右は発見場所の絵地図です。どこだかわかるかな?(「らせんとうげ」ってどこだ!?), ※見つけても、さわらずにそっとやさしく観察してくださいね。 雨にぬれて、赤くつややかに光るすがたが美しいですね。 現在、国立科学博物館に写真を送って、調べてもらっています。 | |
 |  |
 |  |
2020年10月8日(木) じっと雨宿り・・・ 園芸植物※として私達を楽しませてくれる上小のアブチロンは、春から秋にかけて気ままに咲き、雨の日も陽気な姿を見せてくれています。(左上) 四年生が発見してくれました!梅の木にツマグロヒョウモンのサナギです。(近くにはの食草のスミレがあります)金色のつぶつぶがステキ!(右上) 桜の木に雨宿りしていたカマドウマ。(左下) 漢字で書くと『 竈馬 』カッコイイ! 雨の日でもツマグロオオヨコバイ(通称バナナ虫)にはよく会えます。(右下) ※園芸植物とは、観賞するために人間が気持ちを込めて作った植物の事です。全てではないのですが、虫達はこの園芸植物を好んでやってきません。なので、トンボ池で観察できる植物は花屋さんのものとは違います( ◠‿◠ ) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月7日(水) トンボ池事件簿〜 ❶ふと見上げると・・・うわっわっわ〜っっ、イチジクが何者かにやられてる〜っ ❷『真下にいた、あなたのしわざですか‼』 それどころじゃないわっ! とアゲハの幼虫。(ふむ。そうだろうね、、) ❸『かくれているつもりの君ですか‼』 ぼ、ぼくは知りませんっ!!とアマガエル。(あやしい。本当は犯人を知っているハズ) ❹きっとイチジクは、空を自由に飛ぶつぶらな瞳の持ち主によってやられたんだと思われます。 おしまいの口直しはシュウカイドウ。7月から10月中旬ごろまで咲くお花。 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月6日(火) ちょっぴりすずしくなってきた校庭で 三角葉っぱのイシミカワ。青い実をつけました。(左上) トンボ池のミカンの木にアゲハチョウの幼虫がいました。(右上) 二匹いました!アマガエル。トンボ池のアシタバ、お気に入りのようです。(左下) カナヘビのようです。とてもすばしっこい。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月5日(月) キンモクセイ満開 ヤマイモの赤ちゃん、ムカゴができています。(左上) 今日も元気です!トンボ池のアマガエル。(右上) ヒメジャノメ。幼虫はススキの葉などを食べるそうです。 もしかしたら、見つけられるかも。(左下) あちらこちらで咲いているキンモクセイ。良い香りをたくさん届けてくれています。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年10月1日(木) 秋の色、見っけ!⑤ とんぼ池のススキ。今日は中秋の名月ですね。(左上) カラスウリ。夜に咲くモシャモシャの白い花を見たことありますか?(右上) マルバルコウソウ。いろいろな場所で咲いています。(左下) ノゲシ。春あたりから観察できましたがもうそろそろおしまいです。(右下) | |
 |  |
 |  |
アシタバレストランのお客様しょうかい アシタバの花は3~4年すると見られ、花の後はタネをこぼして、かれるのだそうです。 トンボ池でアシタバの花に集まってきたのは・・・ ノイエバエ(左上) ヒメホシカメムシ(右上) クロウリハムシ(左下) そして、視線を下に下ろすとアマガエルが!!(右下) 毎回、登場の仕方がかわいすぎますっっ!!! (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月30日(水) 秋の色、見っけ!④ 開花期の長いムクゲ(上小では7月〜10月くらい)。今日はハエが遊びにきてました。(左上) 胸部に黒い線が長くのびているのがアキアカネなのだそうです。(右上) ヒメアカタテハ。しょっかくの先が白くてオシャレです。タテハチョウ科の共通ポイント。(左下) マメガキ。霜にあたって黒ムラサキ色になる頃が、おいしいのだそうです。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月29日(火) 秋の色、見っけ!③ トンボ池のイチジク。ほんのり色がついてきました。(左上) 初夏から秋にかけて咲くヒメジオン。さまざまな虫が蜜(みつ)をもらいにやってきます。(右上) 草取りをしたらジグモの巣がたくさんありました。(左下) そこには、ヤモリもいました。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月28日(月) 秋の色、見っけ!② オンブバッタ。すごしていた所によって色がかわるようですが、出会ったいきさつを聞いてみたいものです。(左上) たくさんふまれても、へっちゃら!そのかわりに種をはこんでね、っとアピールするオオバコは、薬草としてりようされています。(右上) ヤブミョウガの白い花のあとは青い実。うしろで気ままに咲いているのはチョウが好きなメドーセージ。(左下) トンボ池のヨメナの花。ほっとする可愛らしさ。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月23日(水) トンボ池のお彼岸 トンボ池のヒガンバナも咲きはじめました。(左上) 校庭の南がわで、土いじりをしていたらアマガエルがひょっこり出てきました。(右上) モモスズメの幼虫、サクラの葉を食べて大きくなったようです。毒はないのでさわっても大丈夫です。(左下) トンボ池ではカクトラノオ、チカラシバも見ごろです。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
2020年9月16日(水) 秋の色、見っけ!① 東門の花だんにあるハナミズキの実が葉とともに、赤くそまってきました。(左写真) ヒヨドリなどの野鳥が食べにやってくるそうです。 校舎うらには、メジロなどの鳥たちが食べにおとずれるコムラサキシキブも見ごろをむかえています。(右写真) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月14日(月) 木のかんさつ 東門を入って見上げると、ピンク色のサルスベリがさいています。 長い期間(7月ごろから9月ごろまで)花を楽しませてくれることから百日紅(ひゃくじつこう)と言う名前ももっているそうです。 花にはハチも大好きなみつを持っているので、注意してかんさつしてみると木のかわ(樹皮=じゅひ )がはがれていました。これは、元気に成長しているしるしです。 ほかにもこのように大きくなる木を、学校でかんさつすることができます。 ユーカリ(校庭の西がわ)・・・とても大きく成長した木からダイナミックに、かわがはがれおちます。はがれておちた後、しばらくは木の色は白く、目立ちます。 プラタナス(校庭の西がわ)・・・大きな葉がとくちょうのプラタナスのかわは少しずつはがれます。 写真左上・サルスベリ・・・見あげたところ。 右上・はがれてたあとはツルツル、スベスベ、うらやましい。 左下・ユーカリ・・・はがれる音をきいてみたい。 右下・プラタナス・・・宝の地図。。。だと良い^ ^ (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月11日(金) 校庭のカラフルさんたち③ トンボ池にて・・・星の花、アサザがたくさんふえました。(左上) 校庭の体育倉庫、のき下にて ・・・現場は夏からフェンス工事で入れません。アシナガバチだったようです。(右上) 西門付近にて ・・・カリン。ジュースにして飲んでみたいですね!(左下) 東門コンクリート通路のわきにて ・・・ツマグロヒョウモンの幼虫。食草のスミレを探していたのでしょうか? (付近のスミレはなくなってしまったので裏の畑へ移動してもらいました。)(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月10日(木) 校庭のカラフルさんたち② トンボ池バタフライガーデンにてクロウリハムシ ・・・特にカラスウリ類の葉を好むそうです。(左上) 校舎裏の畑にてセセリチョウ ・・・せせる(つつく)ようにミツを吸うところから名付けられたそうです。(右上) 校舎裏の畑にてショウリョウバッタ ・・・漢字で書くと『精霊飛蝗』(左下) 校舎裏の畑にてツマグロヒョウモン ・・・こちらはオス。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月9日(水) 校庭のカラフルさんたち 東門の花だんから ・・・アジサイの葉にキマダラカメムシの幼虫。(左上) ヒャクニチソウが好きみたい ・・・ツマグロヒョウモン、これはメス。(はじの黒色がメスのしるし)(右上) トンボ池のバタフライエリアからランタナのみつをいただくのは ・・・白いしるしがなかったのでキチョウかな?(左下) 校舎裏のしげみからヤブガラシなどを食べて育つトビイロトラガ ・・・強そうだけど毒なし。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月8日(火) 残暑が続きますが花や虫は元気です! 東門の花だんにてシジミチョウ ・・・シジミ貝のように小さなかわいいチョウ。(左上) 校庭の西側、モミジ ・・・プロペラのじゅんび、進んでます。(右上) 校庭の西側、ザクロ ・・・これからもっと、赤くなるところ。(左下) 校舎裏のアシタバ ・・・キアゲハの幼虫。みどり色が出てくる前は、白いのですね。(右下) (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月7日(月) 雨上がりの校庭で見つけたよ 雨上がりのアマガエル ・・・職員室前の草のしげみ中から トンボ池のまわりで咲く ・・・ホトトギス 校舎うら、クワの赤い実・ ・・黒くなったら食べごろ。 木にからまったヘクソカズラからスズメガの幼虫 ・・・ホシホウジャクかな? (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 |  |
 |  |
2020年9月1日(火) クワの葉で見つけたよ クワの葉の裏で、クサギカメムシとツマグロオオヨコバイ(通称バナナ虫)が過ごしていましたよ。 上左 クサギカメムシ 上右 クサギカメムシの幼虫 下左 ツマグロオオヨコバイの成虫(右)と幼虫(左) 下右 ツマグロオオヨコバイの抜け殻 (画像と情報提供:スタッフのSさん) | |
 | |
2020年8月28日(金) 咲いてます!! トンボ池で初めてのハスの花が咲きました。 (画像と情報:スタッフのSさんより) |
 |  |  |
2020年8月24日(月) ハスがもうすぐ咲きます! 始業式の24日に咲くかと思われましたが、この日は咲きませんでした。今週中には咲くと思われます。 (情報と画像:スタッフのくるしまパパ・おおさわさん・いとうママより) | ||
 | |
 | |
2020年8月17日(月) 今日の雲 毎日暑いですね。毎年・毎日記録的暑さが昇っているような気がしています。 数分前(17日18:40頃)に見えた雲です。 下から夕焼けが当たり、上がぼやけている雲を初めて見ました。よくあることなのでしょうか。ちょっと嬉しくてメールしました。 東公園から石神井公園方面に見上げた所です。 (画像と情報:スタッフのKさん) ※積乱雲の上部が平らにおしつぶされたような形に広がった「かなとこ雲」でしょうか。ちょうど夕陽が当たってきれいな写真ですね~。昼間は強烈な暑さで空など見上げる元気もないですが、午後になるとこのように積乱雲が発達して夕立が来たり、その後みごとな虹が出たり・・・夏は空の観察も面白いですね。 |
 | |
2020年8月5日(水) セミの羽化を見に行こう! セミの羽化がピークをむかえています。今年は例年行っている夜の観察会は行いませんが、ぜひご家族で観察に行ってみましょう。観察会をする善福寺公園や関公園はもちろん、近くの公園や憩いの森などでも見つけることはできるはずです。 ぬけがらを集めて、種類を調べたり、ほかにも夜に咲く花、オシロイバナの香りを楽しんだり、カラスウリのレースのような美しい花を探したり・・・夜のお散歩はきっと楽しいはずです。 そうそう、空を見上げれば大きな月(昨日が満月でしたね)も見られるし、木星(-2.6等)と土星(0.4等)が並ぶすがたにも気が付くはず。 また、5日はISS(国際宇宙ステーション)が大きな流れ星のようにゆっくりと空を横切る様子もよい条件で見られます。 19:41~19:47西北西→南西→南南東 高度51度 明るさ-3.2等 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |
 | |
2020年7月30日(木) アライグマがいました! 30日の夜に上石神井でアライグマを見ました。 ペットから野生化してしまったのか、とっても太っていて近くでも逃げませんでした。 写真は撮れませんでしたが、数日前には憩いの森にたぬきもいたようです。 (画像と情報:6年生隊員のRさん) ※これまでもタヌキやハクビシンの情報はありました。アライグマも都内で増えているという話は聞いていましたが、上石神井でのアライグマ情報は探検隊では初めてです。 報告ではある程度人なれしていたようですが、それにしてもうまく撮れています。まさに「ラスカル」ですね! |
 |  |  |  |
2020年7月24日(金) トンボ池に子ども達が帰ってきました~校庭開放再開~ 久しぶりに休みの日に校庭開放が出来ました。まだ児童と家族だけですが。 トンボ池での写真です。 (左から順に) 子どもが蚊(か)の餌食(えじき)になりながら、持っていた棒にとまらせたシオカラトンボ シオカラトンボと赤いトンボ 鮮やかな赤色のトンボ アブのような虫がカメムシをおさえこんでいたところ (情報と画像:校庭開放指導員のIさん) ようやくお休みの日の校庭開放が段階的に再開されたようです。 さっそくトンボ池で生き物と遊ぶ子ども達の様子と、そこで見られた生き物の写真を送っていただきました。ありがとうございます。ブルーのトンボはシオカラトンボのオスでしょうか。全身あざやかな赤色のトンボはショウジョウトンボですね。アブがカメムシをおさえこんだ瞬間はまさに自然のドラマですね。 | |||
 |  |
2020年7月16日(木) プールになぞのオタマ発見! 今年の夏は、残念ながらプールを使った水泳の授業はありません。例年なら今ごろ子ども達の歓声(かんせい)がひびいているはずのプールをのぞいてみたところ、3月~5月頃トンボ池で見ることのできるヒキガエルの黒いオタマジャクシとは明らかにちがうオタマジャクシがたくさん泳いでいるのを見つけました。 ※連絡を受けてさっそく探検隊のスタッフがかけつけて調べてみると、どうやらアマガエルのオタマジャクシのようです。アマガエルは田んぼや草原などで見かける緑色の小さなカエル。石神井川沿いに水田が広がっていた昭和30年代までは上石神井でも普通に見ることができた日本在来のカエルです。「練馬区の動物について」(昭和38年練馬区教育委員会編)によると「比較的多くいる種類である。雨天の時などに、よく見かける」と記録されています。石神井川の河川改修と水田の埋め立てで姿を消していましたが、近年進められている石神井川沿いの緑地再整備などに伴い、復活が期待される生き物です。 (情報:隊員のSさん 画像:スタッフのつとむさん) | |
 | |
2020年7月8日(水) 校舎内にタカのなかま「ツミ」が侵入!! 8日(水)の午後の2時過ぎ、職員室前のろうかに大きなタカが入ってきて図工室入り口のドアの上のガラスにぶつかりました。その後開いていたろうかの窓から職員室に飛び込み、職員室内を飛び回りました。職員室にいた先生が窓から逃がそうとしたのですが、ガラス窓にぶつかるなどして、足でつかんでいたエサ(小鳥)を取り落とし、今度は図工室へ。(上の写真は図工室のたなにとまったところ)その後しばらくして、ようやく図工室の窓から外へと飛んで行きました。たまたま職員室にいたわずかな先生しか目撃できなかったのですが、もっとたくさんの方に見ていただきたい衝撃的なできごとでした。 ※後から情報を聞いて、土曜日にスタッフが学校に伺い、一部始終を目撃されたというK先生より詳しい様子を教えていただきました。写真で見る限りこの鳥は猛禽類(もうきんるい=ワシ・タカなどのなかま)の一種の「ツミ」ではないかと思われます。 学校では時々窓ガラスに野鳥がぶつかってしまう事故はありますが、校舎内に鳥が、しかも東京ではめずらしい猛禽類が飛び込んでくるとは、本当にびっくりなニュースです。コロナ対策であちこちの窓やドアを開放していることとも関係あるのかもしれませんが、いずれにせよ上石神井にツミが生息しているということがわかりました。 このような猛禽類は、食べるものと食べられるものの関係=食物連鎖(しょくもつれんさ)の「ピラミッド」の頂点と言われ、エサになる生き物がたくさんいる豊かな自然環境があって、初めて生息することができる生き物です。それが学校内で見られるなんて本当にすごいことですね。 (画像と情報:隊員のSさん・K先生) |
 |  |
 |  |
2020年6月20日(土) トンボのやじろべえもあるよ~ トンボ池のようすを見てきました。稲も雑草もすくすく育っています。ショウジョウトンボやオオシオカラトンボが来ていたり、ムサラキツユクサの花が咲いていたりしましたよ。草ぬきもしておきました。 職員室前のヤゴの展示コーナーに、図工の先生が紙で作ったトンボのやじろべえが展示されていたので、写真撮ってきました。 (画像と情報提供 スタッフのくるしまパパ) ★雨の日には水分をたっぷり吸いこみ、晴れた日には太陽の日差しをたっぷりあびて・・・この季節、植物はほんとすくすく成長していきますね。みんなでやっても大変な草ぬき、一人でお疲れ様でした。顔まで真っ赤なショウジョウトンボ、オスはブルーがあざやかなオオシオカラトンボ、今年も来ているのですね。 ヤゴ展示コーナーのトンボのやじろべえ。いつの間に!?・・・よく見るとそばに「作りたい人は図工の先生に言ってね!」のポップが。さっそく先生がタイアップして下さったのですね。ありがとうございます!! | |
 | |
 |  |
 |  |
2020年6月16日(火) アオダイショウ発見! 先週、学童クラブの3年生のお友達から「校庭で大きなヘビを見た」という情報がとどいていました。そしてこの日ついに学校のしき地内でそれらしきヘビを発見。連絡を受けた隊のスタッフがかけつけて、アオダイショウであることを確認。子ども達の下校後でしたが、学童クラブの先生と子ども達がさっそく観察に来てくれました。 探検隊隊長でもある井口校長先生もみずから手に持って観察、居合わせた先生方も子ども達に見せるために写真に撮ったり、次々と手に持ってつぶらなひとみ(写真上)を確認したりしていました。 アオダイショウは、毒(どく)のないおとなしいヘビで、ネズミなどを食べてくれるので家のまもり神として昔から人々に大切にされてきたヘビです。上石神井では今でも時々すがたを見ることがありますが、学校のしき地内で見ることは今までほとんどありませんでした。でもいたんですね。 それにしてもヘビは「生態系(せいたいけい)のピラミッドの頂点(ちょうてん)」とよばれ、豊かな自然がないところでは生きていくことができない生物です。上石神井にいるということは、ふだん、どんなものをエサにしているのでしょう。考えてみるとおもしろいですね。 じっくり観察した後、校長先生が教育委員会に確認の上、再び校内の子ども達が直接出会うことの少ないと思われる場所に放しました。これからも上小の守り神として、長生きしてくれるといいなと思います。 おとなりの中学でも先週、アオダイショウの子どもが見つかっていますし、石神井川では泳いでいる姿がよく見られます。ヘビはちょっとこわいし、苦手、という人もいると思いますが、もし出会ってもむやみに恐れず、そっと見守ってみんなで大切にしてあげてくださいね。 (情報:スタッフのしぶやさん 画像:スタッフのつとむさん) | |
 | |
 | |
2020年6月9日(火) モグラ発見!! 夕方、3年生の先生方との打ち合わせを終えて帰って庭に入ったら、通路のコンクリートの上に、はっているような姿勢でモグラが!はじめ、ネズミかと思ったのですが、手の形や短いしっぽからモグラだとわかりました。 短く、すごくやわらかい毛がビッシリと生えているのですね。さわり心地がとてもいいです。 (画像と情報:スタッフのつとむさんより) |
 | |
 | |
2020年6月8日(月) シマヘビ発見!! →アオダイショウの幼体? 今朝は、おとなりの中学でヘビを発見です^ ^ 南門、いどう式のバスケットゴールがならんでいるあたりにいたそうです。 残念ながら、この状態で死んでいました。 大人の指の太さまでいかず、だいたい、80センチ程だと思いますがまだ子供でしょうか? (画像と情報:スタッフのSさんより) ※シマヘビの生息情報は探検隊では、初めてです。調べてみると昭和30年代の終わり頃までは、練馬区でアオダイショウ以外にも、シマヘビ、マムシ、ヤマカガシ、ジムグリ、シロマダラなどのヘビがいたようです。(「練馬区の動物について」昭和38年練馬区教育委員会編)その後の60年で多くはぜつめつしてしまったと思われます。 ★発見当初、シマヘビではと思われたのですが、生息の可能性、からだのもようなどを考え合わせ、その後実物も確認した結果、アオダイショウの幼体(子ども)ではないかと思われます。 |
 | |
2020年6月8日(月) 花ざかりの〇〇〇ミをしらべてみよう この白い花の野草を知っていますか。ちょうど今花ざかりです。まとまってさいていると見ごたえがあります。 人家のかたすみに。空き地のはじっこに。日のあたらないうらにわに。いたるところに生えて花をさかせています。 そう、ちょっといやなにおいのある「ドクダミ」です。 花だん作りをやる人にとっては、根がのこっているとどこでも生えてくるので、なかなかのやっかいものです。でも反面、むかしから「医者いらず」の万能薬(ばんのうやく)としても大切に使われてきました。なににきく薬になるのか調べてみましょう。 葉をてんぷらにするとふしぎとにおいがきえておいしいのですが、あぶらいためにすると、あのにおいがしっかりのこるのはどうしてでしょうか。 さて、ここで「ドクダミクイズ!」です。 ★ドクダミ 四たくクイズ もんだい★ ア)一まいもない (えっそんな!) さあ、正かいはどれでしょうか。しらべてみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 | |
2020年6月5日(金) ギンヤンマが羽化しました!&カブトムシも・・・ 5月にもらったギンヤンマのヤゴが今日羽化(うか)しました。 メスで体長が12cmでした。(上の写真) そしてカブトムシも羽化のと中です。(下の写真) 土の上でさなぎになってしまったので、羽化した時に急いで蛹室(ようしつ)みたいに紙コップをかぶせました。どうなるか楽しみです。 (画像と情報提供 6年生隊員のN君) ※N君、情報ありがとう。今年第1号のギンヤンマの羽化報告なのでトップページでのしょうかいとしました。羽化したばかりの羽のかがやきがきれいですね!この羽化直後の状態を「テネラル」とよぶのだそうです。いまちょうど、プールから救出したヤゴを学校で希望者に配布中です。みなさんも飼育にちょうせんして、ギンヤンマの羽化を自分の目で観察してみましょう。 カブトムシの羽化も始まったのですね。トンボ池のクヌギの木にも今年もカブトムシがやって来るといいですね。 | |
 |
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月2日(火) プールのヤゴを救出しました ~ギンヤンマ683匹!~ 今年は残念ならが毎年行っていた3年生によるプールのヤゴ救出活動ができないことになってしまいました。しかし、先生方が「せめて教室でヤゴの飼育や観察にはとりくみたい。」と考えて下さり、先生方としぜん探検隊スタッフによるヤゴ救出活動が行われました。 ※今年は水泳指導は行われないことになりましたが、管理上一度水を抜いて清そうはしなければならないのだそうです。この時期に水をぬくと、羽化(うか)寸前まで育っているヤゴがみんな死んでします。 この日は、清そう作業に先立ち、水をほとんどぬいたプールに先生方やスタッフが入って、カゴやあみを使ってヤゴを救出しました。今年はすでにトンボになって飛び立っていったものもだいぶいたようでしたが、それでも東京ではめずらしいギンヤンマのヤゴが、過去最高の683匹も救出されました。ほかにもイトトンボやアカトンボ・シオカラトンボのなかまの小型のヤゴもいました。 ギンヤンマやイトトンボは草に卵を産むトンボなので、ふつう、学校のプールでは見ることができません。しかし、上小では毎年秋に3年生がプールに草を浮かべる活動に取り組んでいるおかげで見ることができるものです。 また秋に3年生が放流したクロメダカもたくさんの子どもを産んで大きく育っていたので、それらもすくい上げました。 ヤゴは3年生の教室で飼育するほか、職員室前でも展示します。また自宅での飼育を希望する子ども達にも配布される予定です。 クロメダカは教材として理科室で活用されます。 飼育しきれないものは、おとなりのトンボ池に引っ越ししてもらう予定です。 大きなギンヤンマのヤゴがトンボへと変身する羽化(うか)の様子は、一度見たら忘れられないすばらしい光景です。ヤゴの飼育観察を通して、一人でも多くの子どもたち&大人のみなさんがそれを実際に自分の目で見る体験をしてくれるとうれしいです。 (先生方6人・保護者とスタッフ21人・高校生以上のOB隊員6人:合計33人が参加)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |
2020年5月30日(土) しぜんいっぱいのトンボ池がみんなを待っています! いよいよ1日から学校が再開されます。 長いこと、子ども達が遊びに来ることのなかったトンボ池ですが、たくさんの生き物、自然が首を長くしてみんなを待っています。 緑色の小さなアマガエル。クワの木には黒く熟(じゅく)したあまいクワの実。チョウの庭ではミカンやサンショの葉にアゲハチョウが卵を産みに来ていました。 またみんなで観察を楽しみましょう。 ※トンボ池のまわりは「生き物のための庭」(=ビオトープ)です。生き物や植物はえんりょなくさわったり、手にとって観察してOK。ただし、つかまえて家に持ち帰ることはできません。ルールを守って自然となかよく遊びましょう。 | ||
 | |
2020年5月29日(金) ISS(国際宇宙ステーション)ふたたび! ブルーインパルスの飛行、見られましたか?すてきでしたね。西池袋で見ていました。やはりこんなにかっこいい飛行機は、戦争に使ってはいけない!と思いました。はきだす白いものは、飛行機ぐもではありませんでした。 雲との高さがまるでちがいました。けむりをはいているようでした。水蒸気(はいガス)を出しても、高さがひくいと、温度が高く、くもになりませんからね。さて、昼間はブルーインパルス、夜は ISSです。4月は、明け方のことが多く、なかなか見られなかったと思います。でも、これから6月にかけて、何回か宵(よい)の空に見えます。 つゆのはしりでくもりがちの天気が多いかもしれませんが、晴れ上がったらぜひ観察してみましょう。 今ばんから見えるようですよ。日によって見える方がく、時こく、明るさ、見やすさ、がちがうので、下をさんこうにしてください。 5月29日(金)21:43~21:44北西→北北西(途中で消える) 明るさマイナス1.5等 最大高度24度 北北西 見やすさ △(高さ少し低い) 5月30日(土)20:55~20:58北北西→北北東(途中できえる) 明るさマイナス2.1等 最大高度26度 北北東 見やすさ △(高さ少し低い) 6月1日(月)20:56~20:59 北西→北(空高くできえる) 明るさマイナス3.7等 最大高度70度 北 見やすさ◎(高さ十分 真上) 6月2日(火)20:08~20:13 北西 →北東 → 東 明るさマイナス2.9等 最大高度41度 北東 見やすさ◎(高さ十分) 6月3日(水)19:23~19:26 北→北北東→東 明るさマイナス2.1等 最大高度25度 北北東 見やすさ△(高さ少し低い) 6月3日(水)20:57~21:00西北西→西南西(途中できえる) 明るさマイナス2.4等 最大高度29度 西南西 見やすさ〇 (高さまずまず) 6月4日(木)20:09~20:14 北西→西南西→南南東 明るさマイナス3.4等 最大高度55度 西北西 見やすさ◎(高さ十分) 6月5日(金)19:24~19:28 北北西→東北東→南東 明るさマイナス3.7等最大高度72度東北東 見やすさ◎(高さ十分 真上) ★どうして? どうしてISSは夜中には見えないのかな? どうしてISSはふっときえてしまうことがあるのかな? ※ 情報は下のページをもとにしています。 |
 | |
2020年5月19日(火) 野鳥をさがそう!(先週は愛鳥週間でした) 都会にすんでいても、けっこういろいろな鳥がやってくるものです。最近は少し興味をもって近所にやってくる野鳥を観察しています。 もちろん探検隊の「春のいきものさがし鳥の部」は全クリしましたよ!! 朝、目立つのは、ヒヨドリ、オナガ、カラス。 ヒヨドリは歌がとても上手で、いろいろなさえずりをしています。 オナガは、近所の木のしげみの中に巣を作っているみたいで、小枝をくわえてその中入っていくところを見ました。カラスが近くを飛ぶと、群れがいっせいにギーギー鳴いて、けいかいしているみたいです。 野鳥は子育ての時期にあるみたいですが、スズメやムクドリ、メジロはどこにどんな巣をつくるのでしょうか?調べてみてください。 先週は、朝方ウグイスの声を、練馬のおとなり西東京市内で聞きました。すがたはざんねんながら見つけることはできませんでした。 なんでいつもこの時期にやってくるのでしょうか?今日は小雨の中、夕方にカッコウの声を聞いたので、自転車をとばし、近所の住宅のアンテナで鳴いているところをついにさつえいすることができました。写真のとおり、カッコウは、なんだかハトによくにています。 ここで「カッコウクイズ!」 ★もんだい★ カッコウはしたたかな(=ずるがしこい)鳥だとよくいわれます。 そのわけは次のうちどれでしょう? ア)ほかの鳥の作った巣をよこどりして、もらってしまうから イ)親鳥の運んできたヒナにあげるエサをよこどりするのがうまいから ウ)卵をかってにほかの鳥の巣にうみつけて、ひとまかせで子育てをまったくしないから 動画(→こちら)も見てください。手持ちのカメラでとったので、ちょいとぶれていますが、ふんいきはわかると思います。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |
 |  |
2020年5月18日(土) 稲がしっかり根付いていました 今日は自宅待機の日なので、トンボ池の様子を見てきました。 トンボ池の水位は大丈夫でした。(右写真) 先日田植えした稲もしっかり根付いていましたよ。(左写真) (画像と情報提供 探検隊スタッフのくるパパ) | |
 |  |
 |  |
2020年5月15日(金) ナガミヒナゲシの種を取り出してみよう 左上のオレンジ色の花。見たことのある人も多いのではないかと思います。きれいですね。でもこの花、元々は地中海沿岸地方からやってきたと言われる外来種「ナガミヒナゲシ」です。細長い実(ナガミ)ができるヒナゲシ(ケシという植物の一種)という意味です。今から40年くらい前に東京で発見されてからまたたく間に日本中に広がったと言われています。 人が植えたとは思えないような道路のすきまや空き地にもたくさん咲いていますよね。 どうやってこんなに増えたのでしょうか。人や車がたくさん通る道ぞいでは特にたくさん見かけます。この10年ほどはだれも植えていないのに、上小の校庭でもたくさん見られるようになりました。 ・・・その秘密をさぐるヒントがタネです。そろそろ花の後にタネができてきた季節ですからひとつみなさんの手で調べてみましょう。 公園や花だんの花は勝手に折り取ったりしてはいけませんが、これは人が育てているものではない雑草と考えてよいものなので、タネの入った実の部分(右上写真)を見つけて取ってきてみましょう。取ってくる時はビニル袋やびんなどを用意して、タネがこぼれないように気をつけます。よくじゅくしたタネはフタのような部分の下のすきまから出てきます(左下→の部分)。 うわぁ、小さい黒いつぶがいっぱい出てきました(右下写真)。このひとつぶひとつぶがタネです。いくつくらいあるのかな。これを数えるにはどんな方法があるでしょう。あまりに多いのでおよその数でよいですが、数え方をいろいろくふうして調べてみましょう。 わかったら、ぜひ探検隊まで教えてください。 ※「けしつぶほどの大きさ」という言葉がありますが、ケシのタネくらい小さいという意味です。ケシのなかまのタネはどれも小さいことで昔から知られていたのですね。 ※ケシのたね(けしつぶ)はたぶん、みなさんは食べたことがあるはずです。さてどんな食べ物に使われているでしょう? ヒント→たぶんパン屋さんにあるよ。 (画像と情報提供 探検隊事務局) ★ナガミヒナゲシのようにはんしょく力(なかまをふやす力)が強い外来種が一度持ち込まれると、その場所に昔から生えていた植物(ざいらい種)がへったり、ぜつめつしてしまったりすることがあります。 観察後のタネは地面にまかずに、標本として保存するか、確実に処分するようにしましょう。 | |
 | |
2020年5月9日(土) 西に沈む月と白い富士山 まだ満月を過ぎたばかりの月が朝早く西に沈んでいくところです。画面中央には富士山。今朝も真っ白でした。今朝の4:49です。 ※昨日、一昨日(満月)のきれいな月を見ましたか。満月は太陽の反対がわにあるので、太陽と反対に夜になるとのぼり、朝にしずんでいくことがよくわかる写真ですね。この季節、富士山はまだこんなに白いのですね。東京はいま、だいたい気温20度、湿度50%前後で一年でももっとも気持ちのよい過ごしやすい季節です。家に温度計や湿度計があったら、一日の変化をちょっと調べてみるのもいいですね。(4年生5月の理科の学習です)冬の間の暖房や夏の冷房の設定温度とくらべてみましょう。 (画像と情報:隊員のGママ) |
 |  |
2020年5月8日(金) 田んぼゾーンの田植えをしました 雑草取りと田植えをしてきました(30秒動画→こちら)スタッフ3人で作業をしました。 左の写真は、田植え後の田んぼゾーン奥側、右の写真はサンショについていたアゲハの幼虫 です。 とても良い天気で暑いくらいでしたよ。 ※例年だとこの時期の定例観察会の時にみんなでするトンボ池田んぼゾーンの田植え。今年は残念ですがスタッフだけで行いました。「田んぼ」は人間が作るものですが、トンボをはじめ多くの生き物にとって大切な「すみか」となっている自然です。上石神井にも60年ほど前まで石神井川ぞいにたくさんの田んぼがありましたが、今はまったくありません。探検隊ではトンボ池のわきに田んぼゾーンを作り、毎年田植えをすることで、ささやかですが、田んぼの自然の再生にとりくんでいます。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのくるパパ) | |
 |  |
2020年5月2日(土) ハナムグリとギンヤンマのヤゴ トンボ池のほとりのクヌギの木から樹液(じゅえき)が出て、そこにたくさんのシロテンハナムグリが集まってきていました。数えたら10匹以上いました!夏になったらもっといろいろな昆虫がこの樹液に集まってくるのでしょうか。楽しみです。 昨年の秋に3年生のみんなが産卵用の草などを入れてくれたプールの中もかくにんしてきました。大小さまざまな大きさのギンヤンマのヤゴがいました。もうすぐ羽化してトンボになりそうな大きさのものもいました。放流したクロメダカも数を増やして、むれを作って泳いでいました。 トンボ池の草のあたりでは、すでに羽化したイトトンボも飛んでいました。 (画像と情報提供 探検隊事務局) | |
 |  |
2020年5月1日(金) ふよう土ボックス修理完了! 今日、気になっていたふよう土ボックスのペンキぬりをやってきました。パイプの色もはげた所が目立っていたのでいっしょにぬっておきました。一応、完成しました。早くコロナによる規制が解除になって、探検隊活動したいですねー。ヤゴが気になります。 ・・・今日池を見にきていたスタッフのKさんとそんな話をしました。 中で菜の花ががんばって咲いていました。(右写真) ※だいぶいたんできていたトンボ池のふよう土ボックス。冬の間に持ち前の木工の腕をふるってKパパが修理を進めてきて下さっていました。活動停止でしばらく作業も見合わせていたのですが、最後の仕上げをして下さったのですね。ありがとうございました。これでふよう土作りもまた本格的に再開できそうで楽しみです。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのKパパ) | |
 |  |
2020年5月1日(金) 5月のトンボ池 トンボ池を見て来ました。 池の水はちゃんとありましたし、水源からも少しづつ水が流れ出ていました。 水草が増えていましたが、まだ水面もずいぶんと見えています。メダカはたくさん泳いでいましたが、オタマジャクシは見えませんでした。 バタフライゾーンも雑草は生えているけど、まだジャングルにはなっていないですね。2月に地植えにした9株のうちサンショが1株だけ枯れていましたが、あとは根付いていたので、良かったです。 バタフライゾーンのコンテナではメダカといっしょにオタマジャクシも泳いでいましたよ。 早くコロナ騒ぎがおさまりますように。 ※休校中もスタッフのみなさんや主事さん方がトンボ池の管理をして下さっています。おかげ様で、放っておくと一気に草がしげるこの季節ですが、池のまわりはいつ子ども達が帰ってきてもよいじょうたいです。ありがとうございます。メダカの産卵やトンボの羽化もそろそろ始まるはずです。早くまたみんなで観察したいですね。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのくるパパ) | |
 |
2020年4月28日(火) 雨上がりの東の空 久しぶりに大きな雷が鳴りましたね。でも夕暮れまでに雨があがり、強い西日が差してきたので、上石神井の東の空にきれいな虹が出ていました。あなたも見れましたか? (画像と情報:しぜん探検隊スタッフのみなさん) |
 |
 |  |
2020年4月27日(月) トンボ池の水位低下 トンボ池の水位が落ちているという連絡を学校に出ていらしゃる先生からいただきました。 完全に抜けてしまう前に発見していただいたので、中の生き物はなんとかだいじょうぶだったと思います。よかったです。現在給水していますが、原因がわからないのでしばらく注意が必要かもしれません。 ※久しぶりの池の画像ですが、中の島では今年もフトイの芽が出て、だいぶ育ってきているのがわかります。 毎年4月の終わり頃からこのフトイのくきを上ってギンヤンマのヤゴの羽化が始まります。今年もそろそろですね。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのいとうママ) | |
 |  |
 |  |
2020年4月21日(火) 雨の日クイズ・・・(5)やってみました② 20日の雨でもやってみました。今度は雨量も少なかったですね。 上の2枚。植木ばちの皿ですが、大きいのも小さいのも同じでたまった水の深さは約20㎜。 左下は、前回と同じ細い試験管と太いトールビーカー。試験管は底の形が丸いので本当はくらべる実験には向きませんね。でもこちらもだいたい同じ20㎜。 下右はガラスびんと、ケーキ屋さんのゼリーカップ。きれいだから何かに使えないかと取ってあったもの。 あれ?こちらは同じ場所に置いたのにゼリーカップの方が深く水がたまってますね。なんでかな?ちゃんとことばにして説明してみよう。図を使って説明してもいいよ。 (画像と情報:しぜん探検隊事務局) | |
 |
2020年4月18日(土) 雨の日クイズ・・・(4)やってみました! 金曜日の夜のふり始めから12時間後の様子です。①の細い試験管と②の太いトールビーカーは同じ深さですね。深さをはかるとどちらも同じ70ミリありました。③は入れ物の深さが50ミリしかなかったので、水があふれてしまっていました。このあと雨がやむ夕方まで続けると①②とも水の深さは100ミリになりました。 みなさんの予想とくらべてどうですか? 細い入れ物と太い入れ物、どうして同じ深さになったのでしょう?説明できるかな・・・ (画像と情報:しぜん探検隊事務局) |
 |
2020年4月17日(金) 雨の日クイズ・・・(1)君もやってみよう! これから数日、雨のよほうが出ています。 写真のように、3つの入れものがあります。 これを雨の中に出しておくと、ふった雨水がたまります。 さて、どの入れものが一番ふかくたまるでしょうか? ①小さいコップ・・・・・・・・・・・細いものの方が、すぐに水面が上がってきそうだから。 ②中くらいの白い入れもの・・口が広いと水面が上がりにくいし、細いとあまり雨水が入りにくそうだから ③大きい四かくいカン・・・・・口が大きい方が雨水をたくさんつかまえられるから さて、君のよそうは? |
 |  |
雨の日クイズ・・・(2)じゅんびをしましょう 上の面と下の面が同じ形の「ずんどう形」のいれものを用意します。 と中が細くくびれていたり、太くなっていたりするものはだめです。 (ペットボトルは、底が平らでないのでこの実験でいれものとしては使えません。) 写真のような少し深さのあるおせんべいのかんなども使えます。 とりあえず、大(太い)と小(細い)を用意しましょう。 風が強くなるかもしれないので、とばされないようにまわりから重たいものでおさえます。 左上の写真は4つのペットボトルで横からおさえていますが、いろいろくふうしてみてください。 入れものをおくばしょは、たてものから少しはなれていて、雨をさえぎるものがないところをさがしましょう。 雨の日クイズ・・・(3)雨量(うりょう)ってなんでしょう? 明日ひるごろまでに100~200mmくらいの雨がふるといっています。 これって、なんの長さでしょうか? 出しておく時間を決めてもいいですが、とりあえず、ふり始めから天気がよくなるまでの間のすべての雨を集めてみましょう。 今ばんから明日昼間にかけてふりそうですから、明日の朝から昼まででもいいですし、こんばんから始めてもいいです。ただ、風が強くなりそうですから、とばされないようにくふうしてください。 天気がよくなってから、細い・太いでどのくらいたまったのか、水のふかさをものさしなどではかったみてくらべてみましょう。 とうめいでないもの(牛乳パックなど)は、右上の写真のように新聞紙などを細く切ったものをはりつけたものさしをパックのそこまで入れて、水のふかさをはかってみましょう。手みじかにやれば、ぬれたところをはかることで、たまった水のふかさを知ることができます。 ★人の庭や、きけんなばしょには入らないようにしましょう。また大風の中でのじっけんは、キケンなのでやめましょう。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのコタジー) | |
 |
2020年4月10日(金) ポンポンボトルを作ろう(2)作り方編 ① ポンポンボトルを作るざい料と道具です。 〇ペットボトル(中をかわかしておく) 〇長めのたけひご 〇くきを3センチほどのこしたタンポポのさき終わった花 〇千まいどおし 〇ペンチまたはニッパーなど |
 |  |
②ペットボトルの底のまん中からわずかにずれたところに千まい通しであなをあけます。手で 竹ひごをとおしてしっかり止まるくらいのかたさにします。ゆるくなってしまったら、またとなりにあなをあけてやりなおします。 | ③ボトルの口から出ている竹ひごに、タンポポの中空のくき(3センチくらいに切っておく)をとおします。 |
 |  |
| ④ボトルのそこの方からひごをもち、中へタンポポをゆっくりひき入れます。フタはわた毛が完全に開き終わり、みどり色の部分がかんそうして茶色くなるまでしません。 | ⑤さいごにボトルのそこから出ているよぶんな竹ひごをペンチかニッパーなどで切りおとします。あとはポンポンがひらくのをまちましょう。 |
★注意 ※花がおわり、わた毛が見えているものをつむと、しあがるまでの時間がはやくなります。 ※ひらいていくようすをじっくり見てみましょう。けっこう感動ものですよ。 ※ペットボトルにあなをあけるのは、キケンですから家の人といっしょにやりましょう。 (画像と情報提供:探検隊スタッフのコタジー) | |
 |
2020年4月9日(木) ポンポンボトルを作ろう!!今が旬=しゅん(1) あれれ!どうやってタンポポのわた毛をペットボトルの中に入れたのでしょうか? 入れ方を考えてください。ボトルの底を切ったりはしません。 この時期ちょうどタンポポのさきおわったものが手に入るので、ぜひやってみましょう。 作りかたは、ちかいうちにまたしょうかいします。 今日は、タンポポのさいているところをさがしておきましょう。 ★人の庭や、きけんなばしょには入らないようにしましょう。 ※ヒント:ひつようなもの ペットボトル(とうめい感があり中がよく見えるもの・乳酸菌飲料などの小さいものでもよい)・千枚どおし・竹ひご・タンポポのしぼんだもの(=白いわたげが少し見えているもの) ここまで読んだらピーンときましたね・・・ (画像と情報提供:探検隊スタッフのコタジー) |
 |  |
2020年4月8日(水) ナガミヒナゲシの花も分解してみました Gママさん(左の「見つけたよ!」4月6日参照)に続いて、おしべの数しらべです。道ばたにはえている「ナガミヒナゲシ」の花です。ガクはちょっと見あたりませんがどれでしょうか?やたらおしべが多いので、全部ならべて数えるのに30分以上かかりました。いちおう95本かぞえることができました。つぎは、ツバキの花にちょうせんしようかと思っています。 ところで、昨日の6年生隊員Bくんの写真すごいですね。瞬間をのがさず、デジカメのシャッターをきったときのむねの高なりもつたわってきそうです。あと1分いえ10秒おくれたらこの写真はゲットできなかったことでしょう。 さて、ISS(国際宇宙ステーション)は今日、明日も夕方の夜空に見えるようです。 4月8日(水)19:40ごろから西→南西 明るさ-1等 最高高度14度 南西 4月9日(木)18:52ごろから西北西→南西 明るさ-1.7等 最高高度25度 南西 西の空なので、その時刻にいっしょに月は写せませんが、明るい金星やシリウスがあるので、Bくんのようにコラボの写真をデジカメでぜひねらってみてください。デジカメはできれば三きゃくにこていするか、てすりや台の上にのせてシャッターを切るとぶれにくいでしょう。西の空が見わたせるところがいいです。 ※こどもだけで出かけるのはやめましょう。大人といっしょにやりましょう。 (画像と情報提供 探検隊スタッフのコタジー) | |
 |
2020年4月7日(火) ISS=国際宇宙ステーション&スーパームーン! 情報ありがとうございました。 自宅外より見上げましたが、ISSはこちらであってますか? 北西から南東へ消えて行きました。 (画像と情報提供 6年生隊員のB君) ※すごい!そうです。これです。今日のスーパームーンとISSを両方1枚の写真に写しこむとはたいしたものです。 18:49分くらいに北西の空に現れたISS。ゆっくりと流れる流れ星のようにほぼ真上の空を横切り、18:55分くらいには、ちょうどのぼってきたスーパームーンとすれ違うように南東に消えていきましたね。しっかり見られて、しかも記録も撮れて、よかったですね。 |
 |
2020年4月7日(火) 今年最大の満月 東の空から大きな月がのぼってきましたよ。 今月の満月は、今年一年で月が一番地球に近づくので大きく見えます。 それをスーパームーンなどとよぶこともあるようです。 実際は月の見かけの大きさをくらべることはむずかしいですが、とにかく自分の目で見てみましょう。 大きく見えるかな? 明るさはどうでしょう? (画像と情報提供 スタッフのつとむさん) |
 |  |
2020年4月5日(日) サクラの『おしべの数』をかぞえてみよう! 5年ほど前にうえた、にわの「サクランボ」の木にはじめて花がつきました。 サクランボは、お花見をする「ソメイヨシノ」とはちがう「セイヨウミザクラ」という種類のサクラです。二つのサクラの花にはいろいろなちがいがありました。左右の写真をくらべてみてください。左がサクランボの花、右がソメイヨシノの花です。まず、花びらの色がちがいます。おしべの数や色もちがうようです。さく時期などほかにもいろいろちがいがあるようです。 | |
 |
ソメイヨシノの花はそろそろちってしまいそうですが、もし手に入ったら、花の分かいにちょうせんしてみましょう。 おしべの数は何本あるでしょうか?写真上から花びら、がく、下におしべのたばがおいてあります。おしべのたばをじっくり分かいしてみましょう。 これがけっこう細かくてかんたんではありません。ピンセットがないときには、ようじの先などを使って、1本1本分けて数えてみましょう。花によって本数がちがうのでしょうか。それとも決まっているのでしょうか。じっくり時間をかけてしらべてみましょう。 わかったら探検隊に知らせてくださいね。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) |
 |  |
2020年3月17日(火) 『一番星の早さがし』にちょうせんしてみよう 今日の一番星はなにかわかりますか? そう。気づいている人も多いと思いますが、夕方西の空高くでかがやく金星です。 とても明るいので、青空の中でも見ることができます。とはいっても昼間はいちがきめにくいので、見えていてもなかなかさがすのはむずかしいです。 ※左:青空の中の金星 17日18:04 右:暗い夜空の金星 17日18:56 夕方、日がしずむころ(18日は17時51分)に青空の中にさがしてみましょう。(17日は、17時43分に見つけることができました。空はまだ半分青かったです。) 日がだんだんのびていくので、見つけられる時こくもおそくなっていくと思われますが、やってみましょう。 ところで、もっと早く見つけることはできないでしょうか? できるだけ空が明るいうちに見つけるにはどうしたらいいでしょうか? 『一番星の早さがし』にちょうせんしてみましょう。 ● 金星を早くさがすポイント ①金星は、太陽がしずむころ、うでをのばして水平のいちからげんこつ5つから6つ分見上げたところにあります。 ②かすみやうすぐもが出ていない日をえらびましょう。 ③目のし力は、じゅうぶんですか?そうがんきょうを使うと、見つけやすくなりますので、さらに早い記録がでそうです。 ※3月25日に金星は太陽から一ばんはなれます。またさらに1か月後の4月の末に明るさが一ばん明るくなります。 ◎一人で遠くに行ってかんさつするのはやめましょう。 ◎太陽の明るさはきょうれつです。いちをきめるときに、太陽をあやまって見ないようにしましょう。 ◎そうがんきょうで太陽をのぞくのもキケンです。ぜったいのぞいてはいけません。 ★金星をみつけたら・・・〇見つけた時の正かくな時こく 〇見た場所 〇かんさつした人の名前 〇かんそう などを探検隊事務局までメールで送ってくれるとうれしいです。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) | |
 |  |
2020年3月17日(火) ジャコウアゲハが羽化しました ジャコウアゲハが、けさ羽化したので、そのようすをお伝えします。ジャコウアゲハは、都会では あまり見かけませんが、ちょっとこう外にでると、見つけることができるようです。これは、きょ年隊員のつとむさんからさなぎをいただいたものです。 (以下つとむさんからのコメントです。) きょ年、野さいの本をつくるためのさつえいで、栃木県益子町(ましこまち)の畑に行っていました。その時タラノキに、ウマノスズクサのツルがからまっていることに気づきました。ウマノスズクサはジャコウアゲハのよう虫の食草です。そのウマノスズクサにたくさんの幼虫がついていました。調べるとジャコウアゲハでした。秋になるとウマノスズクサのあった近くの家のかべにいくつかのさなぎがついているのに気づきました。それを持ち帰りました。 ちなみに、ジャコウアゲハは、アリストロキア酸というどくをもっているそうです。それをふくんでいるウマノスズクサを よう虫が食べるためで、よう虫の皮にもこの成分はあるそうです。まぁ、口に入れなければ問題はありません。 いただいたさなぎをわりばしにつけて、春をまっていました。しょくいんしつのつくえの上においていたら、けさ羽化(うか=せい虫になること)しました。午後になり少しあたたかくなってきたので、なの花につけてやると、羽をばたばたとはばたくようなしぐさをかなり長い間やっていました。そして1時ごろに春風にのって空高くとんでいきました。 ★調べてみよう★ ジャコウアゲハには毒があるので、ほかの鳥や昆虫にねらわれにくい、といえそうです。それを利用してジャコウアゲハの形や色ににせて、自分にはどくがあるんだよ。食べちゃいけないよ!と、毒のある昆虫のまねをして身を守る生き物がいます。これを「擬態」(ぎたい)といいます。 どんなものがジャコウアゲハのまねをして身を守っているのか調べてみましょう。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) | |
 |
2020年3月14日(土) ツクシ発見! こんにちは。 千川上水の脇(わき)にツクシがさいていました。 (画像と情報提供 5年生隊員のN君) ※お。よく見つけましたね!上石神井でもツクシが見られる場所はどんどんへっています。以前は見られた畑や空き地などが宅地や駐車場などに変わってしまったからです。N君が見つけたこの場所がいつまでも残されるといいですね。 |
 |
2020年3月13日(金) ウサギの足跡!? きれいにたがやされた畑を横切る動物の足跡(あしあと)。2種類あるのがわかりますか。さて、この主(ぬし)はいったいだれでしょう?・・・ 石神井台、オザキフラワーパークの裏の駐車場2階から撮影。 (画像と情報提供 スタッフのおおさわさん) ※さて、これはいったい・・・!動物の足跡を観察して、その動物の種類や行動を探ることを「アニマル・トラッキング」といいます。一面の雪原などでは足跡が見つけやすいのですが、きれいにたがやされた畑の土でもこんなにくっきりと動物の足跡がわかるのですね。みなさんもぜひ自分で本やネットで「アニマル・トラッキング」について調べてみましょう。 ちなみに「練馬区の動物について」(練馬区教育委員会昭和37年度共同研究)によれば、かつては練馬区内で野ウサギの記録はありますね。 |
 |
 |
2020年3月12日(木) ヒキガエル&おたまじゃくし発見! 立野公園の池でヒキガエルのおたまじゃくし発見! まだちっちゃい! 親のヒキガエルは、連日子ども達にもみくちゃにされて昼間はかくれてます。 (画像と情報提供:6年生隊員のY君) ※みなさんから次々、春のおたよりがとどきはじめました。ありがとう!今年は2月に一度目のヒキガエルの産卵があり、今ちょうど2度目の産卵がはじまっているようですね。トンボ池以外でも立野公園などの公園の池、個人のおたくの小さな池などでも産卵が見られるはず。2月に産んだ卵の方は、もう次々とおたまじゃくしになっているのですね。 ★クイズ★さて、この写真の中にやじるしのものもふくめて、いったい何匹のオタマジャクシがいるでしょう?かく大してさがしてみよう。 |
 |
2020年3月12日(木) アンズの花がまんかいです! 今朝、アゲハチョウが飛んでいるのをベランダから見つけましたが、写真は撮れませんでした。 アンズの花は満開です。サクラは明日くらいですかね・・・ (画像と情報提供 5年生隊員のYママさん) ※隊員さんに「アゲハチョウを見つけたられんらく下さい」と連絡しておいたのですが、さっそくアゲハチョウの情報第1号がとどきました。今あちらこちらで満開になっているきれいなピンク色の花はアンズですね。サクラも早ざきの種類はもうさき始めています。ソメイヨシノもいよいよさき始めるかな。いつさくかが気になるところですね。 学校がお休みで、何か見つけてもお話しするあい手がいない人も多いはず。せめてこの探検隊のホームページで見つけたものをしょうかいし合いましょう。みなさんもどんどん見つけたものを教えてください! |
 |  |
2020年3月9日(月) フラクタルな春~ヤリガイくん食べごろ~ うちの庭で育てたやさいです。時々やおやさんやスーパーで見ることがあります。味はブロッコリー、食感はカリフラワー。なの花の仲間の「ロマネスコ」というやさいです。今が食べごろです。べつ名 ヤリガイくん。 食べるのは、花の芽です。よく見ると、貝がうずをまくようにたくさんならんでいるように見えます。部分を見ても、全体を見てもよくにた形です。これを「自己相似形」(じこそうじけい)とか「フラクタルな形」とかよびます。下の図はシダの葉のようすです。  自然の中には、このフラクタルな形がたくさんひそんでいるようです。 木のじゅ形、いなずま、地図の上の川、山並み、葉、枝・・・さあ、ほかにどんなものがあるでしょうか? 春さがしの時に、こんなことにも気をつけながらあるいてみてください。もしかしたら、自分のからだの中にもあるかもしれませんよ。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) | |
 |  |
2020年2月24日(月) ヒキガエルの産卵が始まりました 今年もトンボ池でヒキガエルの産卵が始まりました。温かいのにカエルの姿がまだ見えないね・・・などと話していましたが、よく見ると池の底の落ち葉の下に6匹のカエルがかくれているのをジュニア隊員さんが発見。まだ数は少ないですが卵も見つかりました(写真左)。産卵を確認したのは昨年は3月4日でしたから、今年は10日ほど早いですね。 トンボ池ではここ2年ほど産卵に来るカエルや産卵数がへっているようです。1年に1度だけの産卵ですのでみなさんでやさしく見守ってあげて下さい。 池のまわりにはフキノトウもたくさん出ています(写真右)。 | |
 |
 |
2020年2月19日(水) 春のおとずれ(その1) 石神井川沿いも、早咲きのものか、桜が咲き出しているものもあり、メジロやヒヨドリが花をつついています。 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) |
 |
2020年2月5日(水) 水星が観察しやすい時期です 水星は太陽系の中で、太陽に一番近いため日没時や日の出時の高度が低く、見つけにくい天体ですが、2月10日の東方最大離角に向けて日の入り直後の西の空で見やすい時期をむかえています。ぜひ夕方の西の空で水星を探してみましょう。双眼鏡があるとなお確実です。 ちょっとわかりにくいですが矢印の先が水星。その左上の明るい星が金星です。 (画像提供 隊員のGママさん) |
 |  |
 |  |
2020年2月1日(土) 生き物の冬ごし観察とケムシ退治 もうすぐ立春。秋に松とヒマラヤスギの木に巻いたコモをはずして、中で冬ごしをしている生き物が出て行ってしまう前に観察をしました。マツカレハの幼虫(=松毛虫) (写真右下)は全部で148匹。ほかにもクモやテントウムシなどがいまいした。増えすぎては困るマツカレハは土にうめて処分し、あとの生き物はトンボ池のまわりに逃がしてやりました。 ※この日の活動の様子(→こちら) ★探検隊では、殺虫剤を使わない害虫退治の方法としてこのとりくみを1999年から毎年続けています。 | |
こもの中にいた生き物 | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) |
マツカレハの幼虫(毛虫) | 1160 | 271 | 317 | 16 | 12 | 148 |
サシガメのなかま(カメムシ) | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
テントウムシのなかま | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
クモのなかま | 12 | 7 | 2 | 2 | ||
ワラジムシ | 177 | 8 | 19 | 2 | ||
ヤモリ | 0 | 2 | 1 | 0 |
 |  |
2020年1月21日(火) いこいの森にあらわれたタヌキ 久しぶりにタヌキを見ました。場所は上石神井いこいの森(上中の西)です。 最近は、上石神井でタヌキを見ることはそんなに珍しいことではなくなっていますが、今から60年ほど前に行われた練馬区の生き物調査(1961年練馬区教育委員会)を見てみると石神井地区では「タヌキ・・・現在は全然見られない」と書かれています。一方で今は全然見られないイタチについては「農家の物置の中などに多少いる」と書かれています。生き物の姿を観察して記録し続けていくといろいろな変化がわかっておもしろいですね。その変化がどうして起きているのか考えてみるのも大事なことかもしれません。みなさんもこの数十年の間にイタチがいなくなり、タヌキが現れたわけをいろいろ考えてみてください。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |
 |
2020年1月11日(土) ルリビタキ 冬に、より寒い場所から寒さをのがれてわたってくる鳥を「冬鳥」とよんでいます。その冬鳥が東京でも見られる季節になりました。 冬は、木の実などエサのある場所、水辺など特定の場所に鳥たちが集まりやすいことや、葉っぱが落ちていて鳥の姿を見つけやすいこともあり、バードウォッチング(野鳥の観察)にはよい季節です。 みなさんも、双眼鏡や図鑑などを持って鳥を探しに外に出てみましょう。 これは探検隊がセミの観察会で行く善福寺公園で出会ったルリビタキ(メス)。公園の中ほどのトイレの近くでよく見かけるような気がしますが、なかなか近づくことはできません。ルリビタキの見られる場所への案内 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) |
見つけたよ! ★身近な発見や情報をメールで事務局までお知らせ下さい。  1月8日(木) トンボ池の氷 寒いですね。今朝はトンボ池に氷が張っていました! (画像と情報:OBのGママさん) ★寒くなってきましたね。トンボ池にも氷が張る季節です。最近は子ども達が霜や氷に触れる機会も少なくなっています。上小トンボ池は、子ども達が直接水や氷に触れることができるよう、深さを管理・調整した上で敢えて柵などを設けない池として25年以上管理しています。ぜひ冬の寒さを肌で感じてください!!(石を投げこんだりはしないでね)  11月2日(日) 夕焼けのきれいな季節です! 上石神井の西の空です。 日が短くなり、寒くなってきましたが、空を楽しみましょう。買い物に出た時にスマホで撮りました。 (画像と情報:スタッフのTさん)   8月1日(金) 何がおきた?君のすいりは? 近くの公園で朝早く見つけました。地面に何かをひきずったあとが長々と見えています。上下同じ写真ですが、写っているはんいが上の方が広いです。その先にはなんと!アブラゼミのぬけがらとすぐそのとなりにくしゃくしゃになった羽化に失敗したセミがもがいているでは・・・。いったいどうしたことでしょう。このセミはどこでだっぴしたのか?セミに何がおこったのか?君のすいりはいかに・・・!  7月24日(木) だ〜れだ?! 写真は、ある昆虫の頭と胸を横から拡大して写したものです。この時期、暑い日に、憩いの森や公園で、エノキやケヤキなどの広葉樹の回りで飛んでいたり、幹にとまっていたりします。コロンと地面に落ちている姿を見かけることもあります。  ①18:00頃 背中が割れてきた  ②18:10頃 腹が半分ほど抜けた  ③18:20頃 完全に抜けた 5月29日(木) ヤゴの脱皮の瞬間 ギンヤンマのヤゴを飼育していて、脱皮の瞬間を観察することができました。目が黄色くなるのが脱皮の合図です。背中が割れてきてから20分ほどで完全に抜けました。 (画像と情報:OBのGママさん) ★ヤゴからトンボになる「羽化」の観察記録は多いですが、ヤゴが成長過程で繰り返す「脱皮」の瞬間は案外観察報告がありません。それでもよく観察していればこうやって見ることができるのですね。貴重な記録です。ありがとうございました。  4月13日(日) 氷漬けの飛行機 イギリス支部活動1枚目です。日本からイギリスへの飛行機の中で窓を見てみると、氷漬けになっていました。フライトマップによると、なんと外の気温はマイナス60度。ちょうど北極の上を飛行中でした。 (画像と情報:中学生OBのT君) ★この春から1年間のイギリスで過ごすことになったというT君は「今晩飛行機で発つ」という日まで観察会に参加してくれたので「向こうに行ったら探検隊イギリス支部作って、イギリスで見つけた自然の情報送ってね」と頼んでおいたところ、さっそく1枚目の写真が届きました。 「マイナス60℃の世界」って想像つきますか? 12月12日(木) 土星食もスマホでパチリ! 先日の土星食、スマホでは環(わ)は見えませんでしたが、位置は確認できました。 出てくるところは、しばらくしてからのものです。 →クリックで拡大 (画像の提供:隊員のMさんより) 月も土星もあかるいので、スマホを向けても、様子がわかるようにとれるんですね。かなり近づくと月の光に負けてしまって、肉がんでは見えないものもしっかり写ることがわかりました。 12月7(土) 月と金星のせっ近、スマホでパチリ! 5日の月と金星のせっ近をスマホでねらいました。わが家は、深夜になると月が高い位置で見えることもあるのですが、お月見の季節や今日の夕方は、電線の間からの月見です。→クリックで拡大 (画像と情報:隊員のMさんより) ★ 月の高さは、いろいろな理由でかわります。見る時間帯、季節(夏は低く冬は高い)月の形(新月に近いほど低く、まん月に近いほど高い)これらが組み合わさると、けっこうふくざつですね。  11月25日(月) 猛禽類(もうきんるい)発見! 西東京市の公園で、大型の野鳥を見かけました。急いで撮影し、家に戻って調べました。ノスリというワシやタカの仲間です。→クリックで拡大 (画像と情報:しぜん探検隊) ★冬になって寒くなると、北の国からやってきた冬鳥や、ふだん山など高いところで生活している野鳥が平地に降りてきて、町中の公園でも姿を見ることができるときがあります。また、冬は多くの木が葉を落とすので、枝に止まった野鳥を見やすくなります。バードウォッチングに最適な季節です。  10月31日(木) いつ白くなるのかな? ちょっと霞んでいますが富士山です。 今日もまだ冠雪していません。130年の観測史上もっとも遅い冠雪記録更新中です。 (画像と情報:隊員のGママより) ★去年の初冠雪(初めて雪で白くなること)は10月5日で、それでも平年より3日遅かったということですから、今年の異常ぶりがわかります。富士山が見える場所を探して観察を続けていきましょう。  9月21日(土) おしゃれなサギ君 石神井川の下流、練馬高野台駅付近で、撮った写真です。 サギの仲間が橋の下で毛づくろいをしているようでした。 どうして、そんなに毛が気になるんだろう? (画像と情報:6年生隊員のHくんより) ★川をのぞきこむといろいろ発見がありますね。石神井川によくいるコサギのようです。エサを取るだけでなくいろいろな仕草をするところを観察するのも楽しいですね。  9月21日(土) どこから入ってきたの? 起きたときに母の悲鳴が聞こえて、見てみたら、寝室のカーテンにバッタがいました。家の中にどうしてこんなに生き物が入ってくるんだろう。 (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★生き物は、新たなすみかを探して常に旅をしているのだといいいますが、このバッタはどうやらまちがって人間のすみかに入ってきてしまったようですね。ここにはおいしいエサはありませんよ!  7月31日(水) 増水時の石神井川 HP(右)を見て思い出しました。7月31日19:00東京に記録的短時間大雨情報が出た日の石神井川です。 武蔵関へ行ったら雨で帰れなくなり、警報も鳴りました。雨がやんでも川はここまで増水していました。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★たまたま通りかかったので記録として残しておいた写真とのこと。右の「上石神井のしぜん最新情報」の8月19日の一番下の写真と同じ場所から撮影したと思われますが、遊歩道部分の手すりがほぼ完全に水没しており、この時よりさらに増水した状態であったことがわかる貴重な記録写真です。  7月28日(日) どこに行きたいの?カマキリ君 ベランダに干した洗濯物を取り入れようとしたら、壁に子どものカマキリがいました。カマキリを家の中に入れないよう、別の窓から家に入りました。カマキリは、涼しい家の中に入りたかったのかな? (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★暑い日が続きますね。カマキリだってこんなに暑いと涼しい家の中に入りたくなるのかな?それにしても思いがけなくベランダで生き物観察ができちゃいましたね!  7月23日(月) クマゼミ クマゼミ(クリック拡大)が鳴き始めました。もともとは南方の暖かい地域のセミですが、最近では関東地方でも数をふやしているといわれます。おもに、日の出からお昼前くらいの午前中に盛んに鳴きます。 (画像と情報:しぜん探検隊) 7月19日(金) 人工衛星(えいせい)の木!? 町なかであまり見たことのない花を見つけました。調べてみると、タニワタリノキとありました。どれが花びらで、どれがおしべなんだか?「じんこうえいせいの木」ともよばれるみたいです。 コロナウイルスの木でもよさそうですが・・・。南の国では大きな木になるようです。 (画像と情報:しぜん探検隊)  7月6日(土) シーズン到来! 昨日初めて善福寺公園に虫取りに行ったらもうカブトムシやクワガタがいました。予想していたよりも多くカブトムシやクワガタがいました。(クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員のNくん) ★カブトムシ観察のシーズン到来ですね。身近なところにも意外にいますよ。みなさんもぜひ探しに行ってみましょう! 6月22日(土) 孵化の瞬間! トンボ池バタフライゾーンのウマノスズクサに産み付けられたジャコウアゲの卵。(→右ページ参照)観察していたら、ちょうど卵から1匹目の幼虫が生まれる孵化(ふか)の瞬間(しゅんかん)を見ることができました!(クリック→拡大) (画像と情報:5年生隊員のSくん) ★運がいいですね~!飼育していても孵化の瞬間はなかなか見ることができず、まして野外で孵化の瞬間をカメラで撮影するのはとても難しいことです。しかもそれがただのアゲハチョウではなく、珍しいジャコウアゲハの孵化の瞬間とは!!ウマノスズクサの葉の形や生えている場所(学校)までもが1枚でよくわかる素晴らしい写真です。 6月1日(土) タマムシの羽を発見! 6月はじめのしぜん探検隊の集まりの日、近くの自然を観察していたら、地面に、タマムシの羽が片方落ちてしました。自分が思うに、これは上石神井小学校にもタマムシが生息しているひとつの証拠となるのでしょうか。いつかは、上石神井小学校にタマムシが現れるときが来るかもしれません。(クリック→拡大) (画像と情報:6年生隊員のHくん) ★鋭い考察ですね。確かに羽が落ちているということは、その近くに実際にタマムシが生息している何よりの証拠と考えられます。アリの巣穴の外で見つけたということでしたから、アリが運んできたものの、羽は大きすぎるからか穴の中まで運び込べなかったということでしょうかね。いろいろ想像もふくらみます。タマムシの食草(食べる植物)や成虫の発生時期などを調べて観察を続けることで、本当に「上小のタマムシ」に出会える日も遠くないかもしれませんよ。  6月13日(木) 街中のキノコ探し 街で見つけたキノコ(学区外だけど千川通り沿いです)ひとつめ(上)は街路樹の桜の木に生えていたベッコウタケ。これが生えると残念ながら枯れて倒れてしまうので伐採されることが多いそうです。 ふたつめ(下)はシュロの切り株に生えているキクラゲ。ちょっとおしゃれ。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★街でもできるキノコ探し。ちょっとおもしろそうですね。キノコというと秋のイメージですが、雨の多くなるこの季節。案外見つけることができたりしますね。みなさんもおもしろいキノコを見つけたら教えてください。  5月24日(金) 水泳の授業開始! 上小の水泳の授業はまだですが、日差しの強さ、暖かさにつられてか、気持ちよさそうに泳ぐアオダイショウを見かけました。場所は、東伏見近くの石神井川です。(クリック→動画) (画像と情報:しぜん探検隊)  5月23日(木) ゴイサギの狩り 石神井公園でゴイサギの幼鳥がエサのザリガニかカニ?をとったところです。 氷川神社の前でジャコウアゲハらしき蝶も見ましたが、上小にはまだきませんか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★あちこちでいろいろな生き物のヒナに出会える季節ですね。巣立っても自分でエサをとって生きていける一人前の大人になるまで修行が続きます。 ジャコウアゲハは、バタフライゾーンに食草のウマノスズクサが植えてあるので次回の観察会で探してみましょう! 5月22日(水) カルガモのヒナだよ 駅にほど近いビルの植え込みの中でピヨピヨとかわいい声がするので見てみると、カルガモのヒナ3匹がうろうろしているのを見つけました。親鳥のすがたは見えませんでした。まわりに水辺はないので、石神井川に移動するときにはぐれてしまったのでしょうか。 (画像と情報:しぜん探検隊)  5月20日(月) 森の音楽家見つけた! 近所の公園で、キツツキがケヤキの幹(みき)を口ばしでたたいている音が聞こえてきました。この公園では初めて聞く音です。時々見かけるアオゲラだと思われます。肉眼では見えましたが、ざんねんながらさつえいはできませんでした。 (画像と情報:しぜん探検隊)  4月26日(金) タンポポのビン詰め タンポポの綿毛がふくらむ季節です。開く前の綿毛を取って、上手にペットボトルやビンに入れて乾燥させると、中で綿毛が開いて素敵なタンポポのビン詰めが出来上がり! (画像と情報:隊員のGママさん)  4月16日(火) 緑色の桜ミッケ! 花びらが緑色の珍しい桜「御衣黄」(ぎょいこう)を見つけました。公園とかで見ることはありますが、今回は意外にも学区内で見つけましたよ。さて、ここはどこでしょう。ヒント:駅のすぐ北側。線路のそばですよ! (画像と情報:隊員のGママさん)  1月8日(月) キイロスズメバチの巣発見! 雑木林の中で発見。たぶんキイロスズメバチの巣だと思われます。この時期は中は空き家のはず。次回観察会に持って行きますね~ (画像と情報:隊員のおおさわさん) ★2月の観察会でさっそく「解体ショー」やりましょう! 12月4日(火) アンテナをつらぬくISS 12月4日に、ISS(国際宇宙ステーション)が夜空をつうかするようすがとてもよく見えました。すごく明るかったのが、ゆっくりゆっくり暗くなっていく様子がなんともふしぎでしたね。これからよく見えるのは 6日(水)17:51ごろ 南西の高い空 7日(木)17:02ごろ 真上(天頂) です。くわしくは・・・・ をさんこうにしてください。  10月29日(日) ナナフシの脱皮殻発見! ぐんま昆虫の森の温室で、たくさんいたナナフシの中で初めて抜け殻を見つけました。 (画像と情報:OB隊員のN君) ★夏にやった「夜の森観察会」ではナナフシを発見したN君。今度はその脱皮殻かぁ。よく見つけましたね!!  9月19日(火) 狩りをするスズメバチ 石神井公園(三宝寺池)でセミを捕まえたスズメバチを見かけました。しつこく撮影していたら、獲物をしっかり抱え込んで運び去っていきました。(クリック→動画)  9月12日(火) どんぐりミッケ! 大きなどんぐりが落ち始めましたよ。どんぐり拾いなら今がチャンスです! (画像と情報:隊員のGママさん) 9月7日(木) 空を見上げなはれ! 18:07の上石神井から西の空です。 ご多忙なみなさんもたまには空を見上げなはれ! (画像と情報:OB隊員Nさん) ★みごとな夕焼けですね。空気中の水蒸気やチリが多いと赤色以外の光は散乱してしまい、このようにより赤く鮮やかな夕焼けになるんだそうです。この時期、夕暮れの西の空から目が離せませんね~  8月14日(月) 石神井公園でタウナギ捕獲! かねてより、タウナギを飼育してみたいと思っていて、14日の夜に石神井公園へガサガサをしに出かけました。 水路を見回ったところ、大きなタウナギがゆっくりと泳いでいるのを見つけました。最初は素手でつかもうとしましたが、思った以上にぬめりが強くて素手で捕まえるのは無理だと考え、網ですくうことにしました。何度か取り逃しましたが、何とか捕まえることができ、家で飼育することにしました。体長は70cmほどでした。 (画像と情報:卒業生の通りすがりのシャムネコさん)  8月13日(日) 流星見ながら羽化したよ! ペルセウス座流星群。極大となる今晩は微妙ですが昨晩は見ることができました。よかったです。写真は流星を見ながら羽化したアブラゼミです。 (画像と情報:OB隊員さん) ★昨晩は雲の間に結構星が見えましたからね。今晩はどうかなぁ・・・  8月9日(水) 8月9日(水)積乱雲の発達と移動 昨日のOB隊員さんからの情報に引き続きまた雲の話題を… 夏といえば積乱雲(入道雲)。雷はイヤですが(実は大好き。ワクワクします)、じっと見ていると積乱雲は実にダイナミックな動きをしています。時間を短縮して撮影するとその動きがよくわかります。→動画 (画像と情報:スタッフのつとむ)   8月8日(火) 空から目が離せません! 台風が近づいてきているようです。長いこと雲一つない青空続きでしたが、ここへ来て雲の変化、気象の変化がおもしろいです。上は太陽の両側に明るく虹色に光る点(「幻日」(げんじつ)が見えています!その下は富士山と幻日です。下の写真は雲の一部が虹色に輝いて見える「彩雲」です。 (画像と情報:OB隊員さん) ★雲の変化が面白いですね!朝夕の急な雨の後には虹が出ることもあります。みなさんも空を見上げてみましょう。   8月7日(月) ついに会えた!念願の・・・ ついに念願の水棲昆虫に会えました。ゲンゴロウです!(→画像拡大) (画像と情報:OB隊員中1のS君) ★S君はゲンゴロウに会いたくて計画を立ててはお父さんと日本各地のため池などを回り、ようやく4年ごしで出会うことができたのだそうです。探して回る中でアメリカザリガニなどの外来種が入り込んでしまって生態系がくずれてしまった地域が多いことにも気づいたと話してくれました。  8月6日(日) ミンミンゼミが羽化しました! 昨日のセミの羽化観察会で持ち帰った幼虫が無事羽化しました。ミンミンゼミでした! (画像と情報:4年生隊員のS君) 8月5日(土) ミノムシくんを見つけたよ 朝おきて家のドアーをあけると、なにやらぶらぶらしたものが目に入りました。ミノムシでした。朝のごあいさつをしにきたのかな?朝から暑いのに、あんなのをからだにまとってだいじょうぶ? (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月31日(月) さてこのトンボは・・・? 静岡県伊東市にて。宿泊先のプールで泳いでいたら、黄色いトンボの大群が飛んでいて、そのうちの一匹が駐車場内で休憩している所を発見しました。シオヤトンボ?? (画像と情報:4年生隊員のS君) ★上石神井ではあまり見ないトンボ?ですね。あれれ・・・よく見るとチョウみたいに長い触覚(しょっかく)がありませんか?(→画像拡大) もしかしてトンボによく似たツノトンボかな?  7月29日(土) どうか逃げないで! 帰宅してドアを開けようと思ったら、交尾をしているムシヒキアブが! どうか逃げないでと思いながら急いで撮影しました。 (画像と情報:4年生隊員のS君) 5月1日(月) 白い花のアカバナユウゲショウを見つけた! 町中を歩いていて、白い花をつけているアカバナユウゲショウを初めて見つけました。単にユウゲショウと呼ぶこともあります。シロバナアカバナユウゲショウなんてちょっとへんな呼び名ですね。シロバナユウゲショウでもいいみたいです。ならべて比べると、アカバナの方は茎は赤茶色をしていますが、シロバナの方は、葉の色と同じ緑色のままです。 アカバナユウゲショウの中に白い花がまじっていないかどうか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月13日(木) 黄砂(こうさ)のえいきょうかな? 夕日をとろうと西の空にカメラを向けてみました。風が強い日なのに、今日ばかりは山かげもどんよりぼんやり見えています。真上はきれいな青空ですが。やはり黄砂のえいきょうでしょうか? (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月12日(水) にげ出した植物 ~石神井川で見つけたよ~ 寒い時期からついこのごろまで、水のない 石神井川の底に黄色く目立つ花がさいています。『キクザキリュウキンカ』というヨーロッパからやってきた花です。どこかの庭先からにげだしたようで、かなり広がりを見せています。ちぎれた根からかんたんにふえるので、野生化するとやっかいです。ヒメリュウキンカ(クリック)との区別がまだしっかりとされていないようです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月6日(木) 4月6日(木)巨大なシロツメクサを発見しました。 場所は、石神井井川沿い、東伏見の早稲田大学グラウンドの、石神井川を挟んだ南側「下野谷 遺跡公園」です。葉もとても大きいのですが、花も大きく、直径3cmくらいあったでしょうか。まるで葱坊主(ネギの花:クリック)のようでした。 (画像と情報:スタッフのMさん)  3月31日(金) エドヒガン桜がやってきた! みなさんにおしまれつつも、幹の中に空洞(くうどう)ができてしまったために切り倒された桜(ソメイヨシノ)に代わり、西門わきに新しい桜の木がやってきました。新しい桜はエドヒガン桜という品種で、ソメイヨシノより少し早く咲く桜です。今回植樹されたエドヒガンはすでに凛(りん)と若葉を出している状態です。花をつけるまで何年かかかるようですが咲いた時の皆さん喜ぶ姿が今から楽しみです (画像と情報:スタッフのSさん) ★上石神井小学校の桜は図書室北側にあるオオシマザクラ以外はソメイヨシノでしたが、開校当初植えられたものは学校と同じくらいの年と考えると樹齢70年を超え、幹が老化して近年次々と切り倒されてしまっています。(ソメイヨシノはひかくてき寿命が短い樹木だそうです)新しく植えられたエドヒガン桜は寿命が長い桜で、中には樹齢数百年と言われているものもあるくらいですから今後も長く上小のシンボルとなっていくといいですね。生物多様性という観点からもソメイヨシノばかりでないというのはよいことだと思われます。 ジョウビタキ 石神井川に沿った都営上石神井アパートの一角。ジョウビタキのメスがいました。冬鳥の季節は終わり、このメスのジョウビタキもそろそろ旅支度でしょうか。(→画像拡大) (画像と情報」:スタッフのT) 3月10日(金) ムクドリの水浴び 春本番のような暖かさに、夕方、たくさんのムクドリが石神井川で水浴びをしていました。ねぐらに帰る前の入浴タイムでしょうか。(→動画)  3月9日(木) 冬眠終了! 一気に春めいた暖かな陽気に誘われて、ニホントカゲも冬眠から目覚め、日向ぼっこを始めたようです。〈上石神井第4踏切と第5踏切(閉鎖中)の間の線路ぎわ〉 (画像と情報:スタッフのつとむさん)  3月8日(水) 幼虫めっけ! 春から育てていた綿が枯れたので、植木鉢の土を空けたら、中から大きな幼虫が4匹も出てきました。コガネムシ?でしょうか。 園芸用の土で大きく育っていて驚きました。 せっかくなので腐葉土を入れたケースに移し替えて、様子を見ることにしました。 (画像と情報:3年生隊員のSさん) ★うえきばちから出てきたというこの幼虫。さてさなぎになって羽化したらいったい何になるのでしょう?ケースに移して飼育して、自分の目で確認するというのはとてもいいとりくみですね!結果がわかったらぜひまた写真を撮って報告してください。 3月2日(木) 見えた!木星と金星の大接近 (画像と情報:隊員のGママさん) 2月23日(木) 夕方の絶景をパチリ! 23日の夕方、家の2階から家族で見ました。とてもきれいでした! はじめはスマホを使ったのですが、手ブレがひどく、次にデジカメでねらいました。すると三きゃくなしでもうまくとれました。(画像クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★いろいろな機材を使ってみたのがいいですね。3つの天体(月・木星・金星)が並んでいる様子がよくわかります。3月の大接近の様子もぜひとってみてください。 2月22日(水) 毎日見てます! 22日の夕方、18:51。古田島先生からの宿題(→こちら)に挑戦中。毎日同じ場所から同じ設定で撮影してみようと思います。(画像クリック→拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★22日と23日の比較画像が届きました。この先も2日の大接近までの変化が楽しみですね。  2月22日(水) 春めっけ!② こんにちは。しぜん探検隊で頂いたサクラソウが綺麗に咲きました!写真を送ります。 (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★スタッフのコタジーが毎年取ったタネから育てた苗を秋に分けてくれているものですね。次々とつぼみが上がってきているようですから、これからもしばらく楽しめそうですね。     2月15日(水) 春めっけ! 先週、三浦海岸に行ってきました。そこではもう春がやって来ていて、ハコベ、タンポポ、オオイヌノフグリ等が咲き、カメムシかな?出てきていました。 (画像と情報:スタッフのKさん) ★恒例「春さがし」の今年の第1報ですね。春はもうすぐそこまで来ているのですね。みなさんもそろそろ冬ごもりを終わりにして外に春を探しに出かけましょう。週末は暖かくなるようですよ~  1月24日(火) 石けんの実、ミッケ! 前に観察会で遊んだ「ムクロジの実」がいっぱい落ちているのを見つけました。(写真・上)まわりの半透明の部分はぬらせばアワがいっぱい出て石鹸遊びができたんですよね。そのまわりの部分を取ると、中から硬くて黒いタネが出てきます。(写真・下)これが、羽根つきの羽根の黒い玉の部分。  見つけたのは、石神井公園。上を見るとまだいっぱいなっていて思わず「ムクロジパーティーだぁ!」  (画像と情報:OB隊員のN&Rちゃん) ★この実をひろえるのは、ちょうど今の季節なんですね。集めておいたら次のリース作りの時のいい材料にもなりそう・・・  1月21日(土) 日の入りも見たよ! 学校の屋上から日の出を見たので、夕方は日の入りも観察してみました。16:56とのことでしたが、ちょうど西の方角に雲があり、太陽が雲にかくれたのは16:29でした。西に雲があるということは、これから天気、悪くなるのかな。 (画像と情報:隊員のGママさん)  1月12日(木) 月齢19の昼間の月 昼間の月がよく見えていました。月齢19だから上石神井の電車の車庫の同じ19番線の上に出ているように撮れたら面白いかなと思ったけど、なぜか19番線だけ表示がない(汗!) (画像と情報:隊員のGママさん)  1月6日(金) 暈と幻日 太陽に巻層雲がかかると、そのまわりに色のついた光の輪や強く光る場所が現れたりすることがあります。今日は丸い輪とその両脇に虹色に光る「幻日}(げんじつ)が見えていました(矢印の下)。左右両側に、はっきり見えていましたが出先にいたのが残念。真ん中の太陽を隠すようにして撮らないとまぶしすぎて暈や幻日がうまく写らないのですが・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) 1月1日(日) 初日の出と初日の入り あけましておめでとうございます。 元日は、風はさほどないのに、とてもすんだ空にめぐまれました。 南東の空から日の出の時こくの数分後には太陽が見えてきました。わずかに広がる低い雲が光をうけて、それ刻々と増していくようすは神々しいものでした。 矢印の先に都庁やドコモタワーが見えています。 日の入りは、富士山の火口のすぐ南がわでした。あと1週間足らずで火口に重なりそうです。 ★初日の出16秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) 12月26日(月) 1時間以内で全部見えた! 日月火水木金土全部を最短時間で見るチャレンジ。1時間以内で全部見られました!! 上から太陽(日):26日16:24撮影・火星:26日17:03撮影・土星・月・水星・金星:26日17:13撮影・木星・土星・月:26日17:13撮影 (→それぞれ画像クリックで拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★すごい。古田島先生もびっくりの最短記録でしょうか。こんな「惑星パレード」は次は2061ねんまで見られないそうです。みなさんもぜひ西の空に注目!(コタジーの記事はこちら・クリック)  12月22日(木) 12月8日(金) 月のくしざし! 天気が悪く、年内のダイヤモンド富士がとれなかったので「タワーくしざし満月」をとってみました。 12月8日は、満月のすぐそばに本当は明るい火星が見えていたですが、さらに明るい月の明るさに合わせてとったので写っていません。 タワーの頂上の部分がぴったり満月の中に入りました。17時半くらいから5分おきにとったものを後で合わせました。 月の軌跡(きせき=動いたあと)を見ると、ずいぶんと地面から立っているのがわかります。 冬の満月の動きは、この時期の太陽とは反対に、天の高いところを通ることがわかります。でもこれは満月の時だけで、月の形がかわると通る高さもかわります。冬では、新月になるほど高さが低くなります。(冬の太陽と同じになる) 夏はこの反対で、満月は低く、新月に近くなるほど高くなります。太陽は、何か月もかかって高さがかわっていきますが、月は2週間くらいの間に、高くなったり低くなったりしているというわけです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  12月4日(日) 桜草咲いた! 先日の観察会で、こたじま先生から頂いた桜草に、花が咲きました。去年はピンク、今年は白でした。今年は二株頂いていて、もう一株もつぼみが出てきたので、何色が咲くか楽しみです。 (画像と情報:4年生隊員のSさん) ★寒くて花の少ない時期にもきれいに咲き続ける桜草(=プリムラマラコイデス)うれしいですね。みなさんのところでは何色が咲くかな。  11月27日(日) 大根できたよ~! 畑プロジェクトで種から育てた大根。できました! (画像と情報:畑プロジェクトメンバー) ★某農大の有名な「大根おどり」を思い起こしました。大根ってできると思わずにぎりしめて踊り出したくなるものみたいですね。わかるわかる。  11月26日(土) バッタのソフト食べたぞ! イナゴが突き刺さったソフトクリーム。長野県の諏訪湖で発見。思わず挑戦しちゃいました。 「ソフトクリームの甘い味にイナゴのしょっぱいところが合っておいしかった。でもちょっと見た目がグロかったよ」(本人談) (画像と情報:4年生隊員のK君) ★地球を救う「昆虫食」がちょっとしたブームとか。イナゴは日本ではひかくてきポピュラーな食べ物みたいですが、ソフトに合わせるとは!隊員なら挑戦したくなるよね~  11月20日(日) 11月20日(日)木の実を拾いに公園に行こう! リースづくりのためのつるとりも終わり、いよいよ12月3日はリースづくり本番。みなさんも、各自で木の実や木の枝など、リースづくりに使えそうな材料集めをしましょう。 11月12日(土) フヨウはふよう?(不要) いいえ、リースに みなさんリース作りの材料は集めていますか?フヨウの実がリース作りに使えるというので、近所の鉄道にそう道や石神井川ぞいの道で見つけたので集めてきました。12/3にもっていきますね。 (画像と情報:スタッフのコタジー) ムクドリの大群 ムクドリの繁殖期は春から夏にかけてで、それが終わると親鳥も巣立った子どもも一緒になって群れを作るようになります。秋から冬にはその群れは大きくなって、何百、何千、場合によってはそれを超える数のムクドリが群れを作るそうです。この時期、上石神井周辺でも、夕方にムクドリの群れを見ることができます。ムクドリは群れでねぐらに集まって寝るそうですが、おもしろいのは、寝ぐらに向かう前に、一回、どこかに集まることです。写真は、夕方、高圧線の鉄塔に集まったムクドリです。こうして集まったあと、何かをきっかけに、群れはねぐらに向かって飛び去っていきます。いくつかの群れが集まっているようで、見ていると、電線に残っているムクドリもいて、すべてのムクドリがいっぺんにねぐらに向かうのではないようです。それでも暗くなる前には、鉄塔や電線には一羽のムクドリもいなくなります。 →画像クリックで拡大 →動画(クリック) 10月27日(木) カノープス見えた! 南の低い空に見ることのできるカノープス。見えました!ただし午前3:23。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★シリウスに次いで明るい星ですが、日本では高度が低いため(東京で約2度)なかなか見ることができない星です。南がよく開けた場所を探して、星座アプリなどで見える時刻(けっこう限られた時間です)を確認して、みなさんもこの冬はカノープス探しにちょうせんしてみましょう。  10月26日(水) 綿の実ができました! 畑に植えた綿(わた)に実ができました! (画像と情報:隊員のKママ) ★白いフワフワの綿の実。このフワフワからみなさんが着るいろいろな服やタオルなどの綿(コットン)製品ができるのですね。このままリースなどの飾りとして使ってもすてきですね。来年はみんなでもっとたくさん育ててみたいですね~  10月23日(日) 虹色の雲発見! 虹色の雲(彩雲=さいうん)が出ていました。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) ★太陽のそばにある高積雲などの端が美しく虹色にかがやく現象です。古くからとても縁起(えんぎ)がよいものとされています。何かいいことあるかな・・・  10月14日(金) 「石神井川そばのソバ 」 ~ にげ出したソバ ~ 西東京市の石神井川は、水が少な目で、川ぞこにたまった土には多くの野草が生えています。 このところ川べりを歩いていてやたら目につくのが、白い小さな花をたくさんさかせているつる性の野草です。大きな群れをなしてさきほこっています。葉は、かどのとれた三角形です。 『シャクチリソバ』というソバの仲間でした。にがくてまずいけれどからだいいいことで有名なダッタンソバの親せきです。昔、小石川植物園に外国から薬草としてもちこまれたものがにげ出して全国に広がったようです。ふえすぎてやっかいものあつかいされてもい ます。 ソバ粉にしてソバをつくってもにがくてまずく、むしろ若い葉を野菜にするということです。 薬草というからには、どんなこうかがあるのか調べてみましょう。(野草をやたらに食べたりしないように (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月12日(水) よっぱらったフヨウだ! 「よっぱらった?フヨウ」を見つけました。「スイフヨウ(酔芙蓉)」といい、街角でふつうに見かける花です。さきはじめた朝は花びらが白いのですが、時がたつにつれて、しぼみながらピンク→赤とかわっていきます。そのようすをよっぱらって顔が赤くなることにたとえたのですね。どうして色がかわるのか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月8日(土) 十三夜の月と木星 雲の合間から見えました! (画像と情報:隊員のGママさん)  10月2日(日) 関公園にて 関公園で出会いました。ヒバカリかな?と思ったけれどアオダイショウ? (画像と情報:隊員のGママさん) 光をあてて拡大してみると!! 浴室や洗面所など水回りでときどき見かけるオオチョウバエ。ただ地味でうっとうしいヤツと思っていましたが、ストロボで光を回して拡大撮影してみると…。  9月24日(土) 小さな細長い貝発見! 画像悪いですが、先ほど初めてキセル貝を見つけました! (画像と情報:隊員のKママ) ★陸にすむ貝はカタツムリだけではないんですよね。よく探すとこのような細長い小さな貝を見つけることがあります。キセル貝は左巻きですが、オカチョウジガイという右巻きのもいます。死んだ貝殻のように見えても水をかけると写真のように動き出すことがあります。探してみましょう!かわいいよ~  9月16日(金) 上小のヒガンバナも咲き始めました この時期になると、すぅ〜っとのびて、パッと花火のように咲くヒガンバナ。トンボ池でも咲きはじめています。 (画像と情報:スタッフのSさん)  9月15日(木) カマキリ釣りにちょうせん! 自宅で子ども文庫を開いている知人に、探検隊の本を寄付しましたところ、利用者の少年が、早速【釣れた】報告を下さったそうです。 (画像と情報:スタッフのMさん) ★探検隊の本から、身近な自然遊びが広がっていっているようでうれしいですね。みなさんもいろいろ挑戦してぜひ報告を聞かせてください。  9月12日(日) 黄色のヒガンバナ見つけた! ヒガンバナが咲き始めています。上小の駐車場わきのはどうですか? 近所に黄色のヒガンバナがあるのに気が付きました。プランター植えです。ヒガンバナは真っ赤、ピンク 白 などがあると思っていたら、黄色のもあるんですね。 黄色いのはショウキズイセンという名でもよばれています。ほかにどんな色のヒガンバナがあるのかさがしてみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  9月9日(金) トチの実 トチの実の季節になりました!公園にたくさん落ちていました。今年はリース教室やるんですか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★風の吹いた次の日、早朝のお散歩のごほうびですね~ピッカピカのトチの実、拾うとうれしくなりますね。リース教室、まだ確定ではないですが今年もやりたいなぁと考えています。みなさんも材料集め始めましょう。  9月8日(木) オケラ発見!! 露天風呂でオケラ発見!近くに田んぼもないのに・・・ (画像と情報:スタッフのKママさん) ★田んぼのような場所で見つけるイメージですが、都内にもいるんですね~。上小でもトンボ池横の側溝でスタッフのSさんが見つけた記録があります。 ※「露天風呂」というのはKママさんのおうちはお風呂屋さんだからです。 ちなみにオケラは泳ぐの得意だそうですよ。  9月7日(水) レンゲショウマ SNSで人気のレンゲショウマ。石神井公園、いろいろありますね。映えないケド・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) ★御岳山まで行かなくても身近なところでも見られるのですね~  9月4日(日) ・・・ドクターブラック・・・ 家の前の道路を黒いきれいなイモムシが3匹も歩いていました! ★頭の部分がななめの流線形。黒いボディーにオレンジ色と黄色の丸い窓みたいなもよう。おしりにはとがったアンテナが1本。新幹線にドクターイエローっていう車両があるけれど、まさにそのブラックバージョン!ということで私は「ドクターブラック」って呼んでいます。 (→資料) この時期、食草のヤブガラシから下りて地面の下でさなぎになります。身近に出会える美しい生き物ベスト3に入ると思いますよ。ちなみにとげはにせもの。さわってもだいじょうぶです。 (画像と情報:隊員のりっちゃん&ママ) 8月19日(金) 夏のオリオン 昨晩から今朝にかけては風が変わりましたね。光にもかすかな秋が感じられます。早朝の上石神井の空には冬の星座オリオンが見えていました。(19日3:38撮影) (画像と情報:隊員のGママさん)  8月13日(土) 昼間からうじゃうじゃカブトムシ 近所の民家(緑が多いところですが、広い緑地は近くにはありません)に、昼間からカブトムシが元気に動き回っている木を見つけました。 シマトネリコという木のことをテレビで紹介しているのを思い出しました。カブトムシというと、夜クヌギなどの木にやってきてじっくりと樹液を吸っているというイメージですが、シマトネリコにやってくるものは、様子がかなり違います。 昼間なのにとにかくよく動きまわり元気です。ブンブン飛び回るものもいます。この木とカブトムシの関係は、まだわからないことも多いみたいですが、埼玉県の小学生の研究も参考にしていろいろと調べてみてください。 50秒動画(→こちら) ★シマトネリコという木になぜかカブトムシが集まるという情報、聞いてはいましたがまだ見たことがありません。このシマトネリコという木は最近、庭木として人気なのだそうですが上石神井にはありますかね。どんな木が調べておいて登下校やお散歩の時などに探してみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  8月10日(水) 街路樹を見上げてみれば いま、あちこちで鳥のヒナが鳴いていますね。新青梅街道の街路樹にも鳥の巣がありました。(写真左上)青梅街道の街路樹にも何かの巣があったし、街路樹って巣作りしやすいんですかね? ★昼夜を問わず人やクルマが絶えず通る場所は、天敵におそわれにくいというようなことがあるのでしょうか。都会に暮らす鳥たちのしたたかな知恵ですね。 (画像と情報:隊員のGママさん)  8月6日(土) 夏のモフモフ 昆虫界のアイドル、セダカシャチホコ? 数日間外廊下の天井にいましたが、とうとう力尽きたご様子。 暑くないのか心配になるほどのモフモフっぷり! (画像と情報:隊員のGママさん) 8月1日(月) 上石神井駅の日の出(夏) 暑い日が続きます。早朝5時の駅から見た東の空。 冬バージョン(2月23日・クリック→動画)とくらべてみてください。 ★暑い暑い・・・と文句言ってないで、ちょっと早起きして空を楽しむのもいいですね~ ちなみに下の空の動画も素敵です。こちらも撮影はGママさん。7月27日。ほかでもない上石神井の空です。 (画像と情報:隊員のGママさん)   7月21日(木) 7月の発見いろいろ 7月に見つけた自然いろいろ。 上・石神井公園内の売店「豊島屋」さんで見つけたタマムシ(7月8日) 中・石神井公園のモミジの木に生えていたキノコ。とてもおいしいキノコなのかハムシがたくさんいました。(7月5日) 下・井草の森公園のアオギリの花。そろそろ開花です。(7月5日) ★今年は梅雨明けが早く、すぐに暑くなったためタマムシはずいぶん早くから見られた気がします。石神井公園にもいるのですね。 みなさんも見つけた夏の自然を教えてください。 (画像と情報:隊員のGママさん)  7月9日(土) オナガの子育て2022(巣立ち編) オナガのヒナたちですが、生まれたのは4羽。そのうち落ちてしまい死んでしまったのが1羽、8日の段階でかなり大きく(巣の中で羽をばたつかせている)育ってきたヒナが3羽が巣の中に確認できました。翌日9日は朝少し早め6時ころに見に行きました。ヒナはもう巣の外に出ていて、一羽は数m下のカエデの木に乗っています。もう1匹はなかなか見つからなかったですが、声をたよりに探してみると巣の真下の低木(アオキやクマザサ)の葉陰にかくれるようにとまっていました。いずれも、何羽もの親鳥がギーギーいきかい、エサを時々やりにきていました。ヒナに近づこうものなら、頭をつつかれそうないきおいでした。残る1羽のヒナはついに見つけられませんでした。ツミの声や姿がよく見らるので、1羽は捕食されてしまったのかもしれません。生きているのはどちらも飛ぶのはかなりおぼつかないヒナです。ちょっと、「巣立ち」が早かったのでしょうか。親からエサをもらっているので、そのうちしっかりしてくると思いますが、なにしろ外敵がけっこういそうなのでちょっと心配です。 5分09秒動画(→こちら)  7月5日(火) オナガの子育て 2022 5月末に近くの公園のけやきの木に巣を見つけてから、3週間以上かかってやっとオナガのヒナがふ化しました。 去年は、どういうわけか親鳥がとちゅうで巣をあきらめてしまったようですが、今年はめでたくヒナのたん生を目にすることができました。ヒナは今はすくすく育っているようですが、途中悲しいこともありました。 同じ園内にいるツミにおそわれそうになる場面もありましたが、なんとか切りぬけられたようです。今は台風の大風や大雨が心配ですが、無事に巣立ってくれるとうれしいです。高い木のななめ下からの撮影ですが、ひなはどんどん大きくなるので、そこそこ中の様子をうかがうことができます。ひなの鳴き声も聞こえます。強拡大するために望遠鏡のレンズを使いました。 2分40秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月2日(土) 10円玉みがきやってみました 探検隊で(カタバミの葉で)10円玉を磨いてから、帰って5円玉も磨いてみました。5円玉は10円玉と違ってそこまで綺麗に光らなかったです。磨いてしばらくするとまた錆びてきてしまいました。 ★今日の観察会でやった「カタバミの葉っぱ」を使った10円玉みがきをさっそく家で発展させて実験してみたんだね。こんなふうに別のものでもいろいろ試してみるとおもしろい発見もあるね。台所にあるお酢などの調味料、庭の別の葉っぱなども試してみたそうですね。こんど結果を詳しく聞かせてください。 (画像と情報:OB隊員中2のNくん)  6月23日(木) なんのまゆかな? 学校のクワの木で見つけました! ★大きな繭(まゆ)ですね。クワの木で見つけたということは、カイコの原種と言われるクワコでしょうか。しっかり糸で繭を作り、中のさなぎが鳥などに食べられないようにガードしているのですね。この糸だけを集めて布を作ろうと考えた昔の人もすごいなぁ。 (画像と情報:隊員のGママさん)   6月22日(水) 見たことあるかい? こんにちは! ハラグロオオテントウ(上)とビロードハマキ(下)です。 ハラグロオオテントウは関町で飛んでいたものです。1.2センチほどあります。 ビロードハマキは石神井公園の旧内田家住宅にいました。図鑑の絵は、はねがひらいて描いてあったので、気がつきませんでした。 どちらもツマグロヒョウモンやアカボシゴマダラ、ナガサキアゲハ、ジャコウアゲハなどと同じように近年北上してきた昆虫ですね。数年前は房総で見つかったとニュースになっていたのに、そこらへんで見られるようになりましたよね。 ★このHPではどちらも初登場の新顔さんです。練馬区内にいるのですね!ハラグロオオテントウはその名の通りの大きさであることが1円玉とのひかくでよくわかります。 (画像と情報:隊員のGママさん)  6月13日(月)ソバの花 市内の新青梅街道そばにソバの花を見つけました。がいろじゅのすぐわきに、いったいだれがまいたのでしょうか? ソバは、年に二回(夏と秋)とれるそうです。▲の形をした種を見たことがありますか? あざやかな赤い花をつける種類もあるそうです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  6月10日(金) キアゲハの幼虫 3齢までの、まだ体全体が黒っぽいうちは数多くいても、緑色が多くなった4齢の幼虫になると、なぜか数を減らしてしまうような気がします。このキアゲハの幼虫は久しぶりに見つけたビッグサイズので、もうじきサナギになるのではないかな。 (画像と情報:スタッフのSさん)  |