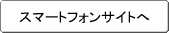| 定例 トンボ池ミニ観察会第11回 土の中の生き物を観察しよう! |
 |  |  |
 |  |  |
2016年3月27日(日) この日は、みんなで土の中の生き物の観察をしました。落ち葉の下やうえきばちをどけた下を見ると、まずミミズやヒルのなかまが見つかりました。土をほっていくとハナムグリやコガネムシの幼虫も見つかります。(下の写真)目に見える生き物だけでなく、土の中には、けんびきょうで見るような小さな生き物がたくさんいることを聞き、みんなでけんびきょうでの観察にもちょうせんしました。 (子ども13名・保護者/スタッフ15名 合計28名が参加) | ||
 |  |
この日、ジュニア隊員さんがうえきばちの下で見つけた小さな細長い貝は、オカチョウジガイのなかま。カタツムリと同じ陸生(りくせい)の貝です。まだ冬眠(とうみん)中のようでしたが、水をたらしてしばらく待つと、小さなつのを出して動きはじめました。バッタ原っぱでは小さなカタツムリも見つかりました。 | この日見つけた土の中の幼虫いろいろ。下の大きな2匹はカブクワハウスのカブトムシの幼虫。上の少し小さいのは、腹(はら)を上にしてせなかですりすり動くのはハナムグリのなかまの幼虫。腹を下にして歩くのはコガネムシの幼虫。みんなでそれぞれのちがいをじっくりと観察しました。 |
| ジュニア隊員の進級・卒業を祝う会 |
 |  |  |
 |  |  |
2016年3月19日(土) はじめに1月にできなかった今年の干支(えと)=サルにちなんだミニ自然教室で、動物としてのサル・なんと上石神井にもある「三猿(見ざる・聞かざる・言わざる)」の像の話・サルから進化した人間だけが手に入れた「火起こし」の方法などについてクイズで楽しく学びました。楽しい昼食会のあとは、トンボ池で卒業生による記念植樹。今年も昔から人々の生活の身近な場所に植えられ、生き物ともつながりの多い木として選んだ「桃」「無花果=イチジク」の苗木を植えました。さらに「ゆみぎり」「まいぎり」「もみぎり」などの道具や「火打石」を使った火起こしをみんなで実際に体験。煙があがったり、火花を火口(ほくち)に移し、うまくロウソクまで点火できた時は、歓声(かんせい)が上がりました。 (子ども23名 ・保護者/スタッフ22名 合計45名が参加) | ||
| 定例 トンボ池ミニ観察会第10回 カエルの卵やヤゴ観察&シイタケを育てよう! |
 |  |  |
 |  |  |
2016年3月5日(土) この日は啓蟄(けいちつ)。まずはトンボ池のヒキガエルの卵をけんび鏡で観察しました。トンボ池では芽が出始めたアサザの間でミズムシという生き物も発見しました。そのあとプールでクロメダカやヤゴなどを観察。今年もいろいろな種類のトンボのヤゴがかなりたくさんプールで冬をこして育っていることがわかりました。そのあとさらに、去年の秋に切りたおしたトンボ池のコナラの幹(みき)にドリルであなを開けて、参加者全員でシイタケ菌を植え付ける作業を行いました。これも雑木林の自然をむだなく生かす昔の人々の知恵。うまくいけば秋にはトンボ池産のシイタケが採れるはず。楽しみです。またこの日とどけられた約20匹のカブトムシの幼虫を大型の植木ばちにトンボ池の落ち葉で作ったふよう土を入れたものに分けて入れ、カブクワハウスでの飼育を開始しました。 (子ども27名 ・保護者/スタッフ14名 合計41名が参加) | ||
| 臨時 トンボ池整備作業 コナラ・クヌギの枝おろし・ふよう土作りなど |
 |  |  |
 |  |  |
2016年2月29日(土) 池のまわりのクヌギとコナラ。毎年手入れをしないと大きくなりすぎてしまいます。この日ははしごをかけて枝や葉を下ろし、葉っぱは、ふよう土ボックスで米ぬかとまぜてふよう土にする作業を行いました。去年の葉っぱはふかふかのふよう土になっていたのでカブクワハウスでカブトムシの幼虫のエサにし、残りはよいひ料になるので畑プロジェクトの畑に運びました。ほかにも池のそうじや整備、バッタ原っぱにあるトカゲのための石づみの補修作業(ネットかけ)、巣箱のかけかえなどの作業を行いました。 (子ども・OB15名 ・保護者/スタッフ15名 合計30名が参加) | ||
| たき火 |
 |  |  |
2016年2月6日(土) この日は、今年は中止になってしまった日の出を見る会の朝に予定していたたき火を行い、同時にトンボ池の整備の際に出た、杭などの廃材や伐採(ばっさい)した小枝、冬の間松の木に巻いていた「こも」などを燃やしました。子ども達もふだん使うことの少ないのこぎりの使い方をお父さんに教わりながら薪を切ったりして、これまた最近ではめったにできない「たき火のお手伝い」をがんばりました。探検隊では、においや煙がなるべく出ずに完全燃焼するように工夫したドラム缶で、消防署にも事前に届け出をした上でこの作業を行っています。最後に残った灰も、畑の肥料やしぜん教室での実験材料として活用します。 (子ども11名 ・保護者/スタッフ10名 合計21名が参加) | ||
| 定例 トンボ池ミニ観察会第9回 こもはずし・冬ごしする生き物の観察 |
 |  |  |
 |  |  |
2016年2月6日(土) 10月にまいた「こも」をはずして、中で冬ごしをしている生き物の観察をしました。(上左・中)マツカレハの毛虫は合計271匹(上右)。これは去年の1160匹からくらべると、だいぶ少ない数でした。ほかにもカメムシ(下左・中)やヤモリ(下右)、テントウムシ、クモ、ワラジムシなどたくさんの生き物を見つけることができました。マツカレハの毛虫だけは、こもを巻いた松やヒマラヤスギの葉を食べつくすこともある害虫なので、土にうめて処分(しょぶん)し、あとの生き物はトンボ池のまわりににがしてやりました。しぜん探検隊では毎年このようにこもを使った自然にやさしい方法で、マツカレハのたいじをしています。 (子ども11名 ・保護者/スタッフ11名 合計22名が参加) | ||
| 定例 トンボ池ミニ観察会第8回 「冬のかおり」クイズをしよう |
 |  |
 |  |
 |  |
2016年1月6日(水) みんなで校庭を回り「冬のかおり」探しをしました。(上の2枚) スイセンのあまいかおり、キクの花や葉の特ちょう的なかおり、ノビルの根のネギのようなかおり、カレーやシチューのかおりづけにも使われる月桂樹(げっけいじゅ=ローリエ)の葉のかおり、そして、へクソカズラのタネの一度でおぼえてしまうあのかおり・・・その場でかいでしっかり覚え、最後に目かくしをして「かおり当てクイズ」にちょうせん。パーフェクト解答の人が5人もいました。 そのあとは、バッタ原っぱでモグラのトンネル観察(中左)、野鳥のためのペットボトルフィーダー(ひまわりのタネ)の取り付け(下左)なども楽しみました。 あたたかかったため、ナナホシテントウ(中右)やバナナ虫にも出会えました。トンボ池では、プランクトンにやわらかい部分を食べられて葉脈(ようみゃく)だけになった葉っぱ(下右)もたくさん見つかりました。 (子ども10名 ・保護者/スタッフ10名 合計20名が参加) | |
| 定例 トンボ池ミニ観察会第7回 バッタ原っぱ整備作業と落ち葉はき・冬の生き物観察 |
 |  |
 |  |
2015年12月5日(土) この日は午後の観察会になりました。トンボ池のまわりの落ち葉をみんなで集めてふよう土ボックスに。砂でうまったみぞもさらいましたが、大きなミミズがいっぱい出てきておもしろかったです。さらにバッタ原っぱの草をかり、トカゲやカナヘビのすみかの石も積み直しました。ずいぶん寒くなりましたが、それでも作業をしているとテントウムシやバナナ虫、クモ、ヨトウガの幼虫など、かれ草のかげや落ち葉の下、土の中で寒さにたえているさまざまな生き物のすがたに出会うことができました。 (子ども8名・保護者/スタッフ8名 合計16名が参加) | |
| ねりま遊遊スクール 「しぜんの素材でオリジナルリースを作ろう!」 |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年12月5日(土)朝早くから100名を超える参加者が体育館に集まりました。 参加者は説明を聞いたあと、まず丸く編まれたつるの中から気に入ったものを選んで自分のリースの土台にします。次に用意された様々な自然の素材の中から使いたい材料を自由に選び、あとは作業台の上でグルーガンや接着剤を使ってつるに材料を貼り付けて思い思いのリースに仕上げる作業にとりくみました。 この教室は練馬区の遊遊スクールの指定講座ということで、上小以外にも区内のたくさんの小学校のお友達も参加してくれて、みんなで楽しく作業にとりくむことができました。また上小の副校長先生や先生も参加して、子ども達と一緒にオリジナルリース作りを楽しんで下さいました。 参加した子ども達からは「友達と楽しく作れたのがうれしかった。」「毎年来ているけれど、年によって木の実とかの種類がちがっていたりしておもしろい。」「かわいくできたのでうれしい。もっとやりたくなった。」保護者の方からは「こんなに本格的なリースが作れるとは思っていなかったので、大満足です。」「たくさんの材料に驚きました。自然のもので好きなように作れてとても楽しく参加できました。」「入学以来毎年参加させていただいています。毎年とても楽しみにしています。」などの感想をいただきました。 今年も地域の素材を生かしたたくさんの手作りリースが、今ごろそれぞれのご家庭に飾られていることでしょう。ご協力いただいたたくさんの皆様、どうもありがとうございました。 (子ども73名・保護者/スタッフ40名 合計113名が参加) | |
| リースの材料・くずのつるを採りに行きました! |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年11月23日(月) 12月5日に予定されている「しぜんの素材でリースを作ろう」に向けて、材料集めなどの準備が進んでいます。 この日は、区内でも大変貴重となった、かつての石神井川沿いの雑木林の自然が残るW学院の敷地で、特別に許可をいただき、葛(くず)という植物のつるを採取させていただきました。木のこずえまで、はい上がった数メートルものつるを根元から切って、みんなで引っぱって採り、その場でリースの形にまいていきました。2時間ほどの作業で150本あまりのつるを採取。つる以外にもドングリやカラスウリの実なども集めることができ、これらはみんなリースの材料として活用します。 雑木林の中には、最近ではめったに見ることのない生き物のすがたも見られ、作業のあいまにみんなで観察しました。左下はムカデ(トビズムカデ)。右下はこれも最近見ることのへった大きなカタツムリです。 (子ども18名・保護者/スタッフ15名 合計33名が参加) | |
| 大泉さくら運動公園 隊員親睦バーベキュー大会 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年11月21日(土) 気持ちのよい秋の一日。上石神井からも自転車で行ける大泉さくら運動公園で元気に遊び、バーベキューで親睦を深める会が行われました。 芝すべりや木登り、木の実ひろい、落ち葉のかけっこ、四つ葉のクローバー探しに虫さがしなどで自然の中でたっぷり遊び、持ちよった食材でにぎやかにバーベキュー・・・と探検隊らしい一日をみんなで楽しむことができました。 定番のソーセージや野菜はもちろん、焼きそば、ピザ、じゃがバター、ポップコーン、トン汁、チーズフォンデュ、焼き鳥、焼きマシュマロ・・・とみんなで少しずつ持ち寄った食材で、多様なアウトドア料理を楽しむことができました。 参加者からは「区内にこんな公園があるのは知らなかった」「明日も来たい!」「今回思い切ってBBQセットを買ってしまった。これをきっかけにアウトドアを楽しみたい」「自然の中で久しぶりに一日のんびりできた」「バーベキューと言ってもこんなにいろんな楽しみ方があるとは知らなかった。次回も楽しみ。」などの声が聞かれました。 (子ども23名 ・保護者/スタッフ22名 合計45名が参加) | |
| 地区祭2015 手作り&自然グッズのお店と魚拓製作ワークショップ・吹きトンボゲームで参加 |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年11月1日(日) 地区祭に参加しました。お店コーナーには、子ども達やお家の方、地域の方がこの日のために準備してくれた様々な手作りグッズ、探検隊らしい自然の素材を生かしたオリジナル商品数百点が並びました。また本物のお魚を使った「魚拓(ぎょたく)作り体験」のワークショップも大人気。スタッフがこの日のために釣ってきたメジナなどの魚に一人ひとり自分で墨(すみ)をぬり、ほとんどの参加者が生まれて初めてという「魚拓作り」にちょうせん。できた作品を大事そうに持ち帰る子ども達のすがたが見られました。またジュニア隊員さん達がアイデアを出し合って用意した「空気てっぽう」の原理でストローでトンボを吹いて模型のトンボ池やプールに入れるゲームのコーナーが大人気。140名もの参加者を集めました。 ※この日の売上はすべて今後のトンボ池等の維持管理やしぜん探検隊の活動に使わせていただきます。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 (子ども33名 ・保護者/スタッフ34名 合計67名が運営に参加) | |
| 地区祭にむけて 前日準備作業 |
 |  |
 |  |
2015年10月31日(土) 地区祭に向けて最後の準儀作業が行われました。商品に値段のシールを付けたり、手書きのポップ、看板を作ったりする作業にみんなで手分けして取り組みました。「なんだか文化祭の準備みたいで楽しい!」と大人も子どももいっしょになっていきいきと夢中になって作業をしていました。こんなところも探検隊らしい風景です。 (子ども6名・保護者/スタッフ16名 合計22名が参加) | |
| 地区祭にむけて 魚拓(ぎょたく)教室リハーサル&ゲームコーナー作り ほか |
 |  |
 |  |
 |  |
2015年10月25日(日) 地区祭で行うワークショップに向けて、魚拓作りの講習会を行いました。ここでコツをつかんだお父さん隊員さん達が地区祭当日は参加する子ども達への体験指導にあたります。またジュニア隊員さん達は、みんなで力を合わせて地区祭でかかげる看板(かんばん)や、ゲームコーナーのセット作りに取り組みました。お母さん方も作業や子ども達のサポートに熱心に取り組んで下さり、家庭科室は本番さながらの熱気につつまれました。 (子ども15名 ・保護者/スタッフ21名 合計36名が参加) | |
| ミニ活動 秋の海づり教室 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年10月17日(土) 横浜市の末広水際プロムナードにてしぜん探検隊恒例、秋の海釣り教室が開かれ、探検隊海釣り部のみなさんが集まりました。 今日はお天気が心配だったのですが、参加者の日頃の行いがいいせいか、幸い雨にも 降られず、1日楽しく釣りができました。 今日の参加者は幹事含めて総勢25人、釣れた魚は メジナ、ウミタナゴ、アジ、サッパ、カワハギ、ハゼです。 地区祭での魚拓体験コーナーで使えそうな、いいサイズのメジナも釣れましたよ。 参加者の中には初めて釣りをする人も何人かいて、釣りの楽しさに目覚めた人もいる のではないかと思っています。 (子ども12名 ・保護者/スタッフ13名 合計25名が参加・画像と情報提供:スタッフの久留島さん・萩原さん) | |
| 定例 トンボ池ミニ観察会第5回 秋の作業と冬ごし前の生き物たちの観察 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年10月12日(月) この日は、まだ東門でアブラゼミの声が聞こえていましたが、それでも気温はぐっと下がってきました。秋です。まずは、田んぼゾーンで稲(いね)かり。鳥よけのネットをはっていましたが、ジュニア隊員さんの観察によると、なんとネットの中に入りこんで稲を食べていたスズメもいたとか!お米をめぐる人間とスズメの長いちえくらべのれきしが、このトンボ池でも続いているようです。 この日のメインの作業は、こうれいのコモまき。ワラでできたコモを校庭のアカマツ・クロマツとヒマラヤスギの木の幹(みき)に巻きつけ、マツカレハの毛虫をはじめとした冬ごしの生き物を集めるしかけです。ワラでできたコモは手を入れてみたり、じっさいに中に入ってみると「ホントだ。あったか~い!」・・・試してみるのが探検隊(笑)。 プールではヤゴやメダカの赤ちゃんなどをすくったり、けんびきょうで観察したりしました。 また、校庭に取り付けてある巣箱の確認も。秋から冬の間に中の古い巣をそうじし、巣箱が落ちてきたりしないようにひもを付け直したりするメインテナンス作業が続きます。 バッタのためのビオトープ=「バッタ原っぱ」では、バッタのエサとなるススキを増やすためにお月見で使ったススキの穂(ほ=タネ)をまいたり、トノサマバッタを放したりする活動も行いました。 ※この日みんなで発見した生き物の一部はトップページ「トンボ池最新情報」で紹介しています。 (子ども13名 ・保護者/スタッフ11名 合計24名が参加) | |
| 中秋の名月の夜の楽しい行事 「お月見どろぼう」を体験しよう! |
 |  |
 |  |
2015年9月27日(日) 夕方から急速に雲が切れ、参加者が続々と今回の会場、平成公園に集まってくるころには、東の空に大きな十五夜の月がのぼってきました。 前半は、古田島先生から月についてのお話を聞き、そのあと全員で4台の望遠鏡で月のもようや表面に見えるクレーターをじっくりと観察しました。「こんなに大きな月を見るの、初めて!」「ほんとにウサギの形に見える!」「色がオレンジ色できれい!」「クレーターがはっきりわかった!」など子どもからも大人からもかん声があがりました。 後半は、地域のご協力も得て、農家の庭先にかざられたお月見のお供えを子ども達がどろぼうに行く「お月見どろぼう」の伝統行事体験です。これは40年くらい前まで練馬でも広く行われていたお月見の夜の行事で、子ども達はこの日だけは、近所の家々にかざられたお供えものをぬすんでもよい、またぬすまれた家はよいことがあるとされていたものです。今では行われることもほとんどなくなってしまっている行事ですが、いわば日本版ハロウィーン。探検隊では2005年からこの行事の復活イベントにとりくんでいます。今回はついに参加者が100名規模となり、参加者みんなで月明かりの下、楽しいドキドキを体験しました。 参加者の感想アンケートは現在募集中。集まり次第、また紹介します。 (子ども47名:保護者/スタッフ48名・地域の方々8名 合計103名が参加) | |
| 地区祭に向けて カード型ミニ標本・竹のびゅんびゅんゴマを作ろう |
 |  |
 |  |
2015年9月13日(日) この日はアオダイショウのぬけがら(スタッフが練馬区内で見つけたものです。1m以上もあるものが合計3本もありました!)や、鳥やチョウの羽をとうめいプラスチックの中に入れてパウチして作る「カード型ミニ標本」(そのままルーペやけんびきょうで観察できます。ヘビのぬけがらはカードケースに入れて持ち歩けば「おまもり」に!?)作り。また、みんなで7月に竹をけずって作って、夏休みの間に絵をかいてもらった「手作りびゅんびゅんごま」にとうめいニスをぬって仕上げる作業にとりくみました。 お父さんやお母さん、地域の隊員もたくさん集まって、ていねいに作業を進めてくれたので、すてきな商品がたくさんできました。これから地区祭までの間、何度かこのような商品せい作会やじゅんび会をおこなっていく予定です。ぜひ参加して下さい。地区祭でワークショップをする「魚拓(ぎょたく)」作りの講習会もお父さん方向けに予定しています。お楽しみに! (子ども14名・保護者/スタッフ11名 合計25名が参加) | |
| 3年生授業サポート トンボの産卵お助け大作戦! |
 |  |
 |  |
 |  |
2015年9月7日(月) この日は、プールに草をうかべて、草がないとたまごを産めないギンヤンマやイトトンボなどのトンボのために産卵(さんらん)場所を作る活動にとりくみました。3年生の子どもたちがみんなで畑の草をとってきて、それをバラバラにならなりようにネットでくるみ、水面にじょうずにうくように、ペットボトルの「うき」を中に入れてしばりました。各クラスで1本ずつ作ったものをプールサイドに運び、みんなで水面にうかべました。 さらに今年は、夏の間にそだてておいたクロメダカを一人1ぴきずつプールに放流(ほうりゅう)する活動にもとりくみました。プールには秋から春の間にエサになるミジンコなどのプランクトンがたくさん発生するので、メダカもよく育つのです。一部のメダカはヤゴのえさにもなりますが、生きのびたメダカは、春にまたたくさんの卵を産むのでさらに数が増えるのです。またメダカがいることで、プールに蚊(か)の幼虫であるボウフラが発生するのをふせぐはたらきも期待されます。 このように、人間がちょっとくふうして、はたらきかけることで、秋から春の間のただの使っていないプールも、いろいろな生き物がバランスよく生活したり、増えたりすることのできる「ビオトープ」(=生き物のための池や庭)になるのです。 この日はあいにく、とちゅうから雨がふり出してしまい、トンボが産卵にくるようすまでは観察できませんでしたが、お天気がよい日には、きっといろいろな種類のトンボが上小のプールに集まってきて、産卵を始めるはずです。上小のみなさんは、その様子もぜひ自分の目で直せつ観察してみてください。 (3年生は学年参加:保護者/スタッフ10名が参加) | |
| 定例 トンボ池ミニ観察会第4回 草取りをしながら生き物とあそぼう! |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年9月5日(土) 8月後半からぐずついたお天気の日が続いていましたが、この日は久しぶりの晴れ間。約50名の参加者が5つのグループに分かれて、夏の間においしげったトンボ池まわりやバッタ原っぱの草をぬいたり、えだを切ったりしてビオトープ(=生き物のための庭)としての環境を整える作業にあせをながしました。葉っぱの上・中・下から次々のすがたをあわわす昆虫やクモ・トカゲ・カエルなどの生き物を手にとって観察したり遊んだり。 トンボ池では産卵にやってきたトンボがみんなの指の上でひと休み。こんな時間も楽しいですね。 作業をしながら、夏休みの思い出や、楽しい発見を交かんしあうこともできました。自由研究でアゲハチョウとキアゲハを飼育して観察をしたという人。セミの羽化がらを集めて分類したという人。「夏休みの終わりごろになるとセミはメスがふえるって気付いたの!」などという発見も聞かせてくれました。 ※この日みんなで発見した生き物の一部はトップページ「トンボ池最新情報」で紹介しています。 (子ども29名 ・保護者/スタッフ18名 合計47名が参加) | |
| 3年生授業サポート トンボの産卵お助け大作戦!事前授業 |
 |  |
2015年9月3日(木)上小のプールには2000年まではギンヤンマのヤゴは1匹もいませんでした。ふつう、学校のプールにはギンヤンマが来て産卵することはあまりないのです。それが子ども達があるとりくみを始めたことにより、毎年たくさんのギンヤンマが産卵にやってくるようになったのです。いったいどんなとりくみをしたのか?それをすることによってなぜギンヤンマが来るようになったのか?これまでのデータやトンボの生態について探検隊スタッフの田中さんの説明を聞いて3年生みんなで学習しました。すでにプールでのヤゴの救出を体験し、教室や自宅でギンヤンマのヤゴを飼育した子ども達の関心は高く、よく話を聞き、田中さんの問いかけにもどんどん手をあげて答えていました。さすが! (3年生は学年参加:保護者/スタッフ7名が参加) | |
| ミニ活動 善福寺公園 セミの羽化観察会 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年8月8日(土) 今年はセミの出現が早いようだったので、はたしてこの時期で十分観察できるか心配もしていたのですが、いざ池のまわりを歩き始めると、まちがってふみつけないか心配しながら歩くほど大量のセミの幼虫がいて、参加者からはおどろきの声があがりました。上石神井近辺で見られる6種類のセミ(ニイニイゼミ・アブラゼミ・ミンミンゼミ・ツクツクホウシ・ヒグラシ・クマゼミ)すべての幼虫またはぬけがらを確認することもできました。またセミだけではなく、夜の森に姿をあらわしたヤモリ・ナナフシ・ヒキガエル・スズメガの仲間・鳴きはじめた虫の声・落ち葉についた小さな虫の卵まで、一つひとつ立ち止まって観察し、発見やおどろきをみんなでゆっくりと共有することのできた探検隊らしい観察会となりました。保護するためにそっと取りあげた幼虫が手の中でもぞもぞ動く感しょく。ライトの光にうかび上がるすき通るようなまっ白なセミのすがた。おそるおそるさわったヤモリのつめたいはだ・・・は、子どもにも大人にも忘れられない夏の思い出となったことでしょう。 みなさんも資料などを参考に見分け方を覚えて、ぜひ6種類のセミのぬけがらコレクションにも挑戦してみてください。 ※参考書籍 「セミのおきみやげ」 (たくさんのふしぎ傑作集・福音館書店) ★現在絶版ですので図書館で探してみましょう。このほかにもセミをテーマにした子ども向けの本はたくさん出ています。興味をもった時が読みどきです。ぜひいろいろさがしてみましょう。 (子ども23名 ・保護者/スタッフ19名 合計42名が参加) | |
| ミニ活動 野菜プロジェクト夏のしゅうかく祭 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年8月6日(木) 夏の強い日ざしをあびて、春に植え付けたさまざまな作物が実りのじきをむかえています。この日はミニ活動「野菜プロジェクト」のメンバーが集まり、トマト・ニンジン・ナス・ゴーヤ・にら・青じそ・赤じそ・ミント・バジル・みょうがなどをしゅうかくし、サラダやパスタ・ピザ・チヂミなどに調理して味わいました。自分たちで育てたとれたての野菜の味はかくべつでしたよ。 (子ども10名 ・保護者/スタッフ8名 合計18名が参加) | |
| ミニ活動 竹でびゅんびゅんゴマを作ろう・おもしろい炭を作ろう |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2015年7月25日(土) 秋に予定されている地区祭に向けての作品作りが始まりました。この日の1つ目のプログラムは、地元の天然素材「竹」を使って作るびゅんびゅんゴマ作り。竹を切って、紙やすりできれいにけずってまん中に糸を通すあなをあける作業。みんなでもくもくとがんばって100個以上作ることができました。このあともようを入れたりして作品として仕上げます。2つ目のプログラムは高学年向け「空きカンを使った炭づくり」。リース作りに時に使ったマツボックリなどの木の実やビスケットなど、面白い形の材料を選んでアルミはくでふたをしたカンの中で煙(けむり)が出なくなるまで蒸し焼き(むしやき)に。できあがった炭は、手作りのカゴに入れてお部屋のインテリアに。炭なので脱臭効果(だっしゅうこうか)もあるかな。このほかにも探検隊では地区祭に向けてさまざまなオリジナルグッズの製作をしていく予定です。地区祭は11月1日(日)上小の校庭で開かれます。楽しみにしていてください。 (子ども13名・保護者/スタッフ15名 合計28名が参加) | |
| ミニ活動 上石神井の森・夜の観察会 |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年7月18日(土) 台風11号のあとの風と雨がようやくやんできた午後7時。西の空には夕焼け、東の空にはきれいな虹(にじ)がかかっているのを見上げながら、ぞくぞくと参加者がヒグラシも鳴き始めた森に集合しました。雨があがるのをじっと待っていたのでしょうか、クヌギの樹液(じゅえき)にはたくさんの虫が集まっていました。カナブンやガにまじって、カブトムシ、コクワ、ノコギリクワガタなどが次々と見つかり、子どもからも大人からも歓声があがりました。紫外線(しがいせん)の出る特別なライトを使った「ライトトラップ」にもたくさんの虫が集まりました。ナナフシ、ニイニイゼミ、カメムシ、夜には目が黒くなるカマキリなどをかいちゅう電とうの光の中でじっくりと観察して楽しんだあと、すべての虫を元いた場所にもどして、無事夜の観察会は終了しました。 (子ども31名 ・保護者/スタッフ26名 合計57名が参加) | |
| 定例 トンボ池ミニ観察会第3回 ヤブガラシとり・フトイのかぶわけ・セメント工事 |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
2015年7月4日(土) 梅雨(つゆ)に入り、トンボ池のまわりも草や木々が一気においしげってきました。そこでまずは、ほうっておくと下の木を弱らせてしまうヤブガラシのつるをみんなでとりのぞきました。プールわきのバッタ原っぱは小さいけれどバッタやコオロギのだいじなすみかなので、バッタのエサになるイネのなかま(イネ科)の草だけをのこしてそれいがいの草とりをしました。トンボ池の入口の土どめがくずれていた部分はセメントで修理(しゅうり)して、さいごにセメントに葉っぱの型(かた)をつけてもようにしました。トカゲのための石づみもくずれにくいように下の方をセメントでかためました。毎年秋にプールにしずめるための植物を植えたコンテナボックスは上小で長年取り組んでいるオリジナルのアイデア。でもフトイの株(かぶ)が大きくなりすぎていたので、久しぶりに中を土ごととり出して、株分けをしました。このコンテナは夏の間は水をはって中にメダカなどを入れたミニビオトープにします。プールが子ども達でいっぱいの間は、こちらに来てたまごを産むトンボもきっといるはずです。今日は参加者も多く、力仕事ではお父さん隊員が力を出し合って大活やくしてくれました。 ★この日見つかった生き物はトップページ「トンボ池最新情報」(→こちら)の方でしょうかします。 (子ども32名 ・保護者/スタッフ23名 合計54名が参加) | |
| 1年生の教室でのヤゴ飼育をサポート(2) |
 |  |
2015年6月26日(金) 5月から毎週金曜日の中休みにジュニア隊員と保護者隊員で続けてきた1年生の教室でのヤゴの飼育のサポート活動。いよいよ、残り1クラス一匹のみとなりました。来週の金曜日で、今年の1年生教室での活動は終了の予定です。 毎週、毎週、熱心に話しかけてくれる1年生の女の子は今年から探検隊に入隊してくれたジュニア隊員さん。今日は「家で飼ってたヤゴも羽化したんだよ!」と小おどりしながら教えてくれました。サポート活動を続けてきてよかったなと思えるうれしい瞬間です。 7月3日(金)の最終回、お手伝いいただける保護者の方は10時にトンボ池にお集まり下さい。 ※羽化が終了しなかったので10日(金)も行います。 | |
| ミニ活動 畑プロジェクト じゃがいもの収穫と畑のおせわ |
 |  |
 |  |
2015年6月20日(土) 梅雨(つゆ)晴れ間、じゃがいものしゅうかくにミニ活動・野菜プロジェクトのメンバーが集まりました。このジャガイモは春に植えつけたメークイン。今年は5月のお天気がよかったせいか、丸々と大きないもが予想以上に育っていました。その場でさっそくふかして味見をしました。 この時期、畑は世話をしないとすぐに草が生えてきます。しゅうかくだけでなく、みんなで畑やそのまわりの草取りもしながら植物や昆虫の観察も楽しみました。 じゃがいものしゅうかくの終わった4畝(うね)分の場所にはさっそく、土のじょうたいを調整する苦土石灰(くどせっかい)という白い粉をまいて、トンボ池の「ざっそうの森」からえいようたっぷりのふかふかの黒土を運んで耕運機(こううんき)でたがやしました。 倉庫がわの新しいスペースには、ゴーヤ(にがうり)の苗を植え付け、ネットをはりました。 畑ではほかにも、ナス、トマト、ゴマ、青じそ、ニンジン、ラッカセイ・・・などいろいろな作物を育てています。みなさんも学校に来た時にのぞいてみてください。 (子ども8名 ・保護者/スタッフ8名 合計16名が参加) | |
| 臨時作業 ペンキぬり・トンボ池のまわりの整備作業 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2015年6月13日(土) 梅雨(つゆ)のあいまをぬって、ふよう土ボックスやしざい小屋、けいじ板などのいたんだ部分のペンキぬりをしました。きれいになったふよう土ボックスにはジュニアリーダーさん達がきれいに色をぬってくれたプレートを取り付けました。 大人隊員は、カブクワハウス前にたまっていた古い枝や草もかたづけ、土をふるいにかけてきれいにしました。田んぼゾーンには前回少したりなかったなえを追加で田植えして、新しいプレートも立てました。 トンボ池のまわりにはたくさんのカマキリの赤ちゃん、池にはまっ赤なショウジョウトンボ、コナラのひこばえ(切ったみきから出てきた芽)をかき分けると中にカナブン・・・と、作業のあいまにもたくさんの生き物に出会えました。校庭の梅の木には今年もりっぱな青梅が! (子ども4名 ・保護者/スタッフ6名 合計10名が参加) | |
| 第1回しぜん教室 プールの生き物について知ろう・ヤゴ救出大作戦! |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2015年6月6日(土) 前半は図書室でヤゴとはどんな生き物か、なぜプールのヤゴを救出(きゅうしゅつ)するのかなどについてクイズをといたり、写真や動画を見たりしながら学習しました。そのあと大人も子どもも実さいにプールに入って、探検隊で用意したプラスチックのカゴを使ってヤゴやメダカなどプールの生き物の救出活動を行いました。見つけた生き物は種類ごとに分けて数をかくにん。ヤゴやメダカは家でかってみたい参加者に持って帰ってもらい、のこりはトンボ池に。 ジュニア隊員さんの何人かは午後も来て、スタッフといっしょに用具の後かたづけやプールのおそうじにあせを流しました。夕方までかかってプールの中のヘドロを全部流し、ヤゴやメダカも最後の1匹まですくいだしてくれました。 ここから3カ月。9月まではプールの主役はヤゴから子ども達にこうたいです。 (子ども 63名 ・保護者/スタッフ 43名 合計106名が参加) | |
★参加者の声より★ ・はじめての参加でしたが、すごく楽しかったです。トンボの種類も勉強になり、より興味が増しました。 ・子どもが楽しく興味深く参加でき、とてもよかったです。安全にもとても気を付けていただいていました。説明やクイズもわかりやすく大変よかったです。 ・子どもが「絶対に行きたい!」と学校からの手紙をうれしそうに持ってきました。初めての参加でなかなか体験できないことを経験できてとてもよかったです。また参加したいです。 ・大人が本気でヤゴ取りをしているすがたがすてきでした。 ・初参加でした。とても楽しかったです。童心にかえれました。きょうだいや友達に声をかけてみんなで来年も参加したいです。 ・(最後に一直線にならんで)いっせいにやるのがおもしろいと思いました。 ・子どもが初めてのヤゴ取りに夢中になっている姿を見てとてもよかったです。自分も子どもの頃を思い出しました。(このような活動を)ぜひ続けてほしいです。 | |
| 職員室横 ヤゴの展示コーナーを開設しました(羽化写真募集中!) |
 |  |
2015年6月2日(火)今年も南校舎1階のしょくいんしつ前のろうかにヤゴの展示コーナーを開設しました。上小のプールでとれた各種のヤゴを生きたじょうたいで見ることができます。それぞれ特ちょうのある形ですから、じっさいに見て、ちがいを観察してみて下さい。 今年はヤゴの羽化写真を掲示(けいじ)するコーナーも作りました。教室や家でヤゴを飼育している場合は、そのヤゴがトンボになったらぜひ写真をとってヤゴ展示コーナーに自由に掲示してください。展示コーナーのつくえの上にふせん紙がありますので、名前を書いて(ニックネームOK)写真にそえてください。 | |
| 3年生授業サポート プールのヤゴ救出大作戦! |
 |  |
 |  |
2015年6月2日(火) 3年生の総合的な学習の授業「プールのヤゴ救出大作戦」を大人隊員でサポートしました。 この日は気持ちのよい青空のもと、3年生の子ども達が交たいでプールに入り、プラスチックのカゴを使って、水中のヤゴを救出しました。すくったヤゴは種類ごとに分るいして、子ども達が数を記録しました。 結果は、アカトンボ型(コノシメトンボなど)44匹・シオカラトンボ型5匹・イトトンボ型1匹・ギンヤンマ型333匹・その他クロメダカ350匹など。 ふだんの年にくらべて今年は5月にお天気がよく、あつい日が多かったこともあり、プールに入れたコンテナボックスのガマなどの草には、すでにかなりたくさんのヤゴのぬけがらがついていましたから、じっさいにはこれよりかなり多くのヤゴがこのプールでそだっていたのでしょう。救出したヤゴは、このあと3年生が各クラスで班ごとに、また家でかってみたい子は家に持ち帰ってトンボになるまでしいく、かんさつをしていく予定です。 (3年生の全3クラスと先生方+しぜん探検隊スタッフ/保護者19名が参加) | |
| 3年生授業サポート事前準備 プールのクロメダカ救出大作戦! |
 |  |
 |  |
2015年6月1日(月) 3年生のヤゴ救出の授業のために学校がプールの水をぬいてあさくしてくれました。そのプールの中には秋に放したクロメダカとその赤ちゃんがいっぱいいます。ヤゴ救出(きゅうしゅつ)用のかごでは、小さなメダカはうまくすくえません。そこで目のこまかいネットを用意して探検隊のスタッフがヤゴ救出の前にメダカの救出にとりくみました。とれたメダカはバケツ1ぱいで300匹いじょう。そのバケツが5はい。すごい数です。 (なぜか小さなアメリカザリガニも1匹見つかりました。いったいどこからプールに来たのでしょう。) (保護者/スタッフ8名が参加) | |
| 定例 トンボ池ミニ観察会第2回 トンボ池の大そうじ・田植え |
 | 2015年5月30日(土)トンボ池は小さな池なので1年に1度人間の手でかんきょうをととのえるひつようがあります。たまったどろや石、ふえすぎた植物などをとりのぞき、ヤゴやメダカを食べてしまうアメリカザリガニや大きな魚がいないかもたしかめます。 3チームにわかれて、こうたいで池に入り、中をさらい、生き物をすくい出してしゅるいをしらべました。大人も子どももどろんこになって楽しみました。(写真左・下) |
 |  |
 | 今年もクロメダカ(写真・左)がたくさんふえていることがわかりました。このほかクチボソ(モツゴ)、アブラハヤ、ヌマエビ、ヤゴなどがかくにんできました。みなさんのきょうりょくで今年もザリガニやバスなどの外来種はいませんでしたが、中の島に外来種のキバナショウブが生えてきていたのでとりのぞきました。 池に流れ込む水路は「田んぼゾーン」です。毎年田んぼの自然を再現(さいげん)するために稲(いね=お米のなえ)をうえる「田植え」をしています。(写真・下2枚) |
 |  |
 |  |
 | 2時間ほどの作業のあとは、水を入れて、一度すくった生き物をかんさつして、みんなで池にもどしました。(写真・上2枚) 今年はプールで秋にデング熱たいさくで入れたクロメダカがたくさんのたまごをうんでふえたので、きぼうする隊員には家でかってもらうことにして帰りにくばりました。 (子ども35名・保護者/スタッフ25名・計60名が参加) |
| 3年生のヤゴ救出活動 事前授業 サポート |
 |  |
2015年5月27日(水)6月2日に予定されている3年生の総合的な学習としての「プールのヤゴ救出活動」に向けて、事前学習が行われました。ゲストティーチャーとしてスタッフのつとむさんが3年生の子ども達にヤゴとはどんな生き物か、なぜプールのヤゴを救出するのかなどについてたくさんの写真や動画を見せながら説明しました。(写真左)そのあとスタッフが具体的なヤゴ救出のやり方を説明しました。(写真右)子ども達は問いかけに活発に反応しながらよく話を聞き、具体的な質問もたくさん出されました。 (3年生は学年参加:保護者/スタッフ9名が参加) | |
| 1年生の教室でのヤゴ飼育をサポート |
 |  |
2015年5月22日(金)「ギンヤンマの来る学校=上石神井小学校」の1年生にヤゴの飼育や観察をとおしてギンヤンマなどのトンボに親しんでもらおうと、探検隊では毎年1年生の教室でのヤゴの飼育をサポートする活動をしています。毎週金曜日の中休みにジュニア隊員さんと、保護者隊員が水かえやエサやりなどのお手伝いをしています。教室ではすでに大きな美しいギンヤンマがヤゴから次々と羽化しています。 お手伝いいただける保護者の方は毎週金曜日の10時にトンボ池にお集まり下さい。 | |
| 多摩六都科学館 ウェルカム遠足 |
 | |
2015年5月16日(土) 新入隊員との親睦(しんぼく)を目的としたウェルカム遠足。あいにくの天気のため、今回は西東京市の多摩六都科学館に行きました。館内ではさっそくたてわりの4グループに分かれて、ワークシートの問題をみんなで力を合わせて解きながら見学したり、各コーナーを体験したりして楽しい時間を過ごすことができました。お弁当のあとは、あちらこちらで子ども達はお菓子交かんを、大人はお茶とおしゃべりを楽しむすがたが見られました。 見学を終えて、ようやく晴れてきた外で記念写真を撮る頃には、今年から入隊した新しいなかまもすっかりうちとけて、みんなで鬼ごっこなどして元気に遊ぶことができました。 参加されたみなさんからの感想メールより・・・ 「お疲れさまでした。 うちの子供達は久しぶりの科学館で、喜んでいました。 」「六都でも楽しめましたね。 なにより、あのたてわりグループが楽しそうでした。 家族で行くのともお友達同士で行くのともまたちょっと違ってよかったですね。 いつもの観察会に来られない方ともお話できたので、保護者からもよかったと思います。」 (子ども・OB39名・保護者/スタッフ35名・計74名が参加) |
| 第1回 定例トンボ池ミニ観察会・顔合わせ会 |
 |  |
 |  |
2015年5月9日(土) 今年度第1回目の観察会。参加者もたいへん多かったので、3つのグループに分かれて、トンボ池・カブクワハウス・プールそれぞれの生き物や植物を観察しました。後半は顔合わせ会と遠足の説明会だったため、みじかい時間でしたが、ギンヤンマやイトトンボのヤゴ、クロメダカ、ヌマエビ、カブトムシの幼虫、アゲハチョウの幼虫などたくさんの生き物に出会うことができました。 また、去年の秋にトノサマバッタが産んだたまごから、小さなバッタの赤ちゃんがたくさん生まれたので、一部をバッタ原っぱに放(はな)しました。( 画像提供:隊員の久保田さん・中野さんほか) (子ども・36名・保護者/スタッフ25名・計61名が参加) | |
| ミニ活動 畑プロジェクト 種まきとチンゲンサイの収穫 |
 |  |
 |  |
2015年5月2日(土) ミニ活動は、隊員の「こんなことをやってみたい」というアイデアを元に探検隊内で仲間をつのって行う有志活動です。昨年から畑づくりをやってみたい仲間で学校の使っていない学級園の区画を借りて、野菜やハーブ作りに取り組んでいます。 今回は除草と土づくり、空いたところに黒・白のゴマの種まき、アスパラガスの移植をしました。 アスパラガスが植えてあった部分には落花生が植えられるように場所を空けてあります。ジャガイモの横が2畝分あるので花の種を2,3種植える予定です。 子どもたちはあまりの暑さにさっそく水遊び、そして泥だらけ。楽しかったです。 チンゲンサイ、ホウレンソウ、キヌサヤエンドウの収穫がありました。 作業の合間にも、ニホントカゲ、ニジュウヤホシテントウ、ハナムグリやヨトウガの幼虫などたくさんの生き物の観察もできました。写真(右下)は、アオスジアゲハ。 (子ども5名・保護者/スタッフ6名・計11名が参加) | |
 |  |
2015年4月18日(土) 新年度の活動説明会を実施しました。入隊を希望する保護者の方(新規・継続含む)が集まり、今年度のしぜん探検隊の活動方針や年間計画を聞かれ、そのあと登録の手続きをされました。18日現在、今年度の登録を済ませた隊員は、子ども52名、大人52名の104名となりました。(この他に活動を支えて下さる地域の保護者OB,卒業生などの「サポート隊員」18名がいます。) また、今年度版のしぜん探検隊Tシャツも予約数が40枚に達しましたので、製作が決定しました。 | |
| トンボ池メインテナンス 土どめのくいの補修(ほしゅう)作業 |
 |  |
 |  |
2015年4月12日(日) 古くなっていたんでいたトンボ池南側の植えこみ部分の土どめの杭(くい)約10m分を新しいものに入れかえる作業をしました。休日を利用して久しぶりに顔を見せてくれたたのもしい卒業生2名をはじめ、お父さん方や地域のボランティアの方々のパワフルな働きでまたたく間に作業が進みました。小学生スタッフは、カブクワハウス用のふよう土の天地返しもしてくれました。今年もいいふよう土ができてきていました。 (子ども・OB6名・保護者/スタッフ5名・計11名が参加) | |
第11回 定例トンボ池ミニ観察会・活動見学会 |
 | 2015年4月4日(土)桜の花びらのたくさんういたトンボ池やプールで春の自然観察を楽しみました。たくさんのアズマヒキガエルのオタマジャクシにまじって、クロメダカやイトトンボ・ギンヤンマのヤゴ・アメンボ・ヌマエビなどを見つけてじっくり観察することができました。 |
 |  |
 | 観察用にすくった生き物を入れたバケツの中でギンヤンマのヤゴが脱皮(だっぴ)するなかなか見られないめずらしいしゅんかん(左写真)をみんなで観察することもでき、おおいにもり上がりました。 プールの水温が17度。トンボ池は14度でした。 |
 | 先日切ったクヌギを枝を機械を使ってチップにしてふよう土にする作業もがんばりました。(右写真) またこの日は、新年度から新たに探検隊の活動に参加をけんとうしてくれている子どもと保護者の方が実さいの活動を見学に来ていっしょに活動に参加して下さいました。 新しい仲間をむかえての活動は18日の活動説明会のあと、5月からスタートする予定です。楽しみにしていて下さい。 (子ども19名・保護者/スタッフ16名・計35名が参加) |
 |  |
 |  |
| ジュニア隊員の進級・卒隊お祝い会 |
 | 2015年3月21日(土) 毎年3月のお楽しみ、1年間いっしょに活動してきたジュニア隊員の進級・卒隊お祝い会がひらかれました。今回の目玉食材は「ダチョウのたまご」ふつうのたまご約25個分、重さは1.2㎏というジャンボサイズ。黄身の大きさを下の写真で見て下さい!これを「ぐりとぐら」の絵本と同じにフライパンでカステラにやきあげました。そのおいしかったこと!! また卒隊メンバーがトンボ池に記念に木を植えました。今年は「クリ」。縄文(じょうもん)時代から日本人が食べてきたみぢかな実のなる木です。上石神井の町にもかつては栗林がたくさんあり、イガをひろって遊んだ思い出のある人も多いはず。いろんな虫が集まる木でもあり、これからの成長が楽しみです。 (子ども34名・保護者/スタッフ27名・計61名が参加) |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
| ジュニア隊員の進級・卒業お祝い会に向けて 司会の打ち合せと準備 |
 |  |
 |  |
2015年3月14日(土) 21日に予定されている恒例の「ジュニア隊員の卒業・進級を祝う会」に向けて準備を行いました。司会進行役に応募してくれた4・5年生が司会の分担を決めたり、原こう作りをしたりしました。 お母さん方は今年の目玉企画「ダチョウの卵を使って作る《ぐりのぐらの》カステラ」の試作に挑戦。卵の風味豊かなおいしいカステラが焼けました。今から当日が楽しみです。 (子ども9名・保護者/スタッフ5名・計14名が参加) | |
| ミニ活動 畑プロジェクト 畑のかたづけと準備 |
 |  |
 |  |
2015年3月8日(日) 今年度からスタートした探検隊の中で希望者をつのってテーマごとにグループを作って取り組む「ミニ活動」。その一つ「畑プロジェクト」のために、学校から使っていない畑を貸していただいていました。年度の終わりをむかえたので、そこを一度学校にお返しするために、整備する作業を行いました。 あいにくの雨の中でしたが、1年間お世話になった畑とそのまわりの草をみんなでぬいて、石灰と肥料をすきこんでよく耕しました。新年度、この畑がまた有効に活用されることを願っています。(子ども2名・保護者/スタッフ5名・計7名が参加) | |
| 第9回 定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2015年2月7日(土) 秋に校庭の松やヒマラヤ杉の木に巻いた「コモ」(左写真)をはずして、中で越冬(えっとう=冬ごし)している生き物の観察をしました。 マツカレハの幼虫(毛虫)がたくさんいました。みんなで1匹ずつピンセットなどでつまんで数えていくと、西門の赤松1本だけでなんと1160匹もいました。となりの黒松では少し大きい幼虫が約300匹(右下)いました。 |
 |  |
 |  |
 | 幼虫は春になるとコモから出てさらに葉を食べ大きくなります。マツカレハが増えすぎると松の木に害(がい)をあたえる上に幼虫の毛には毒があるので、集めた幼虫は土にうめて駆除(くじょ)しました。コモを使うことで農薬を使わずに害虫をへらすことができるので、上小ではもう10年以上毎年このとりくみを続けています。 コモの中にはナミテントウ、カメムシ、クモ、ヤモリなどほかにもたくさんの生き物が越冬していたのでこれらはにがしてやりました。(子ども18名・保護者/スタッフ7名・計25名が参加) |
 |  |
 | |
| しぜん教室 屋上から上石神井の日の出を見よう! |
2015年1月24日(土) 今年で14回目を迎えた「日の出を見る会」。まだ暗い6時から100名を超える参加者が集まり、空が暗いうちは望遠鏡で土星や木星(4つの惑星もくっきり!)を観察し、そのあと東側のフェンスぞいに集まり、少しずつ明るくなる空を見つめながら①日の出の正確な位置②日の出が実際に屋上から観察される時刻、を当てるクイズに挑戦。ワークシートに自分の予想を書き込み、日の出の瞬間を待ちました。 今日の東京の日の出は、暦の上では6:47となっていましたが、ちょうど新宿の都庁の後ろあたりの雲の間から太陽が顔を出したのは6:57。その瞬間には屋上から大きな歓声があがりました。東の方角には東京スカイツリー、西の方角には朝陽に美しく照らされた富士山を見ることもできました。 (子ども・OB62名・保護者/スタッフ43名・計105名が参加) | |
 |  |
 |  |
 | |
そのあとは、今年の干支(えと)にちなんだ羊(ひつじ)クイズをみんなで楽しみ、さらに今回は羊の腸(ちょう)を使ったソーセージ作りを見学しました。ソーセージ作りを実演しながら説明して下さったのは、東大泉にある手作りソーセージの専門店「ル・ジャンボン」さん。http://www.lejambon.net/html/company.html?code=lejambon 本物の羊の腸にもさわらせてもらいました。そのあとボイルしたての手作りソーセージをみんなで試食しました。 また探検隊野菜プロジェクトのメンバーが学校の畑を借りて作った練馬大根や白菜の入った温かいスープで冷えた体をあたためました。 終了後はジュニア隊員/OB・保護者/大人スタッフで、たき火を囲み、バウムクーヘンを焼いたり、マシュマロを焼いたり、竹筒でごはんを炊いたり・・・と思い思いの楽しいひとときを過ごすこともできました。 | |
 |  |
 |  |
 |  |
| ミニ活動 手作りソーセージのお店の取材 |
2015年1月10日(土) 日の出を見る会に向けて、準備が始まりました。この日は今回の「しぜん教室」の司会進行役に立候補してくれたジュニア隊員が学校の図書室に集まり「ヒツジ」に関する資料探しをしたり、クイズの構成について話し合ったりしました。その後、今回ご協力いただく予定の東大泉にある手作りソーセージの専門店「ル・ジャンボン」さんhttp://www.lejambon.net/html/company.html?code=lejambonを訪ね、取材をしました。「お店はいつからやっているのですか」「お店のこだわりはどんなことですか」「材料のヒツジの腸はどこの国からとりよせているのですか」など子ども達から次々出る質問に、社長の高山さんが一つひとつていねいに答えて下さいました。子ども達もますます興味が高まったようで、帰りには「おこづかいでソーセージ買っていい?」と言い出す子までいました。当日は高山さんが学校にいらしてお話や実演をして下さる予定です。お楽しみに! (子ども9名・保護者/スタッフ8名・計17名が参加) | |
 |  |
 |  |
| 第8回 定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2015年1月4日(日) まずは霜柱(しもばしら)や氷の観察。バケツの丸い氷はレンズのように太陽の光を集め、手をかざすと温かいのがはっきり感じられました。そこに小さな氷のかけらや霜柱をおくと、溶けていく様子も観察できました。氷で氷を溶かすなんておもしろい!ミカンを切って枝にさすと、さっそくメジロが食べに来る様子もまぢかに観察できました。プールのヤゴ観察、コナラの枝のチップ作り、落ち葉集めなどもしました。砂場には鳥や小動物の足あとがいっぱい。さて、何の足あとでしょう? (子ども7名・保護者/スタッフ7名・計14名が参加) |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
| 第7回 定例トンボ池ミニ観察会 |
2014年12月7日(日) リース作りのあと、午後の1時間ほどの短い時間でしたが、学芸会で土曜日にできなかった12月のミニ観察会と整備作業を行いました。校庭の朝礼台のうしろの桜の木にかけてあった巣箱を外すと、中にはシジュウカラが巣を作って利用したあとが残っていました。作ってから4年がたち、こわれかかっていた巣箱も子ども達がていねいに直し、また使えるようになりました。(写真右上)また、まだ校庭南西のヒマラヤスギの木にまいたマツ毛虫をとるコモにも説明のプレートを取り付けました。(左下)クヌギの木の枝からはコカマキリの卵やクヌギカメムシのゼリー状の物質につつまれためずらしい卵を発見。生き物のすがたがあまり見られない冬でも、トンボ池のまわりでは毎回なにか新しい発見があります。 今はクヌギやコナラの落ち葉がたくさん出る季節です。スタッフみんなで集めて腐葉土置き場に運びこみました。(右下)この作業は落ち葉が出る間は、平日もボランティアスタッフで続ける予定です。みなさんもお時間のある時にご協力をよろしく! (子ども3名・保護者/スタッフ8名・計11名が参加) | |
 |  |
 |  |
| しぜん教室 しぜんの素材でリースを作ろう (ねりま遊遊スクール) |
2014年12月7日(日) この季節恒例の人気企画です。今年も体育館にあらかじめ申し込んでくれた90名近い親子が集まりました。まず一人ひとりが体育館の床いっぱいに広げられた100本以上のリースの台(自然のつるで編んだもの)から気に入ったものを選び、次にステージに並べられたたくさんの自然の木の実、葉、花などの中からすきなものをバイキング形式で選び、それらを使って思い思いにリース作りをスタートさせました。 グルーガンなどを上手に使いこなし、1時間ほどですてきなオリジナルリースが次々とできあがりました。クリスマスカラーの鮮やかなリースもあれば、お正月を意識した和風のリースもあったりして、記念撮影のあと、それぞれが世界に一つしかない手作りリースを大事にかかえて帰っていきました。 (子ども57名・保護者/スタッフ31名・計87名が参加) | |
 |  |
 |  |
 |  |
 | |
| ミニ活動 リース用オーナメント作製 |
2014年11月29日(土) マツボックリなどの木の実を使って、来週のリース作りのしぜん教室で材料として提供するオーナメント作りの作業を行いました。 子どもたちの作業のあまりの速さにおどろかされました。保護者の方々もたくさん参加してくださり、ステキなサンタと、かわいいトナカイができました。お正月かざり用の青竹もバッチリ。リース作りのしぜん教室の当日が楽しみです。 (申し込み状況は1日現在、上小関係だけで65名です。メールでの申し込みはお早めに!) (子ども15名・保護者/スタッフ18名・計33名が参加) | |
 |  |
 |  |
 |  |
| 大泉さくら運動公園 「野外遊びと隊員親睦BBQの会」 |
 | 2014年11月22日(土) 今年は自転車でも行ける区内の公園に場所を変更して行いました。おだやかな晴天に恵まれた秋の一日、芝すべりや木登りなどで思いっきり体を動かし、またおいしいバーベキューでお腹も満足。楽しいおしゃべりで子どもも大人も親睦を深めることができました。 (子ども25名・保護者/OB/OG・スタッフ28名・計53名が参加) |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
| リース作りに向けて 「つるの採取作業」 |
 | 2014年11月16日(日) 地元W高等学院のご協力のもと、同校敷地内に自生する葛(くず)のつるを採取させていただきました。つるのある場所は急ながけなので、まず大人が入ってつるの根元を切り出し、へいの外から子ども達がみんなでつるをひっぱり、とれたつるをその場でどんどんリースの形に編んでいきました。2時間ほどの作業で100本以上ができあがり、これが12月のしぜん教室でみなさんのリース作りの材料になります。 |
 |  |
 | この場所はかつて石神井川にそって広がっていた雑木林の自然が今に残る貴重な一画。木に高くからみついた自然のくずのつるの中にはびっくりするくらい太くてりっぱなものがありました。ほかにもカラスウリのつるには赤い実がありましたし、子ども達はドングリやバッタやカマキリの卵(下の写真)などたくさんの自然を見つけて観察を楽しみました。 (子ども18名・保護者/スタッフ20名・計38名が参加) |
 |  |
| しぜん教室 「上石神井の昔へタイムスリップしよう」 |
 | 2014年11月2日(日) 今回は子ども達が夏休みに調べた上石神井の昔の様子や石神井川の生き物の昔と今等について報告会形式のしぜん教室でした。クイズやビデオ、立体模型を使って、学校ができた60年前くらいを境に、一面の田んぼだった石神井川のあたりがうめたれられて急速に自然が失われていったこと、でも今はまた川にいろいろな生き物がもどってきていることなどをいっしょに学びました。 |
 |  |
 | 「校庭にたくさんあるこの大きな石は何?」答えは学校ができた時道路と校庭の境にと地域の方が寄付して下さったかつて練馬大根の漬物作りに使っていた重石。「石神井川に今も海から上ってくる生き物は?」・・・大人も子どもも新しい発見がたくさんあった90分間でした。司会進行や受付は今回も隊員の子ども達が分担してがんばりました。 ※参加者のみなさんの感想(クリック) (子ども24名・保護者/スタッフ19名・区/学校/地域関係3名・計46名が参加) |
 |  |
| 第6回定例トンボ池ミニ観察会 |
2014年11月2日(日) 雨で一日のびての実施。まずはプールでの生き物観察。水中にはほぼ終齢まで大きく育ったウスバキトンボのヤゴ(右写真の右)がたくさんいました。左側のしまもようの小さいヤゴはギンヤンマ。ずいぶん大きさがちがいますね。 ウスバキトンボは、春に南の国から日本に飛んで来て、夏の間に何度も発生をくりかえすのですが、最後は日本の冬の寒さにはたえらえず、ヤゴのまま、あるいは羽化しても結局死んでしまうふしぎなトンボ。観察のために持ち帰った人は、このあとのようすをぜひ知らせて下さい。 一方ギンヤンマは今は小さいですが、冬の寒さにもたえて少しずつ成長し、来年の6月ころには成虫へと羽化します。 |  |
 | 左の写真はプールで見つけたすきとおった葉。 水中のプランクトンの力でやわらかい部分が食べられて、かたい葉脈(ようみゃく)だけが残ったじょうたいです。これをヒントに薬品を使わない「葉脈標本」作りをしようということになりました。かための葉を集めてネットに入れて、プールにしずめました。さて、どのくらいで左のようなとうめいになるでしょう。楽しみです。 |
トンボ池の東がわのフェンスぞいに「上石神井いこいの森」でひろってきたアラカシのどんぐりをうめました。(下の2枚)アラカシは冬でも葉が落ちない木=常緑樹(じょうりょくじゅ)なので、発芽したものを上手にかりこんで育てて植物による目かくしの生け垣(いけがき)にしていく計画です。 この日は2年生の保護者の方からカブクワハウスにカブトムシの幼虫10匹の寄付もいただきました。(右写真) (子ども13名・保護者/スタッフ10名・計23名が参加) |  |
 |  |
| ミニ活動 秋の海釣り教室 |
2014年11月1日(土) あいにくのお天気ではありましたが、釣り教室を敢行しました。今回の参加者は総勢11名で、現地に向かう途中では本格的な雨になり、どうなることかと思いましたが幸いにも現地に到着するころには雨も止んで、ほとんど雨に濡れずに釣りができました。 でもそのおかげで周りにはほとんど釣り人がおらず、ほとんど貸切状態で釣りができました。釣果の方は、27cmのメジナを筆頭に、メジナとウミタナゴ、それにメバルが全部で33匹釣れました。参加者の皆さん、秋の釣りを満喫してきましたよ。 (子ども6名・保護者/スタッフ5名・計11名が参加) | |
 |  |
| 東公園の樹木に名前を付けよう!③(取り付け作業) |
 | 2014年10月11日(土) 完成した17種41本分の手作り樹木プレートをいよいよ東公園の木に取り付けました。 はしごに登ってちょっとドキドキ!作業のあとは、みんなで取り付けたプレートを確認して回りながらそれぞれの樹木について緑化協力員さんに説明をしていただきました。身近な東公園にこんなにいろいろな木があったことに改めて気付き、同時に木の名前もたくさん覚えることができました。記念に木とプレートの写真の入った緑化協力員さん特製の下じきを、さらに差し入れのバナナもいただき、記念写真を撮って楽しく活動を終了しました。 (子ども9名・東公園体操の会・区緑化協力員さん16名・区みどり推進課より1名・保護者/スタッフ9名・計35名が参加) |
 |  |
 |  |
| 第5回定例トンボ池ミニ観察会(こもまき) |
 |  |
 |  |
2014年10月4日(土) まずはこの季節恒例、ひっつき虫(オナモミの実=右上写真)合戦をみんなで楽しみました。 そのあと4つのグループに分かれ、校庭の赤松・黒松とヒマラヤスギの木に「こも」を巻く作業。 その合間にはツバキの実(=右中写真)を見つけて「ぼく達もツバキから油を取るんだ」と先日のTV番組「〇〇ダッシュ」に負けじと自分たちでツバキの実集めを始める子ども達も。 さらにトンボ池やバッタ原っぱでヤブガラシとセイタカアワダチソウの草とり作業を行いました。右の写真はセイタカアワダチソウ。背の高いJ君とくらべても本当に「せいたかのっぼ」の草であることがわかりますね。 |  |
 | 後半は、リクエストの多かった理科実験「割れないシャボン玉」作りに挑戦。 中学生隊員のKさんがメスシリンダーを使って台所用合成洗剤70ml+PVA洗濯のり400ml+精製水530mlの割合で調合してくれた特製シャボン玉液をウチワの骨やハンガーの枠にたっぷり付けてみんなで走ると、校庭はきれいなシャボン玉でいっぱいになりました。 (子ども24名・保護者/スタッフ12名・計36名が参加) ★画像提供:中野・松本・矢澤・二宮さん |
| ミニしぜん教室「皆既(かいき)月食について知ろう」 |
 | 2014年10月4日(土) この日は隊員の親睦のための昼食会でみんなでお弁当を食べたあと、古田島先生から10月8日(水)の夜に見られる「皆既(かいき)月食」についてのお話を聞きました。 左の写真、先生が持っているのは月でも地球でも太陽でもなくなんと地球の「かげ」!宇宙にできるこのかげの中に月が入る時、月食がおきるのだそうです。わかりやすい説明と楽しいクイズで、みんな水曜日の夜がすっかり楽しみになったはずです。晴れるといいですね! (子ども・OB22名・保護者/スタッフ14名・計36名が参加) |
| ミニ活動 稲刈り(いねかり) |
 | 2014年9月13日(土) トンボ池に流れこむ水路の部分は、小さいけれど「田んぼゾーン」と位置づけられていて、探検隊では毎年5月に田植えをしてここで稲を育てています。田んぼはトンボのヤゴやオタマジャクシ、クロメダカなどもともと田んぼでくらす生き物の大切なすみかとなる環境です。 今年もわずかですがこの田んぼで稲が実ったので、子ども達が稲刈りをしました。しゅうかくした稲やワラはリースのかざりや野菜作りの時の資材として活用する予定です。 |
| 東公園の樹木に名前を付けよう!②(ニスをぬって仕上げよう) |
 | 2014年9月13日(土) 前回の活動で作った樹木名と絵を入れたプレートにとうめいなニスをぬって仕上げる作業をしました。今回も練馬区緑化協力員の方々が準備を整え丁寧に指導して下さいました。また東公園の近くにお住まいの地域の方々もいらして作業を見守ったり手伝ったりして下さいました。ニス塗り作業は初めてという子どもがほとんどでしたが、みんな熱心にとりくみ、きれいに二度塗りで仕上げることができました。 |
 |  |
(子ども7名・東公園体操の会より2名・区緑化協力員さん8名・保護者/スタッフ11名・計28名が参加) ★画像提供:東公園体操の会 中村様 ほか |
| 「トンボの産卵おたすけ大作戦」(3年生授業サポート) |
 | 2014年9月8日(月) 水泳の授業の終わったプールに草を浮かべることで、草がないと産卵できないギンヤンマなどのトンボもプールにやってくるようになります。上小では2000年からずっとこのとりくみを続けています。今年も3年生が総合的な学習の授業の一環として校庭の草を集めてネットに入れ、ペットボトルの浮きを付けてプールに浮かべました。しぜん探検隊はその授業のお手伝いをさせていただきました。 (保護者/スタッフ12名が参加) |
 |  |
 | ←草を入れ終わると、さっそくどこからともなく大きな緑色のギンヤンマがプールにやってきました。(ちょっとわかりにくいですが、中央の白線の上) これからしばらくの間、様々な種類のトンボが産卵にやってくるはずです。ぜひ自分の目で観察してみましょう。また、草を入れることでミジンコなど多様なプランクトンも発生し、プールの水をきれいにすんだ状態に保ってくれるのです。そんな様子は次回の定例観察会でも観察する予定です。 |
| 東公園の樹木に名前を付けよう!①(樹木プレート作り) |
 | 2014年9月6日(土) 練馬区みどり推進課と練馬区緑化協力員さんのご協力のもと、上小の子ども達がよく遊ぶ東公園の樹木に付ける樹木名プレートの作成に取り組みました。材料は間伐材を活用した天然木のプレートです。それに緑化協力員さんが用意して下さった各樹木ごとの資料を参考に木の名前とイラストを描いていきました。どれもすてきなできばえで、公園に設置されるのが楽しみです。 |
 |  |
 |  |
 | 東公園の樹木の種類などを詳しく調べて今回の企画を区に提案して下さった地元東公園体操の会のメンバーも一緒に参加されて、全部で40枚近いプレートをみんなで楽しく作り上げました。できたプレートはこのあとニスを塗って仕上げて、10月中には練馬区によって東公園に取り付けられる予定です。 (子ども23名・東公園体操の会より4名・区緑化協力員さん8名・区みどり推進課より1名・保護者/スタッフ17名・計53名が参加) |
| 3年生への事前授業(トンボの産卵お助け大作戦) |
 | 2014年9月5日(金) 3年生の総合的な学習の授業のゲストティーチャーとしてスタッフの田中さんが、いろいろな生き物の産卵の特徴、トンボの産卵の2つのパターン、プールに草を入れる意味、具体的な作業の方法などについてお話ししました。 3年生の子ども達もとても熱心に話を聞いて、質問も活発に出ました。プールに実際に草を入れる授業は8日の予定です。 |
| ミニ活動 石神井川今むかし探検 共同研究として校長先生に提出 |
 | 2014年9月5日(金) 夏休みのミニ活動として希望者で取り組んできた「石神井川今むかし探検」の活動のまとめ(立体地図と資料)を参加した子ども達全員の共同研究として、昼休みに探検隊隊長の校長先生のところに提出に行きました。校長先生も副校長先生も熱心に説明を聞いて下さり「たくさんの人に見てもらえるようにどこかに展示しましょうね。」と約束して下さいました。 |
| 第4回定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2014年8月30日(土) カブクワハウスの整備をしました。古い土を出し、みんなでバケツリレーで新しい腐葉土を運びこみました。これでみんなが夏休み中に飼育したカブトやクワガタの卵や幼虫をまたカブクワハウスに持ってきてもらって育てることができます。夏の間にのびたトンボ池のまわりの草を刈ったりしながら、カマキリ、バッタ、カエル、ナメクジなどたくさんの生き物と出会うこともできました。 (子ども19名・大人13名・計32名が参加) |
 |  |
 |  |
 | 去年の秋にドングリをまいて育てたクヌギなどの苗をひとまわり大きなはちに植え替えました。(上左)田んぼゾーンの稲も花が終わり稲が実ってきたので鳥よけのネットをかぶせました。(上右)左はヤブカラシの葉を食べていたセスジスズメというスズメガの幼虫。すごくカラフルですね。でも、おしりに付いているのは幼虫の体内に寄生した寄生バチのまゆのようです。 |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検⑥ (まとめ) |
 |  |
 | |
2014年8月29日(金) 石神井川のいま昔探検のまとめをしました。立体地図の残っていた部分(西武線の線路や水路の水の取り入れ口の「せき」・橋など)を完成させ、これまでに集めた石神井川の古い写真や地図・見学に行った時写した写真などを画用紙に貼って説明を書きこんでまとめていきました。できあがったものは、しぜん探検隊の「共同研究」という形で、学校に出して上小のみんなにも見てもらう予定です。 | |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検⑤(地形模型つくり-2-) |
 | 2014年8月24日 立体地図に色を塗り、道を描いたり雑木林を作ったりしました。左の写真は下ぬりをした模型の上に昔の地図をプロジェクターで映して、道の線を写しているところです。下の白い線は西武新宿線、赤い点は今の上石神井小学校の場所(昭和30年当時はまだ畑)です。 下の写真は石神井川の下流から上流側を見る形です。手前の赤いピンが上小。緑色のピンがのちに上中になる場所です。右手前の出っぱった林が扇山。今はこの山を切りさく形で新青梅街道が走っています。川が奥で左にカープするあたりが今もある神学校の森です。次回は橋や水門の「せき」を作る予定です。 60年前の上石神井の町と石神井川の様子がだんだんと再現されてきました。 |
 | |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検④(地形模型つくり) |
 |  |
 | |
2014年8月10日(日) 昔の石神井川は今のようにまっすぐではなく、まわりには用水路が引かれ、今の団地のあたりは一面の田んぼが広がっていたと聞き、 その様子を立体地図で再現することにしました。まだ田んぼがあった昭和30年頃の地図を元に、①大きな発ぽうスチロールの上にプロジェクターで形を映し、川の流れやがけを表す線、当時の道、西武鉄道の線路などを書き写していきます。②土手の線にそって切り取り、斜面をなだらかにけずってていきます。③右手高台の奥が学校のあたりです。このあと色をぬって仕上げていく予定です。今から60年前の上石神井小の北側の様子が再現できる予定です。 | |
| ミニ活動 セミの羽化 夜の観察会(武蔵関公園) |
| 2014年8月9日(土) 夜の武蔵関公園で恒例のセミの羽化観察会を行いました。アブラゼミ・ヒグラシ・ツクツクホウシなどのセミの羽化の様々な段階をじっくりと間近に観察することができました。 台風の影響が心配されましたが雨にもふられず、かなりの数の羽化を見ることができました。 (子ども18名・大人18名・計36名が参加) (写真提供:長谷川さんほか) ★今夜はセミのうかを見ました。これで夜に行くたんけんは3回目になります。その中でもいちばんたのしくてセミがいっぱい見られました。はねがうすいみどりですきとおっていて、とてもきれいでした。 (2年生のいつき君の感想です) |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検③(昔のお話を聞く会) |
 |  |
 | 2014年8月9日(土) この日は上石神井の昔のことをよくご存知の田中武夫さん・尾崎幸雄さんとごいっしょに石神井川沿いを歩きながら昔の石神井川の様子や、生き物、子ども達の遊びなどについていろいろお話をうかがいました。川沿いの団地ができる前は、一面の田んぼでホタルもたくさんいたそうです。子ども達は川で泳いだりして遊んだそうです。川ではウナギもとれたとか。戦争中の空襲のお話もうかがいました。 (子ども6名・大人13名が参加) |
| ミニ活動 野菜プロジェクト しゅうかく祭 |
 | 2014年8月6日(水)野菜プロジェクトで作っている作物が真夏の日差しをあびて、大きく育ち、次々と収穫の時期をむかえてきたので、プロジェクトのメンバーで収穫祭をしました。 畑でとれたトマト、オクラ、ニンジン、ジャガイモ、ゴーヤ、トウモロコシ、アシタバ、それにシソやミントなどのハーブ。これらの食材を使って、カレーやパスタ、天ぷら、飲み物なども作ってみんなで試食しました。 カブト虫の幼虫が落ち葉をフンに、そのフンをミミズやたくさんの微生物がさらに細かく分解して作り上げた「黒土」、その黒土を使って育てたのが探検隊の野菜です。 ★私は、野菜プロジェクトを通して「新鮮な野菜はこんなに美味しいものなんだ!」と、再認識させられました。また、娘たちも採れたてのズッキーニやきゅうりを食して、野菜の「みずみずしさ」を実感したようで、親としても喜んでいます。(野菜PJメンバーのNさんのお母さんからのメッセージ) |
 |  |
 |  |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検②(生き物調査) |
 | 2014年8月3日(日)「石神井川のいま昔探検」第3回となるこの日は、石神井川の生き物を調査しました。あらかじめ川に捕獲用のカゴをセットして、それを引き上げて入っている魚や生き物を調べました。 左の魚は「アブラハヤ」です。また、今回「モクズガニ」というカニが発見されました。このカニは海から川を上ってくるもので、石神井川では正式な記録はありませんが、今回の調査で改めて生息が確認されました。 |
 |  |
 | 「モクズガニ」は左上の写真で子どもの手の大きさとくらべてもわかるようにかなり大きなカニです。はさみに藻屑(もくず)のようなふわふわした毛が生えていることからこの名前があります。 今回の調査では、魚ではアブラハヤが見つかりましたが、以前の調査で見つかったヨシノボリやドジョウ、ザリガニなどの姿は確認することができませんでした。水温は19度。においもなく、水は澄んで水底までよく見える状態でした。 |
| ミニ活動 石神井川のいま昔探検① |
 | 2014年7月30日(水) 恒例の石神井川探検。今年は何回かに分けてミニ活動として行い、石神井川の今と昔を調べることになりました。この日は古い地図や写真を見ながら、石神井川の古い流れをたどったり、かつて川から田んぼに水を流していた用水路の跡を探検して回りました。 |
| 海づり教室 |
 | 2014年7月19日(土) 希望者によるミニ活動の第3弾。横浜の末広水際プロムナードで海釣りを楽しみました。サッパとイワシの群れにあたり、結果は稀にみる大漁となりました。 釣果はメジナ2匹、アジ18匹、サッパ65匹、イワシ(カタクチイワシ)177 匹ヒイラギ15匹、キス2匹、ウミタナゴ1匹合計なんと279匹でした。 |
| ミニ活動 上石神井の森 夜の観察会 |
 | 2014年7月18日(金) 上石神井に残る貴重な森で恒例のミニ活動「夜の森観察会」を行いました。開始時刻の7時頃からちょうど霧雨がふり始めてしまいましたが、約50名が参加。クヌギの樹液に集まるカナブンや蛾。設置したライトトラップ(白布のスクリーンにブラックライトの光を当てたもの)に集まる甲虫の仲間などを観察しました。ナナフシを見つけた子もいて、みんなでさわったり、写真を撮ったり。 後半はコクワガタ・ノコギリクワガタにも出会うことができ、みんな大興奮。 (写真はノコギリクワガタの♂・撮影=OBの浦君) 記念撮影をして、最後に、この森と生き物がいつまでもこの町に生き続けてくれることを祈って観察のために一度つかまえた生き物をすべて元の森に逃がして観察会を終えました。 |
 | |
| 第3回定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2014年7月6日(日) 雨で一日のびましたが、この日は梅雨の晴れ間。 グループに分かれ、A.腐葉土の天地返し作業 B.雑草の森での観察 C.野菜プロジェクトの畑観察 D.トンボ池での生き物観察という4つのプログラムを順番に行いました。雑草の森ではクモのお母さんが卵を守っている様子、畑ではミントの葉の味見、トンボ池ではオオシオカラトンボの産卵などをじっくり観察することができました。 |
 |  |
 | 腐葉土の天地返しの作業では、冬には箱いっぱいだった落ち葉の体積が半年で半分になることもわかりました。 大きなミミズやアズマヒキガエルにも出会えました。 田んぼゾーンでは5月に植えた稲が2倍以上の大きさに成長していることを確認しました。ほとんどの子が見たことがないという稲の花が何色かも楽しみです。 |
| しぜん教室 「プールの生き物について知ろう」(ねりま遊遊スクール指定講座) |
 | 2014年6月7日(土) クイズやお話、体験を通して身近な自然について楽しく学ぼうという探検隊の「しぜん教室」。毎年6月は学校のプールを使って、ヤゴなど水の中の生き物について学びます。今年も上小以外の学校からの参加者もふくめた76名の参加者が集まり、ヤゴの種類や生態について学びました。あいにくの雨でプールでのヤゴ救出活動は中止となりましたが、自宅でヤゴの飼育に挑戦したい人は、スタッフがあらかじめ用意したヤゴとエサの赤虫を大事そうに持ち帰る姿が見られました。 |
 |  |
 | しぜん教室終了後、スタッフでプールに残っている生き物の最後の救出を行いました。プールの横幅いっぱいにあみを広げて、はしから生き物を追いこんでいきました。ギンヤンマのヤゴにまざって、たくさんのクロメダカが取れました。これは、秋に探検隊で親メダカを入れておいたものが、春先から卵を産んでプールの中でふえたものです。プールの中にはミジンコなど豊富なエサがあり水温も安定しているため、わずかな期間で大量の子メダカが育っていたのです。そのメダカは今トンボ池で元気に泳いでいます。 |
| 3年生ヤゴ救出活動の授業サポート |
 | 2014年6月2日(月) 今年は改修工事で小学校のプールが使えないため、おとなりの上石神井中学校のプールをお借りして、3年生がヤゴ救出をしました。秋に去年の3年生がプールに草をうかべて、トンボの産卵環境を整えてくれていたので、中学校のプールにも今年はギンヤンマやイトトンボ、アカトンボなどたくさんの種類のヤゴがいて、それらを救出することができました。 →当日の様子(コマ撮り) |
 |  |
| 第2回定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2014年5月31日(土) トンボ池の水をぬいて大そうじをしました。そこにたまったどろや石をどけて、ふえすぎた植物をぬいて整理しました。同時に池の生き物しらべもしました。たくさんのヤゴや魚、大きなドジョウなどがいました。 |
 |  |
 | 池の中の島には少なくなっていた「ガマ」という植物をうえました。 また、田んぼゾーンにはみんなで「イネ」(お米)のなえをうえる「田うえ」をしました。 |
| ミニ活動 「手の平にのる自然・ミニ盆栽を作ろう!」 |
 | 2014年5月17日(土) 希望者によるミニ活動の第2回。今回はプロの植木職人の永田さんを講師に迎え、雑木林の下に生える実生(タネから生えた木の赤ちゃん)とコケを使って「手の平にのる小さな自然=ミニ盆栽」作りを楽しみました。 植木鉢は青竹を切って、使うスコップはペットボトルから手作りしました。 |
| ウェルカム遠足 |
 | 2014年5月10日(土) 新しいメンバーの歓迎会をかねて、85名の参加で、東久留米・南沢湧水地&落合川に遠足に行きました。 東久留米川クラブのみなさんのご協力により楽しく川遊びをしたり、川の自然について学んだりすることができました。 |
| 第1回定例トンボ池ミニ観察会 |
 | 2014年5月3日(土) 新年度最初のトンボ池清掃&ミニ観察会。 上小のしぜん探しビンゴゲームで楽しみました。 コマ撮り動画を公開しています。 画像(左上)をクリックしてください。 |
 |  |
 |  |
 |  |
| ミニ活動 カブクワハウスの土で野菜を作ろう |
 | 2014年4月12日(土) 希望者によるミニ活動の第1回。 カブト虫の幼虫が落ち葉を食べ、そのフンをミミズなど土の中の生き物がさらに細かく分解して、黒土が生まれます。 カブクワハウスのメインテナンスでこの黒土がたくさん出たので、それを使って野菜作りのミニ活動を始めました。 |
見つけたよ! ★身近な発見や情報をメールで事務局までお知らせ下さい。  11月2日(日) 夕焼けのきれいな季節です! 上石神井の西の空です。 日が短くなり、寒くなってきましたが、空を楽しみましょう。買い物に出た時にスマホで撮りました。 (画像と情報:スタッフのTさん)   8月1日(金) 何がおきた?君のすいりは? 近くの公園で朝早く見つけました。地面に何かをひきずったあとが長々と見えています。上下同じ写真ですが、写っているはんいが上の方が広いです。その先にはなんと!アブラゼミのぬけがらとすぐそのとなりにくしゃくしゃになった羽化に失敗したセミがもがいているでは・・・。いったいどうしたことでしょう。このセミはどこでだっぴしたのか?セミに何がおこったのか?君のすいりはいかに・・・!  7月24日(木) だ〜れだ?! 写真は、ある昆虫の頭と胸を横から拡大して写したものです。この時期、暑い日に、憩いの森や公園で、エノキやケヤキなどの広葉樹の回りで飛んでいたり、幹にとまっていたりします。コロンと地面に落ちている姿を見かけることもあります。  ①18:00頃 背中が割れてきた  ②18:10頃 腹が半分ほど抜けた  ③18:20頃 完全に抜けた 5月29日(木) ヤゴの脱皮の瞬間 ギンヤンマのヤゴを飼育していて、脱皮の瞬間を観察することができました。目が黄色くなるのが脱皮の合図です。背中が割れてきてから20分ほどで完全に抜けました。 (画像と情報:OBのGママさん) ★ヤゴからトンボになる「羽化」の観察記録は多いですが、ヤゴが成長過程で繰り返す「脱皮」の瞬間は案外観察報告がありません。それでもよく観察していればこうやって見ることができるのですね。貴重な記録です。ありがとうございました。  4月13日(日) 氷漬けの飛行機 イギリス支部活動1枚目です。日本からイギリスへの飛行機の中で窓を見てみると、氷漬けになっていました。フライトマップによると、なんと外の気温はマイナス60度。ちょうど北極の上を飛行中でした。 (画像と情報:中学生OBのT君) ★この春から1年間のイギリスで過ごすことになったというT君は「今晩飛行機で発つ」という日まで観察会に参加してくれたので「向こうに行ったら探検隊イギリス支部作って、イギリスで見つけた自然の情報送ってね」と頼んでおいたところ、さっそく1枚目の写真が届きました。 「マイナス60℃の世界」って想像つきますか? 12月12日(木) 土星食もスマホでパチリ! 先日の土星食、スマホでは環(わ)は見えませんでしたが、位置は確認できました。 出てくるところは、しばらくしてからのものです。 →クリックで拡大 (画像の提供:隊員のMさんより) 月も土星もあかるいので、スマホを向けても、様子がわかるようにとれるんですね。かなり近づくと月の光に負けてしまって、肉がんでは見えないものもしっかり写ることがわかりました。 12月7(土) 月と金星のせっ近、スマホでパチリ! 5日の月と金星のせっ近をスマホでねらいました。わが家は、深夜になると月が高い位置で見えることもあるのですが、お月見の季節や今日の夕方は、電線の間からの月見です。→クリックで拡大 (画像と情報:隊員のMさんより) ★ 月の高さは、いろいろな理由でかわります。見る時間帯、季節(夏は低く冬は高い)月の形(新月に近いほど低く、まん月に近いほど高い)これらが組み合わさると、けっこうふくざつですね。  11月25日(月) 猛禽類(もうきんるい)発見! 西東京市の公園で、大型の野鳥を見かけました。急いで撮影し、家に戻って調べました。ノスリというワシやタカの仲間です。→クリックで拡大 (画像と情報:しぜん探検隊) ★冬になって寒くなると、北の国からやってきた冬鳥や、ふだん山など高いところで生活している野鳥が平地に降りてきて、町中の公園でも姿を見ることができるときがあります。また、冬は多くの木が葉を落とすので、枝に止まった野鳥を見やすくなります。バードウォッチングに最適な季節です。  10月31日(木) いつ白くなるのかな? ちょっと霞んでいますが富士山です。 今日もまだ冠雪していません。130年の観測史上もっとも遅い冠雪記録更新中です。 (画像と情報:隊員のGママより) ★去年の初冠雪(初めて雪で白くなること)は10月5日で、それでも平年より3日遅かったということですから、今年の異常ぶりがわかります。富士山が見える場所を探して観察を続けていきましょう。  9月21日(土) おしゃれなサギ君 石神井川の下流、練馬高野台駅付近で、撮った写真です。 サギの仲間が橋の下で毛づくろいをしているようでした。 どうして、そんなに毛が気になるんだろう? (画像と情報:6年生隊員のHくんより) ★川をのぞきこむといろいろ発見がありますね。石神井川によくいるコサギのようです。エサを取るだけでなくいろいろな仕草をするところを観察するのも楽しいですね。  9月21日(土) どこから入ってきたの? 起きたときに母の悲鳴が聞こえて、見てみたら、寝室のカーテンにバッタがいました。家の中にどうしてこんなに生き物が入ってくるんだろう。 (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★生き物は、新たなすみかを探して常に旅をしているのだといいいますが、このバッタはどうやらまちがって人間のすみかに入ってきてしまったようですね。ここにはおいしいエサはありませんよ!  7月31日(水) 増水時の石神井川 HP(右)を見て思い出しました。7月31日19:00東京に記録的短時間大雨情報が出た日の石神井川です。 武蔵関へ行ったら雨で帰れなくなり、警報も鳴りました。雨がやんでも川はここまで増水していました。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★たまたま通りかかったので記録として残しておいた写真とのこと。右の「上石神井のしぜん最新情報」の8月19日の一番下の写真と同じ場所から撮影したと思われますが、遊歩道部分の手すりがほぼ完全に水没しており、この時よりさらに増水した状態であったことがわかる貴重な記録写真です。  7月28日(日) どこに行きたいの?カマキリ君 ベランダに干した洗濯物を取り入れようとしたら、壁に子どものカマキリがいました。カマキリを家の中に入れないよう、別の窓から家に入りました。カマキリは、涼しい家の中に入りたかったのかな? (画像と情報:4年生隊員のHくんより) ★暑い日が続きますね。カマキリだってこんなに暑いと涼しい家の中に入りたくなるのかな?それにしても思いがけなくベランダで生き物観察ができちゃいましたね!  7月23日(月) クマゼミ クマゼミ(クリック拡大)が鳴き始めました。もともとは南方の暖かい地域のセミですが、最近では関東地方でも数をふやしているといわれます。おもに、日の出からお昼前くらいの午前中に盛んに鳴きます。 (画像と情報:しぜん探検隊) 7月19日(金) 人工衛星(えいせい)の木!? 町なかであまり見たことのない花を見つけました。調べてみると、タニワタリノキとありました。どれが花びらで、どれがおしべなんだか?「じんこうえいせいの木」ともよばれるみたいです。 コロナウイルスの木でもよさそうですが・・・。南の国では大きな木になるようです。 (画像と情報:しぜん探検隊)  7月6日(土) シーズン到来! 昨日初めて善福寺公園に虫取りに行ったらもうカブトムシやクワガタがいました。予想していたよりも多くカブトムシやクワガタがいました。(クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員のNくん) ★カブトムシ観察のシーズン到来ですね。身近なところにも意外にいますよ。みなさんもぜひ探しに行ってみましょう! 6月22日(土) 孵化の瞬間! トンボ池バタフライゾーンのウマノスズクサに産み付けられたジャコウアゲの卵。(→右ページ参照)観察していたら、ちょうど卵から1匹目の幼虫が生まれる孵化(ふか)の瞬間(しゅんかん)を見ることができました!(クリック→拡大) (画像と情報:5年生隊員のSくん) ★運がいいですね~!飼育していても孵化の瞬間はなかなか見ることができず、まして野外で孵化の瞬間をカメラで撮影するのはとても難しいことです。しかもそれがただのアゲハチョウではなく、珍しいジャコウアゲハの孵化の瞬間とは!!ウマノスズクサの葉の形や生えている場所(学校)までもが1枚でよくわかる素晴らしい写真です。 6月1日(土) タマムシの羽を発見! 6月はじめのしぜん探検隊の集まりの日、近くの自然を観察していたら、地面に、タマムシの羽が片方落ちてしました。自分が思うに、これは上石神井小学校にもタマムシが生息しているひとつの証拠となるのでしょうか。いつかは、上石神井小学校にタマムシが現れるときが来るかもしれません。(クリック→拡大) (画像と情報:6年生隊員のHくん) ★鋭い考察ですね。確かに羽が落ちているということは、その近くに実際にタマムシが生息している何よりの証拠と考えられます。アリの巣穴の外で見つけたということでしたから、アリが運んできたものの、羽は大きすぎるからか穴の中まで運び込べなかったということでしょうかね。いろいろ想像もふくらみます。タマムシの食草(食べる植物)や成虫の発生時期などを調べて観察を続けることで、本当に「上小のタマムシ」に出会える日も遠くないかもしれませんよ。  6月13日(木) 街中のキノコ探し 街で見つけたキノコ(学区外だけど千川通り沿いです)ひとつめ(上)は街路樹の桜の木に生えていたベッコウタケ。これが生えると残念ながら枯れて倒れてしまうので伐採されることが多いそうです。 ふたつめ(下)はシュロの切り株に生えているキクラゲ。ちょっとおしゃれ。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★街でもできるキノコ探し。ちょっとおもしろそうですね。キノコというと秋のイメージですが、雨の多くなるこの季節。案外見つけることができたりしますね。みなさんもおもしろいキノコを見つけたら教えてください。  5月24日(金) 水泳の授業開始! 上小の水泳の授業はまだですが、日差しの強さ、暖かさにつられてか、気持ちよさそうに泳ぐアオダイショウを見かけました。場所は、東伏見近くの石神井川です。(クリック→動画) (画像と情報:しぜん探検隊)  5月23日(木) ゴイサギの狩り 石神井公園でゴイサギの幼鳥がエサのザリガニかカニ?をとったところです。 氷川神社の前でジャコウアゲハらしき蝶も見ましたが、上小にはまだきませんか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★あちこちでいろいろな生き物のヒナに出会える季節ですね。巣立っても自分でエサをとって生きていける一人前の大人になるまで修行が続きます。 ジャコウアゲハは、バタフライゾーンに食草のウマノスズクサが植えてあるので次回の観察会で探してみましょう! 5月22日(水) カルガモのヒナだよ 駅にほど近いビルの植え込みの中でピヨピヨとかわいい声がするので見てみると、カルガモのヒナ3匹がうろうろしているのを見つけました。親鳥のすがたは見えませんでした。まわりに水辺はないので、石神井川に移動するときにはぐれてしまったのでしょうか。 (画像と情報:しぜん探検隊)  5月20日(月) 森の音楽家見つけた! 近所の公園で、キツツキがケヤキの幹(みき)を口ばしでたたいている音が聞こえてきました。この公園では初めて聞く音です。時々見かけるアオゲラだと思われます。肉眼では見えましたが、ざんねんながらさつえいはできませんでした。 (画像と情報:しぜん探検隊)  4月26日(金) タンポポのビン詰め タンポポの綿毛がふくらむ季節です。開く前の綿毛を取って、上手にペットボトルやビンに入れて乾燥させると、中で綿毛が開いて素敵なタンポポのビン詰めが出来上がり! (画像と情報:隊員のGママさん)  4月16日(火) 緑色の桜ミッケ! 花びらが緑色の珍しい桜「御衣黄」(ぎょいこう)を見つけました。公園とかで見ることはありますが、今回は意外にも学区内で見つけましたよ。さて、ここはどこでしょう。ヒント:駅のすぐ北側。線路のそばですよ! (画像と情報:隊員のGママさん)  1月8日(月) キイロスズメバチの巣発見! 雑木林の中で発見。たぶんキイロスズメバチの巣だと思われます。この時期は中は空き家のはず。次回観察会に持って行きますね~ (画像と情報:隊員のおおさわさん) ★2月の観察会でさっそく「解体ショー」やりましょう! 12月4日(火) アンテナをつらぬくISS 12月4日に、ISS(国際宇宙ステーション)が夜空をつうかするようすがとてもよく見えました。すごく明るかったのが、ゆっくりゆっくり暗くなっていく様子がなんともふしぎでしたね。これからよく見えるのは 6日(水)17:51ごろ 南西の高い空 7日(木)17:02ごろ 真上(天頂) です。くわしくは・・・・ をさんこうにしてください。  10月29日(日) ナナフシの脱皮殻発見! ぐんま昆虫の森の温室で、たくさんいたナナフシの中で初めて抜け殻を見つけました。 (画像と情報:OB隊員のN君) ★夏にやった「夜の森観察会」ではナナフシを発見したN君。今度はその脱皮殻かぁ。よく見つけましたね!!  9月19日(火) 狩りをするスズメバチ 石神井公園(三宝寺池)でセミを捕まえたスズメバチを見かけました。しつこく撮影していたら、獲物をしっかり抱え込んで運び去っていきました。(クリック→動画)  9月12日(火) どんぐりミッケ! 大きなどんぐりが落ち始めましたよ。どんぐり拾いなら今がチャンスです! (画像と情報:隊員のGママさん) 9月7日(木) 空を見上げなはれ! 18:07の上石神井から西の空です。 ご多忙なみなさんもたまには空を見上げなはれ! (画像と情報:OB隊員Nさん) ★みごとな夕焼けですね。空気中の水蒸気やチリが多いと赤色以外の光は散乱してしまい、このようにより赤く鮮やかな夕焼けになるんだそうです。この時期、夕暮れの西の空から目が離せませんね~  8月14日(月) 石神井公園でタウナギ捕獲! かねてより、タウナギを飼育してみたいと思っていて、14日の夜に石神井公園へガサガサをしに出かけました。 水路を見回ったところ、大きなタウナギがゆっくりと泳いでいるのを見つけました。最初は素手でつかもうとしましたが、思った以上にぬめりが強くて素手で捕まえるのは無理だと考え、網ですくうことにしました。何度か取り逃しましたが、何とか捕まえることができ、家で飼育することにしました。体長は70cmほどでした。 (画像と情報:卒業生の通りすがりのシャムネコさん)  8月13日(日) 流星見ながら羽化したよ! ペルセウス座流星群。極大となる今晩は微妙ですが昨晩は見ることができました。よかったです。写真は流星を見ながら羽化したアブラゼミです。 (画像と情報:OB隊員さん) ★昨晩は雲の間に結構星が見えましたからね。今晩はどうかなぁ・・・  8月9日(水) 8月9日(水)積乱雲の発達と移動 昨日のOB隊員さんからの情報に引き続きまた雲の話題を… 夏といえば積乱雲(入道雲)。雷はイヤですが(実は大好き。ワクワクします)、じっと見ていると積乱雲は実にダイナミックな動きをしています。時間を短縮して撮影するとその動きがよくわかります。→動画 (画像と情報:スタッフのつとむ)   8月8日(火) 空から目が離せません! 台風が近づいてきているようです。長いこと雲一つない青空続きでしたが、ここへ来て雲の変化、気象の変化がおもしろいです。上は太陽の両側に明るく虹色に光る点(「幻日」(げんじつ)が見えています!その下は富士山と幻日です。下の写真は雲の一部が虹色に輝いて見える「彩雲」です。 (画像と情報:OB隊員さん) ★雲の変化が面白いですね!朝夕の急な雨の後には虹が出ることもあります。みなさんも空を見上げてみましょう。   8月7日(月) ついに会えた!念願の・・・ ついに念願の水棲昆虫に会えました。ゲンゴロウです!(→画像拡大) (画像と情報:OB隊員中1のS君) ★S君はゲンゴロウに会いたくて計画を立ててはお父さんと日本各地のため池などを回り、ようやく4年ごしで出会うことができたのだそうです。探して回る中でアメリカザリガニなどの外来種が入り込んでしまって生態系がくずれてしまった地域が多いことにも気づいたと話してくれました。  8月6日(日) ミンミンゼミが羽化しました! 昨日のセミの羽化観察会で持ち帰った幼虫が無事羽化しました。ミンミンゼミでした! (画像と情報:4年生隊員のS君) 8月5日(土) ミノムシくんを見つけたよ 朝おきて家のドアーをあけると、なにやらぶらぶらしたものが目に入りました。ミノムシでした。朝のごあいさつをしにきたのかな?朝から暑いのに、あんなのをからだにまとってだいじょうぶ? (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月31日(月) さてこのトンボは・・・? 静岡県伊東市にて。宿泊先のプールで泳いでいたら、黄色いトンボの大群が飛んでいて、そのうちの一匹が駐車場内で休憩している所を発見しました。シオヤトンボ?? (画像と情報:4年生隊員のS君) ★上石神井ではあまり見ないトンボ?ですね。あれれ・・・よく見るとチョウみたいに長い触覚(しょっかく)がありませんか?(→画像拡大) もしかしてトンボによく似たツノトンボかな?  7月29日(土) どうか逃げないで! 帰宅してドアを開けようと思ったら、交尾をしているムシヒキアブが! どうか逃げないでと思いながら急いで撮影しました。 (画像と情報:4年生隊員のS君) 5月1日(月) 白い花のアカバナユウゲショウを見つけた! 町中を歩いていて、白い花をつけているアカバナユウゲショウを初めて見つけました。単にユウゲショウと呼ぶこともあります。シロバナアカバナユウゲショウなんてちょっとへんな呼び名ですね。シロバナユウゲショウでもいいみたいです。ならべて比べると、アカバナの方は茎は赤茶色をしていますが、シロバナの方は、葉の色と同じ緑色のままです。 アカバナユウゲショウの中に白い花がまじっていないかどうか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月13日(木) 黄砂(こうさ)のえいきょうかな? 夕日をとろうと西の空にカメラを向けてみました。風が強い日なのに、今日ばかりは山かげもどんよりぼんやり見えています。真上はきれいな青空ですが。やはり黄砂のえいきょうでしょうか? (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月12日(水) にげ出した植物 ~石神井川で見つけたよ~ 寒い時期からついこのごろまで、水のない 石神井川の底に黄色く目立つ花がさいています。『キクザキリュウキンカ』というヨーロッパからやってきた花です。どこかの庭先からにげだしたようで、かなり広がりを見せています。ちぎれた根からかんたんにふえるので、野生化するとやっかいです。ヒメリュウキンカ(クリック)との区別がまだしっかりとされていないようです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  4月6日(木) 4月6日(木)巨大なシロツメクサを発見しました。 場所は、石神井井川沿い、東伏見の早稲田大学グラウンドの、石神井川を挟んだ南側「下野谷 遺跡公園」です。葉もとても大きいのですが、花も大きく、直径3cmくらいあったでしょうか。まるで葱坊主(ネギの花:クリック)のようでした。 (画像と情報:スタッフのMさん)  3月31日(金) エドヒガン桜がやってきた! みなさんにおしまれつつも、幹の中に空洞(くうどう)ができてしまったために切り倒された桜(ソメイヨシノ)に代わり、西門わきに新しい桜の木がやってきました。新しい桜はエドヒガン桜という品種で、ソメイヨシノより少し早く咲く桜です。今回植樹されたエドヒガンはすでに凛(りん)と若葉を出している状態です。花をつけるまで何年かかかるようですが咲いた時の皆さん喜ぶ姿が今から楽しみです (画像と情報:スタッフのSさん) ★上石神井小学校の桜は図書室北側にあるオオシマザクラ以外はソメイヨシノでしたが、開校当初植えられたものは学校と同じくらいの年と考えると樹齢70年を超え、幹が老化して近年次々と切り倒されてしまっています。(ソメイヨシノはひかくてき寿命が短い樹木だそうです)新しく植えられたエドヒガン桜は寿命が長い桜で、中には樹齢数百年と言われているものもあるくらいですから今後も長く上小のシンボルとなっていくといいですね。生物多様性という観点からもソメイヨシノばかりでないというのはよいことだと思われます。 ジョウビタキ 石神井川に沿った都営上石神井アパートの一角。ジョウビタキのメスがいました。冬鳥の季節は終わり、このメスのジョウビタキもそろそろ旅支度でしょうか。(→画像拡大) (画像と情報」:スタッフのT) 3月10日(金) ムクドリの水浴び 春本番のような暖かさに、夕方、たくさんのムクドリが石神井川で水浴びをしていました。ねぐらに帰る前の入浴タイムでしょうか。(→動画)  3月9日(木) 冬眠終了! 一気に春めいた暖かな陽気に誘われて、ニホントカゲも冬眠から目覚め、日向ぼっこを始めたようです。〈上石神井第4踏切と第5踏切(閉鎖中)の間の線路ぎわ〉 (画像と情報:スタッフのつとむさん)  3月8日(水) 幼虫めっけ! 春から育てていた綿が枯れたので、植木鉢の土を空けたら、中から大きな幼虫が4匹も出てきました。コガネムシ?でしょうか。 園芸用の土で大きく育っていて驚きました。 せっかくなので腐葉土を入れたケースに移し替えて、様子を見ることにしました。 (画像と情報:3年生隊員のSさん) ★うえきばちから出てきたというこの幼虫。さてさなぎになって羽化したらいったい何になるのでしょう?ケースに移して飼育して、自分の目で確認するというのはとてもいいとりくみですね!結果がわかったらぜひまた写真を撮って報告してください。 3月2日(木) 見えた!木星と金星の大接近 (画像と情報:隊員のGママさん) 2月23日(木) 夕方の絶景をパチリ! 23日の夕方、家の2階から家族で見ました。とてもきれいでした! はじめはスマホを使ったのですが、手ブレがひどく、次にデジカメでねらいました。すると三きゃくなしでもうまくとれました。(画像クリック→拡大) (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★いろいろな機材を使ってみたのがいいですね。3つの天体(月・木星・金星)が並んでいる様子がよくわかります。3月の大接近の様子もぜひとってみてください。 2月22日(水) 毎日見てます! 22日の夕方、18:51。古田島先生からの宿題(→こちら)に挑戦中。毎日同じ場所から同じ設定で撮影してみようと思います。(画像クリック→拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★22日と23日の比較画像が届きました。この先も2日の大接近までの変化が楽しみですね。  2月22日(水) 春めっけ!② こんにちは。しぜん探検隊で頂いたサクラソウが綺麗に咲きました!写真を送ります。 (画像と情報:OB隊員・中1のY君) ★スタッフのコタジーが毎年取ったタネから育てた苗を秋に分けてくれているものですね。次々とつぼみが上がってきているようですから、これからもしばらく楽しめそうですね。     2月15日(水) 春めっけ! 先週、三浦海岸に行ってきました。そこではもう春がやって来ていて、ハコベ、タンポポ、オオイヌノフグリ等が咲き、カメムシかな?出てきていました。 (画像と情報:スタッフのKさん) ★恒例「春さがし」の今年の第1報ですね。春はもうすぐそこまで来ているのですね。みなさんもそろそろ冬ごもりを終わりにして外に春を探しに出かけましょう。週末は暖かくなるようですよ~  1月24日(火) 石けんの実、ミッケ! 前に観察会で遊んだ「ムクロジの実」がいっぱい落ちているのを見つけました。(写真・上)まわりの半透明の部分はぬらせばアワがいっぱい出て石鹸遊びができたんですよね。そのまわりの部分を取ると、中から硬くて黒いタネが出てきます。(写真・下)これが、羽根つきの羽根の黒い玉の部分。  見つけたのは、石神井公園。上を見るとまだいっぱいなっていて思わず「ムクロジパーティーだぁ!」  (画像と情報:OB隊員のN&Rちゃん) ★この実をひろえるのは、ちょうど今の季節なんですね。集めておいたら次のリース作りの時のいい材料にもなりそう・・・  1月21日(土) 日の入りも見たよ! 学校の屋上から日の出を見たので、夕方は日の入りも観察してみました。16:56とのことでしたが、ちょうど西の方角に雲があり、太陽が雲にかくれたのは16:29でした。西に雲があるということは、これから天気、悪くなるのかな。 (画像と情報:隊員のGママさん)  1月12日(木) 月齢19の昼間の月 昼間の月がよく見えていました。月齢19だから上石神井の電車の車庫の同じ19番線の上に出ているように撮れたら面白いかなと思ったけど、なぜか19番線だけ表示がない(汗!) (画像と情報:隊員のGママさん)  1月6日(金) 暈と幻日 太陽に巻層雲がかかると、そのまわりに色のついた光の輪や強く光る場所が現れたりすることがあります。今日は丸い輪とその両脇に虹色に光る「幻日}(げんじつ)が見えていました(矢印の下)。左右両側に、はっきり見えていましたが出先にいたのが残念。真ん中の太陽を隠すようにして撮らないとまぶしすぎて暈や幻日がうまく写らないのですが・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) 1月1日(日) 初日の出と初日の入り あけましておめでとうございます。 元日は、風はさほどないのに、とてもすんだ空にめぐまれました。 南東の空から日の出の時こくの数分後には太陽が見えてきました。わずかに広がる低い雲が光をうけて、それ刻々と増していくようすは神々しいものでした。 矢印の先に都庁やドコモタワーが見えています。 日の入りは、富士山の火口のすぐ南がわでした。あと1週間足らずで火口に重なりそうです。 ★初日の出16秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) 12月26日(月) 1時間以内で全部見えた! 日月火水木金土全部を最短時間で見るチャレンジ。1時間以内で全部見られました!! 上から太陽(日):26日16:24撮影・火星:26日17:03撮影・土星・月・水星・金星:26日17:13撮影・木星・土星・月:26日17:13撮影 (→それぞれ画像クリックで拡大) (画像と情報:隊員のGママさん) ★すごい。古田島先生もびっくりの最短記録でしょうか。こんな「惑星パレード」は次は2061ねんまで見られないそうです。みなさんもぜひ西の空に注目!(コタジーの記事はこちら・クリック)  12月22日(木) 12月8日(金) 月のくしざし! 天気が悪く、年内のダイヤモンド富士がとれなかったので「タワーくしざし満月」をとってみました。 12月8日は、満月のすぐそばに本当は明るい火星が見えていたですが、さらに明るい月の明るさに合わせてとったので写っていません。 タワーの頂上の部分がぴったり満月の中に入りました。17時半くらいから5分おきにとったものを後で合わせました。 月の軌跡(きせき=動いたあと)を見ると、ずいぶんと地面から立っているのがわかります。 冬の満月の動きは、この時期の太陽とは反対に、天の高いところを通ることがわかります。でもこれは満月の時だけで、月の形がかわると通る高さもかわります。冬では、新月になるほど高さが低くなります。(冬の太陽と同じになる) 夏はこの反対で、満月は低く、新月に近くなるほど高くなります。太陽は、何か月もかかって高さがかわっていきますが、月は2週間くらいの間に、高くなったり低くなったりしているというわけです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  12月4日(日) 桜草咲いた! 先日の観察会で、こたじま先生から頂いた桜草に、花が咲きました。去年はピンク、今年は白でした。今年は二株頂いていて、もう一株もつぼみが出てきたので、何色が咲くか楽しみです。 (画像と情報:4年生隊員のSさん) ★寒くて花の少ない時期にもきれいに咲き続ける桜草(=プリムラマラコイデス)うれしいですね。みなさんのところでは何色が咲くかな。  11月27日(日) 大根できたよ~! 畑プロジェクトで種から育てた大根。できました! (画像と情報:畑プロジェクトメンバー) ★某農大の有名な「大根おどり」を思い起こしました。大根ってできると思わずにぎりしめて踊り出したくなるものみたいですね。わかるわかる。  11月26日(土) バッタのソフト食べたぞ! イナゴが突き刺さったソフトクリーム。長野県の諏訪湖で発見。思わず挑戦しちゃいました。 「ソフトクリームの甘い味にイナゴのしょっぱいところが合っておいしかった。でもちょっと見た目がグロかったよ」(本人談) (画像と情報:4年生隊員のK君) ★地球を救う「昆虫食」がちょっとしたブームとか。イナゴは日本ではひかくてきポピュラーな食べ物みたいですが、ソフトに合わせるとは!隊員なら挑戦したくなるよね~  11月20日(日) 11月20日(日)木の実を拾いに公園に行こう! リースづくりのためのつるとりも終わり、いよいよ12月3日はリースづくり本番。みなさんも、各自で木の実や木の枝など、リースづくりに使えそうな材料集めをしましょう。 11月12日(土) フヨウはふよう?(不要) いいえ、リースに みなさんリース作りの材料は集めていますか?フヨウの実がリース作りに使えるというので、近所の鉄道にそう道や石神井川ぞいの道で見つけたので集めてきました。12/3にもっていきますね。 (画像と情報:スタッフのコタジー) ムクドリの大群 ムクドリの繁殖期は春から夏にかけてで、それが終わると親鳥も巣立った子どもも一緒になって群れを作るようになります。秋から冬にはその群れは大きくなって、何百、何千、場合によってはそれを超える数のムクドリが群れを作るそうです。この時期、上石神井周辺でも、夕方にムクドリの群れを見ることができます。ムクドリは群れでねぐらに集まって寝るそうですが、おもしろいのは、寝ぐらに向かう前に、一回、どこかに集まることです。写真は、夕方、高圧線の鉄塔に集まったムクドリです。こうして集まったあと、何かをきっかけに、群れはねぐらに向かって飛び去っていきます。いくつかの群れが集まっているようで、見ていると、電線に残っているムクドリもいて、すべてのムクドリがいっぺんにねぐらに向かうのではないようです。それでも暗くなる前には、鉄塔や電線には一羽のムクドリもいなくなります。 →画像クリックで拡大 →動画(クリック) 10月27日(木) カノープス見えた! 南の低い空に見ることのできるカノープス。見えました!ただし午前3:23。 (画像と情報:隊員のGママさん) ★シリウスに次いで明るい星ですが、日本では高度が低いため(東京で約2度)なかなか見ることができない星です。南がよく開けた場所を探して、星座アプリなどで見える時刻(けっこう限られた時間です)を確認して、みなさんもこの冬はカノープス探しにちょうせんしてみましょう。  10月26日(水) 綿の実ができました! 畑に植えた綿(わた)に実ができました! (画像と情報:隊員のKママ) ★白いフワフワの綿の実。このフワフワからみなさんが着るいろいろな服やタオルなどの綿(コットン)製品ができるのですね。このままリースなどの飾りとして使ってもすてきですね。来年はみんなでもっとたくさん育ててみたいですね~  10月23日(日) 虹色の雲発見! 虹色の雲(彩雲=さいうん)が出ていました。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) ★太陽のそばにある高積雲などの端が美しく虹色にかがやく現象です。古くからとても縁起(えんぎ)がよいものとされています。何かいいことあるかな・・・  10月14日(金) 「石神井川そばのソバ 」 ~ にげ出したソバ ~ 西東京市の石神井川は、水が少な目で、川ぞこにたまった土には多くの野草が生えています。 このところ川べりを歩いていてやたら目につくのが、白い小さな花をたくさんさかせているつる性の野草です。大きな群れをなしてさきほこっています。葉は、かどのとれた三角形です。 『シャクチリソバ』というソバの仲間でした。にがくてまずいけれどからだいいいことで有名なダッタンソバの親せきです。昔、小石川植物園に外国から薬草としてもちこまれたものがにげ出して全国に広がったようです。ふえすぎてやっかいものあつかいされてもい ます。 ソバ粉にしてソバをつくってもにがくてまずく、むしろ若い葉を野菜にするということです。 薬草というからには、どんなこうかがあるのか調べてみましょう。(野草をやたらに食べたりしないように (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月12日(水) よっぱらったフヨウだ! 「よっぱらった?フヨウ」を見つけました。「スイフヨウ(酔芙蓉)」といい、街角でふつうに見かける花です。さきはじめた朝は花びらが白いのですが、時がたつにつれて、しぼみながらピンク→赤とかわっていきます。そのようすをよっぱらって顔が赤くなることにたとえたのですね。どうして色がかわるのか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  10月8日(土) 十三夜の月と木星 雲の合間から見えました! (画像と情報:隊員のGママさん)  10月2日(日) 関公園にて 関公園で出会いました。ヒバカリかな?と思ったけれどアオダイショウ? (画像と情報:隊員のGママさん) 光をあてて拡大してみると!! 浴室や洗面所など水回りでときどき見かけるオオチョウバエ。ただ地味でうっとうしいヤツと思っていましたが、ストロボで光を回して拡大撮影してみると…。  9月24日(土) 小さな細長い貝発見! 画像悪いですが、先ほど初めてキセル貝を見つけました! (画像と情報:隊員のKママ) ★陸にすむ貝はカタツムリだけではないんですよね。よく探すとこのような細長い小さな貝を見つけることがあります。キセル貝は左巻きですが、オカチョウジガイという右巻きのもいます。死んだ貝殻のように見えても水をかけると写真のように動き出すことがあります。探してみましょう!かわいいよ~  9月16日(金) 上小のヒガンバナも咲き始めました この時期になると、すぅ〜っとのびて、パッと花火のように咲くヒガンバナ。トンボ池でも咲きはじめています。 (画像と情報:スタッフのSさん)  9月15日(木) カマキリ釣りにちょうせん! 自宅で子ども文庫を開いている知人に、探検隊の本を寄付しましたところ、利用者の少年が、早速【釣れた】報告を下さったそうです。 (画像と情報:スタッフのMさん) ★探検隊の本から、身近な自然遊びが広がっていっているようでうれしいですね。みなさんもいろいろ挑戦してぜひ報告を聞かせてください。  9月12日(日) 黄色のヒガンバナ見つけた! ヒガンバナが咲き始めています。上小の駐車場わきのはどうですか? 近所に黄色のヒガンバナがあるのに気が付きました。プランター植えです。ヒガンバナは真っ赤、ピンク 白 などがあると思っていたら、黄色のもあるんですね。 黄色いのはショウキズイセンという名でもよばれています。ほかにどんな色のヒガンバナがあるのかさがしてみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  9月9日(金) トチの実 トチの実の季節になりました!公園にたくさん落ちていました。今年はリース教室やるんですか? (画像と情報:隊員のGママさん) ★風の吹いた次の日、早朝のお散歩のごほうびですね~ピッカピカのトチの実、拾うとうれしくなりますね。リース教室、まだ確定ではないですが今年もやりたいなぁと考えています。みなさんも材料集め始めましょう。  9月8日(木) オケラ発見!! 露天風呂でオケラ発見!近くに田んぼもないのに・・・ (画像と情報:スタッフのKママさん) ★田んぼのような場所で見つけるイメージですが、都内にもいるんですね~。上小でもトンボ池横の側溝でスタッフのSさんが見つけた記録があります。 ※「露天風呂」というのはKママさんのおうちはお風呂屋さんだからです。 ちなみにオケラは泳ぐの得意だそうですよ。  9月7日(水) レンゲショウマ SNSで人気のレンゲショウマ。石神井公園、いろいろありますね。映えないケド・・・ (画像と情報:隊員のGママさん) ★御岳山まで行かなくても身近なところでも見られるのですね~  9月4日(日) ・・・ドクターブラック・・・ 家の前の道路を黒いきれいなイモムシが3匹も歩いていました! ★頭の部分がななめの流線形。黒いボディーにオレンジ色と黄色の丸い窓みたいなもよう。おしりにはとがったアンテナが1本。新幹線にドクターイエローっていう車両があるけれど、まさにそのブラックバージョン!ということで私は「ドクターブラック」って呼んでいます。 (→資料) この時期、食草のヤブガラシから下りて地面の下でさなぎになります。身近に出会える美しい生き物ベスト3に入ると思いますよ。ちなみにとげはにせもの。さわってもだいじょうぶです。 (画像と情報:隊員のりっちゃん&ママ) 8月19日(金) 夏のオリオン 昨晩から今朝にかけては風が変わりましたね。光にもかすかな秋が感じられます。早朝の上石神井の空には冬の星座オリオンが見えていました。(19日3:38撮影) (画像と情報:隊員のGママさん)  8月13日(土) 昼間からうじゃうじゃカブトムシ 近所の民家(緑が多いところですが、広い緑地は近くにはありません)に、昼間からカブトムシが元気に動き回っている木を見つけました。 シマトネリコという木のことをテレビで紹介しているのを思い出しました。カブトムシというと、夜クヌギなどの木にやってきてじっくりと樹液を吸っているというイメージですが、シマトネリコにやってくるものは、様子がかなり違います。 昼間なのにとにかくよく動きまわり元気です。ブンブン飛び回るものもいます。この木とカブトムシの関係は、まだわからないことも多いみたいですが、埼玉県の小学生の研究も参考にしていろいろと調べてみてください。 50秒動画(→こちら) ★シマトネリコという木になぜかカブトムシが集まるという情報、聞いてはいましたがまだ見たことがありません。このシマトネリコという木は最近、庭木として人気なのだそうですが上石神井にはありますかね。どんな木が調べておいて登下校やお散歩の時などに探してみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  8月10日(水) 街路樹を見上げてみれば いま、あちこちで鳥のヒナが鳴いていますね。新青梅街道の街路樹にも鳥の巣がありました。(写真左上)青梅街道の街路樹にも何かの巣があったし、街路樹って巣作りしやすいんですかね? ★昼夜を問わず人やクルマが絶えず通る場所は、天敵におそわれにくいというようなことがあるのでしょうか。都会に暮らす鳥たちのしたたかな知恵ですね。 (画像と情報:隊員のGママさん)  8月6日(土) 夏のモフモフ 昆虫界のアイドル、セダカシャチホコ? 数日間外廊下の天井にいましたが、とうとう力尽きたご様子。 暑くないのか心配になるほどのモフモフっぷり! (画像と情報:隊員のGママさん) 8月1日(月) 上石神井駅の日の出(夏) 暑い日が続きます。早朝5時の駅から見た東の空。 冬バージョン(2月23日・クリック→動画)とくらべてみてください。 ★暑い暑い・・・と文句言ってないで、ちょっと早起きして空を楽しむのもいいですね~ ちなみに下の空の動画も素敵です。こちらも撮影はGママさん。7月27日。ほかでもない上石神井の空です。 (画像と情報:隊員のGママさん)   7月21日(木) 7月の発見いろいろ 7月に見つけた自然いろいろ。 上・石神井公園内の売店「豊島屋」さんで見つけたタマムシ(7月8日) 中・石神井公園のモミジの木に生えていたキノコ。とてもおいしいキノコなのかハムシがたくさんいました。(7月5日) 下・井草の森公園のアオギリの花。そろそろ開花です。(7月5日) ★今年は梅雨明けが早く、すぐに暑くなったためタマムシはずいぶん早くから見られた気がします。石神井公園にもいるのですね。 みなさんも見つけた夏の自然を教えてください。 (画像と情報:隊員のGママさん)  7月9日(土) オナガの子育て2022(巣立ち編) オナガのヒナたちですが、生まれたのは4羽。そのうち落ちてしまい死んでしまったのが1羽、8日の段階でかなり大きく(巣の中で羽をばたつかせている)育ってきたヒナが3羽が巣の中に確認できました。翌日9日は朝少し早め6時ころに見に行きました。ヒナはもう巣の外に出ていて、一羽は数m下のカエデの木に乗っています。もう1匹はなかなか見つからなかったですが、声をたよりに探してみると巣の真下の低木(アオキやクマザサ)の葉陰にかくれるようにとまっていました。いずれも、何羽もの親鳥がギーギーいきかい、エサを時々やりにきていました。ヒナに近づこうものなら、頭をつつかれそうないきおいでした。残る1羽のヒナはついに見つけられませんでした。ツミの声や姿がよく見らるので、1羽は捕食されてしまったのかもしれません。生きているのはどちらも飛ぶのはかなりおぼつかないヒナです。ちょっと、「巣立ち」が早かったのでしょうか。親からエサをもらっているので、そのうちしっかりしてくると思いますが、なにしろ外敵がけっこういそうなのでちょっと心配です。 5分09秒動画(→こちら)  7月5日(火) オナガの子育て 2022 5月末に近くの公園のけやきの木に巣を見つけてから、3週間以上かかってやっとオナガのヒナがふ化しました。 去年は、どういうわけか親鳥がとちゅうで巣をあきらめてしまったようですが、今年はめでたくヒナのたん生を目にすることができました。ヒナは今はすくすく育っているようですが、途中悲しいこともありました。 同じ園内にいるツミにおそわれそうになる場面もありましたが、なんとか切りぬけられたようです。今は台風の大風や大雨が心配ですが、無事に巣立ってくれるとうれしいです。高い木のななめ下からの撮影ですが、ひなはどんどん大きくなるので、そこそこ中の様子をうかがうことができます。ひなの鳴き声も聞こえます。強拡大するために望遠鏡のレンズを使いました。 2分40秒動画(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー)  7月2日(土) 10円玉みがきやってみました 探検隊で(カタバミの葉で)10円玉を磨いてから、帰って5円玉も磨いてみました。5円玉は10円玉と違ってそこまで綺麗に光らなかったです。磨いてしばらくするとまた錆びてきてしまいました。 ★今日の観察会でやった「カタバミの葉っぱ」を使った10円玉みがきをさっそく家で発展させて実験してみたんだね。こんなふうに別のものでもいろいろ試してみるとおもしろい発見もあるね。台所にあるお酢などの調味料、庭の別の葉っぱなども試してみたそうですね。こんど結果を詳しく聞かせてください。 (画像と情報:OB隊員中2のNくん)  6月23日(木) なんのまゆかな? 学校のクワの木で見つけました! ★大きな繭(まゆ)ですね。クワの木で見つけたということは、カイコの原種と言われるクワコでしょうか。しっかり糸で繭を作り、中のさなぎが鳥などに食べられないようにガードしているのですね。この糸だけを集めて布を作ろうと考えた昔の人もすごいなぁ。 (画像と情報:隊員のGママさん)   6月22日(水) 見たことあるかい? こんにちは! ハラグロオオテントウ(上)とビロードハマキ(下)です。 ハラグロオオテントウは関町で飛んでいたものです。1.2センチほどあります。 ビロードハマキは石神井公園の旧内田家住宅にいました。図鑑の絵は、はねがひらいて描いてあったので、気がつきませんでした。 どちらもツマグロヒョウモンやアカボシゴマダラ、ナガサキアゲハ、ジャコウアゲハなどと同じように近年北上してきた昆虫ですね。数年前は房総で見つかったとニュースになっていたのに、そこらへんで見られるようになりましたよね。 ★このHPではどちらも初登場の新顔さんです。練馬区内にいるのですね!ハラグロオオテントウはその名の通りの大きさであることが1円玉とのひかくでよくわかります。 (画像と情報:隊員のGママさん)  6月13日(月)ソバの花 市内の新青梅街道そばにソバの花を見つけました。がいろじゅのすぐわきに、いったいだれがまいたのでしょうか? ソバは、年に二回(夏と秋)とれるそうです。▲の形をした種を見たことがありますか? あざやかな赤い花をつける種類もあるそうです。 (画像と情報:スタッフのコタジー)  6月10日(金) キアゲハの幼虫 3齢までの、まだ体全体が黒っぽいうちは数多くいても、緑色が多くなった4齢の幼虫になると、なぜか数を減らしてしまうような気がします。このキアゲハの幼虫は久しぶりに見つけたビッグサイズので、もうじきサナギになるのではないかな。 (画像と情報:スタッフのSさん)  |